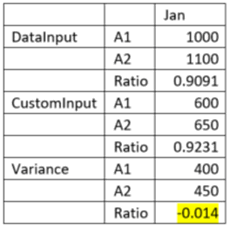メンバー式の解決順(ハイブリッド・モードのみ)
解決順は、ディメンションまたはメンバーのいずれかに設定でき、メンバー評価の順序を定義するメタデータ・プロパティです。解決順は問合せ実行時に適用されます。
解決順は問合せのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。解決順プロパティの値により、メンバー式が計算される優先度が決定します。指定された解決順を持つメンバーの式は、低い解決順から高い解決順に計算されます。
ディメンションまたはメンバーの解決順序を設定するか、Essbaseのデフォルトの解決順序を使用できます。設定可能な最小の解決順は0で、最大は127です。解決順の値が大きいほど、メンバーが後に計算されます。たとえば、解決順が1のメンバーは、解決順が2のメンバーの前に解決されます。
Note:
これは、ハイブリッド最適化アプリケーションにのみ適用されます。関連項目: ハイブリッド集約のアプリケーション・モデルの最適化Table 15-14 デフォルトの解決順設定
| ディメンション/メンバー・タイプ | デフォルトの解決順序の値 |
|---|---|
| 保管済メンバー | 0 |
| 疎ディメンション | 10 |
| 密ディメンション - 勘定科目 | 30 |
| 密ディメンション - 時間 | 40 |
| 密ディメンション | 50 |
| 属性ディメンション | 90 |
| 2パス動的メンバー | 100 |
まとめると、ハイブリッド・モードのデフォルトの解決順序では、アウトラインに表示される順序(上から下)で、保管済メンバーが動的計算メンバーの前に計算され、疎ディメンションが密ディメンションの前に計算されることが指定されています。
解決順序が指定されていない動的メンバーは(式の有無にかかわらず)、2パスとしてタグ付けされている場合を除き、そのディメンションの解決順序を継承します。2パス計算は、正確な値を得るために2回計算する必要がある式を持つメンバーに、非ハイブリッド・モードで適用できる設定です。
2パスはハイブリッド・モードでは適用できず、2パスとしてタグ付けされたメンバーは、属性の後に最後に計算されます。ハイブリッド・モードでは、デフォルトの解決順序が要件を満たさない場合は、2パスではなくカスタム解決順序を実装する必要があります。
ハイブリッド・モードでは、デフォルトの解決順序が次のシナリオに対して最適化されます。
- 前方参照。動的メンバー式がアウトライン順序で後のメンバーを参照します。ハイブリッド・モードでは、アウトライン順序の依存性がありません。
- アウトライン順序に基づく子の値の集約は、同等の式を使用した集約とより厳密に一致します。
- 疎な式内の依存性としての動的な密メンバー。ハイブリッド・モードでは、疎な式が動的な密メンバーを参照する場合、疎ディメンションが最初に計算されるため、この参照は無視されます。この動作を変更するには、疎ディメンションに密ディメンションの解決順序より高い(密ディメンションより後で計算される)解決順序を割り当てます。
デフォルト以外の解決順序を使用する必要がある場合は、ハイブリッド・モードでメンバーのカスタム解決順序を設定できます。解決順を変更する方法については、解決順序の設定(ハイブリッド・モードのみ)を参照してください。
カスタム解決順序を実装すると、デフォルトの解決順序がオーバーライドされます。メンバーまたはディメンションの解決順序が等しい場合は、アウトラインに表示される順序(上から下)によって競合が解決されます。
この動作は、密ディメンションの解決順より高い疎ディメンションにカスタムの解決順を割り当てることにより変更できます。
例:
異なる解決順のメンバーを含む次の例を検討してください。
勘定科目(疎、デフォルトの解決順30)
-
A1
-
A2
-
比率 – メンバー式[A1 / A2]
(勘定科目から継承されたデフォルトの解決順30)
データ・ソース(疎、デフォルトの解決順10)
-
DataInput
-
CustomInput
-
差異 – メンバー式[DataInput - CustomInput]
(データ・ソースから継承されたデフォルトの解決順10)
1月期の交差について次のデータセットを考えてみます:
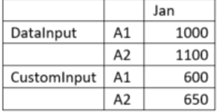
比率と差異に対して異なる解決順を使用する計算
ケース1: 差異より解決順が高い比率
このケースでは、差異が最初に計算され、次に対応する比率が計算されます。
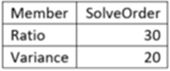
差異の比率は、(Variance->A1)/(Variance->A2)のように計算されます。
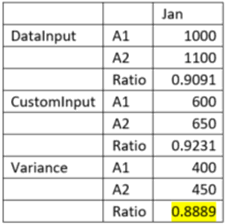
ケース2: 差異より解決順が低い比率
このケースでは、比率が最初に計算され、次に対応する差異が計算されます。
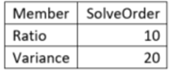
比率の差異は、(Ratio->DataInput) – (Ratio->CustomInput)のように計算されます。