|
|
| Sun ONE Application Server 7 パフォーマンスチューニングガイド |
Sun ONE Application Server のチューニングmodule最適なパフォーマンスを得るために Sun ONE Application Server をチューニングする方法について説明します。この章の項目は次のとおりです。
- HTTP サーバーのチューニング
- 接続プールのチューニング
- JSP とサーブレットのチューニング
- EJB のパフォーマンスチューニング
- 各種 EJB のパフォーマンスに関する注意点
- ORB のチューニング
- 関連する注意点
- トランザクションマネージャのチューニング
HTTP サーバーのチューニング
Sun ONE Application Server のパフォーマンスを最大限に引き出すには、クライアントからの要求を処理する HTTP サーバーの監視とチューニングが重要です。ここでは、HTTP サーバーのチューニングに関する次の項目について説明します。
- stats-xml による統計の有効化
- perfdump ユーティリティによる現在のアクティビティの監視
- 統計に基づくサーバーのチューニング
- ビジー機能
- パフォーマンスバケットの使用
- ファイルキャッシュの設定
- ACL ユーザーキャッシュのチューニング
- サービス品質機能の使用
- スレッド、プロセス、および接続
- Java パフォーマンスの改善
- init.conf のその他の指令
- obj.conf のその他のパラメータ
- サーバーのスケーリング
stats-xml による統計の有効化
perfdump などの既存の監視ツールや同様のカスタムツールを利用するには、stats-xml を使って統計を有効化する必要があります。
stats-xml を使って統計を有効化する手順は、次のとおりです。
- obj.conf のデフォルトオブジェクトの下に次の行を追加します。
NameTrans fn="assign-name" from="/stats-xml/*" name="stats-xml"
- obj.conf に次の Service 機能を追加します。
<Object name="stats-xml">
Service fn="stats-xml"
</Object>次の図は、stats-init というサーバーアプリケーション機能 (SAF) を組み込んだ <instancename>-obj.conf の例です。
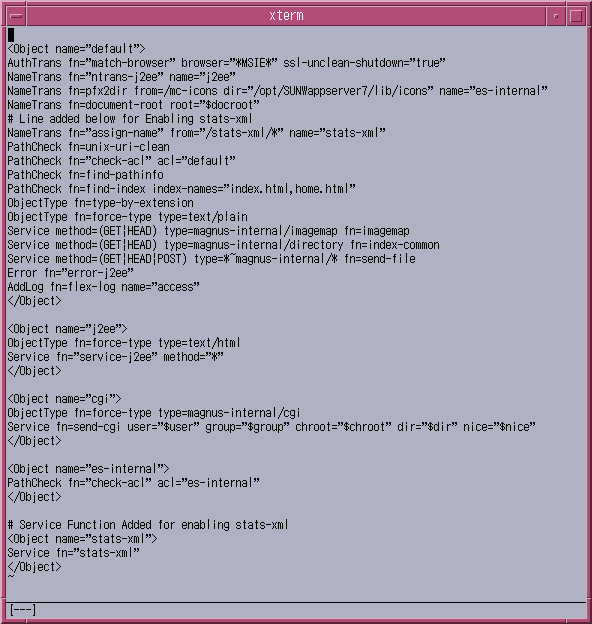
図: <instancename>-obj.conf に組み込まれた statsxml-obj
- init.conf に stats-init SAF を追加します。
init.conf に stats-init を組み込む例を示します。
Init fn="stats-init" update-interval="5" virtual-servers="2000" profiling="yes"
次の図は、stats-xml が有効化された init.conf ファイルを示しています。
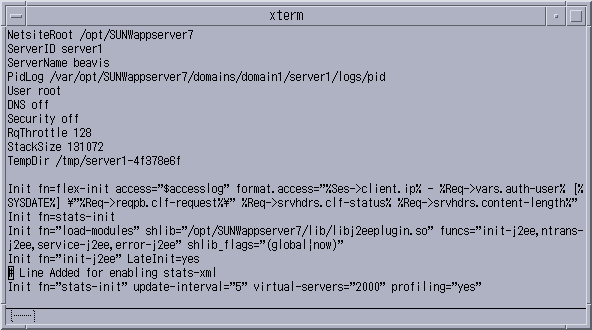
図: stats-xml による統計の有効化
上の例は、次の設定にも適用できます。
- update-interval: 統計を更新する間隔を秒単位で指定します。値を大きく設定するほど更新頻度が下がり、パフォーマンスが向上します。最小値は 1 で、デフォルト値は 5 です。
- virtual-servers: 統計の対象となる仮想サーバーの最大数です。これは、設定する仮想サーバーと同数以上に設定する必要があります。値が小さいほどメモリの消費は少なくなります。最小値は 1 で、デフォルト値は 1000 です。
- profiling: NSAPI パフォーマンスプロファイリングを有効化します。デフォルトは「no」で、サーバーのパフォーマンスに若干有利です。
設定ファイルの編集については、『Sun ONE Application Server NSAPI Programmer's Guide』 (英語) を参照してください。
perfdump ユーティリティによる現在のアクティビティの監視
perfdump ユーティリティは、Sun ONE Application Server に内蔵されている SAF です。これは、アプリケーションサーバーの内部統計からパフォーマンスに関するさまざまな情報を収集し、ASCII テキストとして出力します。perfdump ユーティリティを使うことで、より多くの統計を監視できます。
perfdump ユーティリティのインストール
次の図は、perfdump ユーティリティが設定された <instancename>-obj.conf ファイルの例を示しています。
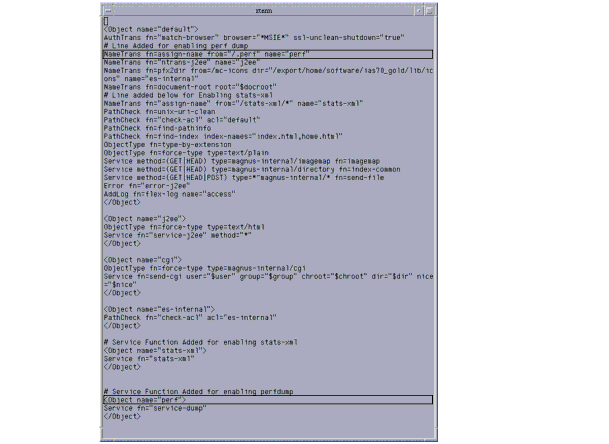
図: perfdump が設定された <instance-name>-obj.conf ファイルの例
perfdump をインストールするには、<instancename>-obj.conf ファイルを次のように変更します。
- <instancename>-obj.conf ファイルのデフォルトオブジェクトの後に、次のオブジェクトを追加します。
<Object name="perf">
Service fn="service-dump"
</Object>
- デフォルトオブジェクトに次の行を追加します。
NameTrans fn=assign-name from="/.perf" name="perf"
- 有効化されていない場合は stats-xml を有効化します。
stats-xml を有効化する方法については、「stats-xml による統計の有効化」を参照してください。
- サーバーソフトウェアを再起動します。
- 次の URL を使って perfdump にアクセスします。
http://yourhost/.perf
- perfdump に統計を要求し、ブラウザの自動更新頻度 (秒単位) を設定できます。次の例では、5 秒ごとの更新が設定されています。
http://yourhost/.perf?refresh=5
次の図は、perfdump の出力例を示しています。
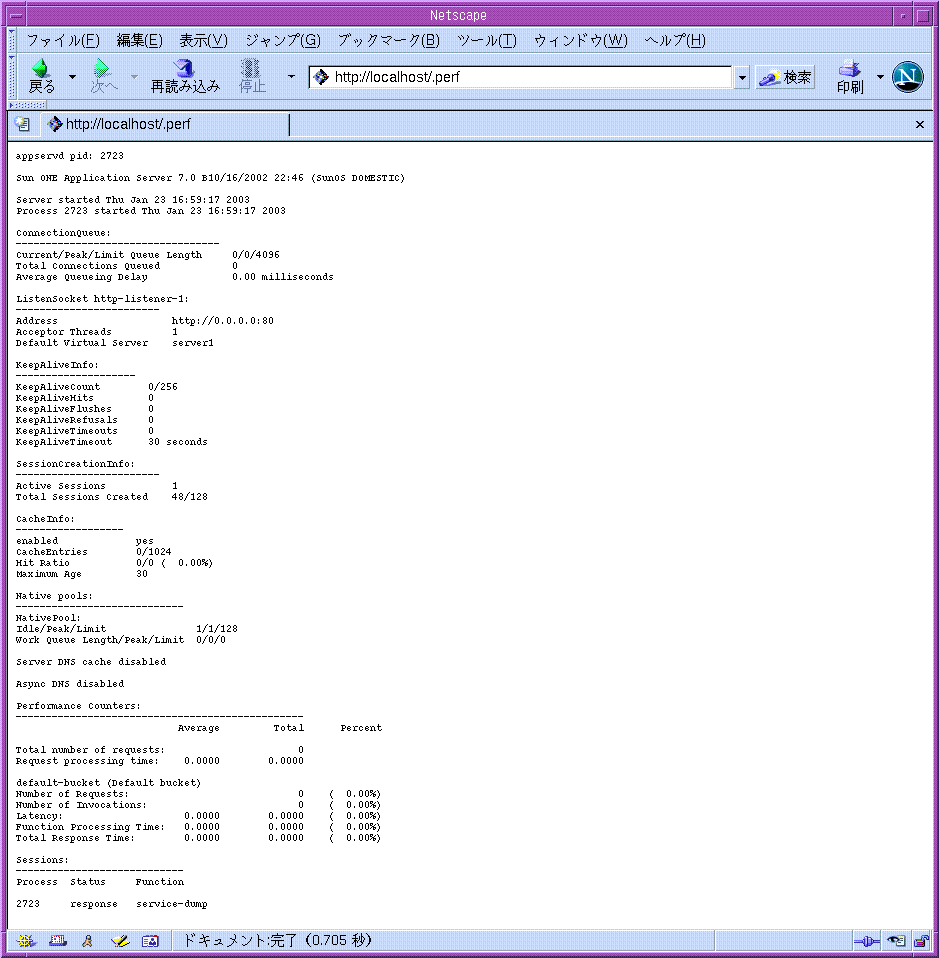
図: perfdump の出力例
ファイルの編集については、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
統計に基づくサーバーのチューニング
ここでは、perfdump ユーティリティから得られる情報と、この情報に基づいて一部のパラメータをチューニングし、サーバーのパフォーマンスを向上する方法について説明します。デフォルトのチューニングパラメータは、非常に大規模な場合を除いてすべてのサイトに適用できます。大規模なサイトで定期的な変更が必要なパラメータは、RqThrottle、MaxKeepAliveConnections、KeepAliveTimeout だけです。これらのパラメータをチューニングするには、Web ベースの管理インタフェースを使うか、<instancename>-obj.conf ファイルを直接編集します。次の図は、管理インタフェースのHTTP サーバーチューニング画面を示しています。
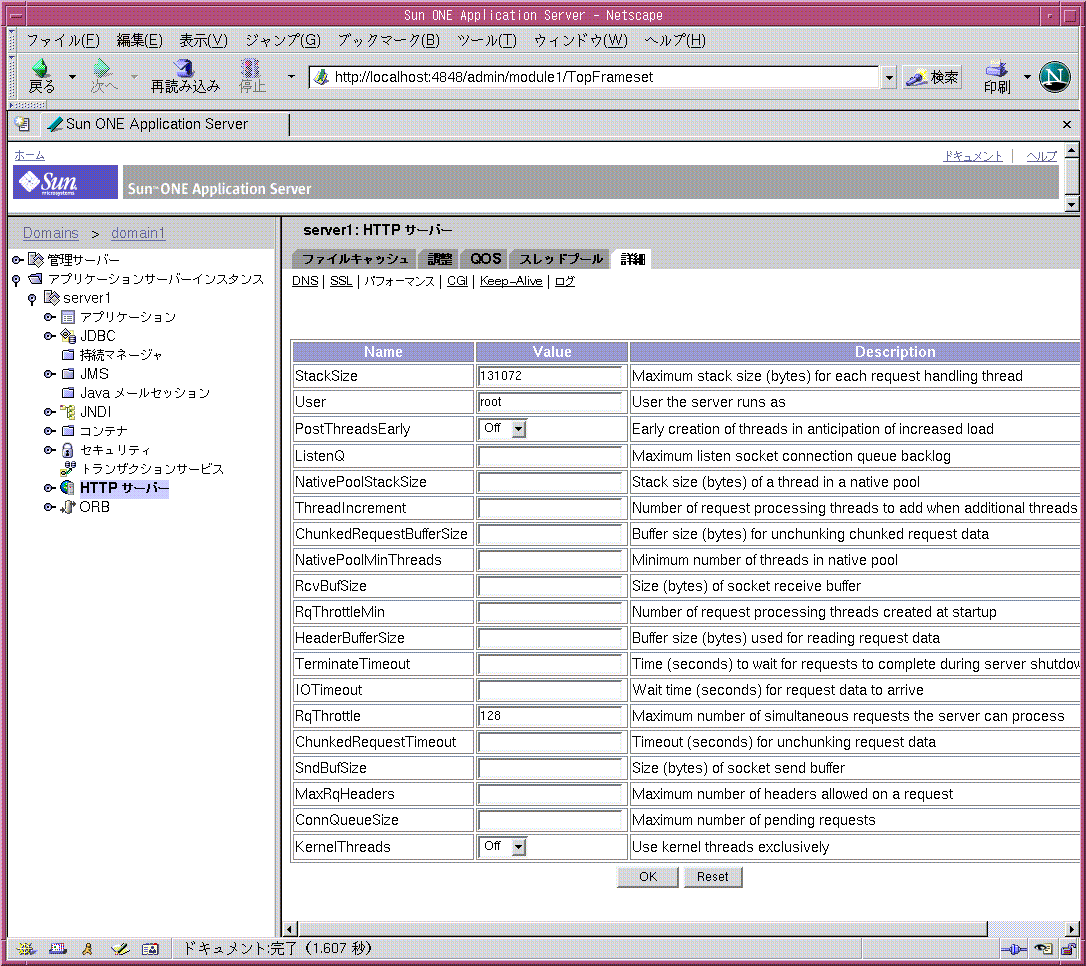
図: 管理インタフェースによるサーバーパフォーマンスのチューニング
perfdump ユーティリティが監視する統計は、次のカテゴリに分かれています。
接続キュー情報
接続キュー情報は、キューに含まれるセッション数と、接続受け入れまでの平均所要時間を示します。
perfdump では、この統計は次のように表示されます。
ConnectionQueue:
---------------------------------
Current/peak/limit queue length 0/48/5000
Total connections queued 3753
Average queueing delay 0.0013 seconds
Current /peak /limit
Current/peak/limit queue length は、順に次の値を示します。
- 現時点でキューに含まれる接続の数
- キューに入れることができる接続の最大数
- 接続キューの最大サイズ
チューニング
キューに含まれる接続の数が上限に近づいた場合、負荷が大きくなる状況ではキューの最大サイズを増やして接続を維持することが必要になります。
キューの最大サイズを変更するには、次の操作を行います。
- Web ベースの管理インタフェースで、ConnQueueSize の値を設定または変更します。「HTTP サーバー」、「詳細」、「パフォーマンス」の順に移動してください。
- init.conf の ConnQueueSize 指示を編集します。
警告
接続キューのサイズを大きく設定すると、サーバーのパフォーマンスが低下することがあります。サイズを設定する目的は、サーバーが処理しきれないほどの接続によってオーバーロードが生じることを防ぐことにあります。オーバーロードが生じた場合に接続キューのサイズを大きくすると、要求処理の待ち時間はさらに長くなり、接続キューは再びいっぱいになってしまいます。
Total Connections Queued
Total Connections Queued は、キューに入れられた接続の総数です。これには、新たに受け入れられた接続と、キープアライブシステムからの接続が含まれます。
これは収集された統計情報であり、チューニングできません。
Average Queuing Delay
Average Queuing Delay は、接続が接続キューに入れられていた平均時間を示します。これは、要求された接続をサーバーが受け入れてから、要求処理スレッド (つまりセッション) が要求の処理を開始するまでの時間を意味します。
これは収集された統計情報であり、チューニングできません。
HTTP リスナーの情報
HTTP リスナーの情報には、そのリスナーの IP アドレス、ポート番号、アクセプタスレッドの数、デフォルト仮想サーバーが含まれます。HTTP リスナーの情報の中で、チューニングに最も重要な情報はアクセプタスレッドの数です。
仮想サーバーでは、いくつでもリスナーを待機させることができますが、デフォルトサーバーインスタンス用に少なくとも 1 つを用意する必要があります (通常は http://0.0.0.0:80)。
Http listeners1:
------------------------
Address http://0.0.0.0:1890
Acceptor threads 1
Default virtual server test
チューニング
HTTP リスナーは、Web ベースの管理インタフェースを使って作成および設定できます。詳細は、『Sun ONE Application Server 管理者ガイド』を参照してください。
複数の HTTP リスナーを作成した場合、perfdump はすべてのリスナーに関する情報を出力します。
すべての HTTP リスナーの TCP/IP 待機キューのサイズを設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf の ListenQ パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで「パフォーマンス」ページにアクセスし、「ListenQ」フィールドに値を入力します。
Address
リスナーの待機アドレスです。IP アドレスとポート番号が含まれます。
HTTP リスナーがマシンのすべての IP アドレスで待機している場合は、アドレスの IP 部分は 0.0.0.0 となります。
チューニング
これを設定するときは、待機ソケットを編集します。0.0.0.0 以外の IP アドレスを指定することで、接続ごとにサーバーのシステム呼び出しが 1 つ少なくなります。最大のパフォーマンスを得るには、0.0.0.0 以外の IP アドレスを指定します。
次の図は、管理インタフェースの HTTP リスナーチューニング画面を示しています。
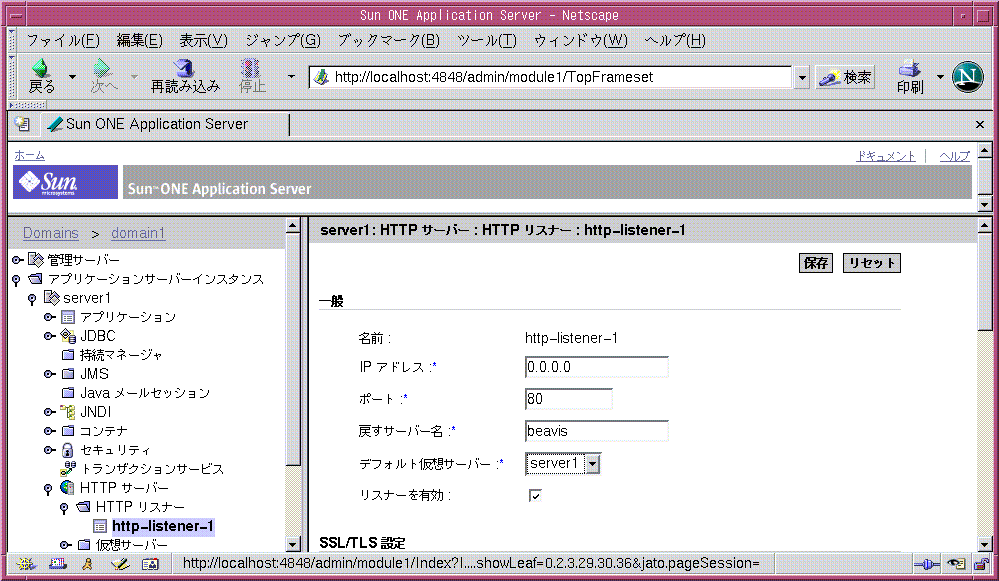
図: 管理インタフェースによる HTTP リスナーのチューニング
Acceptor Threads
Acceptor Threads は、接続を待機するアクセプタスレッドの数を示します。アクセプタスレッドによって受け入れられ、キューに入れられた接続は、ワーカースレッドによって取り出されます。ユーザーからの要求にいつでも対応できるように、常に十分な数のアクセプタスレッドを確保しておくことが理想的ですが、システムに負荷がかかり過ぎない数に抑える必要があります。システムの CPU ごとに 1 つのアクセプタスレッドを用意することをお勧めします。これで TCP/IP 待機キューがいっぱいになるようであれば、CPU の数の 2 倍程度まで値を増やすことができます。
チューニング
アクセプタスレッドの数を変更するときは、「HTTP リスナー」ノードを選択し、右ペインの「詳細」カテゴリでスレッド数を変更します。
次の図は、管理インタフェースのアクセプタスレッドチューニング画面を示しています。
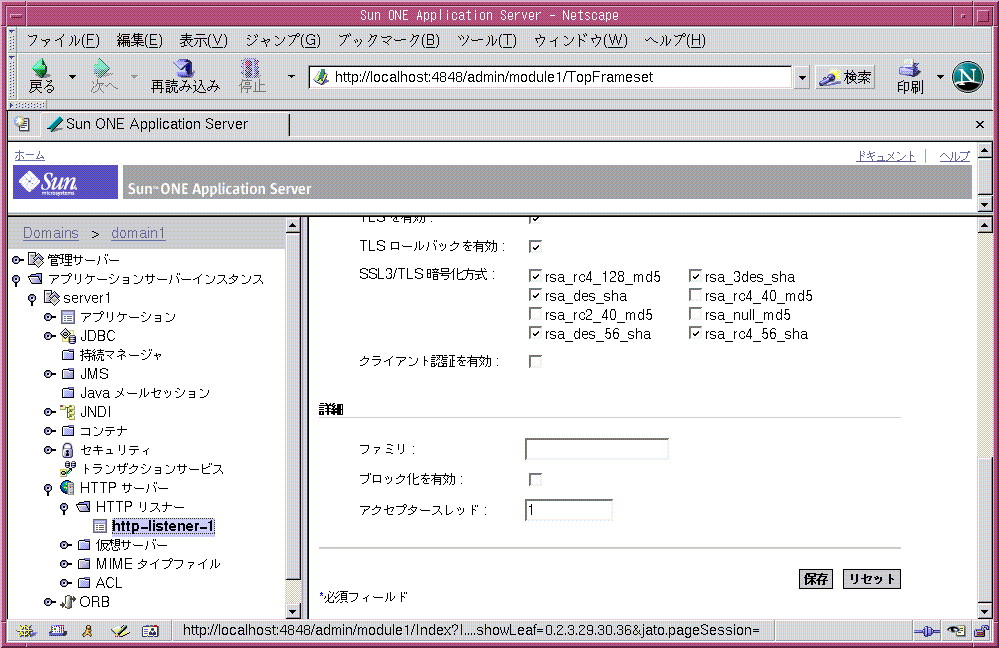
図: 管理インタフェースによるアクセプタスレッドのチューニング
Default Virtual Server
ソフトウェアの仮想サーバーは、HTTP 1.1 Host ヘッダーを使います。エンドユーザーのブラウザがホストヘッダーを送信しない、または指定された仮想サーバーをサーバーが見つけられないときは、Sun ONE Application Server はデフォルトの仮想サーバーを使って要求を処理します。また、ハードウェアの仮想サーバーも、IP アドレスに対応する仮想サーバーをアプリケーションサーバーが見つけられない場合にデフォルトの仮想サーバーを表示します。デフォルトの仮想サーバーを設定して、特定のドキュメントルートからエラーメッセージまたはサーバーページを送信させることができます。
チューニング
待機ソケットおよびサーバーインスタンスのデフォルトの仮想サーバーを指定できます。HTTP リスナーにデフォルトの仮想サーバーが設定されていない場合は、サーバーインスタンスのデフォルト仮想サーバーが使われます。
待機ソケットのデフォルト仮想サーバーは、Web ベースの管理インタフェースを使って設定できます。Web ベースの管理インタフェースで HTTP サーバーの「プリファレンス」タブで「HTTP リスナー」ページにアクセスし、デフォルト仮想サーバーの情報を設定または変更します。「仮想サーバー」をクリックすると、デフォルト仮想サーバーの設定が表示されます。
キープアライブ (持続的) 接続の情報
ここでは、サーバーの HTTP レベルのキープアライブシステムに関する統計について説明します。
次に、perfdump が出力するキープアライブ統計の例を示します。
HTTP 1.0 と HTTP 1.1 は、どちらも 1 つの HTTP セッションによる複数の要求の送信をサポートしています。Web サーバーは、数百もの新規 HTTP 要求を受信できます。すべての要求が接続を開き続けていれば、サーバーは接続でオーバーフローしてしまいます。UNIX または Linux システムでは、これはファイルテーブルのオーバーフローに直結します。
これに対処するために、サーバーは「待ち」状態にあるキープアライブ接続の最大数を一定に維持します。待ち状態のキープアライブ接続は、前回の要求の処理を完了し、同じ接続からの新しい要求を待っています。新しい接続がキープアライブ要求を待つ場合に、開いている接続数がサーバーの最大待ち接続数を超えているときは、サーバーは最も古い接続を閉じます。サーバーが維持する待ち状態のキープアライブ接続の上限は、このアルゴリズムによって一定に保たれます。
Sun ONE Application Server は、クライアントからのキープアライブ要求に常に応じるとは限りません。次の状況では、クライアントがキープアライブ接続を要求する場合にもサーバーは接続を閉じます。
- KeepAliveTimeout が 0 に設定されている
- MaxKeepAliveConnections を超える数の接続が開かれている
- CGI などの動的なコンテンツが HTTP ヘッダーに content-length が設定されていない。これは HTTP 1.0 要求だけに適用されます。HTTP 1.1 要求であれば、content-length が設定されていない場合でもサーバーはキープアライブ要求に対応します。クライアント側でチャンク形式エンコーディングに対応している (要求ヘッダーの transfer-encoding:chunked で識別されます) 場合は、このような要求について、サーバーはこの形式を使います。チャンク形式エンコーディングの詳細は、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
- 要求が HTTP GET または HTTP HEAD でない
- 要求が不正であると識別される。たとえば、クライアントがコンテンツを含まないヘッダーだけを送信した場合などです。
KeepAliveThreads
キープアライブシステムが使うスレッドの数を設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf の KeepAliveThreads パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで、KeepAliveThreads の値を設定または変更します。「HTTP サーバー」、「詳細」タブ、「Keep-Alive」サブメニューの順に移動してください。
KeepAliveCount
ここには次の 2 つの値が出力されます。
- キープアライブモードの接続数
- キープアライブモードの最大同時接続数
チューニング
最も古い接続をサーバーが閉じる前に同時に開くことができる接続の上限値を設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf の MaxKeepAliveConnections パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで、MaxKeepAliveConnections の値を設定または変更します。
注 MaxKeepAliveConnections が指定する接続数は、キープアライブスレッドの間で等分されます。MaxKeeepAliveConnections の値を KeepAliveThreads の値で割り切れないときは、サーバーは実際の MaxKeepAliveConnections の値より若干多めに同時キープアライブ接続を許可します。
KeepAliveHits
キープアライブ状態の接続から正しく受信できた要求の回数です。
これはチューニングできません。
KeepAliveFlushes
KeepAliveCount が MaxKeepAliveConnections を超えているためにサーバーが閉じた接続の数です。
これはチューニングできません。
KeepAliveTimeout
応答のないクライアントとの接続をサーバーが開いた状態で残しておく秒数を表します。Web クライアントは、サーバーへの接続を開いたままにしておくことで、1 つのサーバーに対する複数の要求を 1 つのネットワーク接続だけで処理できます。サーバーが処理できる接続の数には限りがあるため、多数の接続を開いた状態で残しておくと、新しいクライアント接続を開けなくなります。
チューニング
KeepAliveTimeout の設定を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の KeepAliveTimeout パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで、KeepAliveTimeout の値を設定または変更します。
- Web ベースの管理インタフェースで「調整」ページにアクセスし、「HTTP 持続的接続のタイムアウト」フィールドに値を入力します。
KeepAliveQueryMeanTime
これは、KeepAlive サブシステムが処理している接続のポーリング間隔を示します。これを N ミリ秒に設定すると、持続的接続を要求したクライアント側から見て、応答時間のオーバーヘッドは 0 〜 N ミリ秒となります。init.conf ファイルを編集しない場合、この値は 1 ミリ秒に設定されます。並行して行われる KeepAlive 接続の数が 300 程度を上回らない限り、この値で問題ありません。並行負荷がこれを超える場合は、デフォルト値ではスケーラビリティに重大な影響が生じます。このような場合は、適切な値に増やすことをお勧めします。
チューニング
KeepAliveQueryMeanTime の値を変更するときは、init.conf の KeepAliveQueryMeanTime パラメータを編集します。
UseNativePoll
UNIX または Linux システムで最大のパフォーマンスを得るには、このパラメータを有効化する必要があります。
キープアライブシステムのネイティブポールを有効化するときは、Web ベースの管理インタフェースを開き、次の手順を実行します。
- このオプションを有効化するサーバーインスタンスの「HTTP サーバー」ノードを開きます。
- 右ペインの「詳細」タブをクリックします。
- 「Keep-Alive」タブをクリックします。
- UseNativePoll のドロップダウンリストから「ON」を選択します。
- 「OK」をクリックします。
- 左ペインのツリーでサーバーインスタンスを選択します。
- 「変更の適用」をクリックします。
- インスタンスを再起動して変更を反映させます。
次の図は、キープアライブシステムの設定方法を示しています。
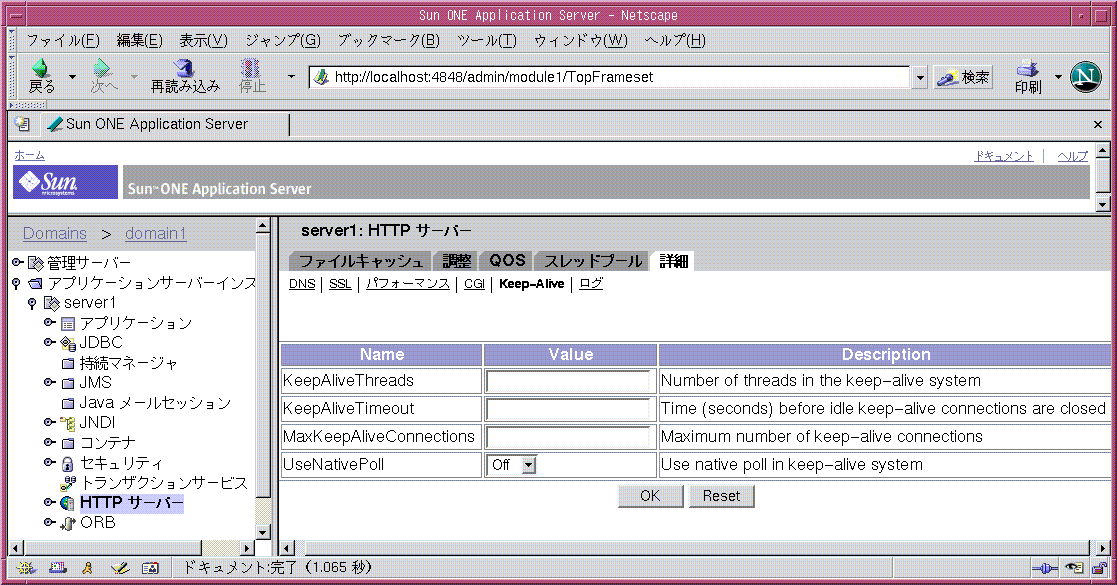
図: 管理インタフェースによるキープアライブ (持続的) 接続のチューニング
セッション作成情報
perfdump では、セッションの作成に関する統計は表示されるだけです。次に、perfdump が表示する SessionCreationInfo の例を示します。
SessionCreationInfo:
------------------------
Active Sessions 1
Total Sessions Created 48/512
Active Sessions は、現在要求を処理しているセッション (要求処理スレッド) の数を示します。
Total Sessions Created は、作成されたセッションの数と、作成可能なセッションの最大数を示します。
設定されているセッション数の最大値に近づくことは、必ずしも問題であるとは言えません。サーバーのセッション数を直ちに増やすような対応は必要ありません。この限界値に達することは、ピーク時にサーバーがそれだけのスレッド数を必要とすることを意味します。要求の処理に遅れがない限り、サーバーは適切にチューニングされていると言えます。ただし、制限値を超えた時点で、接続は接続キューに入れられるため、キューがオーバーフローする可能性は否定できません。perfdump の出力を定期的に確認し、作成されるセッションの総数が頻繁に RqThrottle の値に近づく場合は、この制限値を引き上げることを検討してください。
チューニング
スレッド数の制限値を引き上げる方法は、次のとおりです。
- init.conf の RqThrottle パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで、RqThrottle の値を設定または変更します。
- Web ベースの管理インタフェースで「調整」ページにアクセスし、「最大同時接続」フィールドに値を入力します。
キャッシュ情報
キャッシュ情報のセクションには、ファイルキャッシュがどのように使われているかが示されます。ファイルキャッシュは、サーバーが静的なコンテンツに対する要求を迅速に処理できるように、このようなコンテンツをキャッシュに取り込みます。
perfdump では、キャッシュ統計は次のように表示されます。
CacheInfo:
------------------
enabled yes
CacheEntries 5/1024
Hit Ratio 93/190 ( 48.95%)
Maximum age 30
enabled
キャッシュを無効にすると、このセクションの残りの部分は出力されなくなります。
チューニング
キャッシュは、デフォルトで有効にされています。無効にする方法は次のとおりです。
- Web ベースの管理インタフェースで HTTP サーバーのインスタンスにアクセスし、「ファイルキャッシュ」タブの「ファイルキャッシュ設定」ページで選択を解除します。
- nsfc.conf ファイルの FileCacheEnable パラメータを編集します。詳細は、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
CacheEntries
現在キャッシュされているエントリの数と、キャッシュできるエントリの最大数を示します。1 つのキャッシュエントリは、1 つの URI を表します。
チューニング
キャッシュできるエントリの最大数を設定する方法は、次のとおりです。
- Web ベースの管理インタフェースで HTTP サーバーのインスタンスにアクセスし、「ファイルキャッシュ」タブの「ファイルキャッシュ設定」ページで「最大ファイル数」フィールドに値を入力します。
- nsfc.conf ファイルの MaxFiles パラメータを作成または編集します。詳細は、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
Hit Ratio (キャッシュのヒット回数 / キャッシュのルックアップ回数)
Hit Ratio は、キャッシュのルックアップ回数に対するヒット回数の割合を示します。値が 100% に近づくほどファイルキャッシュが効率的に行われています。反対に、0% に近づくほどファイルキャッシュが処理している要求が少ないことを意味します。
これはチューニングできません。
Maximum Age
Maximum Age は、有効なキャッシュエントリの最大生存期間を示します。このパラメータは、ファイルをキャッシュした後に、その情報をいつまで使用できるかを制御します。Maximum Age より古いエントリは、同じファイルの新しいエントリに置き換えられます。
チューニング
Web サイトのコンテンツが頻繁に更新されない場合は、大きな値を設定することでパフォーマンスを向上できます。Maximum Age を設定する方法は、次のとおりです。
- Web ベースの管理コンソールで HTTP サーバーのノードにアクセスし、「ファイルキャッシュ」タブの「ファイルキャッシュ設定」ページで「最長有効期間」フィールドに値を入力するか、値を変更します。
- nsfc.conf ファイルの MaxAge パラメータを編集します。詳細は、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
次の図は、管理インタフェースのファイルキャッシュシステム設定画面を示しています。
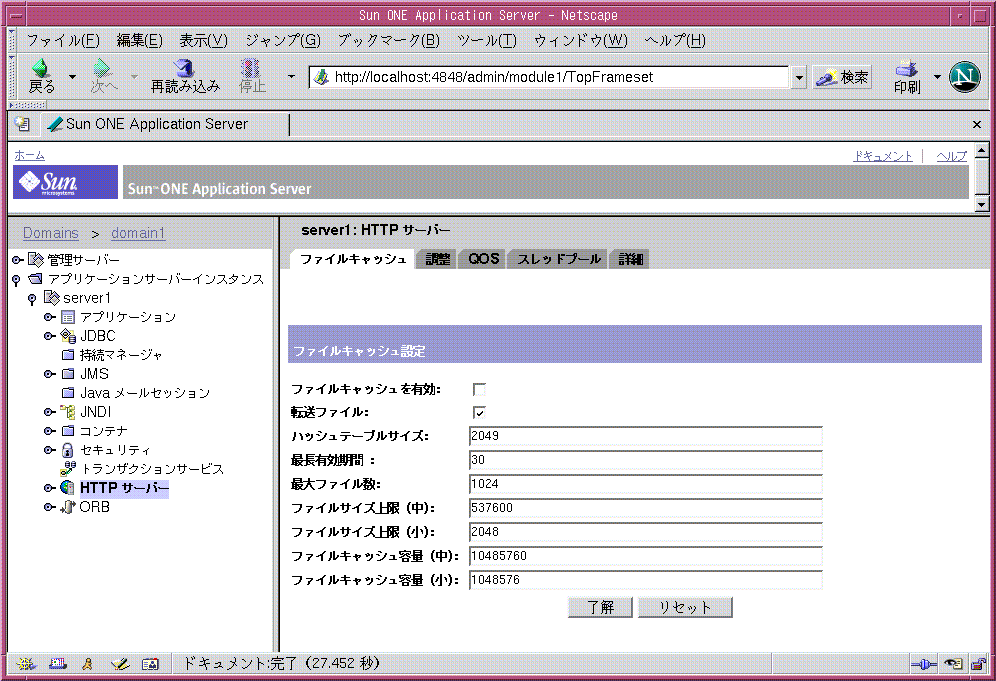
図: 管理インタフェースによるファイルキャッシュ情報のチューニング
スレッドプール
次の図は、管理インタフェースのスレッドプール設定画面を示しています。
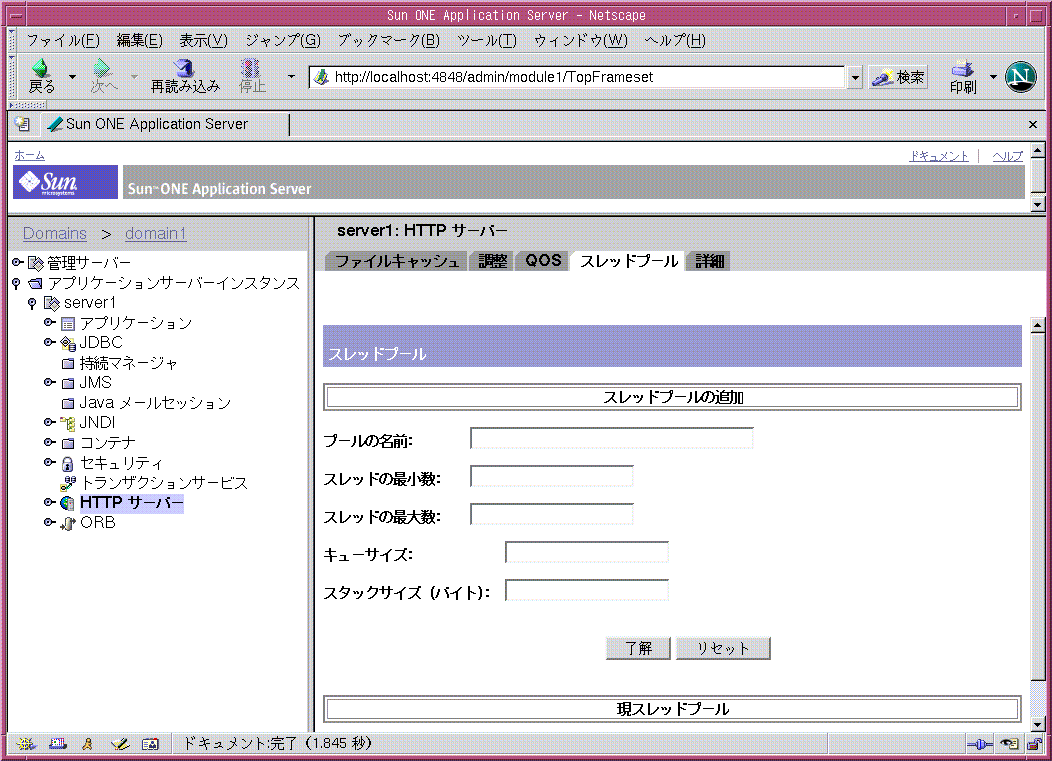
図: 管理インタフェースによるスレッドプールのチューニング
Web ベースの管理インタフェースでは、3 種類のスレッドプールを設定できます。
- スレッドプール (UNIX/Linux)
- ネイティブスレッドプール (NT)
- 汎用スレッドプール (NT)
スレッドプール (UNIX/Linux のみ)
UNIX または Linux 環境では、スレッドは常にオペレーティングシステム (OS) によってスケジュールされます。ユーザーによるスケジュールは行われないため、この環境ではネイティブスレッドプールを使う必要がありません。従って、UNIX または Linux のユーザーインタフェースでは、このオプションは提供されません。しかし、Web ベースの管理インタフェースを使うことで、必要に応じて OS がスケジュールしたスレッドプールを編集したり、新しいスレッドプールを追加することができます。
ネイティブスレッドプール (NT のみ)
NT 環境では、ネイティブスレッドを必要とする NSAPI 機能を実行するときに、サーバーは内部的にネイティブスレッドプール (NativePool) を使います。
Native pools:
----------------------------
NativePool:
Idle/Peak/Limit 1/1/128
Work queue length/Peak/Limit 0/0/0
Windows NT ユーザーは、Web ベースの管理インタフェースを使ってネイティブスレッドプールの設定を変更できます。
Sun ONE Application Server は、ホスト OS のサービにアクセスするために、基本的な移植層として NSPR を使います。この層では、OS から提供されるスレッドとは異なる可能性があるスレッドが抽象化されます。これらの非ネイティブスレッドではスケジュールのオーバーヘッドが低いため、これを利用することでパフォーマンスを向上できます。ただしこれらのスレッドは、I/O 呼び出しなどの OS のブロック呼び出しに反応します。ブロック呼び出しを利用できる NSAPI 拡張機能を簡単に記述できるように、サーバーはブロック呼び出しを安全にサポートするスレッドのプールを維持しています。これは、通常は OS スレッドを意味します。要求の処理時に、非ネイティブスレッドでの実行の安全性が印されていないすべての NSAPI 機能は、ネイティブスレッドプールに含まれるいずれかのスレッドで実行するようにスケジュールされます。
NameTrans、Service、PathCheck 機能などの NSAPI プラグインを独自に作成したときは、デフォルトではこれらのプラグインはネイティブスレッドプールに含まれるスレッドで実行されます。作成したプラグインが I/O に NSAPI 機能を明示的に使用する場合、または NSAPI の I/O 機能をまったく使用しない場合は、非ネイティブスレッドで実行することができます。この場合は、ネイティブスレッドが不要であることを示すために、NativeThread="no" オプションを使って機能をロードする必要があります。
この処理を行うには、init.conf ファイルの "load-modules" Init 行に次の行を追加します。
Init funcs="pcheck_uri_clean_fixed_init" shlib="C:/Netscape/p186244/P186244.dll" fn="load-modules" NativeThread="no"
NativeThread フラグは funcslist のすべての機能に影響するため、ライブラリに含まれる複数の機能のうち一部だけがネイティブスレッドを使う場合は、別の Init 行を使います。
汎用スレッドプール (NTのみ)
NT 環境では、Web ベースの管理コンソールを使って追加のスレッドプールを設定できます。スレッドプールを使うことで、サービス機能が一度に処理できる要求の最大数に制限を設けることができます。追加のスレッドプールは、thread-unsafe プラグインの実行に使われます。プールの最大スレッド数を 1 に設定すると、指定されたサービス機能で許可される要求の数が 1 つに制限されます。
Idle/Peak/Limit
Idle は、現在アイドル状態にあるスレッドの数を示します。Peak は、実際にプールに入れられたスレッドの最大数を示します。Limit は、スレッドプールに入れることができるネイティブスレッドの最大値を示します。この値は、NativePoolMaxThreads の設定によって決定されます。
チューニング
NativePoolMaxThreads を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の NativePoolMaxThreads パラメータを編集します。
- 管理インタフェースで HTTP サーバーのノードにアクセスし、「スレッドプール」タブの「Native スレッドプール」ページにある「スレッドの最大数」フィールドに値を入力するか、値を変更します。
Work Queue Length /Peak /Limit
これらの値は、プールに含まれるネイティブスレッドの使用を待つサーバー要求の数を示します。Work Queue Length は、ネイティブスレッドを待つ要求の現在の数を示します。
Peak は、サーバーの起動後にネイティブスレッドの使用を待つために同時にキューに入れられていた要求の最大数を示します。この値は、ネイティブスレッドを必要とする要求の最大並行性とみなすことができます。
Limit は、ネイティブスレッドを待つ要求を一度にキューにいれておける最大数を示します。この値は、NativePoolQueueSize の設定によって決定されます。
チューニング
NativePoolQueueSize を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の NativePoolQueueSize パラメータを編集します。
- 管理インタフェースで HTTP サーバーのノードにアクセスし、「スレッドプール」タブの「Native スレッドプール」ページにある「キューサイズ」フィールドに値を入力するか、値を変更します。
NativePoolStackSize (NT のみ)
NativePoolStackSize は、ネイティブ (カーネル) スレッドプールのスレッドごとのスタックサイズを指定します。
チューニング
NativePoolStackSize を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の NativePoolStackSize パラメータを編集します。
- Web ベースの管理コンソールで HTTP サーバーのノードにアクセスし、「詳細」タブの「パフォーマンス」サブメニューで NativePoolStackSize の値を設定するか、値を変更します。
NativePoolQueueSize (NT のみ)
NativePoolQueueSize は、キューでスレッドプールを待機するスレッドの数を指定します。プールのスレッドがすべてビジー状態の場合、次の要求処理スレッドはネイティブプールのスレッドが空くまでキューで待機します。キューが満杯の場合は次の要求処理スレッドがキューに入ろうとしても拒否され、クライアントにはビジー応答が返されます。その後、スレッドは解放され、キューで待機状態になっていた要求を処理します。
NativePoolQueueSize の値を RqThrottle より小さく設定すると、プールスレッドからのサービスを待つ要求の数がこの値に達したときに、サーバーは本来の NSAPI 機能を実行せずに、ビジー機能を実行します。デフォルトでは「503 Service Unavailable」が返され、LogVerbose が有効であればメッセージが記録されます。NativePoolQueueSize の値を RqThrottle より大きく設定すると、ビジー機能を実行する前にサーバーは接続を拒否します。
この値は、ネイティブスレッドを必要とするサービスの最大同時要求数を表します。負荷によってシステムが要求を処理できない場合にキューに入れられる要求の数を増やすと、要求の処理を開始するまでの時間が長くなり、要求の処理に利用できるすべてのスレッドがネイティブスレッドを待つことになりかねません。ネイティブスレッドが必要な要求を実行するユーザーの並行最大数を設定することで、この値には、通常は要求が拒否されないように十分な値を設定します。
この値と RqThrottle では、静的な HTML ファイルや画像ファイルなど、非ネイティブスレッド要求のために予約されている要求の数が異なります。予約を維持して要求を拒否することで、サーバーは静的なファイルに対する要求にも対応し続けることができます。こうすることで、動的なコンテンツのロードによって負荷が極端に大きくなる状況でも、サーバーが応答不能になることはありません。サーバーが接続拒否を続けがちなときは、この値が小さすぎるか、サーバーハードウェアがオーバーロードしています。
チューニング
NativePoolQueueSize を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の NativePoolQueueSize パラメータを編集します。
NativePoolMaxThreads (NT のみ)
NativePoolMaxThreads は、ネイティブ (カーネル) スレッドプールの最大スレッド数を指定します。
大きな値を設定すると、より多くの要求を同時に処理できますが、コンテキストの切り替えが必要となるため、オーバーヘッドは増えます。通常は、この値を変更する必要はありませんが、CPU の利用率が飽和状態ではなく、要求がキューに入れられる状況ではこの値を大きめに設定します。
チューニング
NativePoolMaxThreads の値を変更するときは、init.conf の NativePoolMaxThreads パラメータを編集します。
NativePoolMinThreads (NT のみ)
ネイティブ (カーネル) スレッドプール内のスレッドの最小数を指定します。
チューニング
NativePoolMinThreads を変更する方法は、次のとおりです。
- init.conf の NativePoolMinThreads パラメータを編集します。
- Web ベースの管理コンソールで HTTP サーバーのノードにアクセスし、「詳細」タブの「パフォーマンス」サブメニューで NativePoolMinThreads の値を設定するか、値を変更します。
DNS キャッシュ情報
DNS キャッシュは、IP アドレスと DNS 名をキャッシュに取り込みます。デフォルトでは、サーバーの DNS キャッシュは無効に設定されています。Web ベースの管理インタフェースの「調整」にある「性能の調整」には、次の統計が表示されます。
enabled
DNS キャッシュが無効な状態では、このセクションの残りの部分は出力されなくなります。
チューニング
デフォルトでは、DNS キャッシュは無効に設定されています。DNS キャッシュを有効化する方法は、次のとおりです。
- init.conf に次の行を追加します。
Init fn=dns-cache-init
- Web ベースの管理インタフェースを使って、「サーバーへアクセスするクライアントを DNS 検索」に値を設定します。
CacheEntries (現在のキャッシュエントリ / キャッシュエントリの最大値)
現在キャッシュされているエントリの数と、キャッシュできるエントリの最大数を示します。1 つのキャッシュエントリは、IP アドレスまたは DNS 名の 1 回のルックアップを意味します。キャッシュは、Web サイトに同時にアクセスするクライアントの最大数に対応できるサイズに設定します。キャッシュに大きすぎる値を設定すると、メモリが無駄になり、パフォーマンスが低下します。
チューニング
DNS キャッシュの最大サイズを設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf に次の行を追加します。
Init fn=dns-cache-init cache-size=1024
デフォルトのキャッシュサイズは 1024 です。
- Web ベースの管理インタフェースで「調整」ページにアクセスし、「DNS キャッシュサイズ」フィールドに値を入力するか、値を変更します。
HitRatio (キャッシュのヒット数 / キャッシュのルックアップ回数)
HitRatio は、キャッシュのルックアップ回数に対するキャッシュのヒット回数の割合を示します。
これはチューニングできません。
注 サーバーの DNS ルックアップを無効にすると、ホスト名の制限が機能しなくなり、ログファイルにホスト名が記録されなくなります。代わりに、IP アドレスが記録されます。
DNS エントリのキャッシング
DNS エントリをキャッシュするかどうかも指定できます。DNS キャッシュを有効にすると、ホストは一度受信したホスト名を格納できるようになります。その後、サーバーがそのクライアントに関する情報を必要とする場合、クエリーを実行することなく、キャッシュされている情報を利用できます。DNS キャッシュのサイズ、およびDNS キャッシュエントリの有効期限を設定することができます。DNS キャッシュには 32 〜 32768 のエントリを保存できます。デフォルト値は 1024 エントリです。キャッシュエントリの有効期限は 1 秒から 1 年の範囲で秒単位で指定できます。デフォルト値は 1200 秒 (20 分) です。
DNS ルックアップの非同期への限定
サーバープロセスでの DNS ルックアップはリソースを多く消費するので、使用しないことをお勧めします。DNS ルックアップを含める必要があるときは、非同期にしてください。
enabled
非同期 DNS を無効にすると、このセクションの残りの部分は出力されなくなります。
チューニング
非同期 DNS を有効化する方法は、次のとおりです。
- init.conf ファイルに AsyncDNS ON というエントリを追加します。
- Web ベースの管理インタフェースで、AsyncDNS の値をON に設定します。
- サーバーマネージャの「プリファレンス」で「調整」の「非同期 DNS を有効」を選択します。
NameLookups
サーバーを起動してから名前ルックアップ (DNS 名による IP アドレスの検索) を実行した回数を示します。
これはチューニングできません。
AddrLookups
サーバーを起動してからアドレスルックアップ (IP アドレスによる DNS 名の検索) を実行した回数を示します。
これはチューニングできません。
LookupsInProgress
現在実行中のルックアップの数を示します。
これはチューニングできません。
次の図は、管理インタフェースの DNS キャッシュ情報設定画面を示しています。
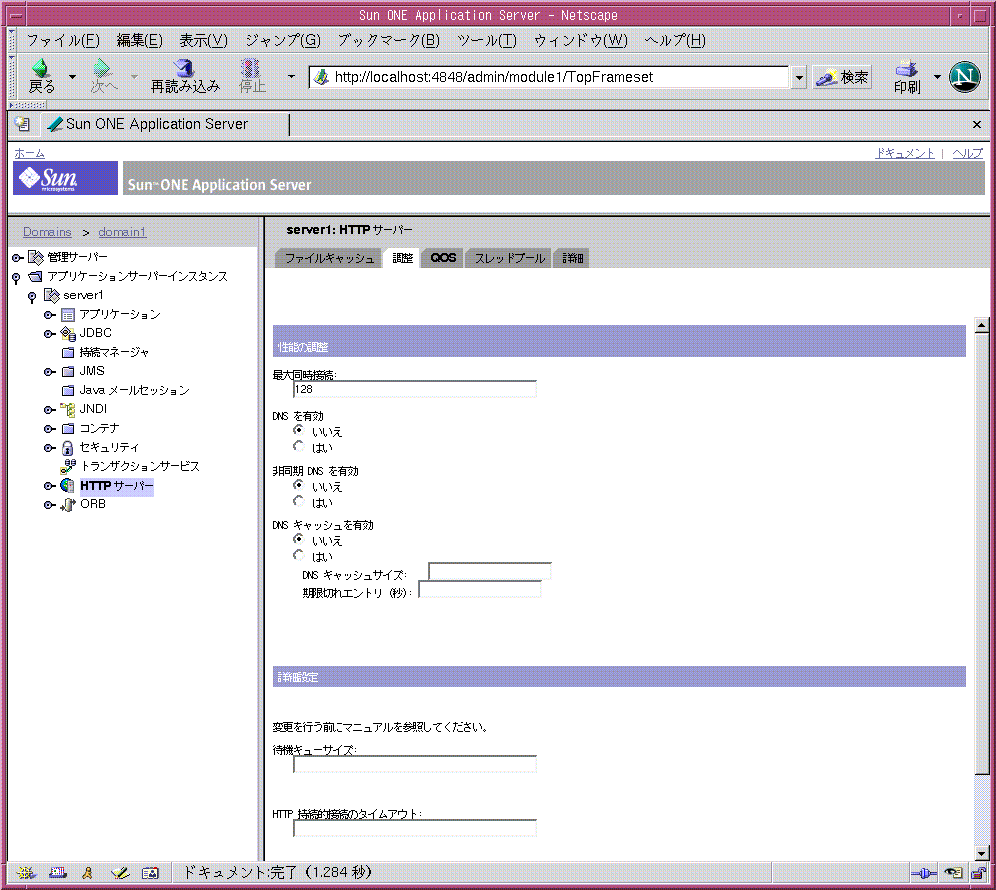
図: 管理インタフェースによる DNS キャッシュ情報のチューニング
ビジー機能
ビジー機能は、デフォルトでは「503 Service Unavailable」を返し、LogVerbose が有効であればメッセージを記録します。アプリケーションによっては、この動作を変更する必要があります。パフォーマンスに関するトラブルシューティングを効率的に行うには、NSAPI 機能について独自のビジー機能を <instancename>-obj.conf ファイルに設定すると便利です。この場合は、次の形式で設定ファイルにサービス機能を追加します。
busy="<my-busy-function>"
たとえば、次のようにサービス機能を設定します。
Service fn="send-cgi" busy="service-toobusy"
これにより、サーバーが要求の処理時に過度なビジー状態になった場合は、異なる応答 (Service、AddLog、PathCheck など) を返すことができます。独自のビジー機能は、デフォルトのスレッドタイプが非ネイティブな場合に、ネイティブスレッドを必要とするすべての機能に適用されます。
デフォルトのビジー機能ではない独自のビジー機能をサーバー全体で使用するときは、次のように、func_insert 呼び出しを含む NSAPI の init 機能を記述します。
extern "C" NSAPI_PUBLIC int my_custom_busy_function(pblock *pb, Session *sn, Request *rq);
my_init(pblock *pb, Session *, Request *)
{
func_insert("service-toobusy", my_custom_busy_function);
}
ビジー機能はプールスレッドでは実行されないため、スレッドのブロックを生じる機能呼び出しを行わないように注意してください。
パフォーマンスバケットの使用
パフォーマンスバケットを使うことで、バケットを定義し、それをさまざまなサーバー機能と関連づけることができます。いずれかの機能が呼び出されると、サーバーは統計データを収集し、それをバケットに追加します。たとえば、send-cgi と NSServletService は、それぞれ CGI 要求と Java サーブレット要求を処理します。CGI 要求とサーブレット要求のそれぞれにバケットを定義してカウンタを独立させることも、1 つのバケットを作成して動的なコンテンツである両方の要求に対応することもできます。この情報収集に要するリソースの消費は少ないので、通常はサーバーのパフォーマンスに与える影響を無視できます。バケットには、次の情報が記録されます。
- バケット名: バケットと機能の関連づけにはこの名前が使われます。
- 記述: バケットに関連づけられている機能の説明です。
- この機能の要求数: この機能が呼び出された合計回数です。
- この機能の実行回数: 一部の機能は 1 回の要求で複数回実行されるため、この値は機能の要求回数と一致しないことがあります。
- 機能の応答時間またはディスパッチ時間: サーバーが機能を実行するまでにかかった時間です。
- 機能に要する時間: 機能の完了までにかかった時間です。
default-bucket は、事前にサーバーに定義されています。これは、ユーザー定義のバケットに関連づけられていない機能の統計を記録します。
設定
パフォーマンスバケットのすべての設定情報は、init.conf ファイルと <instancename>-obj.conf ファイルに設定します。自動的に有効化されるのはデフォルトバケットだけです。
次の例は、init.conf に新しいバケットを定義する方法を示しています。
Init fn="define-perf-bucket" name="acl-bucket" description="ACL bucket"
Init fn="define-perf-bucket" name="file-bucket" description="Non-cached responses"
Init fn="define-perf-bucket" name="cgi-bucket" description="CGI Stats"
上の例では、acl-bucket、file-bucket、cgi-bucket という 3 つのバケットが作成されます。これらのバケットを機能に関連づけるときは、obj.conf ファイルを開き、パフォーマンスを測定する機能 bucket=bucket-name を追加します。次に例を示します。
PathCheck fn="check-acl" acl="default" bucket="acl-bucket"
...
Service method="(GET|HEAD|POST)" type="*~magnus-internal/*" fn="send-file" bucket="file-bucket"
...
<Object name="cgi">
ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/cgi"
Service fn="send-cgi" bucket="cgi-bucket"
</Object>パフォーマンスレポート
パフォーマンスバケットに関する情報は、perfdump が出力するレポートの最後に含まれます。
詳細は、「stats-xml による統計の有効化」および「パフォーマンスバケットの使用」を参照してください。
レポートには、次の情報が含まれます。
- 「Avarage」、「Total」、「Percent」列は、各要求の統計データを示します。
- 「Request Processing Time」は、これまでにサーバーが受信したすべての要求の処理にかかった合計時間を示します。
- 「Number of Requests」は、その機能が要求された合計回数を示します。
- 「Number of Invocations」は、その機能が実際に実行された合計回数を示します。一部の機能では、1 つの要求の処理で複数回実行されるため、この値は機能の要求回数と異なることがあります。この行のパーセント値を示す列は、すべてのバケットに記録されている実行回数の合計に対する、その機能の実行回数の割合を示します。
- 「Latency」は、Sun ONE Application Server がその機能を呼び出すまでにかかった時間を秒単位で示します。
- 「Function Processing Time」は、Sun ONE Application Server がその機能の実行に要した時間を秒単位で示します。「Function Processing Time」と「Total Response Time」のパーセントの値は、「Request Processing Time」に対するそれぞれの割合を示します。
- 「Total Response Time」は、「Function Processing Time」と「Latency」の合計で、単位は秒です。
次に、perfdump から出力されるパフォーマンスバケット情報の例を示します。
Performance Counters:
------------------------------------------------
Average Total Percent
Total number of requests: 474851
Request processing time: 0.0010 485.3198
Default Bucket (default-bucket)
Number of Requests: 597 ( 0.13%)
Number of Invocations: 9554 ( 1.97%)
Latency: 0.0000 0.1526 ( 0.03%)
Function Processing Time: 0.0256 245.0459 ( 50.49%)
Total Response Time: 0.0257 245.1985 ( 50.52%)
ファイルキャッシュの設定
Sun ONE Application Server は、静的な情報を迅速に処理するため、ファイルキャッシュを使用します。ファイルキャッシュには、ファイルに関する情報と静的なファイルコンテンツが含まれます。ファイルキャッシュには、サーバー解析 HTML の処理を高速化するために使用する情報も格納されます。
ファイルキャッシュはデフォルトで有効になっています。ファイルキャッシュの設定情報は、nsfc.conf ファイルに格納されています。Web ベースの管理インタフェースを使って、ファイルキャッシュの設定を変更することができます。
次の図は、管理インタフェースのファイルキャッシュ設定画面を示しています。
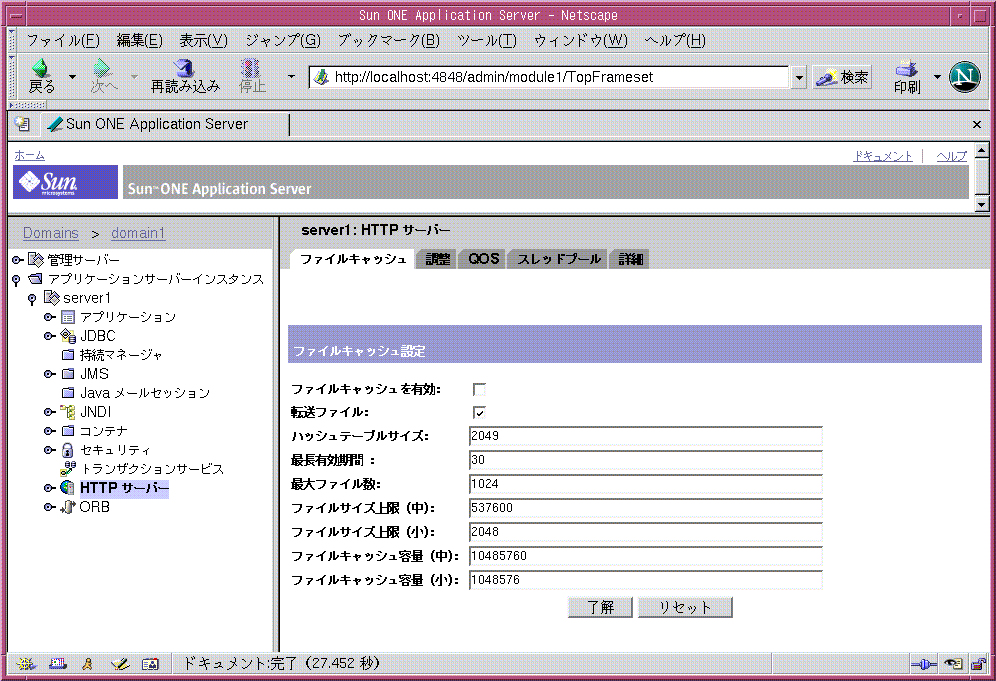
図: 管理インタフェースによるファイルキャッシュのチューニング
ファイルキャッシュを設定するには、次の手順を実行します。
- HTTP サーバーの「ファイルキャッシュ」タブを選択します。
- 「ファイルキャッシュを有効」にチェックマークがつけられていない場合は、これを選択します。
- ファイルを転送するかどうかを選択します。
「転送ファイル」を有効にすると、サーバーはファイルの内容ではなく、開いているファイル記述子をファイルキャッシュに取り込みます。クライアントへのファイルコンテンツの送信には、PR_TransmitFile が使われます。「転送ファイル」が有効な場合、開いているファイル記述子だけがキャッシュされるので、通常は区別されるファイルのサイズの違いがファイルキャッシュに適用されなくなります。デフォルトでは、「ファイル転送」は NT では有効、UNIX では無効に設定されています。UNIX では、OS が PR_TransmitFile をネイティブサポートしているプラットフォームでは「ファイル転送」を有効化します。現時点では、HP-UX と AIX がこれに含まれます。その他の UNIX または Linux プラットフォームで有効にすることはお勧めできません。
- ハッシュテーブルのサイズを入力します。
デフォルトのサイズは、ファイルの最大数の 2 倍に 1 を加えた数です。たとえば、ファイルの最大数が 1024 の場合、デフォルトのハッシュテーブルサイズは 2049 となります。
- キャッシュエントリの最長有効期間を秒単位で入力します。
デフォルトでは、30 分に設定されます。
この設定により、ファイルがキャッシュされてから、キャッシュされた情報がどれだけ長く使用されるかが制御されます。MaxAge より古いエントリは、同じファイルがキャッシュから参照されるときに、そのファイルの新しいエントリに置き換えられます。
最長期間を設定するときは、ファイル内容の更新 (既存ファイルの修正) が規則的なスケジュールで行われるかどうかを基準にします。たとえば、コンテンツを 1 日に 4 回等間隔で更新する場合は、最長期間を 21600 (6 時間) に設定します。それ以外の場合は、更新してからその内容を最も長く使用するコンテンツファイルに合わせて最長期間を設定します。
- キャッシュするファイルの最大数を「最大ファイル数」に入力します。
デフォルトでは、1024 分に設定されます。
- 中と小のファイルサイズ上限をバイト単位で指定します (UNIX/Linux のみ)。
デフォルトでは、「ファイルサイズ上限 (中)」は525000 (525 キロバイト) に設定されています。
デフォルトでは、「ファイルサイズ上限 (小)」は2048に設定されています。
キャッシュの動作は、ファイルサイズの大、中、小に応じて異なります。「中規模」のファイルの内容は、ファイルを仮想メモリにマッピングするでキャッシュされます (UNIX/Linux プラットフォーム)。「小さい」ファイルの内容は、ヒープ領域を割り当て、ファイルをそのヒープ領域に読み込むことでキャッシュされます。「大きな」ファイル (「中」より大きなファイル) の場合、ファイルに関する情報はキャッシュされますが、その内容はキャッシュされません。
小規模なファイルと中規模なファイルを区別することで、小規模なファイルが多い場合に仮想メモリのページを無駄にすることがなくなります。このため、通常は VM ページのサイズより若干少ない容量を「ファイルサイズ上限 (小)」に設定します。
- 中規模と小規模のファイルキャッシュ容量を設定します (UNIX/Linux のみ)。
中規模ファイルの領域は、すべての中規模サイズのファイルをマップするために使用する仮想メモリのサイズ (バイト単位) となります。デフォルトでは、10000000 (10 メガバイト) に設定されます。
小規模ファイルの領域は、小さいファイルをキャッシュするために使用するヒープ領域を含めて、キャッシュに使用するヒープ領域のサイズ (バイト単位) となります。UNIX または Linux 環境では、この値はデフォルトで 1 メガバイトに設定されます。
- 「了解」をクリックします。
- 「適用」をクリックします。
- 「変更の適用」をクリックしてサーバーを再起動します。
nocache パラメータの使用
send-file サービス機能の nocache パラメータを使って、特定のディレクトリに含まれるファイルをキャッシュしないように設定できます。たとえば、キャッシュの有用性を欠くほど頻繁に更新するファイルがある場合は、そのファイルを特定のディレクトリに保存し、<instancename>-obj.conf ファイルを編集してサーバーがそのディレクトリ内のファイルをキャッシュしないように設定します。
次に例を示します。
<Object name=default>
...
NameTrans fn="pfx2dir" from="/myurl" dir="/export/mydir" name="myname"
...
Service method=(GET|HEAD|POST) type=*~magnus-internal/* fn=send-file
...
</Object>
<Object name="myname">
Service method=(GET|HEAD) type=*~magnus-internal/* fn=send-file nocache=""
</Object>
上の例では、/myurl というプレフィックスを持つ URL から要求された場合に、サーバーは /export/mydir/ ディレクトリに含まれる静的なファイルをキャッシュしません。
ファイルキャッシュの動的な制御と監視
次のように、<instancename>-obj.conf ファイルにオブジェクトを追加することで、サーバーの稼働中に nsfc.conf ファイルキャッシュを動的に監視および制御することができます。
デフォルトオブジェクトに NameTrans 指示を追加します。
NameTrans fn="assign-name" from="/nsfc" name="nsfc"
オブジェクト定義 nsfc を追加します。
<Object name="nsfc">
Service fn=service-nsfc-dump
</Object>これにより、/nsfc という URI からアクセスされるファイルについて、ファイルキャッシュの制御と監視の機能 (nsfc-dump) が有効化されます。NameTrans 指示の from パラメータの値を変更することで、別の URI も指定できます。
次の例は、この URI にアクセスした場合に表示される情報を示しています。
Sun ONE Application Server File Cache Status (pid 7960)
The file cache is enabled.
Cache resource utilization
Number of cached file entries = 1039 (112 bytes each, 116368 total bytes)
Heap space used for cache = 237641/1204228 bytes
Mapped memory used for medium file contents = 5742797/10485760 bytes
Number of cache lookup hits = 435877/720427 ( 60.50 %)
Number of hits/misses on cached file info = 212125/128556
Number of hits/misses on cached file content = 19426/502284
Number of outdated cache entries deleted = 0
Number of cache entry replacements = 127405
Total number of cache entries deleted = 127407
Number of busy deleted cache entries = 17
Parameter settings
HitOrder:false
CacheFileInfo:true
CacheFileContent:true
TransmitFile:false
MaxAge:30 seconds
MaxFiles: 1024 files
SmallFileSizeLimit: 2048 bytes
MediumFileSizeLimit: 537600 bytes
CopyFiles:false
Directory for temporary files: /tmp/netscape/https-axilla.mcom.com
Hash table size: 2049 buckets
/nsfc という URI にアクセスするときに、クエリ文字列を含めることができます。認識される値は次のとおりです。
- ?list - キャッシュに含まれるファイルをリスト表示します。
- ?refresh=n - クライアントに n 秒ごとにページを再読み込みさせます。
- ?restart - キャッシュを終了し、開始し直します。
- ?start - キャッシュを開始します。
- ?stop - キャッシュを終了します。
?list オプションを設定したときに表示される情報は、ファイル名、フラグの設定、キャッシュエントリに対する現在の参照回数、ファイルサイズ、内部ファイル ID の値です。フラグには次の種類があります。
- C - ファイルのコンテンツがキャッシュされています。
- D - キャッシュエントリに削除の印がつけられています。
- E - このファイルについて PR_GetFileInfo() がエラーを返しています。
- I - ファイルに関する情報 (サイズ、更新日時など) がキャッシュされています。
- M - ファイルのコンテンツが仮想メモリにマッピングされています。
- O - ファイル記述子がキャッシュされています (TransmitFile が true に設定されている場合)。
- P - ファイルがプライベートデータに関連づけられています (shtml ファイルで表示されます)。
- T - キャッシュエントリに一時ファイルがあります。
- W - キャッシュエントリへの書き込みアクセスが禁止されています。
コンテンツの更新がスケジュールされているサイトでは、コンテンツの交信中はキャッシュを停止し、更新完了後に開始し直します。パフォーマンスは低下しますが、キャッシュがオフでもサーバーは通常どおりに機能します。
ACL ユーザーキャッシュのチューニング
デフォルトでは、ACL ユーザーキャッシュは ON に設定されています。キャッシュのデフォルトサイズ (200 エントリ) により、ACL ユーザーキャッシュがボトルネックになったり、トラフィックの多いサイトではキャッシュが機能しないことがあります。アクセスの多いサイトでは、キャッシュエントリのライフタイムが終わるまでに ACL 保護されたリソースに対して 200 以上のユーザーがアクセスすることもあります。このような状況では、Sun ONE Application Server はユーザーを検証するために LDAP サーバーに頻繁にクエリを送信しなければならず、これがパフォーマンスに影響します。
このボトルネックを回避するには、init.conf の ACLUserCacheSize 指示を使って ACL キャッシュのサイズを増やします。キャッシュサイズを大きくすると、その分だけキャッシュを保持するための RAM も必要になることに注意してください。
また、キャッシュエントリに格納できるグループの数 (デフォルトでは 4) がボトルネックになることもあります (ただし、可能性は高くありません)。ユーザーが 5 つのグループに所属し、ACL キャッシュのライフタイム中に 5 つの異なるグループに対して確認が必要となる 5 つの ACL にアクセスした場合は、追加のグループエントリ用にキャッシュエントリを作成する必要が生じます。2 つのキャッシュエントリがある場合、元のグループ情報を格納したエントリは無視されます。
パフォーマンスに関するこのような問題が生じることは極めてまれですが、1 つの ACL キャッシュエントリに格納できるグループ数を変更するときは、ACLGroupCacheSize 指示を使います。
ACL ユーザーキャッシュ指示
ACL ユーザーキャッシュの値を変更するときは、通常は init.conf ファイルに次の指示を手動で追加します。
- ACLCacheLifetime
- ACLUserCacheSize
- ACLGroupCacheSize
ACLCacheLifetime
この指示には、キャッシュエントリの有効期間を秒単位で設定します。キャッシュのエントリが参照されるたびに、経過時間が計算され ACLCacheLifetime と照合されます。経過時間が ACLCacheLifetime 以上の場合、このエントリは使用されません。デフォルト値は 120 秒です。この値を 0 にすると、キャッシュが無効になります。この値を大きくすると、LDAP エントリを変更した場合に Sun ONE Application Server の再起動が必要になることがあります。たとえば 120 秒に設定すると、Sun ONE Application Server は 2 分間 LDAP サーバーと同期が取れなくなる可能性があります。LDAP が頻繁に変更されない場合は、大きな値を設定できます。
ACLUserCacheSize
この指示には、ユーザーキャッシュのサイズをエントリ数単位で設定します (デフォルトは 200)。
ACLGroupCacheSize
この指示には、1 つの UID またはキャッシュエントリにキャッシュできるグループ ID の数を設定します (デフォルトは 4)。
ACL ユーザーキャッシュ設定の確認
LogVerbose を使うことで、使用中の ACL ユーザーキャッシュの設定を確認できます。LogVerbose を実行している場合は、サーバー起動時のエラーログに次のようなメッセージが記録されます。
User authentication cache entries expire in ### seconds.
User authentication cache holds ### users.
Up to ### groups are cached for each cached user.
チューニング
LogVerbose を ON にするときは、init.conf の LogVerbose パラメータを編集します。
警告
本稼働環境で LogVerbose を ON にしないでください。パフォーマンスが低下し、エラーログのサイズが大きくなります。
サービス品質機能の使用
サービス品質機能を使うことで、サーバーインスタンス、仮想サーバーのクラス、または個々の仮想サーバーの帯域幅と接続数を制限できます。パフォーマンスに関するこれらの制限を設定し、結果を追跡してからオプションとして実行することができます。
次の図は、管理インタフェースのサービス品質設定画面を示しています。
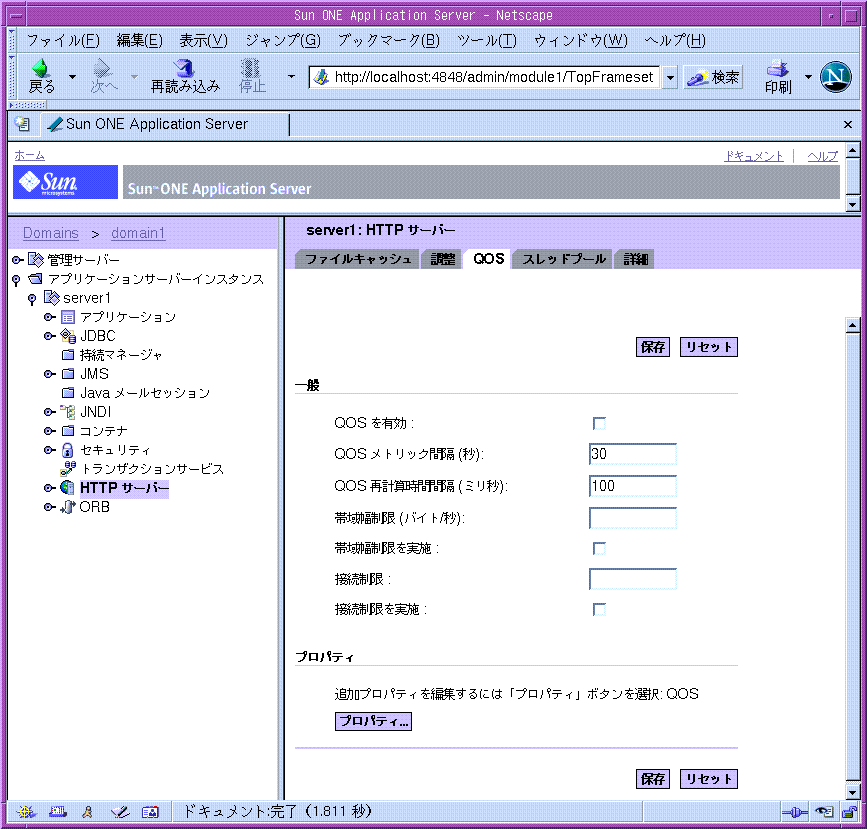
図: 管理インタフェースによるサービス品質のチューニング
詳細は、『Sun ONE Application Server 管理者ガイド』の「サービス品質の使用」を参照してください。
スレッド、プロセス、および接続
Sun ONE Application Server では、HTTP リスナーのアクセプタスレッドは、受け入れた接続を接続キューで待機させます。次にセッションスレッドがキューから接続を受け取って要求を処理します。要求が必要とする場合は、より多くのセッションスレッドが生成されます。新しいスレッドは、接続キューが次のような状態の場合に追加されます。
- 新しい接続が返されるたびに、キューで待機している接続数 (接続のバックログ) と作成済みセッションスレッドの数が比較されます。待機している接続の数が作成済みスレッドの数よりも多ければ、次の要求完了時にスレッドがさらに追加されます。
- 前述のバックログが追跡され、次の場合に ThreadIncrement と同数のスレッドの追加がスケジュールされます。
セッションスレッドの数からバックログの値を差し引いた結果が ThreadIncrement の値より小さい
- 新しいセッションスレッドの追加が RqThrottle によって厳密に制限されている場合に追加されます。
- ベンチマーク負荷の開始などによってバックログが急に増えても、作成されるスレッドが多くならないようにするために、16 回または 32 回ごとの接続時にスレッドが必要かどうかが決定されます。この回数は既に存在するセッションスレッドの数によって決まります。
次の指示は、スレッド、プロセス、接続の数に影響します。チューニングには、Web ベースの管理コンソールまたは init.conf を使います。
- ConnQueueSize
- HeaderBufferSize
- AcceptTimeOut
- KeepAliveThreads
- KeepAliveTimeout
- KernelThreads
- ListenQ
- MaxKeepAliveConnections
- MaxProcs (UNIX のみ)
- PostThreadsEarly
- RcvBufSize
- RqThrottle
- RqThrottleMin
- SndBufSize
- StackSize
- TerminateTimeout
- ThreadIncrement
- UseNativePoll (UNIX のみ)
これらの指示の詳細については、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』 (英語) を参照してください。
HTTP リスナーのアクセプタスレッド
待機ソケットで受け入れを待機するスレッドの数を指定することができます。この値は、システムで使用する CPU の数と同じ、またはそれより小さく設定することをお勧めします。
チューニング
HTTP リスナーのアクセプタスレッドの数を設定する方法は、次のとおりです。
- server.xml ファイルを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで HTTP リスナーのノードを選択します。
最大同時要求数
Web サーバーが処理できる同時トランザクションの最大数は、init.conf ファイルの RqThrottle パラメータによって決定されます。デフォルト値は 128 です。この値を変更してサーバー側の処理可能数を絞り込み、実行するトランザクションの待ち時間を最小化することができます。RqThrottle の値は複数の仮想サーバーにまたがって適用されますが、負荷の分散 (ロードバランス) は行われません。
同時要求の数を計算するために、有効な要求の数を追跡し、新しい要求を受信するたびに 1 を加え、要求を完了するたびに 1 を差し引きます。新しい要求を受信すると、サーバーは処理中の要求数が最大値に到達していないかどうかをチェックします。上限に到達している場合、有効な要求の数が最大値を下回るまで、サーバーは新しい要求を保留します。
理論的には、最大同時要求数を 1 に設定してもサーバーは機能します。この値を 1 に設定すると、サーバーが同時に処理できる要求の数は 1 つに限定されますが、静的なファイルに対する HTTP 要求は一般に存続時間が短く (応答時間が 5 ミリ秒程度のこともあります)、一度に処理できる要求が 1 つだけでも 1 秒間に 200 程度までの要求に対応できます。
しかし実際は、インターネットクライアントはサーバーに接続し、要求を完了しないことがよくあります。この場合、サーバーはタイムアウトとなるまで 30 秒以上も待つことになります。このタイムアウトまでの時間は、init.conf の AcceptTimeOut 指示を使って設定できます。デフォルト値は 30 秒です。また、完了までに数分を要する大規模なトランザクションが必要なサイトもあります。これらの要因は、どちらも最大同時要求数に影響します。処理の完了までに何秒もかかる要求を数多く処理するサイトでは、最大同時要求数を高めに設定する必要があります。AcceptTimeOut の詳細については、「AcceptTimeOut 情報」を参照してください。
RqThrottle の値としては、負荷に応じて 100 〜 500 が適しています。
RqThrottleMin は、起動時にサーバーが初期化するスレッドの最小数です。デフォルト値は 48 です。RqThrottle は同時に実行できるアクティブスレッドの最大数に対する物理的な制限であり、パフォーマンス上のボトルネックになることがあります。デフォルト値は 128 です。
チューニング
同時要求の数をチューニングする方法は、次のとおりです。
- init.conf ファイルの RqThrottleMin と RqThrottle を編集します。
- Web ベースの管理インタフェースで「プリファレンス」タブの「調整」ページにアクセスし、「最大同時接続」フィールドに値を入力します。
Java パフォーマンスの改善
Sun ONE Application Server では、さまざまな方法で Java パフォーマンスを向上できます。次のような方法があります。
- 代替スレッドライブラリの使用
- コンパイル済み JSP の使用
- クラスの再読み込み設定
代替スレッドライブラリの使用
Solaris 8 以降では、libthread または /usr/lib/lwp などの代替スレッドライブラリを使ってパフォーマンスを最適化できます。libthread は、デフォルトで有効にされています。
コンパイル済み JSP の使用
JSP のコンパイルはリソースを消費し、時間もかかります。サーバーにインストールする前に JSP をコンパイルしておくことで、パフォーマンスを向上できます。
クラスの再読み込み設定
パフォーマンスを向上するには、動的な再読み込みのフラグは無効に設定しておく必要があります。このように設定するには、server.xml を編集して dynamic-reload-enabled="false" に設定します。
init.conf のその他の指令
次に、サーバーの効率化に役立つ init.conf のその他の指示について説明します。
AcceptTimeOut 情報
クライアントとの接続を受け入れてから、情報を受信するまでのサーバーの待ち時間は、AcceptTimeOut を使って秒単位で設定します。デフォルトの設定は 30 秒です。ほとんどの状況では、この設定を変更する必要はありません。デフォルトの 30 秒より短く設定すると、スレッドを早く解放できます。ただし、接続速度が遅いユーザーの接続も切断してしまうことになります。
チューニング
AcceptTimeOut を設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf の AcceptTimeOut パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースのパフォーマンスサブメニューで値を変更します。
CGIStub プロセス (UNIX/Linux)
UNIX または Linux システムでは、CGIStub パラメータを調整できます。Sun ONE Application Server では、必要に応じて CGI エンジンが CGIStub を生成します。大きな負荷を処理し、CGI が生成するコンテンツに大きく依存するシステムでは、CGIStub プロセスがシステムのすべてのリソースを消費してしまうことも考えられます。このような状況が生じるサーバーでは CGIStub プロセスをチューニングして、新規生成される CGIStub プロセスの数、タイムアウト値、一度に実行できる CGIStub プロセスの最小値を設定できます。
注 init.conf ファイルに init-cgi 機能が設定され、マルチプロセスモードで実行している場合は、init-cgi 行に LateInit = yes を追加する必要があります。
CGI スタブの制御をチューニングする 4 種類の指示とそれぞれのデフォルト値は、次のとおりです。
- MinCGIStubs
- MaxCGIStubs
- CGIStubIdleTimeout
- CGIExpirationTimeout
MinCGIStubs は、デフォルトで起動するプロセス数を制御します。最初の CGIStub プロセスは CGI プログラムが呼び出されると起動します。デフォルト値は 2 です。init.conf ファイルに init-cgi 指令があれば、最小数の CGIStub プロセスが起動時に生成されます。
MaxCGIStubs は、サーバーが生成する CGIStub プロセスの最大値を制御します。これは CGIStub 実行時の最大同時プロセス数であり、保留された要求の最大数ではありません。デフォルト値はほとんどのシステムに適合します。この値を大きくしすぎると実際のスループットが減少します。デフォルト値は 10 です。
CGIStubIdleTimeout に設定された秒数の間アイドル状態にある CGIStub プロセスは、サーバーによって強制終了されます。プロセスの数が MinCGIStubs に達すると、サーバーはそれ以上のプロセスを終了しなくなります。デフォルト値は 45 です。
CGIExpirationTimeout は、CGI プロセスを実行できる最大時間を秒単位で制限します。
チューニング
CGIStub プロセスのすべての指令を設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf ファイルを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースの「詳細」タブにある CGI サブメニューで値を変更します。
バッファサイズ
サーバーソケットの送信バッファ (SndBufSize) と受信バッファ (RcvBufSize) のサイズを設定できます。これらのバッファについては、UNIX または Linux のマニュアルを参照してください。
チューニング
バッファサイズを設定する方法は、次のとおりです。
- init.conf の SndBufSize パラメータと RcvBufSize パラメータを編集します。
- Web ベースの管理インタフェースの「詳細」タブにある「パフォーマンス」サブメニューで SndBufSize と RcvBufSize の値を設定または変更します。
obj.conf のその他のパラメータ
obj.conf ファイルの一部のパラメータを使ってサーバーのパフォーマンスを向上できます。次に示す情報のほかに、「nocache パラメータの使用」も参照してください。
obj.conf の詳細は、『Sun ONE Application Server Developer's Guide to NSAPI』を参照してください。
find-pathinfo-forward
PathCheck 機能の find-pathinfo、および NameTrans 機能の pfx2dir と assign-name では、find-pathinfo-forward パラメータを設定してパフォーマンスを向上できます。このパラメータを設定すると、サーバーはサーバー機能 find-pathinfo のパスを最後から逆方向に検索せずに、パスの ntrans-base の後の PATH_INFO を順方向検索します。
注 サーバー機能 find-pathinfo を呼び出したときに、rq->vars に ntrans-base パラメータが設定されていない場合、サーバーは find-pathinfo-forward パラメータを無視します。デフォルトでは、ntrans-base は設定されています。
次に例を示します。
NameTrans fn="pfx2dir" find-pathinfo-forward="" from="/cgi-bin" dir="/export/home/cgi-bin" name="cgi"
NameTrans fn="assign-name" from="/perf" find-pathinfo-forward="" name="perf"
この機能を利用することで、サーバー機能 find-pathinfo で実行する stat が少なくなるため、特定の URL についてパフォーマンスを向上できます。Windows NT ではこの機能を使って、PathCheck サーバー機能 find-pathinfo を利用するときに、サーバーが「¥」を「/」に変更することを防ぐこともできます。
nostat
NameTrans 機能の assign-name に nostat パラメータを指定することで、指定した URL についてサーバーが stat を実行しないように設定できます。構文は次のとおりです。
nostat=virtual-path
次に例を示します。
<Object name=default>
NameTrans fn="assign-name" from="/nsfc" nostat="/nsfc" name="nsfc"
</Object>
<Object name=nsfc>
Service fn=service-nsfc-dump
</Object>
上の例では、ntrans-base が設定されている場合に、パス /ntrans-base/nsfc と /ntrans-base/nsfc/* についてサーバーは stat を実行しません。ntrans-base が設定されていない場合、サーバーは URL /nsfc と /nsfc/* について stat を実行しません。デフォルトでは、ntrans-base は設定されています。この例は、デフォルトの PathCheck サーバー機能の利用を前提としています。
assign-nameNameTrans で nostat= virtual-path を指定すると、サーバーは指定の virtual-path で stat が失敗するものと判断します。このため、NSAPI プラグインの URL など、virtual-path のパスがシステムに存在しない場合にだけ nostat を使ってください。これらの URL に nostat を適用することで、不要な stat を回避できるため、パフォーマンスを向上できます。
サーバーのスケーリング
ここでは、サーバーのサブシステムと最適なパフォーマンスについて説明します。
プロセッサ
Solaris と Windows NT では、Sun ONE Application Server は複数 CPU の利点を透過的に活用できます。一般に、複数 CPU の効果はオペレーティングシステムの種類と作業負荷に応じて異なります。システムにプロセッサを追加することで、動的なコンテンツの処理パフォーマンスは向上します。静的なコンテンツは主に I/O に関連しており、CPU よりも I/O でより多くの時間が使われます。一次メモリを増やすほど多くのコンテンツがキャッシュされます (サーバーがメモリの有効利用に合わせてチューニングされている場合)。当社の測定では、4 CPU のマシンで CPU の数を 2 倍に増やすと、NSAPI で 40 〜 60% の改善、サーブレットで 50 〜 80% の改善が見られました。
メモリ
Solaris と Windows では、Sun ONE Application Server は 256 メガバイトの RAM を必要とします。これは、Sun ONE Studio を実行していないサーバーで稼働するアプリケーションサーバーに適用される値です。Sun Microsystems の Web サイトで、『Sun ONE Application Server インストールガイド』を参照してください。
ディスク容量
OS、ドキュメントツリー、ログファイルに適した十分なディスク容量が必要です。ほとんどの場合は、合計で 2 ギガバイトが必要となります。
OS、スワップファイルとページングファイル、Sun ONE Application Server のログファイル、ドキュメントツリーは、それぞれを別のハードディスクドライブに保存します。これにより、ログドライブでログファイルが一般になっても、OS に影響が及びません。また、たとえば、OS のページングファイルにドライブアクティビティを実行させるかどうかも指定できます。
スワップとページングにどれだけの容量を割り当てるべきか、OS のベンダーが推奨していることもあります。テスト結果によれば、RAM と同容量をスワップファイルの容量に割り当てると Sun ONE Application Server のパフォーマンスが最適化され、ドキュメントツリーのマッピングにも十分に対応できます。
ネットワーク
インターネットサイトでは、サーバーがピーク時に処理する同時アクセスユーザーの数を求め、その値にサイトの平均要求サイズを掛け合わせます。平均的な要求には、複数のドキュメントが関わることがあります。よくわからないときは、ホームページ、および関連するすべてのサブフレームと画像を適用してください。
次に、ピーク時のユーザーがドキュメントを待つ平均時間を秒単位で求めます。これでサーバーに必要な WAN 帯域幅を求めることができます。
たとえば、ピーク時のユーザー数が 50 で、平均ドキュメントサイズが 24 キロバイト、各ドキュメントの転送時間が 5 秒であれば、240 キロバイト (毎秒 1920 キロビット) が必要となります。この場合、2 本の T1 回線 (それぞれは毎秒 1544 キロビット) が必要となり、将来の成長に備えてオーバーヘッドも確保できます。
サーバーのネットワークインタフェースカードは、接続する WAN より大きな値に対応している必要があります。たとえば、最大で 3 本の T1 回線を利用するには、10BaseT インタフェースが必要です。1 本の T3 回線 (毎秒 45 メガビット) を利用するには、100BaseT が必要です。しかし、WAN の帯域幅が毎秒 50 メガビットを超える場合は、複数の 100BaseT インタフェースを利用するか、ギガビットイーサネットの採用を検討してください。
イントラネットでは、ネットワークがボトルネックとなることはほとんどありません。ただし、必要帯域幅の決定には前述と同じ計算方法を適用できます。
接続プールのチューニング
ここでは、JDBC 接続プールのチューニング方法について説明します。
データベースを多用するアプリケーションでは、Sun ONE Application Server が管理する JDBC 接続プールを最適なパフォーマンスに合わせてチューニングすることができます。この接続プールは、データベースとの有効な物理接続を数多く維持します。この接続を再利用することで、データベースとの接続を開閉するオーバーヘッドを減らすことができます。
JDBC リソースは、Sun ONE Application Server の設定ファイル server.xml の <jdbc-resource> 要素に定義され、<jdbc-connection-pool> を参照するように設定されます。J2EE アプリケーションは、JDBC リソースを使って JDBC 接続プールが維持する接続を取得します。複数の JDBC リソースが 1 つの JDBC 接続プールを参照することもできます。この場合、物理的な接続プールはすべてのリソースによって共有されます。
JDBC 接続プールは、Web ベースの管理コンソールを使うか、server.xml ファイルの jdbc-connection-pool 要素を編集することで定義および設定できます。定義した各プールはサーバーの起動時にインスタンス化されますが、物理的な接続が設定されるのは、最初にアクセスされたときです。
JDBC 接続プールの設定に使う属性は、次のとおりです。
JDBC 接続プールのチューニング
JDBC 接続プールのチューニングでは、次の処理をお勧めします。
- 別の分離レベルを指定してもアプリケーションが正常に動作し、その分離レベルのほうがパフォーマンスの向上に適していることが確実でない限り、setTransactionIsolationLevel() を呼び出さずにドライバのデフォルトの分離レベルを使います。
- アイドル状態によるタイムアウトの値を 0 秒に設定します。この指示によって、アイドル状態の接続が一切削除されなくなります。これにより、通常は接続を新規作成するときにリソースが消費されなくなり、アイドル監視スレッドが無効化されます。ただし、長期間使われなかった接続は、データベースサーバーによってリセットされる可能性があります。
- 接続プールのサイズを変更するときは、次の長所と短所を検討する必要があります。
表: 接続プールのサイズ変更に関する長所と短所
接続プール
長所
短所
小規模な接続プール
大規模な接続プール
- max-wait-time-in-millis を 0 に設定します。これにより、接続を利用できるようになるまでクライアントスレッドがブロックされます。また、要求ごとに待ち時間の経過を追跡するタスクが軽減されるので、パフォーマンスが向上します。
- すでに説明したように、transaction-isolation-level の設定を変更しないようにします。変更が必要なときは、is-isolation-level-guaranteed フラグを false に設定し、アプリケーションがプログラムによって接続の分離レベルを変更しないようにします。
- is-connection-validation-required パラメータを true に設定すると、プールから接続が返されるたびに接続評価アルゴリズムの適用が実施されます。これにより、getConnection() の反応時間にオーバーヘッドが追加されます。データベースとの接続が信頼できるものであれば、評価を行う必要はありません。
次の図は、管理インタフェースの接続プール設定画面を示しています。
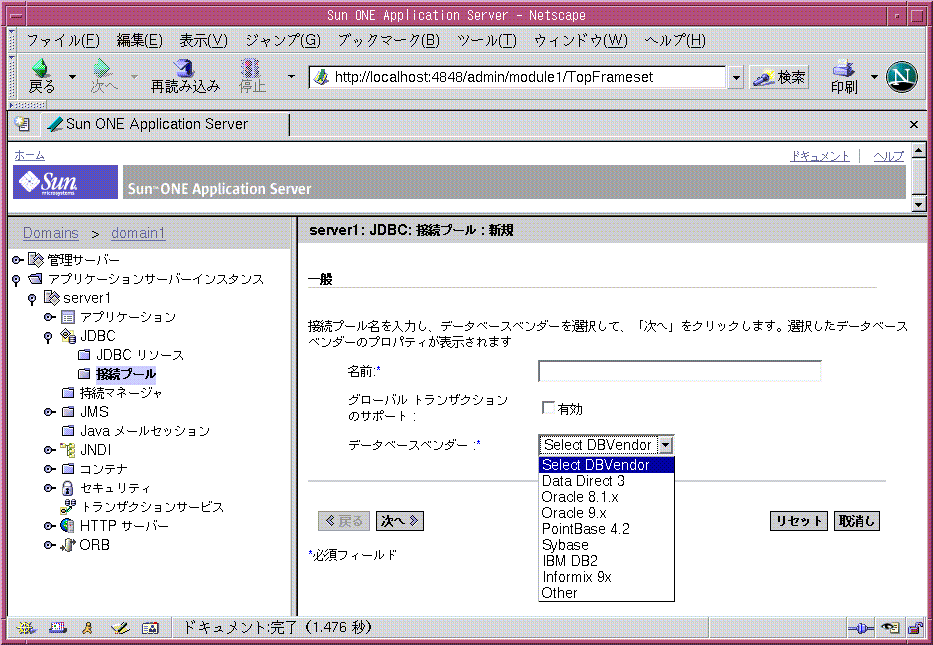
図: 管理インタフェースによる JDBC 接続プールのチューニング
JSP とサーブレットのチューニング
ここでは、コード作成に関する注意点と、Sun ONE Application Server の設定に関する注意点を示し、JSP アプリケーションとサーブレットアプリケーションのチューニング方法について説明します。
JSP とサーブレットのコード作成に関する注意点
JSP アプリケーションおよびサーブレットアプリケーションのコードを記述するときは、次の点に注意することをお勧めします。
- 規模の大きなオブジェクトを HttpSession 変数として格納しません。
- 不要になった HTTP セッションを解放するときは、javax.servlet.http.HttpSession.invalidate() を使います。
- HTTP セッションが必要なくなった場合に自動作成を停止するには、<%page session="false"%> 指示を使います。
- サーブレットでの Java 同期を最小化します。
- サーブレットではシングルスレッドモデルを使いません。
- 多くのリソースを消費する 1 回の初期化では、サーブレットの init() メソッドを使います。
- System.out.println() 呼び出しを使わないようにします。
JSP とサーブレットのパフォーマンスに影響する設定
次の設定によってパフォーマンスが向上します。これらの設定が本稼働環境を前提としていることに注意してください。一部の設定は開発中の JSP やサーブレットには効果がありません。
- サーバーの CLASSPATH 設定から余分なディレクトリを取り除くことで、クラスのロード時間が短縮されます。関連するクラスは、JAR ファイルにまとめてください。
- HTTP の設定 (接続とキープアライブサブシステムの設定) では、キープアライブサブシステムと HTTP サーバーの一般的なチューニングによって応答時間が変化します。詳細については、HTTP サーバーのチューニングを参照してください。
- 再コンパイルと再読み込みの間隔を -1 に設定して、JSP が再コンパイルされないようにします。
- SSL には mtmalloc を使います。このライブラリに含まれる機能には、ヒープ領域への同時アクセスを提供する malloc ルーチンのセットが用意されています。libmtmalloc 用のパッチは、http://www.sunsolve で入手できます。該当するサーバーインスタンスの /bin/startserv にある startserv スクリプトを編集し、LD_LIBRARY_PATH に so ファイルの場所の指定を追加します。
- JSP とサーブレットのキャッシングを設定します。詳細は、『Sun ONE Application Server 7 Web アプリケーション開発者ガイド』の「サーブレットの使用」という章にある「キャッシュ機能」を参照してください。
- EJB を含まないアプリケーションは、EAR ファイルではなく、WAR ファイルとして配備します。
- セキュリティマネージャは多くのリソースを消費します。これは、必要なリソースへのすべての呼び出しが doPrivileged() メソッドを呼び出すためです。また、問題となったリソースは server.policy ファイルと照合されます。アプリケーションに server.policy を適用する意味がなく、サーバーで不正なコードが実行されないことが確実であれば、server.xml の該当行をコメントアウトして server.policy を無効化することがあります。
たとえば、次のように記述することで server.policy をコメントアウトできます。
<!-- jvm-options> -Djava.security.policy=/export/home/software/ias70_gold3/domains/domain1/server1/config/server.policy
</jvm-options -->
EJB のパフォーマンスチューニング
Sun ONE Application Server の高性能な EJB コンテナには、パフォーマンスをチューニングするための多数の設定可能要素 (それぞれにデフォルト値があります) が用意されており、server.xml 設定ファイルと各 Bean の配備記述子で変更できます。server.xml に設定されている値は、個々の Bean の配備記述子に設定されている場合を除き、すべての EJB に適用されます。Bean の配備記述子に設定したプロパティは、常に server.xml の設定に優先して適用されます。server.xml ファイルの <ejb-container> 要素の詳細については、『Sun ONE Application Server 管理者用設定ファイルリファレンス』を参照してください。
EJB 2.0 配備記述子に含まれる一部のプロパティは、チューニングにも適しています。server.xml ファイルの <ejb-container> 要素のデフォルト設定は、シングルプロセッサのコンピュータシステムに合わせて設定されています。コンテナから最大の性能を引き出すには、デフォルト設定を変更する必要があります。チューニングによって、次の効果を得られます。
- スピード : できるだけ多くの Bean を EJB キャッシュにキャッシュすることで、応答時間を簡単に短縮できます。これにより、CPU を多用するいくつかの処理を回避できます (後述します)。ただし、キャッシュを大きくしすぎると、キャッシュを管理するタスク (ガベージコレクションを含む) に時間がかかるようになるため、リソースとして利用できるメモリには限りがあります。
- メモリの消費 : プール内またはキャッシュされている Bean は、Java 仮想マシンのヒープのメモリを消費します。プールやキャッシュのサイズを大きくしすぎると、ガベージコレクションに要する時間と頻度が増えるため、パフォーマンスは低下します。
- 機能のプロパティ (ユーザータイムアウト、コミットオプション、セキュリティオプション、トランザクションオプションなど): これらのプロパティのほとんどは、J2EE サーバー内のアプリケーションの機能と設定に関連します。パフォーマンスのために機能面で妥協することはお勧めできませんが、このような状況が生じた場合の対応方法について選択肢を提供することはできます。
EJB コンテナのパフォーマンスチューニング
各種 Bean のライフサイクルは、EJB 仕様に正式に定義されています。このマニュアルでは、読者が Bean のライフサイクルイベントに習熟していることを前提とします。コンテナ内のアクティブ Bean は、要求を処理し、パフォーマンスを向上するためにキャッシュまたはプールに格納されます。パフォーマンスのチューニングでは、キャッシュとプールのプロパティをチューニングすることが重要です。
Bean の種類によっては、推奨されるチューニング方法を特定のコンテナに適用できないことがあります。
設定可能要素の使用について
次の表は、キャッシュとプールの設定に使われる設定可能要素を EJB の種類別に示しています。
EJB 記述子のプロパティ
EJB コンテナに含まれる各 Bean の設定には、次のプロパティを利用できます。
- steady-pool-size: Bean の初期数と最小数を指定します。steady-pool-size は、プールで保持する必要があります。指定できる値は、0 から MAX_INTEGER の範囲です。この値は、サーバーインスタンスレベルで指定します。Bean 固有の設定にも同じ名前のプロパティを使います。この変数も含め、次のすべての変数では、Bean レベルで値が設定されている (sun-ejb-jar.xml に指定) 場合は、Bean レベルで指定した値が適用されます。
- pool-resize-quantity: resize-quantity は、サーバーがプールを処理するときに、作成または削除する Bean の数を指定します。有効な値は 0 から MAX_INTEGER の範囲内で、上限値の適用対象となります。デフォルト値は 16 です。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は resize-quantity です。
- max-pool-size: max-pool-size は、プールの最大サイズを指定します。指定できる値は、0 から MAX_INTEGER の範囲です。デフォルト値は 64 です。0 を指定すると、プールサイズは無制限になります。この場合、JVM ヒープがプールに格納するオブジェクトでいっぱいになることが考えられます。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-pool> 要素の max-pool-size です。
- max-wait-time-in-millis (現在は使われません)
- pool-idle-timeout-in-seconds: pool-idle-timeout-in-seconds は、ステートレスセッション Bean やメッセージ駆動型 Bean がアイドル状態でプール内に存在できる最大時間を指定します。この時間を過ぎると、ステートレスセッション Bean または メッセージ駆動型 Bean は削除されます。この時間は、サーバーが参考にします。pool-idle-timeout-in-seconds のデフォルト値は 600 秒です。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-pool> 要素の pool-idle-timeout-in-seconds です。
- cache-resize-quantity: cache-resize-quantity は、サーバーがキャッシュを処理するときに、作成または削除する Bean の数を指定します。有効な値は 0 から MAX_INTEGER の範囲内で、上限値の適用対象となります。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-cache> 要素の resize-quantity です。
- max-cache-size: max-cache-size は、キャッシュに入れることができる Bean の最大数を指定します。1 より大きな値を設定する必要があります。デフォルト値は 512 です。0 を設定すると、キャッシュできる Bean の数は無制限になります。この場合、キャッシュサイズは cache-idle-timeout-in-seconds と cache-resize-quantity によって制限されます。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-cache> 要素の max-cache-size です。
- cache-idle-timeout-in-seconds: cache-idle-timeout-in-seconds は、ステートフルセッション Bean やエンティティ Bean がアイドル状態でキャッシュ内に存在できる最大時間を指定します。この時間を過ぎると、Bean はバックアップストアで非活性化されます。cache-idle-timeout-in-seconds のデフォルト値は 600 秒です。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-cache> 要素の cache-idle-timeout-in-seconds です。
- is-cache-overflow-allowed (現在は使われません)
- removal-timeout-in-seconds: ステートフル Bean が非活性化される (バックアップストアでアイドル状態になっている) 時間は、removal-timeout-in-seconds パラメータによって制御されます。removal-timeout-in-seconds の時間を過ぎてもアクセスされなかった場合、Bean はバックアップストアから削除され、クライアントからアクセスできなくなります。removal-timeout-in-seconds のデフォルト値は 60 分です。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-cache> 要素の removal-timeout-in-seconds です。
- victim-selection-policy: victim-selection-policy は、ステートフルセッション Bean のキャッシュから削除対象を特定するアルゴリズムを指定します。設定できる値は、FIFO | LRU | NRU です。デフォルトは NRU (pseudo-random) です。sun-ejb-jar.xml で対応する属性は、<bean-cache> 要素の victim-selection-policy です。
- commit-option: 有効な値は B または C です。デフォルトは B です。この設定は、EJB 固有のトランザクションの commit-option に反映されます。
- refresh-period-in-seconds: (BMP の読み取り専用 Bean のみ) refresh-period-in-seconds は、読み取り専用 Bean をデータソースに基づいて更新する頻度を指定します。0 (更新しない) または正数 (指定した間隔で更新する) を指定できます。デフォルトは 600 秒です。
EJB プールのチューニング
プール内の Bean の状態は、EJB のライフサイクルでは「プールされた状態」となります。つまり、この状態の Bean には固有の情報が含まれません。Bean をプールに保持する利点は、要求を受信したときに Bean を最初から作成する時間を節約できることです。コンテナには、プールオブジェクトをバックグラウンドで作成し、要求されたパスに Bean を作成するための時間を節約するメカニズムが用意されています。
システムの通常の負荷に合わせて steady-pool-size に値を設定します。steady-pool-size には 0 より大きい値を設定することをお勧めします。これにより、受信した要求を処理するインスタンスが常にプール内に保持されます。
max-pool-size には、システムで予想される高負荷に合わせて値を設定します。プールサイズを大きくしすぎると、メモリが無駄になり、システムの処理速度が低下することがあります。接続の効率を考えると、プールサイズを小さくしすぎることも問題です。
<max-pool-size> の値を変更するときは、<pool-resize-quantity> の設定を再確認することをお勧めします。この値は、定期的なクリーニングで回収される Bean の数に対応します。最大サイズを増やす場合は、それに応じて回収する Bean の数も増やす必要があります。
その他の設定可能要素では、<pool-idle-timeout-in-seconds> の値が重要です。プール内に <steady-pool-size> を超える数の Bean が存在する場合、Bean の数が <steady-pool-size> に戻るまで、<pool-idle-timeout-in-seconds> 秒ごとに <pool-resize-quantity> の数だけ Bean が削除されます。pool-idle-timeout-in-seconds の値が大きく、pool-resize-quantity の値が小さすぎる場合、Bean の数が pool-resize-quantity に戻るまでの時間が長くかかることになります。これを事前に理解しておくか、設定を修正する必要があります。
次の図は、サーバーインスタンスの EJB プールをチューニングするための管理インタフェースの画面を示しています。
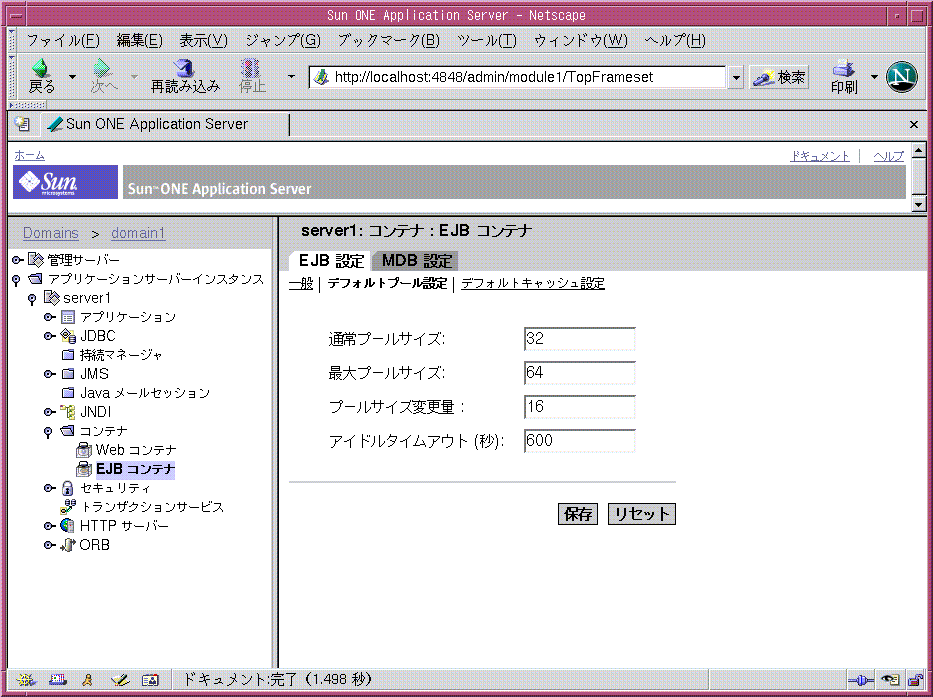
図: 管理インタフェースによる EJB プールのチューニング
EJB キャッシュのチューニング
キャッシュ内の Bean の状態は、EJB のライフサイクルでは「使用可能状態」となります。つまり、この状態の Bean には関連する固有の情報 (主キー、セッション ID など) が含まれます。キャッシュから取り出した Bean は、EJB のライフサイクルに従って非活性化または削除する必要があります。非活性化された Bean をキャッシュに戻すには、活性化し直す必要があります。通常、エンティティ Bean はデータベースに格納され、なんらかのクエリ言語セマンティクスを使ってデータをロードまたは格納します。セッション Bean を非活性化してディスクまたはデータベースに格納するときは直列化する必要があり、活性化するときは直列化を復元する必要があります。
受信した要求が、キャッシュに入れられた「使用可能状態」の Bean を使用する場合、Bean の作成、固有情報の設定、活性化のオーバーヘッドが回避されます。このため、理論上はできるだけ多くの Bean をキャッシュするべきです。しかし、大規模なキャッシュには次のような問題があります。
- すべての Bean が消費するメモリは、仮想マシンが利用できるヒープのサイズに影響します。
- キャッシュに必要なオブジェクトとメモリが増えると、ガベージコレクションにかかる時間が長くなり、頻度も増す可能性があります。
- アプリケーションサーバーがメモリ不足になる可能性があります (ピーク負荷に合わせてヒープが慎重にチューニングされている場合を除く)
<cache-idle-timeout-in-seconds> を過ぎてもキャッシュに残っているすべての Beanは、定期的なクリーニングで削除されます。
次の図は、コンテナ全体の EJB キャッシュをチューニングするための管理インタフェースの画面を示しています。
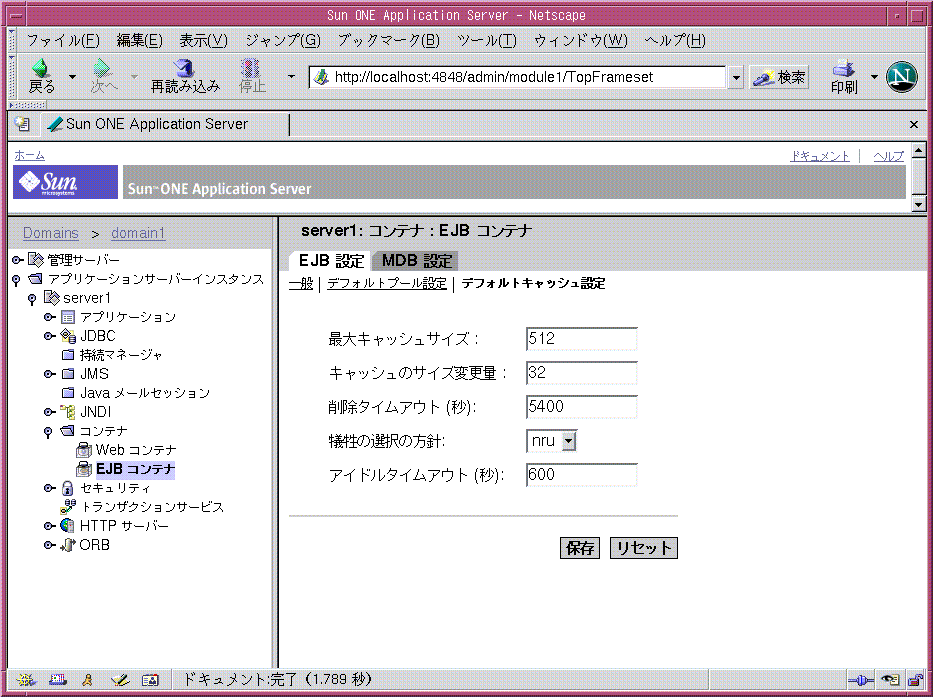
図: 管理インタフェースによる EJB キャッシュのチューニング
各種 EJB のパフォーマンスに関する注意点
次の図は、プールとキャッシュを個々の Bean に設定する Bean 記述子の例を示しています。
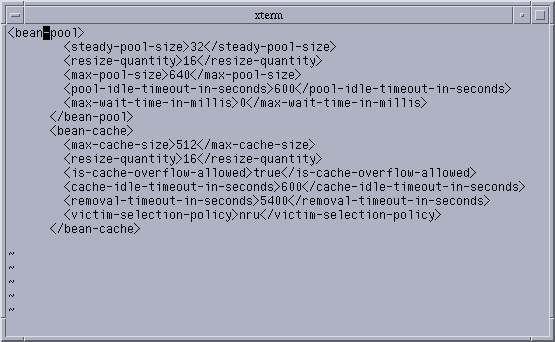
図: 個々の Bean の Bean 記述子
次に、パフォーマンスに関する注意点を Bean の種類別に示します。
- エンティティ Bean: 特定のエンティティ Bean の利用状況によっては、あまり使われない Bean (作成後、トランザクションが終了すると使われなくなる注文など) がキャッシュされる回数を減らし、頻繁に使われる Bean (頻繁に参照される在庫項目など) がキャッシュされる回数を増やせるように、max-cache-size を設定する必要があります。エンティティコンテナをチューニングするその他の方法については、「コミットオプション」を参照してください。
- ステートフルセッション Bean: ステートフル Bean がユーザーを表す場合は、アプリケーションサーバープロセスの予想並行ユーザー数に合わせて Bean の max-cache-size を設定します。通常のユーザー負荷から見て小さすぎる値を設定すると、Bean の非活性化と活性化が頻繁に行われ、CPU を多用する直列化と直列化復元およびディスク I/O が増えるため、応答時間に悪影響を生じます。もう一つの重要な設定可能要素は cache-idle-timeout-in-seconds です。cache-idle-timeout-in-seconds を過ぎてもアクセスされなかったキャッシュ内のすべての Bean は、cache-idle-timeout-in-seconds の間隔で非活性化されます。HTTP セッションの非活性化とアイドルのタイムアウトと同様に、removal-timeout-in-seconds を過ぎてもアクセスされなかった Bean は削除されます。非活性化された Bean は直列化され、ディスクに格納されます。多数の Bean を非活性化することは、ディスクシステムのファイル数が増えるだけでなく、呼び出す前にセッションの状態を直列化復元しなければならないため、応答時間が遅くなります。
- ステートレスセッション Bean: ステートレスセッション Bean には、関連する状態がなく、エンティティ Bean やステートフルセッション Bean より利用しやすい状態でプールされます。この Bean を最適にチューニングするには、設定可能要素 steady-pool-size、pool-resize-quantity、max-pool-size に適切な値を設定します。事前の設定をプールに含めておく場合は、steady-pool-size に 0 より大きな値を設定します。これにより、コンテナが起動されると、steady-pool-size で指定した数の Bean を持つプールが作成されます。プールに事前に Bean を用意しておくことで、メソッドを呼び出すときにオブジェクトを作成する時間を節約できます。steady-pool size に大きすぎる値を設定すると、メモリの消費が必要以上に多くなり、GC にかかる時間が長くなります。pool-resize-quantity は、プールの増大だけでなく縮小にも影響します。縮小は指数関数的に行われるため、小さな値を設定することをお勧めします。max-pool-size に小さな値を設定すると、現在のプールサイズが max-pool-size を超える場合にプールからインスタンスが削除されるため、余分なオブジェクト削除が行われることになります (これは、余分なオブジェクト作成を行った結果です)。
- 読み取り専用エンティティ Bean: データベースを更新することのない通常の BMP Bean を使うときは、代わりに読み取り専用 Bean を使ってみてください。デフォルトでは、その Bean が示すデータベース行がバックグラウンドで変更されない場合にだけ読み取り専用 Bean は正常に機能します。Sun ONE Application Server では、読み取り専用 Bean は Bean 管理持続 (BMP) だけでサポートされています。読み取り専用 Bean がデータベースを更新することはありません (ejbStore が呼び出されることはありません)。このため、BMP Bean と読み取り専用 Bean がパフォーマンスに与える影響には大きな違いがあります。トランザクションを使って読み取り専用 Bean のメソッドにアクセスすると (ejb-jar.xml に指定されたメソッド記述子が TX_REQUIRED または TX_REQUIRES_NEW であるため)、ejbLoad() が常に呼び出されます。キャッシュされたデータをデータベースと常に同期させるには、トランザクションを使って読み取り専用 Bean のメソッドにアクセスします。読み取り専用 Bean は ejbLoad() によるオーバーヘッドを回避しようとするため、これはトランザクションアクセスとはなりません。この場合に重要な設定可能要素は、refresh-period-in-seconds です。これらの Bean のコンテナの現在の実装はプルキャッシュです。つまり、どの Bean インスタンスでも refresh-period-in-seconds を経過した場合、この Bean インスタンスにアクセスするユーザーはビジネスメソッドを実行する前に Bean で ejbLoad() を呼び出す必要があります。データが変更される時間を想定し、これに適切な値を入力します。通常は数分間です。たとえば、株価情報を 5 分間保持するときは、refresh-period-in-seconds を 300 秒に設定します。
注 読み取り専用 Bean がキャッシュしたデータを更新する通常の BMP Bean があるときは、プログラムによる更新機能の利用を検討します。詳細は、『Sun ONE Application Server Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』を参照してください。
注 Sun ONE Studio を使って Bean を開発し、アプリケーションサーバーに配備したときは、Bean プールと Bean キャッシュについて、個々の Bean の記述子を編集する必要があります。この設定は、本稼働環境レベルの配備には適さないことがあります。
- メッセージ駆動 Bean: これらの Bean のコンテナ、エンティティ Bean やセッション Bean のコンテナとは若干異なります。現在のバージョンのアプリケーションサーバーの MDB コンテナでは、MDB プール内の Bean にセッションとスレッドが関連づけられています。これは、コンテナ内のメッセージ駆動型の要求を実行するスレッドをプールする場合に適しています。このため、Bean プールには、他のアプリケーションも含めてサーバーのすべてのパラメータを考慮した値を設定する必要があります。たとえば、500 を超える値は適していません。
次の図は、メッセージ駆動型 Beanのプールをチューニングするための管理インタフェースの画面を示しています。
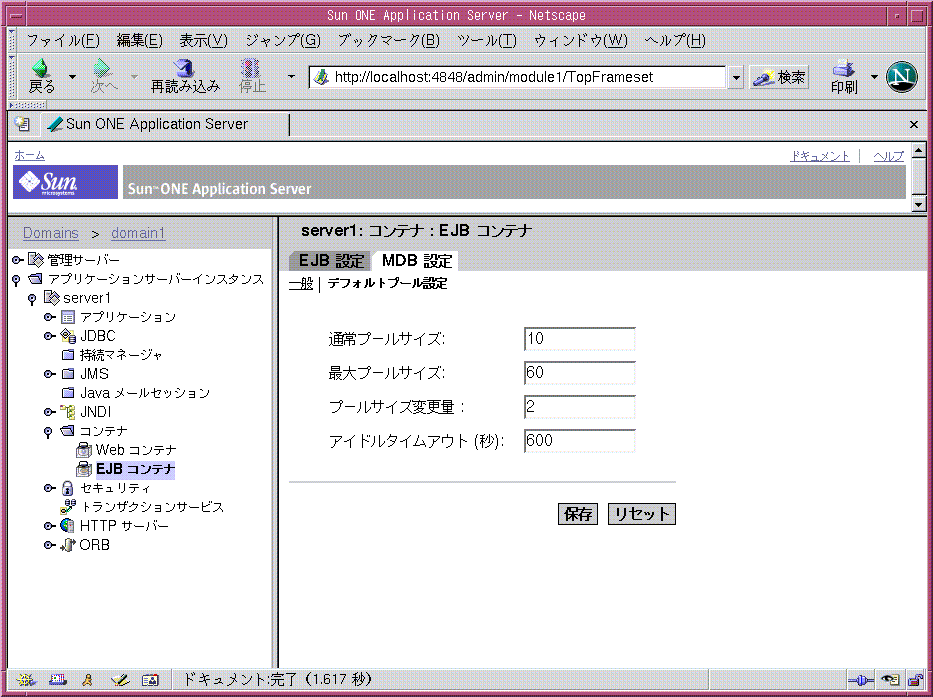
図: 管理インタフェースによるメッセージ駆動型 Bean コンテナの設定
関連する注意点
次に、EJB の使用に関連する注意点を示します。
- リモートインタフェースとローカルインタフェース
EJB は、リモートインタフェースとローカルインタフェースを持つことができます。アプリケーションサーバーインスタンスと異なる場所にあるリモートクライアントは、Bean へのアクセスにリモートインタフェースを使います。リモートインタフェースへの呼び出しは、引数の操作、ネットワークによるデータの転送、受信側でのデータの操作と処理を必要とするため、より多くのリソースが必要となります。アプリケーションサーバーインスタンスと同じ場所にあるローカルクライアントは、Bean のローカルインタフェースがあれば、これを利用できます。引数の操作や転送が必要ないため、ローカルインタフェースを使った方が効率的です。引数は参照を使って渡されるので、渡されたオブジェクトを呼び出す側と呼び出される側の両方が共有できます (このためには、共有できるように適切に実装する必要があります)。同じ場所にあるクライアントだけが使用できるように Bean が記述されている場合、その Bean にローカルインタフェースを持たせ、クライアントにローカルインタフェースを利用させることができます。一方、場所に関係なく利用できるように Bean が記述されている場合は、リモートクライアントはリモートインタフェースを使用し、ローカルクライアントはローカルインタフェースを使用するように、リモートインタフェースとローカルインタフェースの両方を持たせることができます。
- pass-by-value セマンティクスと pass-by-reference セマンティクス
リモートインタフェースとローカルインタフェースを適切に使うことで、クライアントがアクセスする Bean を効率的に記述るようになります。しかし、次のような場合はローカルインタフェースを利用できません。
- アプリケーションの仕様が EJB2.0 より古く、ローカルインタフェースの利用が記述されていない
- Bean から Bean の呼び出しが含まれ、呼び出される Bean が同じ場所にあるという前提がクライアント Bean に記述されていない
このような状況に対応できるように、Sun ONE Application Server 7.0 には、Bean のリモートインタフェースに呼び出しを行うときに、同じ場所にあるクライアントが引数を参照を使って渡せる pass-by-reference オプションが用意されています。デフォルトでは、Sun ONE Application Server は同じ場所にある Bean のリモートインタフェースを呼び出すときに pass-by-value セマンティクスを使います。pass-by-value セマンティクスでは、渡す前に引数のコピーが作成されるため、リソースの消費が多くなります。pass-by-reference オプションは、アプリケーション全体または Bean 単位で適用できます。アプリケーションレベルで適用すると、アプリケーションのすべての Bean のリモートインタフェースに引数を渡すときに、pass-by-value セマンティクスが利用されます。Bean レベルで適用した場合は、その Bean のリモートインタフェースへの呼び出しだけで pass-by-value セマンティクスが利用されます。pass-by-value フラグの詳細については、『Sun ONE Application Server Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』および『Sun ONE Application Server 開発者ガイド』を参照してください。
- トランザクション分離レベル
トランザクションに関するアプリケーションセマンティックを明確にすることで、パフォーマンスを最適にする分離レベルを決定できるようになります。次に、パフォーマンスの向上に適しているものから順にトランザクション分離レベルを示します。
これらの値は、データベース接続プールの属性 (jdbc-connection-pool) として設定できます。
- EJB コンテナから見た場合、次のトランザクション属性を指定することができます。パフォーマンスの向上に適しているものから順にオプションを示します。
コミットオプション
コミットオプションは、Bean が関与するトランザクションが完了したときに、コンテナがその Bean に対して実行する処理を制御します。コミットオプションが Bean のコードを変更することはありません (Bean 開発者は、コミットオプションを考慮する必要はありません)。ただし、コミットオプションはパフォーマンスに大きく影響します。
Sun ONE Application Server は、コミットオプション B、C をサポートしています。
どのコミットオプションをいつ使うかについて説明する前に、各コミットオプションを使った場合のコンテナの動作について説明します。
コミットオプション B では、トランザクションが完了すると Bean はキャッシュに保持され、固有の情報も残されます。つまり、同じ主キーが次に呼び出されたときに、キャッシュに保持されているインスタンスをそのまま使えます。もちろん、データベースとの同期をとるメソッド呼び出しの前に、Bean の ejbLoad が呼び出されます。
コミットオプション C では、トランザクションが完了すると、Bean の ejbPassivate() メソッドが呼び出され、Bean と主キーとの関連づけを解除した上で、Bean は空きプールに戻されます。つまり、同じ主キーが次に呼び出されたときは、プールから空き Bean を取り出し、このインスタンスに PrimaryKey を設定した上で、そのインスタンスが ejbActivate を呼び出す必要があります。この場合も、データベースとの同期をとるメソッド呼び出しの前に、Bean の ejbLoad が呼び出されます。
コミットオプション B では、ejbAcivate と ejbPassivate は呼び出されません。ejbActivate と ejbPassivate の呼び出し、およびプールからオブジェクトの取得とプールへのオブジェクトの解放がないため、ほとんどの場合はコミットオプション C よりもコミットオプション B のほうがパフォーマンスには有利です。ただし、コミットオプション C のほうが有効な場合もあります。キャッシュに入れられた Bean の再利用がまれで、Bean がコンスタントにキャッシュに追加される場合は、Bean をキャッシュする意味がありません。
これはコミットオプション C の動作とまったく同じです。コミットオプション C を利用すると、メソッドの呼び出し後、またはトランザクションの完了後にコンテナは Bean をキャッシュせずに、プールに戻します。これにより、インスタンスはより効率的に再利用され、VM に生存するオブジェクトの数が減るために GC のサイクルも短くなります。
コミットオプション B と C のどちらを利用するかをどのように決定すべきでしょうか。まず、Bean の監視コマンドを使ってキャッシュのヒット率を確認します。キャッシュに残されていない回数より、キャッシュに残されている (ヒットする) 回数のほうが多い場合は、コミットオプション B のほうが適していると言えます。結果を最適化するには、更に max-cache-size と cache-resize-quantity の調整が必要です。キャッシュのヒット回数が少なく、キャッシュに残されていない回数が極端に多い場合は、アプリケーションは Bean インスタンスを効率よく再利用していないことになるので、キャッシュサイズを大きくしても (max-cache-size を使います) 効率の改善は望めません (アクセスパターンが変化しない場合)。この場合は、コミットオプション C を指定します。キャッシュに残されている回数と残されていない回数に大きな違いがない場合は、max-cache-size および cache-idle-timeout-in-seconds をチューニングする必要があります。
次の図は、コミットオプションの設定を示しています。
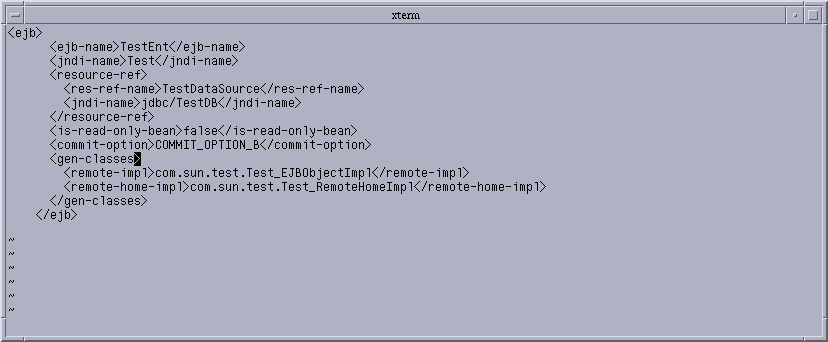
図: コミットオプションの設定
EJB コンテナの監視を有効にしておくことで、いつでも個々の Bean の統計を調査、分析し、プールとキャッシュのチューニングに利用することができます。プールの設定は、ステートレスセッション Bean とエンティティ Bean に対して有効です。キャッシュの設定は、ステートフルセッション Bean とエンティティ Bean に対して有効です。server.xml ファイルのプロパティを設定することで、コンテナの設定をサーバーインスタンスレベルで変更できます。この設定は、sun-ejb-jar.xml に指定した各 Bean の設定によってオーバーライドされます。次の設定可能要素の説明は、「EJB 記述子のプロパティ」を参照してください。
サーバーインスタンスレベルで指定できる設定可能要素は、次のとおりです。
- steady-pool-size
- pool-resize-quantity
- max-pool-size
- cache-resize-quantity
- max-cache-size
- pool-idle-timeout-in-seconds
- cache-idle-timeout-in-seconds
- removal-timeout-in-seconds
- victim-selection-policy
- commit-option
- log-level
- monitoring-enabled
Bean レベルで指定できるプールの設定可能要素は、次のとおりです。
- steady-pool-size
- resize-quantity
- max-pool-size
- pool-idle-timeout-in-seconds
Bean レベルで指定できるキャッシュの設定可能要素は、次のとおりです。
- max-cache-size
- resize-quantity
- is-cache-overflow-allowed
- cache-idle-timeout-in-seconds
- removal-timeout-in-seconds
- victim-selection-policy
次の監視コマンドを実行すると、ステートフルセッション Bean のキャッシュ統計が出力されます。監視コマンドの出力例も合わせて示します。
$./asadmin get --user admin --password netscape --host e4800-241-a --port 4848 -m specjcmp.application.SPECjAppServer.ejb-module.supplier_jar.statefu l-session-bean.BuyerSes.bean-cache.*
resize-quantity = -1
cache-misses = 0
idle-timeout-in-seconds = 0
num-passivations = 0
cache-hits = 59
num-passivation-errors = 0
total-beans-in-cache = 59
num-expired-sessions-removed = 0
max-beans-in-cache = 4096
num-passivation-success = 0
次の監視コマンドを実行すると、エンティティ Bean のプール統計が出力されます。
$./asadmin get --user admin --password netscape --host e4800-241-a --port 4848 -m specjcmp.application.SPECjAppServer.ejb-module.supplier_jar.statefu l-entity-bean.ItemEnt.bean-pool.*
idle-timeout-in-seconds = 0
steady-pool-size = 0
total-beans-destroyed = 0
num-threads-waiting = 0
num-beans-in-pool = 54
max-pool-size = 2147483647
pool-resize-quantity = 0
total-beans-created = 255
次の監視コマンドを実行すると、ステートレス Bean のプール統計が出力されます。
$./asadmin get --user admin --password netscape --host e4800-241-a --port 4848 -m test.application.testEjbMon.ejb-module.slsb.stateless-session-bean. slsb.bean-pool.*
idle-timeout-in-seconds = 200
steady-pool-size = 32
total-beans-destroyed = 12
num-threads-waiting = 0
num-beans-in-pool = 4
max-pool-size = 1024
pool-resize-quantity = 12
total-beans-created = 42
Bean をチューニングするには、対象となる Bean のキャッシュとプールの動作を記録し、時間とともにどのように変化するかを調べます。たとえば、次のような動作を観察します。
- 非活性化が頻繁に行われ、VM ヒープのサイズが小さく維持されている場合は、max-cache-size または cache-idle-timeout-in-seconds の値を大きくします。
GC が頻繁に行われ、プールサイズが大きくなり、それでもキャッシュのヒット率が上がらない場合は、pool-idle-timeout-in-seconds の値を小さくして削除されるインスタンスを増やします。
注 max-pool-size に 0 を指定すると、プールサイズに制限がなくなります。プールに入れられた Bean は、pool-idle-timeout-in-seconds に短い間隔を指定しない限り削除されません。本稼働環境のシステムでは、プールのサイズを無制限にすることはお勧めできません。
ORB のチューニング
Sun ONE Application Server には、高性能でスケーラブルな CORBA ORB (Object Request Broker) が用意されています。ORB は、サーバー上の EJB コンテナの基礎となります。ORB のほとんどの機能は、次の方法で Enterprise JavaBeans を実行したときに使用されます。
- アプリケーションクライアントコンテナを使ったアプリケーションクライアント (またはリッチクライアント) からの RMI/IIOP パス
- 別の Sun ONE Application Server インスタンス ORB からの RMI/IIOP パス
- 別のベンダーの ORB からの RMI/IIOP パス
- Web/MDB (メッセージ駆動型 Bean) コンテナからのプロセス内パス
サーバーインスタンスから別のサーバーインスタンス ORB への接続が作成されると、最初のインスタンスがクライアント側 ORB として動作します。IIOP を介した SSL では、最適化された (最も高速な) トランスポートを使い、暗号化アルゴリズムのネイティブ実装を利用することで優れた性能を維持します。
クライアントから ORB への接続方法
リッチクライアント Java プログラムは、クライアント側の ORB インスタンスを呼び出す initialContext() を新たに呼び出します。これは、Sun ONE Application Server の IIOP ポートへのソケット接続を作成します。このクライアントからの IIOP 要求を処理するサーバー ORB で、読み取りスレッドが開始されます。initialContext を使った場合、クライアントコードはサーバーに配備された EJB をルックアップします。クライアントには、サーバーに配備された EJB へのリモート参照となる IOR が戻されます。このオブジェクト参照を使って、クライアントコードは EJB でリモートメソッドを呼び出します。
Bean の InitialContext ルックアップとメソッド呼び出しにより、Java で記述されたアプリケーション要求データの配列は IIOP メッセージに変換され、サーバー ORB が作成したソケット接続に送信されます。次に、サーバーは応答データを作成し、それを同じ接続に戻します。このデータの配列はクライアント ORB によって解除され、処理のためにクライアントコードに戻されます。リッチクライアントアプリケーションが終了すると、クライアント ORB は接続を終了し、閉じます。
ORB のパフォーマンスチューニング
高いパフォーマンスやスケーラビリティを得るために、デフォルト設定や、非標準オプションの追加が必要になることがあります。ORB のチューニングに利用できる主要コンポーネントは、次のとおりです。
- ORB 間通信インフラストラクチャ
- サーバー ORB スレッドプール
負荷のバランス、複数の共有接続、サーバースレッドプール、メッセージのフラグメントサイズをチューニングすることで、応答時間を短くすることができます。スケーラビリティは、複数の ORB サーバーを使ってクライアントからの負荷を均等に分散し、クライアントとサーバーの間の接続数をチューニングすることで得られます。
ORB の設定可能要素
ORB には、次の設定可能要素があります。
- ORB 間通信インフラストラクチャ: このインフラストラクチャを利用することで、メッセージサイズ、ロードバランス (負荷が大きい場合)、高スループット、高パフォーマンスに適したチューニングを行えます。
- サーバー ORB スレッドプール: ORB スレッドプールでは、値を設定して制御できるマルチスレッドを使って、必要な作業を迅速かつ同時に実行できます。スレッドをプールすることで、スレッドの作成、スレッドスタックの割り当て、スレッドに関連する GC などのオーバーヘッドを回避できます。場合によっては、スレッドの作成と削除が過剰に行われ、OutOfMemoryError, が生じることがあります。スレッドプールにしきい値を設定することで、これを回避できます。
ORB スレッドプールには、タスクキューのスレッドとプールのスレッドがあります。タスクはタスクキューに入れられ、空きスレッドはキューからタスクを取り出して実行します。タスクキューが常に空になるほどスレッドプールを大きくすることはお勧めできません。アプリケーションインスタンスの「現在のタスクキューのサイズ」と max-thread-pool-size の比率は、常に 1:10 程度となるのが普通です。スレッドプールには、max-thread-pool-size を steady-thread-pool-size (通常サイズ) より大きく設定していると、現在のサイズが通常サイズより大きくなったときに通常のサイズに戻す機能があります。steady-thread-pool-size には、標準的な (RMI/IIOP) 負荷に必要な平均スレッド数を設定します。
アプリケーションサーバーの現在のバージョンでは、ORB スレッドプールは主に次の 2 つの目的で使用されます。
- すべての ORB 要求の実行
- EJB プールおよびキャッシュの縮小
このため、リモート呼び出しに ORB を使わない (RMI/IIOP を経由しない) 場合でも、EJB プールとキャッシュのクリーニング機能を利用できるように、スレッドプールのサイズを設定しておく必要があります。
ORB のプロパティ
ORB をチューニングするプロパティは、管理インタフェースを使って管理できます。
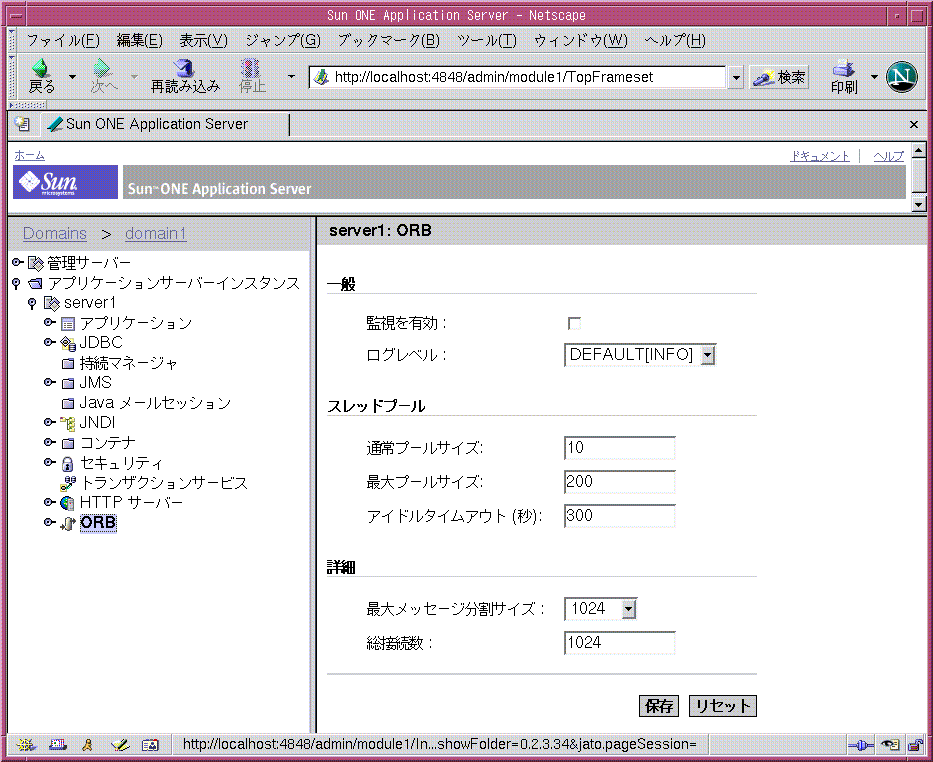
図: 管理インタフェースによる ORB プロパティのチューニング
ORB のチューニングには、次の標準プロパティを利用できます。
- message-fragment-size: このサイズ (バイト単位) を超える CORBA GIOPv1.2 メッセージは分割されます。すべてのサイズは、8 の倍数で指定する必要があります。複数に分割できる GIOP v1.2 メッセージは、Request、Reply、LocateRequest、LocateReply です。最初のメッセージは通常の Request または Reply メッセージで、分割の可否を指定するフィールドは true に設定されています。ORB 間メッセージのほとんどがデフォルトサイズ (1024 バイト) より大きい場合は、このサイズを大きくすることで、分割によるネットワーク待ち時間を短縮できます。
- steady-thread-pool-size: ORB スレッドプールの最小スレッド数を指定します。サーバーが安定した状態 (通常の負荷状態) で要求 (および EJB のクリーニング) の処理に必要なアクティブスレッドの数に近い値を設定する必要があります。
- max-thread-pool-size: ORB スレッドプールの最大スレッド数を指定します。
- idle-thread-timeout-in-seconds: アイドル状態のスレッドがプールから削除されるまでのタイムアウト値を指定します。スレッドプールのサイズを縮小することができます。
- max-connections: すべてのリスナーで一度に受け付けることができる接続の最大数を指定します。接続数の上限を設けることで、サーバーの状態を保護します。この値は、接続からアクティブにデータを読み取るスレッドの最大数とも一致します。
- iiop-listener: このプロパティは、ORB にリスナー (SSL または HTTP) を追加し、リスナーのホストとポートを指定します。有効化された ORB リスナーは、サーバーソケットで受信する接続要求をアクティブに待機するスレッドに変換します。
次の図は、管理インタフェースの IIOP リスナーチューニング画面を示しています。
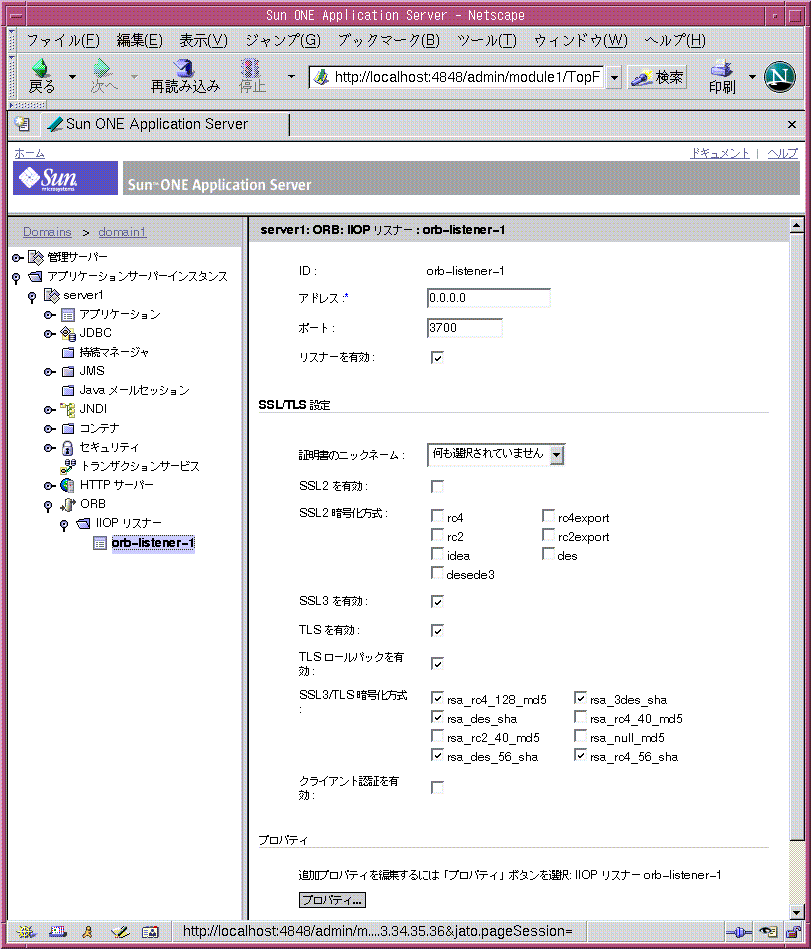
図: 管理インタフェースによる HTTP リスナーのチューニング
標準外の ORB プロパティとその機能
次の値を指定するときは、クライアントプログラムを起動するときに引数 -D を指定します。
クライアントとサーバー ORB の間の通信の制御
クライアントでデフォルトの JDK ORB を使うときは、最初のコンテキストを作成するたびにクライアント ORB からアプリケーションサーバー ORB への接続が作成されます。これらの接続が同じプロセスで作成された場合に、これををプールする、または共有するときは、クライアント ORB の設定に次の行を追加します。
-Djava.naming.factory.initial=com.sun.appserv.naming.S1ASCtxFactory
複数接続によるスループットの改善
Sun ONE コンテキストファクトリ (com.sun.appserv.naming.S1ASCtxFactory) を使うときは、クライアント ORB からサーバーへの接続数を指定する設定可能要素も重要になります (デフォルト値は 1)。この機能を利用することで、ネットワーク上のアプリケーションインスタンスで、サーバーとの通信スループットが改善されます。クライアント ORB の設定を変更するときは、次の jvm オプションを追加します。
-Djava.naming.factory.initial=com.sun.appserv.naming.S1ASCtxFactory
-Dcom.sun.appserv.iiop.orbconnections=[number]
DNS の設定によるサーバー側の負荷のバランス
特別に設定した DNS を使うことで、1 つまたは複数のクライアント ORB が負荷を均等に分散できます。nslookup を呼び出すたびに、nslookup が特定ホストの IP アドレスのリストを利用して本来の負荷バランス機能を利用できるように、DNS にはホスト名のリストが設定されています。セクション 2.3.2 に指定されている接続プールを使って、利用する接続の数を指定することもできます。クライアント ORB の設定を変更するときは、次の jvm オプションを追加します。
-Djava.naming.factory.initial=com.sun.appserv.naming.S1ASCtxFactory
-Djava.naming.provider.url.pkgs=com.sun.enterprise.naming
-Djava.naming.provider.url=iiop://${SERVER_HOST}:${ORB_PORT}
クライアント側でのサーバーインスタンスの設定によるサーバー側のロードバランス
複数の ORB リスナー (または複数の独立した ORB プロセス) で単純なラウンドロビンスキームを利用することで、1 つまたは複数の ORB が負荷を均等に分散できます。制御された数のクライアントが RMI/IIOP パスを使ってサーバーに負荷を加える B2B 環境では、この設定をお勧めします。セクション 2.3.2 に指定されている接続プールを使って、利用する接続の数を指定することもできます。クライアント ORB の設定を変更するときは、次の jvm オプションを追加します。
-Djava.naming.factory.initial= com.sun.appserv.naming.S1ASCtxFactory
-Djava.naming.provider.url.pkgs=com.sun.enterprise.naming 5.
-Dcom.sun.appserv.iiop.loadbalancingpolicy=roundrobin,host1:port1,h ost2:port2,... ,host[n]:port[n]
優れたパフォーマンスの CORBA Util Delegate クラス
JDK にバンドルされた ORB または Sun ONE Application Server ORB を使うときは、CORBA Util Delegate の優れたパフォーマンスを利用できます。これを利用するには、設定 (server.xml) に次の行を追加します。
<jvm-options>-Djavax.rmi.CORBA.UtilClass=com.iplanet.ias.util.orbut il.IasUtilDelegate</jvm-options>
ORB の負荷のバランスと接続をチューニングするときは、サーバー ORB に作成できる接続の数に注意する必要があります。常に少数の接続から始めて徐々に数を増やし、パフォーマンスの改善を調べることをお勧めします。サーバーへの接続は、その接続からアクティブにデータを読み取る ORB スレッドに変換されます。これらのスレッドはプールされませんが、接続が閉じられるまでは存在し続けます。
設定可能要素の使用について
次の表は、アプリケーションのチューニングに関連する ORB モジュールと、サーバーの設定可能要素を示しています。
スレッドプールのサイズ設定
これまでに説明した方法でインバウンドとアウトバウンドの接続の数を調べたら、スレッドプールのサイズをチューニングします。これは、サーバーのパフォーマンスと応答時間に大きく影響します。
このサイズを計算するときは、並行して処理する要求の数、マシンで利用できるリソース (CPU の数、メモリの量など)、クライアント要求の処理に必要な応答時間を考慮する必要があります。小さすぎる値を設定すると、サーバーが並行して処理できる要求の数に影響します。ワーカースレッドによる処理が開始されるまでタスクがタスクキューに入れられるため、要求への応答時間が長くなります。一方、要求を処理するワーカースレッドの数を増やすと、スレッド数の増加によってより多くの並行処理が行われるようになるため、より多くのシステムリソースが消費され、システム全体のパフォーマンスが低下することがあります。つまり、スレッドが EJB コンテナ内の共有ストラクチャを取得するまでにかかる時間が長くなり、応答時間に影響します。ワーカースレッドプールは、プールやキャッシュの縮小など、EJB コンテナのクリーニング用にも使用されます。サイズを決定するときは、この処理も考慮する必要があります。
サーバーはすべてのスレッドを維持する必要があるため、ORB ワーカースレッドの数を過剰に増やすことも問題です。アイドル状態のスレッドは、idle-thread-time-out-in-seconds を過ぎると削除されます。次の例は、server.xml の一部のコードを示しています。これには、iiop-service のセクションが含まれます。
<iiop-service>
<orb message-fragment-size=1024
steady-thread-pool-size=10
max-thread-pool-size=200
idle-thread-timeout-in-seconds=300
max-connections=1024
monitoring-enabled=false />
<iiop-listener id=orb-listener-1 address=0.0.0.0 port=3700 enabled=true>
</ioop-listener>
関連する注意点
pass-by-value セマンティクスと pass-by-reference セマンティクスに関する注意点については、「EJB コンテナのパフォーマンスチューニング」を参照してください。
IIOP メッセージの分析
Sun ONE Application Server から渡される IIOP メッセージの内容の分析が役立つことがあります。メッセージのダンプを取得するには、-Dcom.sun.CORBA.ORBDebug=giop を jvm オプションとして server.xml に渡します。ダンプは server.log ファイルに生成されます。クライアント ORB でも同じオプションを利用できます。
次に、出力例を示します。
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: ++++++++++++++++++++++++++++++
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: Message(Thread[ORB Client-side Reader, conn to 192.18.80.118:1050,5,main]):
createFromStream: type is 4 <
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: MessageBase(Thread[ORB Client-side Reader, conn to 192.18.80.118:1050,5,main]): Message GIOP version: 1.2
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: MessageBase(Thread[ORB Client-side Reader, conn to 192.18.80.118:1050,5,main]): ORB Max GIOP Version: 1.2
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: Message(Thread[ORB Client-side Reader, conn to 192.18.80.118:1050,5,main]): createFromStream: message construction complete.
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: com.sun.corba.ee.internal.iiop.MessageMediator(Thread[ORB Client-side Reader, conn to 192.18.80.118:1050,5,main]): Received message:
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: ----- Input Buffer -----
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: Current index: 0
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: Total length : 340
[29/Aug/2002:22:41:43] INFO (27179):CORE3282:stdout: 47 49 4f 50 01 02 00 04 0 0 00 01 48 00 00 00 05 GIOP.......H....
注 -Dcom.sun.CORBA.ORBdebug=giop フラッグを指定すると、ログファイルに多数のデバッグメッセージが生成されます。メッセージの分割が想定される場合にだけこのオプションを利用してください。
分割メッセージ
上の例では、「createFromStream」の種類は 4 と出力されています。これは、このメッセージが、容量の大きなメッセージを分割した一部であることを示しています。分割サイズを変更することで、メッセージが分割されないようにすることができます。これは、メッセージが複数に分割されずに単体として送信されるため、分割した複数のメッセージ (部分) を送信するオーバーヘッドと、受信側でメッセージを元の状態に戻すオーバーヘッドを回避できることを意味します。分割サイズの指定が小さいために、アプリケーションに送信するほとんどのメッセージが分割される場合は、分割サイズを大きくすると効率が向上する可能性があります。一方、ごく少数のメッセージしか分割されない場合は、分割されるメッセージの数が増えない程度に分割サイズを小さくすることで、メッセージの書き込みに割り当てるバッファを小さくすることができます。
EJB のローカルインタフェース
EJB のローカルインタフェースを使う場合は、ORB が使用されないことに注意してください。この場合、すべての引数は参照によって渡され、オブジェクトのコピーは行われません。
トランザクションマネージャのチューニング
分散トランザクションシステムでは、後からトランザクションを復元できるように、トランザクションアクティビティがトランザクションログに書き込まれます。しかし、トランザクションログへの書き込みはパフォーマンスに影響します。トランザクションの復元よりもパフォーマンスの方が重要な場合は、disable-distributed-transaction-logging プロパティを使ってログの記録を無効化します。このプロパティは、デフォルトでは server.xml に設定されていません。
トランザクションマネージャを使う場合は、automatic-recovery 属性と key-point-interval 属性もパフォーマンスに影響します。automatic-recovery を true に設定すると、disable-distributed-transaction-logging が無視され、トランザクションログが常に記録されます。automatic-recovery を false に設定した場合は、disable-distributed-transaction-logging に従ってトランザクションログを記録するかどうかが決定されます。
automatic-recovery
この値は、disable-distributed-transaction-logging 属性とともにパフォーマンスに影響します。これは次のように機能します。
- automatic-recovery を true に設定すると、トランザクションログが常に記録されます。
- automatic-recovery が false で、disable-distributed-transaction-logging がオフ (デフォルトの設定) の場合は、ログは記録されます。
- automatic-recovery が false で、disable-distributed-transaction-logging がオンの場合は、トランザクションログは記録されません。これにより、パフォーマンスを約 20% 改善できますが、トランザクションログが残らないため、復元は不可能となります。言い換えれば、トランザクションログを記録する 1 と 2 では、パフォーマンスが約 20% 低下します。これらの結果は、グローバルトランザクションの集中テストによって得られた値です。実際のアプリケーションでは、影響が小さくなることがあります。
keypoint-interval
このプロパティのデフォルト値は 2048 です。キーポイントを設定することで、完了したトランザクションのエントリを削除してログファイルをクリーニングする頻度が設定され、プロセスの物理的なログサイズが大きくなり過ぎないように制限できます。頻繁にチェックするポイントを設定すると、パフォーマンスに影響します。ほとんどの場合は、デフォルトの設定で問題ありません。
次の図は、管理インタフェースのトランザクションマネージャ設定画面を示しています。
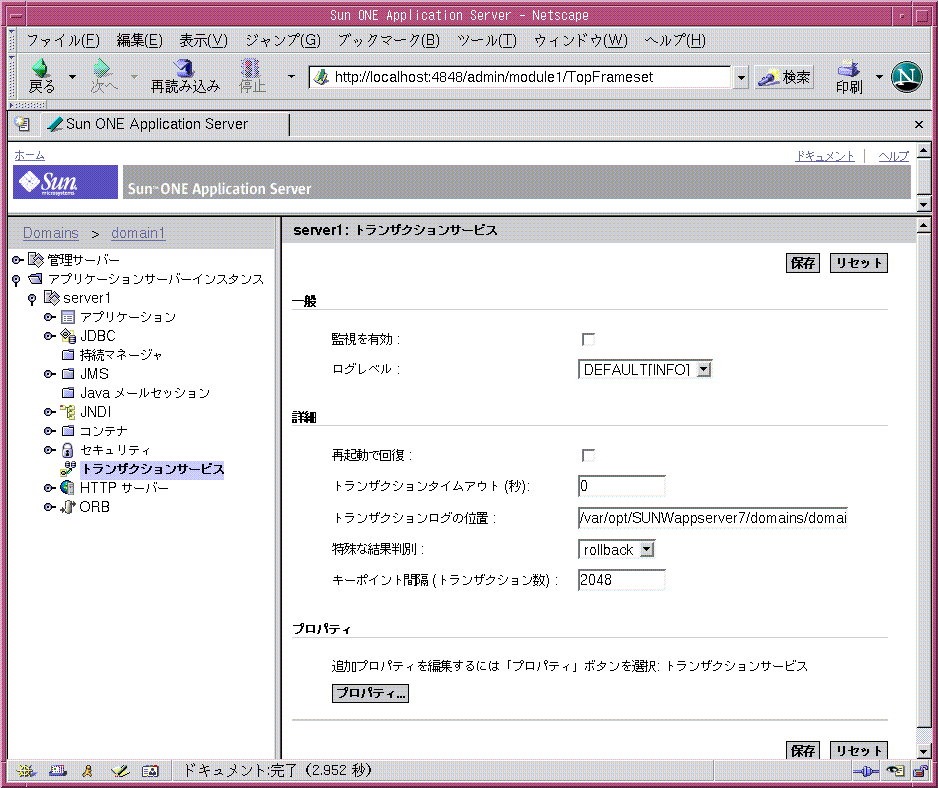
図: 管理インタフェースによるトランザクションサービスのチューニング
トランザクションマネージャの監視
トランザクションマネージャを監視して、パフォーマンスに関する統計を得ることができます。この統計を出力するには、asadmin ユーティリティを使って次のコマンドを実行します。
asadmin>export AS_ADMIN_USER=admin AS_ADMIN_PASSWORD=password AS_ADMIN_HOST=localhost
asadmin>get -m server1.transaction-service.*次の、上記コマンドの出力例を示します。
********** Stats for JTS ************
total-tx-completed = 244283
total-tx-rolled-back = 2640
total-tx-inflight = 702
isFrozen = False
inflight-tx =
Transaction Id , Status, ElapsedTime(msec)000000000003C95A_00, Active, 999
参考資料
- プロファイルの詳細については、『Sun ONE Application Server 開発者ガイド』の「J2EE アプリケーションの開発」の章にある「プロファイルツール」を参照してください。
- SNMP 監視の詳細については、『Sun ONE Application Server 管理者ガイド』の「Sun ONE Application Server の監視と管理」の章を参照してください。
- server.xml ファイルの詳細は、『Sun ONE Application Server 管理者用設定ファイルリファレンス』を参照してください。