リリース12
E06012-01
目次
前へ
次へ
| Oracle Advanced Supply Chain Planningインプリメンテーションおよびユーザーズ・ガイド リリース12 E06012-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この章のトピックは、次のとおりです。
割付の調整
「物流計画ワークベンチ」では、物流センター間または物流センターから最終需要(受注および予測)への供給割付の分析および更新について、複数の方法が用意されています。割付計画または水平プランにアクセスし、搬送計画による不足分の供給の割付方法に関する情報を確認できます。社内転送を調整して確定し、受注および予測に割り付けることができます。
割付を調整するには、次の方法があります。
割付計画を更新します。ソースから宛先組織への割付を調整します。
複数組織の表示水平プランを分析し、「需要/供給」ウィンドウで転送日と数量を確定します。
社内受注および購買依頼の数量を確定して更新し、計画済のインバウンド出荷とアウトバウンド出荷も確定します。
実績発注と計画発注および計画購買依頼を確定します。
確定計画オーダーを更新して、宛先組織に対する仕入先生産能力の割付を調整します。
受注と予測に対して手動で組織別に割り付けます。
物流センターに対する割付の調整
割付計画のコンテキストは、ユーザーのアクセス場所から導出されます。次の場所から右クリックします。
「水平プラン」で右クリックすると、水平プランの同一組織品目の割付計画がオープンします。
「品目」ウィンドウで右クリックすると、「品目」行と同じソース組織品目の割付計画がオープンします。
「供給と需要」ウィンドウで右クリックすると、需要行または供給行と同じソース組織品目の割付計画がオープンします。
水平ディメンション、顧客、顧客サイトおよび需要区分には3つの選択肢があります。割付計画を右クリックして水平ディメンションを変更できます。
フォーム上部の日付範囲は、各割付バケットの開始日です。割付バケットが週次の場合、この日付は週の開始日です。搬送計画では、他の週次または期間レベルには集計されません。2週間など、一部の割付バケットは期間レベルに正しく集計できないことがあります。
受注、予測、転送需要またはキット需要のいずれであるかに関係なく、バケット別の制約なし需要が表示されます。これは、受注の失効または終了後の正味需要数量ではなく、当初需要数量です。受注には計画オプションに基づく需要日が反映されますが、この日付は搬送計画での再予定日ではなく、提示納期です。
割付計画(搬送計画の新機能)
「供給と需要」ウィンドウ、「水平プラン」、ワークベンチのナビゲータ・ツリーおよび「計画要約」から品目組織の割付計画にアクセス
ソース組織から宛先組織、顧客と顧客サイトおよび需要区分への割付を表示
割付バケット別の表示
顧客リストを使用した特定の顧客の表示
ダブルクリックして「需要/供給」ウィンドウをオープン可能
右クリックして「水平プラン」をオープン可能
顧客に対する割付のレビュー
制約なし需要: 宛先組織、顧客、顧客サイトまたは需要区分に関する制約なし需要合計とバケット内の提示納期。
期限切れ需要: 期限切れ需要の合計数量とバケット内の提示納期(受注および予測)。
ターゲット安全在庫: 割付バケット終了時の組織のターゲット安全在庫レベル。
供給: このソース組織からのこのバケット中の有効供給数量合計(「全組織」ビューには非表示)。
確定割付: 宛先組織の場合、ソース組織からの計画確定転送数量または実績確定転送数量が含まれます。
提示割付数量: このバケット中の供給のうち、この宛先組織、顧客、顧客サイトまたは需要区分に割り付けられた数量。割付元はバケット中の供給で、任意のバケットに提示納期を持つ需要に割り付けることができます。
手動割付数量: コンテキストが宛先組織の場合のユーザー編集可能フィールド。
有効割付数量: このバケットの割付合計(手動割付数量)。NULLの場合は、確定割付と提示割付数量のうち、大きい方の数量。
累積制約なし需要: この宛先組織、顧客、顧客サイトまたは需要区分に対する制約なし需要の累積合計。
累積期限切れ需要: この宛先組織、顧客、顧客サイトまたは需要区分に対する期限切れの制約なし需要の累積合計。
累積供給: このソース組織のこれ以前の全バケットの有効供給数量合計。
累積提示割付数量: この宛先組織、顧客、顧客サイトまたは需要区分に対する累積提示割付数量。
累積履行レート: 100% * 累積制約なし需要 / 累積提示割付数量。ターゲット在庫と安全在庫は累積制約なし需要に含まれないため、数量がターゲット在庫または安全在庫に割り付けられている場合は、このレートが0(ゼロ)より大きくなることがあります。
手動割付
ソース組織から宛先組織への手動割付数量を入力できます。数量を入力するには、「割付計画」->「手動割付数量」を選択します。フォームを保存すると、新規の確定計画インバウンド出荷および確定計画アウトバウンド出荷(計画オーダー)が次のように作成されます。
ソース組織から宛先組織への割付。
ソース・ルールからランク1の出荷方法が使用されます。ランク1の出荷方法が複数存在する場合は、最もパーセントの高い出荷方法が使用されます。最上位のパーセントが2つ存在する場合は、最速の出荷方法が使用されます。
出荷日は、割付バケットの開始日に(出荷カレンダと移動中カレンダを考慮して)設定されます。
納入予定日は、出荷方法、移動中カレンダおよび受入カレンダに基づいて設定されます。
新規計画オーダーの数量は、確定割付数量と手動割付数量の差異です。
保存後に更新された表示は、新規に作成された確定計画オーダーを含む確定割付を示します。割付が行われたため、「手動割付数量」フィールドは消去されます。
メッセージ・バーに「<number>件の新規確定計画オーダーが作成されました」というメッセージが表示されます。
確定割付を削減する入力は許可されません。確定割付を削減する必要がある場合は、「供給」ウィンドウをオープンし、確定実績出荷または確定計画出荷を取り消すことができます。
「割付計画」の「手動割付数量」の機能は、次のとおりです。
ユーザー編集可能フィールドです。
「割付計画」で「再設定」ボタンを選択すると、フォームが消去されます。
「割付計画」で「再計算」ボタンを選択すると、有効割付数量が更新され、割付数量が供給数量を超えている場合は警告が表示されます。
手動割付数量の入力を保存すると、確定計画オーダーが次のように作成されます。
ソースから宛先組織への割付です。
デフォルトでソース・ルールからランク1の出荷方法が使用されます。
出荷日は、割付バケットの開始日です。
納入予定日は、出荷方法とカレンダに基づいて計算されます。
水平プラン
「割付計画」のみでなく、水平プランを使用して物流ネットワークでの割付を分析できます。個別の供給レコードにドリルダウンし、計画割付を調整できます。
拡張水平プランを使用して、社内全体の資材の流れをレビューします。複数の組織と、組織固有のインバウンド転送およびアウトバウンド転送が表示されます。
右クリックして割付詳細にナビゲートし、搬送計画の割付決定をレビューします。
ダブルクリックして「需要/供給」ウィンドウにナビゲートし、個別の需要/供給レコードを分析および更新し、ペギング・データをレビューします。
調整後、再計画を使用してダウンストリームへの影響を計算します。
搬送計画の新機能として、水平プランをコールするたびに、水平プランの組織選択オプションが表示されます。表示する初期組織を選択し、水平プラン内で選択内容を変更できます。
ユーザーが設定時に組織リストを定義した場合は、組織リスト名も「組織選択」リストに選択肢として表示されます。
組織表示には、次の組織が含まれます。
単一組織
出荷元組織と出荷先組織
全組織
組織リスト内の組織
水平プランには、次のフィールドを表示できます。
外部需要: 受注と予測が含まれます。
受注
予測
キット需要: キット需要は、キットの構成部品に対する制約付き依存需要です。たとえば、品目Aが品目Xの製造に使用されるとします。キット需要は、品目Xを製造するための計画オーダーとショップ型製造オーダーから生成される、品目Aに対する需要です。
アウトバウンド出荷: 社内受注と計画アウトバウンド出荷が含まれます。計画担当は、この行のバケットの「供給と需要」ウィンドウにドリルダウンし、社内受注と計画アウトバウンド出荷を表示できます。
その他需要: 確定在庫引当(対象は受注)、需要計画としての他の物流計画からの組織間需要、コピーされた計画需要、需要区分消込、期限切れロット、廃棄需要および非標準需要が含まれます。
需要合計: 外部需要、計画アウトバウンド出荷、その他需要およびキット需要が含まれます。キット需要は、キットの計画オーダー需要、非標準ショップ型製造オーダー需要およびショップ型製造オーダー需要で構成されます。
要求アウトバウンド出荷: 要求アウトバウンド出荷である制約なし転送需要が含まれます。
制約なしキット需要: 制約なしキット計画オーダー需要とショップ型製造オーダー需要が含まれます。
その他制約なし需要: 確定在庫引当、搬送計画の組織間需要、コピー済計画需要、需要区分消込、期限切れロット、破棄需要および非標準需要が含まれます。
制約なし需要合計: 制約なしキット需要、その他制約なし需要、外部需要および要求アウトバウンド出荷が含まれます。
内部供給: 期首在庫数量、仕掛数量、受入中資材および計画オーダーが含まれます。
期首在庫数量
受入中: 受入中の合計数量です。
WIP
外部供給: 移動中、発注、購買依頼および計画オーダーが含まれます。
要求インバウンド出荷: 制約なし転送供給数量。ユーザー・インタフェースにより、ソース組織の要求アウトバウンド出荷の提示納期 + デフォルト出荷方法の移動中リード・タイムとして導出されます。その他の日付は、カレンダを使用して再計算されます。計画エンジンからの直接出力ではありません。要求インバウンド出荷は、オーダー・サイズ違反となる場合があります。
インバウンド出荷: 供給振替。移動中、購買依頼および計画インバウンド出荷が含まれます。計画担当は、この行のバケットの「需要/供給」ウィンドウにドリルダウンして供給を表示できます。
移動中
発注
購買依頼
全計画オーダー: 計画製造オーダー、計画発注および計画インバウンド出荷が含まれます。
供給合計: 仕掛、発注、購買依頼、移動中、受入中、計画オーダーおよび返品が含まれます。
現行計画受入: 仕掛、発注、購買依頼、移動中、受入中および返品が含まれます。
予定在庫数量: 「予定使用可能残高」と同じですが、計画オーダーは含まれません。
予定使用可能残高: 期首在庫数量、供給合計および需要合計が含まれます。
制約なし予定使用可能残高: 期首在庫数量、供給合計および制約なし需要合計が含まれます。
最大数量
ターゲット数量
安全在庫数量
インバウンド移動中在庫
アウトバウンド移動中在庫
ネットATP
失効済ロット
水平プランの割付詳細の表示
需要優先度、割付バケット、ソース組織、宛先組織および確定フラグごとに、供給割付詳細行があります。品目が構成部品の場合は親品目ごとの1行もありますが、宛先組織はNULLになっています。割付バケットの詳細を表示するには、需要または供給行を右クリックして「割付詳細」を選択します。
次のようなフィールドが表示されます。
需要優先度: 在庫再残高計算需要は、優先度0(ゼロ)として表示されます。他のすべての需要は、当初需要優先度で表示されます。
確定フラグ: 需要が確定であるか、宛先組織での確定供給からペグされるかを示します。
確定需要繰越バケット: 確定需要が繰り越される割付バケット数。確定需要が現行バケットにある場合、バケット数量は0(ゼロ)です。
割付詳細行
優先度別の需要、各需要タイプに対する供給の割付方法および優先度が表示されます。
前の割付バケットから繰り越された需要が表示されます。
割付バケット別の期間が表示されます。
オーダー・タイプ
「供給と需要」ウィンドウには、次の新規オーダー・タイプが表示されます。
要求インバウンド出荷と要求アウトバウンド出荷: 組織間の社内転送に対する制約なし需要。ソース組織についてはアウトバウンド、宛先組織についてはインバウンドが表示されます。
計画インバウンド出荷と計画アウトバウンド出荷: 計画社内転送に対する制約付きの需要および供給オーダー・タイプ。
社内受注と社内購買依頼が存在する場合は、既存の社内転送に対する制約付きの需要および供給オーダー・タイプとなります。
計画転送の場合、「供給と需要」ウィンドウには次の行が表示されます。
計画インバウンド出荷
要求インバウンド出荷
計画アウトバウンド出荷
要求アウトバウンド出荷
社内購買依頼と社内受注の場合、「供給と需要」ウィンドウには次の行が表示されます。
社内購買依頼
要求インバウンド出荷
社内受注
要求アウトバウンド出荷
要求インバウンド出荷と要求アウトバウンド出荷は、ソース組織または宛先組織にとっては同じ資材移動であるため、同じオーダー番号が表示されます。
提示納期: 要求インバウンド出荷の納期は、関連付けられている実績需要の納期と同じ日時です。たとえば、予測の納期が3日の00:00:00の場合、要求インバウンド出荷の提示納期も3日の00:00:00となります。
計画タイム・フェンス: 要求インバウンド出荷の提示納期では計画タイム・フェンスが考慮され、リード・タイムが十分でない場合、提示納期は計画タイム・フェンスに設定されます。要求インバウンド出荷の場合、計画タイム・フェンスはオーダー開始日または出荷日ではなく納期に適用されます。
提示納入予定日: 提示納入予定日は、提示納期からの後処理リード・タイム分のオフセットです。提示納入予定日が非稼働日に該当する場合は、前倒しされます。
制約なしキット需要: キットの構成部品である品目について生成された制約なし需要。これは出荷行タイプではありません。
制約付きキット需要: キットの構成部品であり、キットを製造するための計画オーダーの結果である品目について生成された、制約付き需要。 これは出荷行タイプではありません。
割付のペギング
各バケットにおける各需要の割付数量は、最初に割付ルールに基づいて決定されます。その後、各需要がそのバケット中に割付可能な供給にペグされます。各供給は、最終需要組織内の1つ以上の供給にペグされます。
供給間のペグは、ロードの連結の完了後に作成されます。このペギングは、宛先(計画インバウンド出荷または社内購買依頼)での制約付き供給が、ソース(計画インバウンド出荷、社内購買依頼および在庫)での制約付き供給にペグされたことを示します。実際には、ソースからの供給のうち、宛先での制約付き供給に含まれる部分を示します。
組織間で表示されるペギングをオーダー・タイプ別に示すと、次のようになります。
要求インバウンド出荷(制約なし供給)
供給へのペギング: ソース組織での制約なし需要から、ソース組織での供給にペグされます。
需要へのペギング: 表示されません。
要求アウトバウンド出荷(制約なし需要)
供給へのペギング: この組織での供給が表示されます。
需要へのペギング: 表示されません。
計画インバウンド出荷(制約付き供給)
供給へのペギング: ソース組織での供給が表示されます。
需要へのペギング: 同じ組織での需要が表示されます。
計画アウトバウンド出荷(制約付き需要)
供給へのペギング: 表示されません。
需要へのペギング: 宛先組織での供給、計画インバウンド出荷、その上位から需要にペグされます。
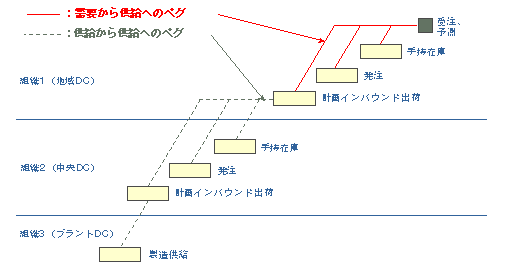
搬送計画では、Oracle Advanced Supply Chain Planningのペギング・プロファイル・オプションは使用しません。
割付調整の検証
オンラインおよびバッチ再計画を使用して、ユーザーが入力した割付調整の結果をチェックできます。再計画されるのは、需要または供給に変更があった品目のみで、トリップが完全に再計画されることはありません。
オンラインおよびバッチ再計画では、計画担当が行った手動変更の内容に基づいて再計画の対象品目が決定されます。
需要変更には、需要の追加と、需要数量、納期または需要優先度の変更が含まれます。
供給変更には、新規供給の追加と確定、および供給数量または日付の変更と確定が含まれます。
仕入先生産能力の変更には、仕入先生産能力の追加または削減が含まれます。
トリップの変更には、トリップの確定(確定がトリップの全アウトバウンド出荷明細にカスケードされます)と、トリップの日付変更(変更後の日付がトリップの全アウトバウンド出荷明細にカスケードされます)が含まれます。
ロードの連結は、オンラインおよびバッチ再計画中には完全に再計算されません。ロード連結の再計算は、次の(変更後の品目に対する)操作を伴います。
既存のトリップから出荷明細がすべて削除されます。
トリップは確定とみなされ、再計画されません。ただし、トリップには新規の出荷明細を追加できます。
トリップを変更後の品目の出荷明細とともにロードできない場合は、トリップが作成されます。
追加した新規出荷明細が十分でないと、変更後の品目の出荷明細が削除された後、既存のトリップが稼働率不足になる場合があります。
受注に対する割付の調整
個別の受注と予測に割り付けるには、「割付計画」または「水平プラン」から「供給と需要」ウィンドウにドリルダウンします。次の操作を実行できます。
納期に受注明細(または予測)全体を確定
新規の日付に受注明細全体を確定
新規の日付に受注明細を分割して一部のみを確定
部分的な受注明細を分割して明細を1つのみ確定
その後、「オンライン再計画」または「バッチ再計画」を実行します。最初に確定需要が割り付けられてから、他のすべての需要が残りの供給に再割付されます。
ユーザーは需要(予測または受注)の「確定フラグ」を選択し、「新規日付」フィールドと「新規数量」フィールドの両方を更新して需要の提示納期を(前日付または先日付に)変更し、オプションで需要数量を変更します。
「確定フラグ」が選択され、新規日付と新規数量が移入されている受注需要と予測需要は、搬送計画でのバッチまたはオンライン再計画中に最初に(他の確定需要とともに)割付を受けます。「確定フラグ」の通常の動作の対象となる受注需要と区別するために、この需要を日付/数量確定と呼びます。「新規日付」および「新規数量」フィールドの値なしで、単に受注を確定する場合、動作に変更はありません。受注の「確定フラグ」が選択されている場合、受注のソース組織は変更できません。
日付/数量確定の受注は、1回の完全な計画実行から次回の計画実行までの間保持されません。日付/数量確定の受注には、「上書きオプション」フラグは適用されません。完全な計画実行により、常に受注のスナップショットが再取得されます。
例:
ユーザーが、4日遅れの受注を選択して確定します。
その受注について新規日付(納期)と新規数量を入力します。
再計画により、この受注に新規日付の供給が割り付けられてから、未確定の他の受注に供給が割り付けられます。
割付計画
「割付計画」で、搬送計画の割付決定を顧客別に表示します。使用する手順は、次のとおりです。
ソース組織から顧客および顧客サイトの需要区分への割付を表示します。
割付バケット別に表示します。
顧客リストを使用して特定の顧客を選択します。
受注数量をダブルクリックして特定の受注の「需要/供給」ウィンドウをオープンし、需要を確定してオプションで分割します。
組織コンテキストのない品目ノードからオープンすると、「割付計画」には企業全体の割付が顧客別に表示されます。全物流センターについて、各顧客への割付合計を分析できます。この方法を使用するのは、多数の顧客サイトが多数の異なる物流センターから調達している場合です。
トリップの連結
ユーザーは、「機会の検索」ウィンドウで特定の転送と連結を選択できます。処理は次のとおりです。
ターゲット・トリップに出荷明細を追加します。
ターゲット・トリップの「重量」および「キューブ」フィールドを更新します。
出荷明細を確定し、新規の出荷日、納入予定日および出荷方法に更新します。
オーダー日や開始日など、他の日付は更新しません。これらの日付は、再計画または完全な計画起動の実行時に更新されます。
計画担当は、稼働率不足のトリップを様々な方法で検索できます。「計画要約」でトリップの稼働率不足例外を最も重要な例外に追加したり、「例外要約」でトリップの稼働率不足例外をオープンできます。また、「トリップ」フォームで稼働率をチェックすることも可能です。これらのどのフォームからも、「トリップの連結」ウィンドウをオープンして作業し、トリップの稼働率を改善できます。
計画担当は、「トリップの連結」ウィンドウから「機会の検索」アルゴリズムを使用できます。このアルゴリズムでは、次の検索基準を入力として使用し、考慮対象となる転送のターゲット・トリップへの配置を制限します。
「稼働率 %」(重量とキューブ): 常に入力値より小さくなります。
出荷日からの日数: ターゲット・トリップの出荷日の前後の日数。
供給可能前倒日数: 個別出荷(社内購買依頼)の場合、これはトリップの出荷日以前の日付になります。マイナスの値を入力すると、個別出荷は、実績出荷の指定日数が出荷のため計画されるまでは使用できない供給とともに考慮されます。この前提により、計画担当が出荷を早めることができます。
トリップから「機会の検索」フォームにナビゲートします。
稼働率不足のトリップが表示されます。
パラメータを入力して、稼働率不足のトリップでロードできる他の転送を検索します。
転送を選択し、選択したアウトバウンド出荷の出荷日、納入予定日および出荷方法を変更します。次に「連結」をクリックし、ターゲットである稼働率不足のトリップに追加します。
オプションで、この時点または後からリリースします。
「トリップの連結」フォームの上部に、計画担当が稼働率を改善しようとしているターゲット・トリップに関する情報が表示されます。
「機会」リージョンに、ユーザーが検索アルゴリズムに入力した値に基づいて選択されたトリップが表示されます。
「出荷明細」リージョンに、「機会」リージョンでハイライトされているトリップの明細が表示されます。
需要遅延日数: ターゲット・トリップ(納入予定日 + 後処理日数) - 希望入手日。遅延の場合は赤で表示されます。
供給遅延日数: トリップ出荷日 - 供給可能日。遅延の場合は赤で表示されます。
「需要遅延日数」および「供給遅延日数」フィールドの両方で、トリップは上部リージョンに表示されているトリップ、つまり、出荷明細の追加先として検索しようとしているトリップを指します。需要納期を満たすことに問題があるか、新規出荷日に有効な供給に問題がある場合は、両方のフィールドが赤で表示されます。
各出荷明細の「供給可能日」フィールドは、ペギング関連に基づいて計算されて表示されるため、供給がソース組織で使用可能になる早期日数を把握できます。現在よりも早いトリップに移動できる場合があります。
供給の前倒し
物流プランナは、同じワークベンチ機能を使用して、MRP/MPS/MPP計画で使用される供給を前倒しできます。例外管理機能とワークベンチ機能を使用して、次の操作を実行できます。
仕入先生産能力の追加
代替仕入先の選択
移動時間の短縮
仕入先応答に基づくオーダーの早期確定
在庫の再残高計算
計画の在庫再残高計算要件をレビューします。
計画オーダーで在庫再残高計算のソース例外が使用されるかどうかをチェックし、在庫再残高計算処理を計画別にレビューします。必要に応じて、在庫をリリースして計画オーダーの再残高計算を実行します。
複数組織に水平プランを使用して、その他の在庫再残高計算が必要かどうかを判断します。
在庫再残高計算機能の詳細は、「MSC: 在庫再残高計算剰余在庫ベース」プロファイル・オプションおよび計画オプション「在庫再残高計算剰余日数」計画オプションを参照してください。
トリップの更新とリリース
「トリップ」フォームを使用してトリップを更新およびリリースします。
トリップの出荷日、納入予定日および出荷方法を更新します。
トリップの変更により、そのトリップによる社内転送がすべて更新されます。
トリップをリリースして、そのトリップによる社内転送をすべてリリースします。
「トリップ」フォームで、ユーザーはトリップの出荷方法、出荷日および納入予定日を変更できます。納入予定日または出荷日の一方を変更し、他方の日付を空白にすると、その日付は選択した出荷方法に基づいて計算されます。出荷方法を選択していない場合は、両方の日付を入力する必要があります。
ユーザーは、「トリップ」フォームでトリップを確定してリリースできます。
トリップのすべての変更内容(日付変更、確定およびリリースなど)は、特定のトリップに関する社内購買依頼、社内受注、計画インバウンド出荷および計画アウトバウンド出荷に伝播します。
ユーザーは「供給と需要」ウィンドウでトリップに対する社内出荷を削除または追加できます。
トリップのロードの分析
「トリップ割付詳細」フォームで、トリップのロード方法を分析します。
トリップを右クリックして「トリップ割付詳細」を表示します。
詳細明細ごとに、次の操作を実行します。
出荷明細のロード時に、宛先での制約なし需要をソースでの制約付き供給に関連付けます。
供給日: この需要に対してソース組織で供給が使用可能になる最早日です。
最早可能納入予定日: トリップで納入可能、かつ宛先組織で最大在庫レベル違反にならない最早日です。
最遅可能納入予定日: トリップで納入可能、かつ宛先組織で安全在庫レベル違反にならない最遅日です。
「トリップ割付詳細」フォームでは、トリップのうち要求出荷日と要求納入予定日が最も早く優先度が最も高い品目と数量を判断できます。これにより、ユーザーはトリップに追加する必要があるトリップ明細と遅延可能なトリップ明細を決定できます。トリップ連結ウィンドウに含まれない日付については、割付詳細は表示されません。
同様の情報は「供給と需要」ウィンドウにも品目別に表示されますが、「トリップ割付詳細」フォームにはさらに詳細な情報が表示されます。最早納入予定日と最遅納入予定日は、どちらもトリップの出荷方法を使用して計算されます。これらの日付は、より高速または低速の出荷方法により変更でき、これは搬送計画エンジンでトリップ割付詳細明細を特定のトリップに割り当てる前に考慮されます。「トリップ割付詳細」フォームの情報は、その出荷方法に基づくものです。
これらの日付を使用して、手動で出荷を連結する際に考慮できる供給とトリップを決定します。
各トリップ割付詳細明細は、次の両方に関連付けられます。
所要量をトリガーした宛先組織からの制約なし需要(要求アウトバウンド出荷)
宛先組織への制約付き供給(計画インバウンド出荷または社内購買依頼)
「トリップ割付詳細」は、需要に次のように関連しています。
割付およびトリップ・ロード・プロセス中に、搬送計画エンジンでは、宛先組織からの需要が評価され、それぞれの制約なし需要に関連したトリップ割付詳細明細が作成されます。
制約なし需要は、「供給と需要」ウィンドウに要求アウトバウンド出荷として表示されます。
この関係は、トリップ・ロード・エンジン・プロセス中に存在し、ペギング・ツリーの一部として表示されることはありません。
トリップ割付詳細明細数量は、関連需要より大きくなる場合と小さくなる場合があります。
複数のトリップ割付詳細明細を、1つの需要行に関連付けることができます。トリップ割付詳細明細の関連と数には、トリップ・サイズ、宛先組織での需要数、オーダー・モディファイアおよびトリップ・ロード時の内部エンジン・ロジックに基づく優先度などのファクタが反映されます。
また、トリップ割付詳細明細数量は、オーダー・モディファイアが原因で関連需要よりも大きくなる場合があります。
社内購買依頼と社内受注の作成
物流計画から転送用の計画オーダーをリリースできます。
計画アウトバウンド出荷または計画インバウンド出荷をリリースします。
搬送計画のリリース・メカニズムでは、宛先組織での社内購買依頼とソース組織での社内受注の両方が自動的に作成されます。社内購買依頼はリリース・メカニズムの一部として自動的にOracle Order Managementにインタフェースされ、社内受注はリリース・プロセスの一部として作成されます。
トリップまたは個別出荷のリリースの動作は、どちらの文書もリリース・メカニズムによりソース内で作成されるため同じです。
搬送計画では、社内購買依頼を作成してOracle Order Managementにインタフェース済のマークを付けるなど、両方の文書の作成に必要なステップをすべて完了する必要があります。社内受注が作成され、社内購買依頼番号が移入され、社内受注に記帳済のマークが付けられます。また、Oracle Order ManagementのループバックAPIにより、出荷日と到着日の両方が社内受注にロードされます。この2つの日付には、計画決定が反映されます。
社内受注は、作成時に「記帳済」ステータスになります。搬送明細も作成され、Oracle Transportation Managementで使用できます。Oracle Transportation Managementでは、モード、運送業者、サービス・レベルを選択でき、預託準備ができるようにロードを計画できます。
社内受注と社内購買依頼についてソース・インスタンスに移入される日付は、物流計画の「供給と需要」ウィンドウ内の日付と次のように関係します。
社内購買依頼の「希望入手日」は、「物流計画ワークベンチ」の「実施納入予定日」から移入されます。
「最早許容日」は移入されません。
「最終受入期限日」は移入されません。
「計画出荷日」は、「物流計画ワークベンチ」の「実施出荷日」から移入されます。
「計画到着日」は、「物流計画ワークベンチ」の「実施納入予定日」から移入されます。
「要求日」は、「物流計画ワークベンチ」の「実施出荷日」から移入されます。
「納期」は、「物流計画ワークベンチ」の「実施出荷日」から移入されます。
「最早出荷日」(搬送明細で参照可能)は、「資材使用可能日」から移入されます。
受注の「最早出荷日」は「受注」フォームでは参照できませんが、ユーザーはOracle Shippingで受注明細に関連する搬送明細を表示するときに参照できます。そのためには、品目がATP品目であることと、「OM: TP早期出荷/搬送日のソース」プロファイル・オプションが「最早許容日」に設定されていることが必要です。
品目がATP品目で、「OM: TP早期出荷/搬送日のソース」プロファイル・オプションが「最早許容日」に設定されている場合、搬送明細の「最早出荷日」は最早許容日と最早出荷日のうち遅い方の日付に設定されます。
品目がATP品目でない場合、搬送明細の「最早出荷日」には受注明細の「最早許容日」が移入され、その日付がNULLの場合は今日の日付が使用されます。受注の「最早出荷日」は、ATP品目の搬送明細にのみ渡されます。
社内受注と社内購買依頼の再計画
計画担当は、社内転送の再計画と取消をリリースできます。
社内受注は、新規の日付(および、異なる場合は新規の数量または新規の出荷方法)で更新されます。
供給の追跡情報は再計画のリリースにより更新されるため、社内受注が再計画された後も、社内受注と社内購買依頼の供給と需要は同期化されます。
再収集されたデータと物流計画は、社内受注が再計画された後も、同期状態の社内受注日と社内購買依頼日を示します。
ユーザーが再計画後の社内購買依頼と社内受注をリリースすると、Oracle Order Managementの受注処理APIがコールされます。これにより、社内受注が新規日付と新規数量に更新されます。
Oracle PurchasingではOracle Order Managementにインタフェース済の購買依頼の更新が許可されないため、購買依頼自体は変更されません。かわりに、Oracle Order Managementの受注処理APIにより、供給(社内購買依頼から)の追跡情報も更新されます。物流計画では、社内受注からの実績日付および数量が使用され、社内購買依頼詳細は、Oracle Order Managementの受注処理APIにより社内受注との同期状態が維持されている資材供給情報から設定されます。
社内購買依頼と社内受注では、日付が異なる場合があります。ただし、データが収集されて搬送計画で使用された後は、社内購買依頼と社内受注が同期化されます。
受注変更のリリース
物流プランナは、次のような顧客受注の更新をソース・インスタンスにリリース(計画結果をOracle Order Managementに公開)できます。
ソース組織
出荷方法
確定フラグ
提示出荷日
計画到着日
移動中リード・タイム
資材使用可能日
搬送計画には、MRP/MPS/MPP計画と同じ機能が用意されています。「グローバル予測」がサポートされており、搬送計画を使用して受注に最も適したソース組織が選択されます。
競合する各需要に割り付けられる有効供給数量のフェア・シェア・パーセントは、様々なフェア・シェア割付方法(オーダー・サイズ方法以外)により決定されます。
現在の需要率
なし
固定パーセント
安全在庫率
オーダー・サイズ
フェア・シェア割付方法は、次の場合に起動されます。
競合する2つ以上の需要の需要優先度が同一の場合
競合する需要の1つ以上が受注間転送の場合
現行割付バケット中に供給不足があり、特定の優先度の全需要を充足できない場合
オーダー・サイズ・フェア・シェア割付ルールを使用すると、各組織にはオーダー・サイズとフェア・シェア・パーセントに従って有効供給数量が割り付けられます。最初に最大パーセントを持つ組織に割り付けられてから、オーダー・サイズが適用されるため、供給数量が増加する場合があります。次に、2番目に高いパーセントを持つ組織にも、オーダー・サイズに従って供給が割り付けられます。2つの組織が同じパーセントを持つ場合は、まず上位ランクの組織に供給が割り付けられます。
各フェア・シェア・ルールの違いは、フェア・シェア・パーセントの計算方法のみです。計算されたフェア・シェア・パーセントは、まったく同じ方法で適用されます。
供給割付ルールの場合、パーセントまたはオーダー・サイズが同一の場合は、タイブレークにするために組織ランクが使用されます。組織ランクは、組織がフォームに入力された順序から推測されます。2つの組織が特定の供給割付ルールに基づいて同等の場合に、どちらの組織が最初に考慮されるかを管理する必要がある場合は、フォームの上部に最上位優先度の組織を入力します。「需要優先度の上書き」供給割付方法には、推測によるランクは使用されません。
現在の需要率方法
フェア・シェア・パーセントは、現行割付バケット中の競合需要の数量に基づいて計算されます。
1つ以上の組織についてパーセントを入力することもできます。入力したパーセントにより、その組織の実績需要率が上書きされ、残りの組織には需要率に基づいて残りのパーセントが比例配分されます。
パーセントが同一の場合、最初に供給を割り付ける組織はランクを使用して決定されます。
なし(フェア・シェア割付なし)
同一優先度を持つ競合需要に供給を割り付ける際には、現行の先入れ先出しロジックが使用されます。供給は、搬送計画の優先度のペギング・ロジック(先入れ先出し)に基づいて割り付けられます。2つの需要の優先度および納期が同一の場合は、一方の需要が完全に割り付けられてから、他方の需要が考慮されます。どちらの需要が先に割り付けられるかは管理できません。これは、品目-組織に対してフェア・シェア割付方法が指定されていない場合のデフォルト方法です。
固定パーセント方法
ユーザーが「パーセント」フィールドにフェア・シェア・パーセントを入力します。入力したパーセントが割付処理中に使用され、使用可能な供給のうち組織が受け入れる必要のある最小数量が定義されます。割付中には、高パーセントの組織が最初に考慮され、供給がそのパーセントまで割り付けられてから、次の組織が考慮されます。パーセントを定義済の組織がすべて考慮された後、残っている供給があれば先入れ先出し方式で割り付けられます。
定義した固定パーセント値の合計が100%になる必要はなく、計画エンジンにより内部的に100%になるように標準化されることはありません。たとえば、組織1を50%として指定し、他の組織についてはパーセントを指定しないとします。割付時には常に組織1が最初に考慮され、他の組織が考慮される前に供給のうち最大50%の割付を受けることができます。このステップの後、残りの全供給がルール外の組織に1度に1組織に対して割り付けられます。最初に選択される組織により、残りの供給がすべて使い切られる場合があります。すべての組織をルールで定義することを考慮してください。
組織1および組織2がそれぞれ25%として指定され、他に宛先組織がなければ、割付結果はそれぞれ25%がそれぞれ50%に標準化された場合と同様に表示されます。
安全在庫率方法
ある組織のフェア・シェア・パーセントは、その組織の安全在庫レベルを全組織の安全在庫レベルの合計で除算した値です。割付バケット間の安全在庫の平均値を使用して、安全在庫率が決定されます。1つ以上の組織についてパーセントを入力することもできます。
1つ以上の組織についてパーセントを入力することもできます。入力したパーセントにより、その組織の安全在庫率が上書きされ、残りの組織には需要率に基づいて残りのパーセントが比例配分されます。フェア・シェア・パーセントが同一の場合、どの組織に供給を最初に割り付けるかは、ランクを使用して決定されます。
組織の安全在庫が0(ゼロ)の場合は、安全在庫値がプラスの組織よりも下位の優先度が与えられます。割付ステップは次のとおりです。
安全在庫値または指定のパーセントを持つ組織に割り付けられます。
この初回割付の後も供給が残っている場合は、安全在庫が0(ゼロ)の組織に割り付けられます。需要が充足されるまで、ランク別およびランク内で各組織に均等に割り付けられます。
パーセントが同一の場合、最初に供給を割り付ける組織はランクを使用して決定されます。
オーダー・サイズ方法
これは、フェア・シェア・パーセント計算の概念の例外です。「オーダー・サイズ方法」を選択した場合は、固定ロット乗数値を指定する必要があり、ランクも指定できます。固定ロット乗数が最大の組織に固定ロット乗数オーダー・サイズ数量が割り付けられてから、すべての供給が使い切られるか、または供給不足のため固定ロット乗数を充足できなくなるまで、次の組織に固定ロット乗数オーダー・サイズが割り付けられます。2つの固定ロット乗数オーダー・サイズが同一の場合、どの組織に最初に固定ロット乗数オーダー・サイズ数量が割り付けられるかは、ランクにより決定されます。
組織には最初に供給が割り付けられます。ソース組織にオーダーがある場合は、これが他方の宛先組織と併用されてソース組織固有の割付が決定されます。次に、この供給がソース組織の独立需要(受注、予測、ターゲット在庫レベルおよび安全在庫など)に割り付けられます。
オーダー・サイズ方法の場合、搬送計画では社内転送について供給割付ルールのオーダー・サイズ乗数が考慮されます。
供給割付ルールのオーダー・サイズを使用して、特定の出荷元-出荷先組織のペア間の組織間転送にのみ使用する固定ロット乗数(パレット数量など)を定義できます。これらは、ソースを考慮しない組織への全インバウンド出荷に使用される品目属性であるオーダーの固定ロット乗数とは異なっていてもかまいません。
搬送計画では、次のデフォルト設定階層を使用して、社内転送元および転送先組織のペアに使用するオーダー・サイズ乗数が検索されます。
計画実行日の固定ロット乗数に値が設定されている場合は、それがこの組織との間の社内転送に使用されます。品目属性のオーダー・モディファイアはすべて無視されます。
固定ロット乗数がNULLの場合は、宛先組織の品目属性「固定ロット乗数」が使用されます。
宛先組織の品目属性「固定ロット乗数」が「NULL」の場合、品目属性「オーダー数量端数処理」が選択されていれば、固定ロット乗数として1が使用されます(端数処理時には、不足数量が小数になるのを回避するために常に切り上げられます)。
端数数量は小数点以下6桁まで使用されます。
組織をルールに追加しても、オーダー・サイズを定義しなければ、オーダー・サイズ方法には品目属性「固定ロット乗数」が使用されます。フェア・シェア・ルールで指定されていない組織は、オーダー・サイズが指定されている組織に対する全需要が充足されてから処理されます。
「計画オプション」フォームでデフォルト・フェア・シェア割付方法を選択できます。デフォルト方法は、供給割付ルールが明示的に定義されている組織を除くすべての品目-宛先組織に適用されます。計画オプション「デフォルト・フェアシェア 割付方法」の選択肢は、次のとおりです。
現在の需要率
安全在庫率
デフォルト・フェア・シェア割付方法が単一の品目-宛先組織に適用される場合、ランクとパーセントは指定できません。標準的なデフォルト設定ロジックが使用されます。
出荷倉庫について、すべての宛先倉庫を含んでいない供給割付ルールを指定できます。
組織優先度を選択しなければ、計画エンジンではフェア・シェア割付ルールが使用されます。未指定の各倉庫は、指定した倉庫に対する特定の優先度の需要がすべて割付バケット中に充足された後でのみ考慮されます。未充足需要は、次のタイムバケットに移動されます。例:
組織R1、R2およびR3がD2から調達しています。R1およびR2の固定パーセントが50 / 50として指定されています。
R1、R2、R3およびD2の需要数量が需要優先度6にそれぞれ100ずつ使用可能で、供給数量が250単位であれば、R1には100単位が割り付けられ、R2にも100単位が割り付けられます。R1とR2が充足された後にのみ、計画エンジンによりR3とD2が考慮されます。残りの50単位は、R3またはD2に割り付けられます。
割付バケット中に供給不足があるため、フェア・シェア・ルールが起動されます。フェア・シェア・ルールを使用して、同じ割付バケット中の同じ需要優先度を持つ需要に供給数量が割り付けられます。有効供給数量を需要に割り付ける際に、1つの需要が完全に充足されるとはかぎらず、供給数量が需要間で分割される場合があります。
未充足需要の残高は、新規の有効供給数量がある次の割付バケット中に考慮されます。未充足需要の需要優先度は変わりません。次のバケットでは、繰り越された未充足需要の前に、他の上位優先度の需要が考慮されることがあります。未充足需要が多数の割付バケットに繰り越される場合があり、計画期間の最後まで繰り越される可能性もあります。
計画エンジンでは、供給不足を同じ需要優先度を持つ需要に割り付けるために、次のルールが使用されます。
割付は、最初に優先度別の確定需要、次に優先度別の未確定需要へと進行します。各レベルが考慮されるため、いずれかの時点で供給数量が使い切られ、フェア・シェア割付が起動されます。
すべての確定需要が充足されるまで、最初に確定需要に供給数量が割り付けられます。このように需要を形成する割付は、割付で未確定需要が考慮される前に発生します。確定需要とは、確定社内受注、確定計画アウトバウンド出荷、および確定計画オーダーにペグされた需要(宛先組織内の確定供給にペグされた計画アウトバウンド出荷など)です。
確定需要に対する割付は、最初に当初需要優先度別、次に最早日別に行われます。すべての確定需要を充足できなければ、次のバケットに繰り越されます。
最大のフェア・シェア・パーセントを持つ組織には、有効供給数量を最初に受け取る機会が与えられ、フェア・シェア・パーセント以内で有効供給数量の割付を受けることができます。
最大フェア・シェア・パーセントを持つ組織には、需要を充足するための数量のみが割り付けられます。たとえば、組織Aのフェア・シェアが、2000単位の供給数量のうち50%であるとします。ただし、現行割付バケット中の組織Aの需要は500単位のみのため、500単位のみが割り付けられます。
割付ではオーダー・サイズが考慮されるため、オーダー・サイズ制約が原因でバケット中の供給数量が超過割付になる場合があります。割付がオーダー・サイズ要件を満たしていない場合は、オーダー・サイズを考慮して次の固定ロット乗数に達するまで十分な追加供給数量が割り付けられます。
フェア・シェア・パーセントが同等の場合は、タイブレークになるように推測によるランクが使用され、最初に考慮される組織が決定されます。
フェア・シェア・パーセントが指定されている全組織に供給数量が割り付けられた後、フェア・シェア・パーセントが未指定の組織に対して、優先度内の各組織に1度ずつ先入れ先出し方式で供給数量が割り付けられます。デフォルト設定ロジックに依存せずに全組織をルールに定義すると、ニーズに最も適切に対処できる場合があります。フェア・シェア・パーセントが未指定の組織は、次のいずれかの場合に発生する可能性があります。
組織が供給割付ルールには含まれていないが、ソース・ルールに基づく有効な宛先組織である場合。
組織が供給割付ルールには含まれているが、割付値が指定されていない場合(「固定パーセント方法」および「オーダー・サイズ方法」の場合)。ユーザーが各リストの組織について値を指定する必要はありません。
在庫を逆方向へ移動するための転送が生成されることはありません。たとえば、資材を組織D2から他の組織に再割付する目的で、組織R2から組織D2へと逆方向へ移動するための転送が作成されることはありません。
最大の割付パーセントを持つ組織との間の出荷レーンに在庫不足があるために、その組織がフェア・シェアを受け取れない場合があります。有効在庫数量のほとんどが組織R5にあり、組織R1の割付パーセントが最大の場合、R1にフェア・シェアに従って転送されることはありません。この問題は、R1とR5の間の在庫再残高計算配分ルールを定義することで解決されます。
計画エンジンでは、標準的なソース・ルールと供給割付ルールを使用して転送が作成されます。
フェア・シェア・ルールを使用すると、同じ需要優先度を持つ競合需要の間で供給数量が分割されるため、最終的な計画出力における部分需要の充足数が増加します。
全需要を充足できるが安全在庫レベルを満たせない場合は、フェア・シェア割付ルールを適用すると有効在庫数量の再残高計算が実行されます。フェア・シェア・ルールは、そのルールと安全在庫またはターゲット在庫不足を参照して配分される残りの供給に適用されます。
次の例に、RDC1およびRDC2がDC1から調達している場合を示します。DC1には、RDC1およびRDC2からの受注、予測および転送需要があります。
この例は最初の割付バケットに関するもので、DC1の手持数量に関する最初の割付バケット中の3つの異なる供給の割付を示しています。「現在の需要率」フェア・シェア割付方法が使用されています。
| DC1の需要 | 優先度 | 需要数量 | 供給が100の場合の割付 | 供給が300の場合の割付 | 供給が700の場合の割付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| RDC1の要求 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| 予測 | 2 | 100 | 0 | 25 | 100 |
| RDC1の要求 | 2 | 200 | 0 | 50 | 200 |
| RDC1の要求 | 2 | 100 | 0 | 25 | 100 |
| RDC1の要求 | 3 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| RDC1の要求 | -3 | -1000 | -0 | 0 | 90 |
ユーザーが受注と予測に適用する顧客フェア・シェア割付方法を選択できるように、計画オプションが用意されています。受注と予測に対する顧客フェア・シェア割付方法では、需要率供給割付ルールと同じフェア・シェア割付アプローチが使用されます。ソース組織および顧客別に個別のフェア・シェア割付ルールを指定する必要はありません。
オプションは次のとおりです。
フェア・シェアなし: フェア・シェア割付はなく、供給数量は受注と予測に先入れ先出し方式で割り付けられます。これはNULLと同じです。
需要区分: フェア・シェアは需要区分レベルで実行されます。需要区分の下位で、供給数量が先入れ先出し方式で割り付けられます。
顧客: フェア・シェアは顧客レベルで実行されます。顧客の下位で、供給数量が先入れ先出し方式で割り付けられます。
顧客サイト: フェア・シェア割付は顧客サイト・レベルで実行されます。同じ割付バケット中に同じ顧客サイトからの複数のオーダーが存在する場合、供給数量は先入れ先出し方式で割り付けられます。
同じ割付バケット中に同じ需要優先度の競合する受注、予測および要求アウトバウンド出荷需要があるために(需要優先度ルール・セットにより判別)ソース組織に供給不足が発生すると、フェア・シェア割付が使用されます。需要優先度ルール・セットがなければ、受注、予測および超過消込済予測のデフォルト優先度が使用されます。
受注と予測の間のフェア・シェア割付は、供給割付バケット中の各受注および予測に対する需要の比率に基づきます。有効供給数量は、需要合計に対する比率に基づいて各需要に割当てられます。受注と予測の両方について、需要納期までの割付数量が保持され、遅延補充例外メッセージでレポートされます。
計画エンジンでは、顧客のない予測需要がダミーの顧客名を持つ需要として処理されます。つまり、2つの予測(一方は顧客あり、他方は顧客なし)の数量が同一の場合、2つの予測間のフェア・シェアは同じになります。
受注と予測についてフェア・シェア割付を選択しなければ、先入れ先出しロジックが適用されます。供給数量は、使い切られるまで1度に1つの需要を充足するために使用されます。複数の需要の優先度が同一の場合、どの需要が最初に考慮されるかは管理できません。たとえば、それぞれ10単位の受注需要と予測需要があわせて5つあり、すべて同じ優先度で、供給数量が20単位であるとします。フェア・シェアの使用は5つの需要にそれぞれ4単位ずつ割り付けられることを意味し、先入れ先出し方式の使用は2つの需要にそれぞれ10単位ずつ割り付けられることを意味します。
次に示す例に、それぞれフェア・シェア割付なしと、需要区分レベル、顧客レベルおよび顧客サイト・レベルでのフェア・シェア割付を示します。次の表は、6月30日の組織C1の品目に対する需要を示しています。組織C1では、日次供給割付バケットを使用しています。6月30日の品目の手持残高は340です。
| 需要タイプ: オーダー番号 | 優先度 | 需要区分 | 需要ソース | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 受注: SO1 | 1 | DC1 | 顧客A | 100 |
| 受注: SO2 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト1 | 200 |
| 予測: FC3 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト2 | 100 |
| 受注: SO4 | 2 | DC3 | 顧客C | 50 |
| 受注: SO5 | 2 | DC3 | 顧客D | 50 |
| 受注: SO6 | 3 | DC4 | 顧客E | 100 |
| 合計 | - | - | - | 600 |
計画プロセスによる先入れ先出し割付の実行方法は、次のとおりです。
SO1は最上位優先度の受注であるため、SO1に100単位が割り付けられます。優先度1の需要の場合、フェア・シェア割付は不要です。このステップの後、残りの供給数量は240単位となります。
優先度2の需要が400単位ありますが、残りの供給数量は240しかありません。優先度2の需要には、先入れ先出し方式に基づいて供給数量が割り付けられます。その需要が最初に考慮されるかに応じて複数の結果が考えられますが、顧客B、サイト1に需要のうち200単位が割り付けられ、顧客B、サイト2に需要のうち40単位が割り付けられるとします。
優先度3の需要が100単位あり、有効供給数量がないため、割付は発生しません。
次の表に、先入れ先出し割付の結果を示します。
| 需要タイプ: オーダー番号 | 優先度 | 需要区分 | 需要ソース | 数量 | 割付数量(期限充足数量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注: SO1 | 1 | DC1 | 顧客A | 100 | 100 |
| 受注: SO2 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト1 | 200 | 200 |
| 予測: FC3 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト2 | 100 | 40 |
| 受注: SO4 | 2 | DC3 | 顧客C | 50 | 0 |
| 受注: SO5 | 2 | DC3 | 顧客D | 50 | 0 |
| 受注: SO6 | 3 | DC4 | 顧客E | 100 | 0 |
| 合計 | - | - | - | 600 | 340 |
計画プロセスによる需要区分別のフェア・シェア割付の実行方法は、次のとおりです。
SO1は最上位優先度の受注であるため、SO1に100単位が割り付けられます。優先度1の需要の場合、フェア・シェア割付は不要です。このステップの後、残りの供給数量は240単位となります。
優先度2の需要が400単位ありますが、残りの供給数量は240単位しかありません。優先度2の需要には、需要区分に基づいて供給数量が割り付けられます。
DC2に300単位の需要、DC3に100単位の需要があります。割付は、DC2に180単位、DC3に60単位となります。
DC2内では、割付が先入れ先出し方式で進行します。2つの結果が考えられます。SO2に180単位が割り付けられてFC3に何も割り付けられないか、FC3に100単位が割り付けられてSO2に80単位が割り付けられます。SO2に180単位が割り付けられ、FC3に何も割り付けられないとします。
DC3内では、割付が先入れ先出し方式で進行します。2つの結果が考えられます。SO4に50単位が割り付けられてSO5に10単位が割り付けられるか、SO5に50単位が割り付けられてSO4に10単位が割り付けられます。SO4に50単位が割り付けられ、SO5に10単位が割り付けられるとします。
優先度3の需要が100単位あり、有効供給数量がないため、割付は発生しません。
次の表に、需要区分別のフェア・シェア割付の結果を示します。
| 需要タイプ: オーダー番号 | 優先度 | 需要区分 | 需要ソース | 数量 | 割付数量(期限充足数量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注: SO1 | 1 | DC1 | 顧客A | 100 | 100 |
| 受注: SO2 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト1 | 200 | 180 |
| 予測: FC3 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト2 | 100 | 0 |
| 受注: SO4 | 2 | DC3 | 顧客C | 50 | 50 |
| 受注: SO5 | 2 | DC3 | 顧客D | 50 | 10 |
| 受注: SO6 | 3 | DC4 | 顧客E | 100 | 0 |
| 合計 | - | - | - | 600 | 340 |
計画プロセスによる顧客別のフェア・シェア割付の実行方法は、次のとおりです。
SO1は最上位優先度の受注であるため、SO1に100単位が割り付けられます。優先度1の需要の場合、フェア・シェア割付は不要です。このステップの後、残りの供給数量は240単位となります。
優先度2の需要が400単位ありますが、残りの供給数量は240単位しかありません。優先度2の需要には、顧客に基づいて供給数量が割り付けられます。
顧客Bに300単位の需要、顧客Cに50単位の需要、顧客Dに50単位の需要があります。割付は、それぞれ180、30および30となります。
顧客Bの2つのサイトでは、割付が先入れ先出し方式で進行します。2つの結果が考えられます(前者が実際の結果であるとします)。サイト1に180単位が割り付けられてサイト2には何も割り付けられないか、サイト2に100単位が割り付けられてサイト1に80単位が割り付けられます。サイト1に180単位が割り付けられ、サイト2には何も割り付けられないとします。
優先度3の需要が100単位あり、有効供給数量がないため、割付は発生しません。
次の表に、顧客別のフェア・シェア割付の結果を示します。
| 需要タイプ: オーダー番号 | 優先度 | 需要区分 | 需要ソース | 数量 | 割付数量(期限充足数量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注: SO1 | 1 | DC1 | 顧客A | 100 | 100 |
| 受注: SO2 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト1 | 200 | 180 |
| 予測: FC3 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト2 | 100 | 0 |
| 受注: SO4 | 2 | DC3 | 顧客C | 50 | 30 |
| 受注: SO5 | 2 | DC3 | 顧客D | 50 | 30 |
| 受注: SO6 | 3 | DC4 | 顧客E | 100 | 0 |
| 合計 | - | - | - | 600 | 340 |
計画プロセスによる顧客サイト別のフェア・シェア割付の実行方法は、次のとおりです。
SO1は最上位優先度の受注であるため、SO1に100単位が割り付けられます。優先度1の需要の場合、フェア・シェア割付は不要です。このステップの後、残りの供給数量は240単位となります。
優先度2の需要が400単位ありますが、残りの供給数量は240単位しかありません。優先度2の需要には、顧客に基づいて供給数量が割り付けられます。顧客Bのサイト1に200単位の需要、顧客Bのサイト2に100単位の需要、顧客Cに50単位の需要、顧客Dに50単位の需要があります。割付は、それぞれ120、60、30および30となります。
優先度3の需要が100単位あり、有効供給数量がないため、割付は発生しません。
次の表に、顧客サイト別のフェア・シェア割付の結果を示します。
| 需要タイプ: オーダー番号 | 優先度 | 需要区分 | 需要ソース | 数量 | 割付数量(期限充足数量) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注: SO1 | 1 | DC1 | 顧客A | 100 | 100 |
| 受注: SO2 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト1 | 200 | 120 |
| 予測: FC3 | 2 | DC2 | 顧客B/サイト2 | 100 | 60 |
| 受注: SO4 | 2 | DC3 | 顧客C | 50 | 30 |
| 受注: SO5 | 2 | DC3 | 顧客D | 50 | 30 |
| 受注: SO6 | 3 | DC4 | 顧客E | 100 | 0 |
| 合計 | - | - | - | 600 | 340 |
組織優先度上書き
ソース組織に組織上書き優先度を割当てて、ソース組織の独立需要と他の組織からの依存需要の相対優先度レベルを管理します。
計画オプション「組織優先度上書きを使用」を選択した場合、優先度は各組織-品目の供給割付ルールで設定した組織上書き優先度に基づきます。需要優先度ルール・セットは使用できません。
ソース組織から宛先組織への割付は、割当てた宛先組織優先度に基づいて実行されます。
組織-品目に優先度を割当てていない場合、割付は同等優先度に基づいて実行されます。
予測、受注、安全在庫およびターゲット在庫には、割当済の組織優先度と同じ優先度が割当てられます。
「供給割付ルール」の「需要優先度 上書き」リージョンで、次のいずれかを選択できます。
組織優先度を使用: この組織に対する全需要の需要優先度が、組織ごとに指定した値に設定されます。複数の組織からの全需要の相対優先度を設定できます。
なしまたはNULL: 需要優先度は上書きされません。
ソース組織または出荷組織を追加して、出荷組織の優先度を指定することもできます。これにより、受入組織の優先度を指定すると同時に出荷組織の優先度を指定できます。このテクニックを使用すると、他の組織からの需要の優先度がソース組織からの需要よりも上位であるか下位であるかを管理できます。
「組織優先度」を選択すると、未指定の全倉庫は指定した倉庫よりも1つ下位の同一優先度に設定されます。
たとえば、組織R1、R2およびR3がD2から調達しているとします。R1の需要優先度上書きが1、R2が2、D2が2として指定されています。R3の優先度は指定されていません。R3のデフォルト需要優先度上書きは3です。
組織優先度上書きルールを指定しなければ、すべての宛先とソースは同じ優先度を持つものとして処理されます。
組織優先度上書きを使用すると、組織内の全需要に同じ優先度が与えられます。供給数量は、計画オプションの顧客フェア・シェア割付方法に基づいて、この優先度内でフェア・シェアされます。
仕入先から調達する品目についてフェア・シェア割付ルールを定義して割当てることはできませんが、全仕入先のフェア・シェア割付方法を設定するための計画オプションが用意されています。仕入先生産能力が定義されている場合に、需要が割付バケット中に使用可能仕入先生産能力を超過すると、フェア・シェア割付ロジックがコールされます。
仕入先からの供給に適用される割付ロジックは、組織間の割付または供給に使用されるものと同じです。計画オプションの選択肢は、次のとおりです。
なし: フェア・シェア割付は実行されず、供給数量は先入れ先出し方式で割り付けられます。
現在の需要率: 仕入先から調達している組織の現在の需要率を使用して、フェア・シェア割付が実行されます。
安全在庫率: 仕入先から調達している組織の安全在庫率を使用して、フェア・シェア割付が実行されます。
割り付けられる供給合計は、割付バケットの終了までの正味有効供給数量です。これは、仕入先生産能力に基づきます。
たとえば、仕入先生産能力が1日10単位で、すべての日が稼働日で、第2の週次バケットまで需要がなく、需要合計が仕入先生産能力を超過しているとします。第3の週次バケットが第18日に終了する場合、競合需要間の割付数量は合計180単位となります。
計画エンジンでは、次のデフォルト設定階層を使用して仕入先のオーダー・サイズ乗数が検索されます。
承認済仕入先リストの「固定ロット乗数」が空白の場合は、宛先組織の品目属性「固定ロット乗数」が組織間の社内転送に使用されます。
宛先組織の品目属性「固定ロット乗数」が空白の場合は、固定ロット乗数1が使用されます。
品目属性「オーダー数量端数処理」を選択した場合は切り上げられ、それ以外の場合は小数点以下6桁までの小数数量が使用されます。
顧客への出荷の場合、ロード連結は実行されません。供給または顧客についてロード連結が必要な場合は、仕入先または顧客を外部組織としてモデル化できます。
適切な割付が行われるように、仕入先生産能力と固定ロット乗数の両方を考慮してください。たとえば、1月7日に計画が実行され、品目Xの計画タイム・フェンスが4日であるとします。組織AおよびBは、品目Xを仕入先Sから調達しています。仕入先生産能力は1日当たり500(24x7カレンダ)で、固定ロット乗数は750単位です。仕入先フェア・シェア方法の計画オプション値は「現在の需要率」です。ただし、オーダー・サイズは仕入先生産能力と相対であるため、結果が十分にフェア・シェアであるように見えない場合があります。組織AおよびBからの次の需要は、この事例を示しています。
計画タイム・フェンスのため、1月10日より前の日付を期日とする計画オーダーは設定できません。組織Bは合計需要が大きいためにフェア・シェア・パーセントが高いため、最初に組織Bに割り付けられます。組織Bの1月までの需要合計は5830で、端数処理されて6000となります。組織Aの1月10日までの需要合計は4350で、端数処理されて4500となります。1月7日から1月10日までのフェア・シェア生産能力は、2000(毎日500)です。組織Bは857.142(42.8571% * 2000)を取得しますが、残りの生産能力が500のみで、オーダー・サイズが750であるため、端数処理されて0(ゼロ)となります。組織Aは1142.86(57.1429% * 2000)を取得し、端数処理されて1500となります。高パーセントの組織が最初に端数処理され、供給が可能であれば最初に切り上げられます。切り下げられるのは、仕入先生産能力が不十分な場合のみです。
1月11日に、組織Aの繰越需要合計と新規需要は端数処理後に合計6000となります。組織Bの繰越需要合計と新規需要は端数処理後に合計4500となります。1月11日の500に追加するために500が繰り越されるため、有効在庫数量合計は1000となります。フェア・シェア組織Aは571.429(57.1429% * 1000)を取得し、切り上げられて750となり、組織Bは428.571(42.8571% * 1000)を取得し、切り下げられて0となります。
そこで、計画の最初の5日が経過した後、Aに2250単位が割り付けられ、Bには何も割り付けられません。より適切なフェア・シェアを達成するために、オーダー・サイズを小さくするか、割付バケットを週次に変更することを検討します。これにより、オーダー・サイズに対する有効供給数量が大きくなります。
「顧客リスト」フォームを使用して、計画作業環境内のデフォルト顧客選択リストを指定します。このリストは、顧客と顧客サイトの割付計画をオープンするときに使用されます。定義済の顧客リストは「顧客リスト」フォームに表示されます。
「ツール」->「顧客リスト」にナビゲートするか、デフォルトの水平ディメンションが「顧客」のときに割付計画を右クリックして「顧客リスト」を選択します。
顧客リストの名称と所有者を追加します。
「パブリック」ドロップダウン・リストで、定義とユーザーが割付計画を右クリックしたときの表示の両方について、この顧客リストへのアクセスを他の計画担当に許可するかどうかを指定します。デフォルト値は「No」です。顧客リストをパブリックにする場合は、「Yes」に変更します。
顧客リストから顧客を選択して顧客選択リストを定義します。矢印を使用してフォーム内で顧客を上下に移動し、顧客の表示順序を設定します。
必要な場合は、「顧客サイト」フィールドに値を入力します。