リリース12.1
B66926-01
目次
前へ
次へ
| Oracle Enterprise Asset Managementユーザーズ・ガイド リリース12.1 B66926-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この章のトピックは、次のとおりです。
Enterprise Asset Management(eAM)の直接品目調達を使用すると、保守組織に品目を直接オーダーできます。この章のトピックは、次のとおりです。
Enterprise Asset Management(eAM)に組み込まれている最も重要な機能の1つは、作業管理です(「eAM作業管理の概要」を参照)。 作業管理では、資産に問題がある場合に作業要求を作成できます。 承認された後の作業要求は、作業指示に関連付けることができます。 作業指示には、資産に対して実行される保守活動すべてのリストが含まれています。 作業指示の資材所要量(「資材所要量の定義」を参照)には、在庫品目、非在庫直接品目、サービスおよび直接品目(摘要基準品目)が含まれます。 在庫品目は、頻繁に使用される品目や、在庫保有が必須の交換部品を取得するためのリード・タイムが短い重要な品目です。 非在庫直接品目は、内部カタログに含めることができますが、在庫残高を保持しないと判断された品目です。 これらの品目は取引不可、在庫不可ですが、調達は可能です。 直接品目は、非在庫または摘要基準のいずれかです。 非在庫直接品目は、在庫に保有されない品目、つまり仕入先から購買する必要があるサービスを表します。 非在庫直接品目は在庫に保有されませんが、品目マスターでは(購買可能で、購買しても在庫不可の)在庫品目として定義されます(『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の在庫属性グループに関する項を参照)。 直接品目は「ワンオフ」とみなされ、特定の作業指示および工程のためにベンダーから直接購入されます。 これらは、保守作業指示の実行から製造現場に直接搬送されます。 計画済直接品目は、作業指示の部品構成表(BOM)または活動BOMに追加できます。 計画済直接品目は、最初に在庫不可の購買可能在庫品目として品目マスターに作成する必要があります(「非在庫直接品目の設定」を参照)。 購買依頼は、作業指示のリリース時に、必要に応じてこれらの品目に対して自動的に作成されます。
Oracle iProcurementがインストールされている場合、内部カタログには、すべての品目タイプを含めることができます。 プランナは、保守ワークベンチから直接品目を調達できます(「保守ワークベンチの使用」を参照)。 このような品目の購買依頼および発注では、必要な作業指示が取得されます。 作業指示がプロジェクト関連の場合は、購買依頼でプロジェクトおよびタスクの情報が取得されます。 非在庫の直接品目と摘要基準の直接品目は、iProcurementにアクセスせずに調達することもできます。
次の図は、エンタープライズ資産管理と調達管理との統合を示しています。 最初に、保守作業指示が作成されます。 資産に関連付けられた資産または保守BOM(あるいはその両方)に直接品目が含まれている場合、その直接品目は自動的に作業指示の資材所要量の一部となります。 直接品目(非在庫、摘要基準およびサービス)は、作業指示に手動で追加することもできます。 作業指示がリリースされると、資材所要量に含まれていて、「資材の自動要求」チェック・ボックスが選択されている直接品目に対して購買依頼が作成されます。 このチェック・ボックスの設定は、資産または保守BOM(あるいはその両方)の設定からデフォルト設定されますが、作業指示で更新できます。 購買依頼は、作業指示にリンクされ、その後承認されます。 発注は、購買依頼から作成され、その後承認されます。 発注は、最初に購買依頼を作成せずに、手動で作成できます。 いずれの場合も、発注には承認が必要です。 品目は、標準的な受入経路を使用して納入され、保守作業指示に搬送されます。 作業指示の原価は、実際の発注価格として記録されます。
eAM作業指示に対する直接品目調達のプロセス
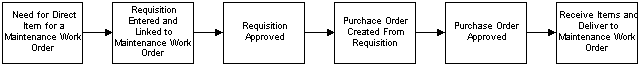
この項のトピックは、次のとおりです。
eAM作業指示の直接品目(仕入先カタログと非カタログ品目の両方)を、eAM作業指示から直接調達できるようにするには、「PO: 製造現場への直送を有効にする」プロファイル・オプションを「Yes」に設定します。 この値が「Yes」に設定されている場合は、eAM関連の購買依頼または発注を作成できます。 eAM固有の情報(作業指示や工程の参照番号など)を入力したり、製造現場搬送先がある購買依頼明細を識別することができます。 作業指示(その資材所要量に直接品目がリストされている)がリリースされると、直接品目(非在庫および摘要基準)に対して購買依頼が自動的に作成されます。
直接品目調達を有効にする手順は、次のとおりです。
「個別プロファイル値」ウィンドウにナビゲートします。
個別プロファイル値
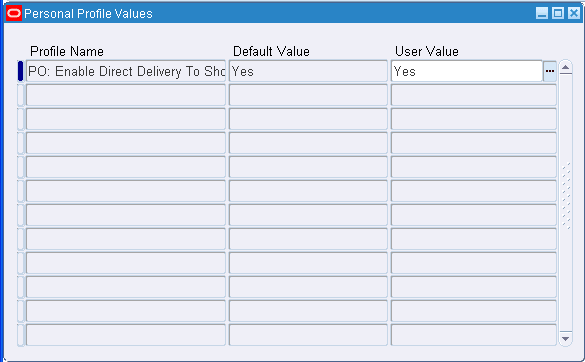
「プロファイル名」値リストから「PO: 製造現場への直送を有効にする」を選択します。
「デフォルト値」値リストから「Yes」を選択します。
作業内容を保存します。
関連項目
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』のPurchasingのプロファイル・オプションに関する項
最初に、保守作業指示が作成されます。 作業指示の資産に関連付けられた資産または保守BOMに直接品目が含まれている場合、その直接品目は自動的に作業指示の資材所要量の一部となります。 直接品目(非在庫および摘要基準)は、作業指示に手動で追加することもできます。 作業指示がリリースされると、資材所要量に含まれていて、「資材の自動要求」チェック・ボックスが選択されている直接品目に対して購買依頼が作成されます。 このチェック・ボックスの設定は、資産または保守BOMの設定からデフォルト設定されますが、作業指示で更新できます。 購買依頼は、作業指示にリンクされ、その後承認されます。 発注は、購買依頼から作成され、その後承認されます。 発注は、最初に購買依頼を作成せずに、手動で作成することもできます。 いずれの場合も、発注には承認が必要です。
重要: 作業指示の複数の直接品目に対して単一の購買依頼を自動的に作成することはできません。 作業指示に複数の直接品目が含まれている場合、購買依頼は手動で作成する必要があります。 保守BOMまたは作業指示の直接品目明細の「資材の自動要求」チェック・ボックスは、選択を解除する必要があります。
購買依頼を自動的に作成する手順は、次のとおりです。
「作業指示」ウィンドウにナビゲートします。
「新規」を選択します。
ヘッダー情報には、資産番号および必要な作業のタイプに関する一般情報が表示されます。
作業指示番号が割り当てられますが、この番号は更新可能です。
保守が必要な資産番号を入力します。 資産グループがデフォルト設定されます(「資産番号の定義」を参照)。
資産活動を選択します。 選択できるのは、この資産番号に関連付けられた資産活動です。
注意: この作業指示が以前から作成されていた場合は、その作業指示が未リリースまたは草案ステータスか、資産活動が事前に定義されていないかぎり、資産活動を追加できます。 タスク、資材または生産資源所要量が存在する場合、既存の作業指示に資産活動を追加する前に削除しておく必要があります。
資産活動を選択した後は、関連する保守BOM(資材)(「保守部品構成表の設定」を参照)および活動に関連付けられた保守工順(生産資源)(「保守工順の定義」を参照)を作業指示に添付します。 作業指示に保存した資産活動は、変更または削除できません。
資産番号に関連付けられた経費(費用)勘定を表す区分コードを入力します。 これは、資産番号(「資産番号の定義」を参照)からデフォルト設定されますが、更新可能です。
ステータスを入力します。 たとえば、未リリース、リリース済、保留中、草案などがあります。 このステータスは、たとえば、作業指示完了などの特定の取引によって自動的に更新されます(「eAM作業指示ステータス」を参照)。
これが作業指示ネットワークの子作業指示で、「関連タイプ」フィールドに親子が移入されている場合、このフィールドには親作業指示が移入されます。
作業指示が先送り計画に基づいている場合は、「予定日」リージョンに作業指示の予定開始日を入力します。 スケジュール処理では、この日付を開始ポイントとして使用して、割り当てられた生産資源と資材に対する予定終了日と期間が計算されます。 資材や生産資源がこの日付までに使用可能にならない場合は、スケジュール処理により開始日が先送りされます(「eAMスケジューリング」を参照)。
前倒し計画の予定完了日を入力します。 この日付は、作業に要求された終了日を示します。 スケジュール処理では、この日付を開始ポイントとして使用して、割り当てられた生産資源と資材に対する予定開始日と期間が計算されます。 資材や生産資源がその日付までに使用可能にならない場合は、スケジュール処理により、要求された終了日までに完了するように開始日が前倒しされます(「eAMスケジューリング」を参照)。
「メイン」タブの「部門」は、選択した資産番号からデフォルト設定されます(「資産番号の定義」を参照)。 これは、この資産番号について責任を負う個人または部門を示します。
(オプション)優先度を選択します。 たとえば、「高」、「中」または「低」を選択します。
(オプション)作業指示タイプを選択します。 作業指示タイプを使用すると、複数の作業指示を区別できます(例: ルーチン、予防、再作成、緊急、施設)。 保守管理では、この情報を使用してレポートおよび予算計画に関する作業活動をソートしてモニターできます。 作業指示タイプは作業指示で参照されます。 有効な値の作成方法は、「作業指示タイプ」を参照してください。
停止タイプは、活動からデフォルト設定されます。 これは、停止が必要なプランナ・グループ作業指示に役立つように、一緒に計画されます。
「確定」チェック・ボックスが選択されている場合は、資材または生産資源の可用性に関係なく、計画およびスケジューリングによってスケジュールが調整されることはありません(「計画およびスケジューリングの概要」を参照)。 このチェック・ボックスは、現在の組織の「エンタープライズ資産管理パラメータ」の設定で指定されている「リリース時に自動確定」チェック・ボックスの設定に従って、選択または選択が解除された状態にデフォルト設定されます(「eAMパラメータの定義」を参照)。 これは、作業指示のリリース後にデフォルト設定されます。
チェック・ボックスが選択されている場合は、作業指示期間に基づいて終了日が計算されます。 スケジューラにより、作業指示の工程(生産資源期間の設定)に基づいて期間が自動的に計算されます。 作業指示に関するこのチェック・ボックスは、「草案」、「リリース済」、「未リリース」、「保留中」または「取消」の各ステータス時に更新できます(「eAM作業指示ステータス」を参照)。
(オプション)「通知必須」チェック・ボックスを選択します。
(オプション)この作業指示を実行する必要がある工程に対してエリアのセキュリティ保護が必要なことを示すには、「タグアウト必須」チェック・ボックスを選択します。 タグは、通常、印刷して資産に取り付けられ、資産が停止中で開始できないことを工場に警告します。このチェック・ボックスは、タグアウトが必要な複数の製造オーダーをプランナが分離する際に役立ちます。
添付機能を使用してタグアウト文書を格納する手順は、次のとおりです。
関連するタグアウト文書を添付するには、「添付」(クリップ)アイコンを選択します。 URL、ファイルまたはテキスト添付ファイルを添付できます。 「作業指示文書の定義」を参照してください。
現在の作業指示が予測作業指示から作成された場合は、「計画」チェック・ボックスが選択されます(「予防保守作業指示」を参照)。
(オプション)現在の作業指示に対する資材の可用性をeAMで管理できるようにするには、「資材出庫要求の有効化」チェック・ボックスを選択します。 資材は、資材要求および検証プロセスを介して、作業指示に対して物理的に使用可能になります。 このチェック・ボックスは、「エンタープライズ資産管理パラメータ」ウィンドウで選択されている場合、デフォルトで選択されます。 作業指示が「リリース済」ステータスの場合、このチェック・ボックスは無効です。
(オプション)「活動」タブを選択します。
(オプション)活動タイプを選択します。 このコードは、この活動に対する保守のタイプを示し、製造オーダーまたは標準製造オーダー(例: 検査、精密検査、注油、修理、サービス、清掃)を定義する際に使用されます。 この値は活動からデフォルト設定されます(「活動の定義」を参照)。
(オプション)この作業の生成原因となった状況を指定するには、活動原因(例: ブレークダウン、破壊、通常減耗、設定)を選択します。 この値は活動からデフォルト設定されます(「活動の定義」を参照)。
(オプション)活動の実行が必要な理由を指定するには、活動ソース(例: 保証準拠、OSHA準拠、軍用規格要件)を選択します。 この値は活動からデフォルト設定されます(「活動の定義」を参照)。
(オプション)「プロジェクト」タブを選択します。 このタブを使用できるのは、プロジェクト製造がインストールされ、有効な場合です。
(オプション)プロジェクトを選択します。
(オプション)タスクを選択します。
この作業指示が再作成可能品目に対して作成されている場合は、「再作成」タブを選択できます。 「再作成作業指示」を参照してください。
(オプション)この作業指示に関連付けられたサービス要求および作業要求を表示するには、「保守要求」タブを選択します。 サービス要求および作業要求は、サービス要求または要求番号をそれぞれ選択することで作業指示に追加できます。 関連付けに使用できるのは、作業指示待機中ステータスでは作業要求、オープン・ステータスでは保守タイプのサービス要求です。 単一の作業指示には複数の作業要求を関連付けることができ、1つのサービス要求に関連付けできる作業指示は1つです。 1つのサービス要求を複数の作業指示に関連付けることができます。 作業指示に対する作業およびサービス要求の関連付けは解除できます。
「構成表, 工順」タブを選択して、事前定義された別のBOMや工順を選択します。 「保守部品構成表の設定」および「保守工順の定義」を参照してください。
別のBOMおよび工順を選択すると、関連する品目を使用して作業指示の実行に必要な関連生産資源が割り当てられます。
(オプション)必要な工程を準備するには、「工程」を選択します。 これらの工程は、現在の活動に関連付けられた保守工順(「保守工順の定義」を参照)からデフォルト設定されますが、更新と追加が可能です(「作業指示工程の準備」を参照)。
(オプション)この発注の資材所要量を表示または更新するには、「資材」を選択します(「資材所要量の定義」を参照)。 この作業指示がリリースされると、「資材の自動要求」チェック・ボックス(右にスクロールすると表示される)が選択されている場合は、資材所要量の直接品目に対して発注または購買依頼が作成されます。 これらの品目は保守BOMからデフォルト設定され、「直接品目」リージョンで参照されます。 直接品目を資産または保守BOMに追加する場合、仕入先および価格の情報は「部品構成表」ウィンドウ内に設定されています。 この情報が作業指示にデフォルト設定されます。
資材所要量
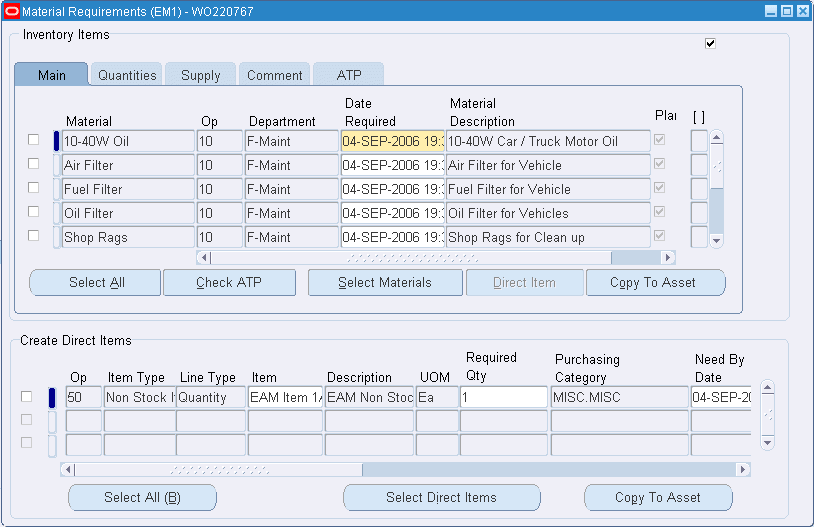
(オプション)各工程に割り当てられた生産資源を表示、追加または更新するには、「生産資源」を選択します。 「生産資源所要量の定義」を参照してください。
(オプション)作業指示のスケジュールを管理するには「関連」を選択し、作業指示の詳細を表示します。 「作業指示関連」を参照してください。
(オプション)現在の作業指示の資産グループに関連付けられた資産経路を表示するには、「資産経路」を選択します。 複数の資産番号について1つの活動を実行する必要がある場合もあります。 同じ活動に対して複数の作業指示が作成されるのを防ぐために、資産経路を定義できます。 「資産経路の定義」を参照してください。
現在の資産番号に資産経路が関連付けられている場合は、「資産経路」を選択できます。
(オプション)「期間別会計情報」リージョンに指定されている特定の会計期間に該当する作業指示の原価を表示するには、「原価」を選択します。 会計期間は、Oracle General Ledger内で定義されます。 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の期間タイプの定義に関する項、および『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』のカレンダの定義に関する項を参照してください。
(オプション)現在の作業指示に対する労務時間、設備時間および資材の実績原価、見積原価および差異原価の要約を表示するには、作業指示を選択し、次に「価額要約」を選択します。
実績原価: これは、資産番号の関連する保守作業指示に対する資材取引および生産資源取引の、指定の期間に基づいたすべての原価の累計です。
見積: BOM(資材部品リスト)および工順(生産資源)は、作業指示に関連付けることができます。 「見積」タブを選択すると、作業指示に関連付けられているすべての資材および生産資源の見積原価が表示され、原価の予算を計画できます。 資材所要量に含まれている直接品目が考慮されます。
差異: 記録された実績原価と見積原価との差異です。
資材: すべての資材および間接材料費の取引原価です。
労務: すべての従業員生産資源および生産資源間接費の取引原価です。
設備: すべての資材生産資源および生産資源間接費の取引原価です。
(オプション)現在の作業指示の特定の工程に対する労務時間、設備時間および資材の実績原価、見積原価および差異原価を表示するには、「詳細」を選択します。
作業内容を保存します。
作成された購買依頼を表示する手順は、次のとおりです。
「購買依頼の検索」ウィンドウにナビゲートします(「購買管理」>「購買依頼」>「購買依頼要約」)。
「参照番号」値リストから保守作業指示番号を選択します。
「検索」を選択します。 保守作業指示が表示されます。 ソースでEAMが読み取られます。
購買依頼ヘッダー要約

注意: 購買依頼は、Webベースのユーザー・インタフェースを使用して自動的に作成することもできます(「作業指示」を参照)。
直接品目の購買依頼は、iProcurementまたは購買管理で手動で作成できます。 Oracle iProcurementがインストールされている場合、仕入先カタログ品目には、eAM作業指示から直接アクセスできます。 iProcurementで購買依頼を作成する場合は、精算に進むと作業指示および工程の情報が生成されます。 直接品目へのリンクには、保守ワークベンチ(「保守ワークベンチの使用」を参照)を使用してアクセスするか、「作業指示」ウィンドウ内でアクセスできます。 非在庫の直接品目と摘要基準の直接品目は、iProcurementにアクセスせずに調達することもできます。 購買依頼は、Webベースのユーザー・インタフェースを使用して作成することもできます。 「作業指示」を参照してください。
重要: 作業指示の複数の直接品目に対して単一の購買依頼を自動的に作成することはできません。 作業指示に複数の直接品目が含まれている場合、購買依頼は手動で作成する必要があります。
Oracle iProcurementを使用して直接品目の購買依頼を入力する手順は、次のとおりです。
「作業指示」ウィンドウにナビゲートします。
作業指示番号を選択します(「eAM作業指示ステータス」を参照)。
「資材」を選択し、この発注の資材所要量を表示または更新します(「資材所要量の定義」を参照)。 この作業指示に対して、直接品目に関連する発注または購買依頼を作成すると、それらは「直接品目」リージョンで参照されます。
注意: 発注および購買依頼は、フォーム・アプリケーション内では参照されません。 これらは保守スーパーユーザー職責を使用して参照できます。 「作業指示」を参照してください。
資材所要量
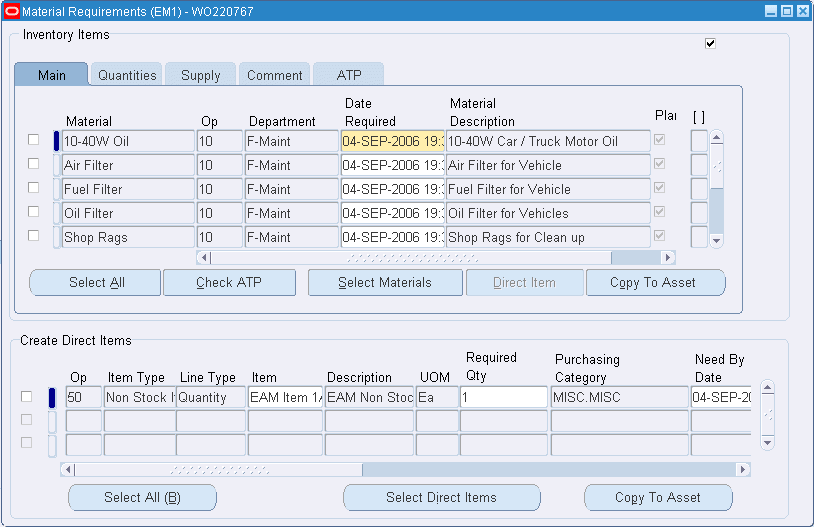
Oracle iProcurementを使用して直接品目を選択し、仕入先および仕入先以外のカタログから直接品目を購買するか、購買する直接品目を「直接品目の作成」リージョンに入力します(「直接品目資材所要量の定義」を参照)。
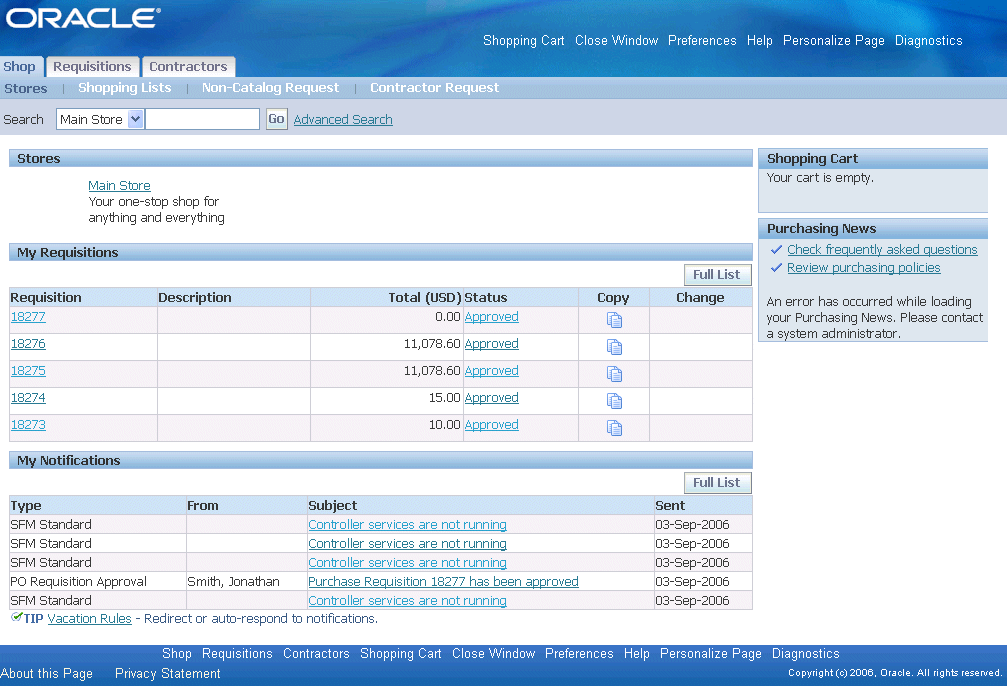
調達した非在庫、サービスまたは摘要基準の購買依頼番号(あるいはそのすべて)が「自分の購買依頼」リージョンに表示されます。
必要な品目を購入し、精算します。 これらの品目は、作業指示に自動的に関連付けられます。
作業内容を保存します。
Oracle Purchasingを介して直接品目の購買依頼を手動で入力する手順は、次のとおりです。
作業指示から直接品目を直接調達することに加え(「直接品目資材所要量の定義」を参照)、直接品目調達機能には、購買管理を使用してアクセスできます。 この機能は、エンタープライズ資産管理がインストールされている場合に使用できます。
購買依頼はフォーム・アプリケーションと保守ユーザーの両方で入力できます。 フォーム・アプリケーションで購買依頼を入力する場合は、eAM作業指示から実行せずに、保守ユーザーで操作する場合のように、「購買依頼」ウィンドウ内で直接実行します。 「作業指示」を参照してください。
「購買依頼」ウィンドウにナビゲートします(「購買管理」>「購買依頼」>「購買依頼」)。
購買依頼
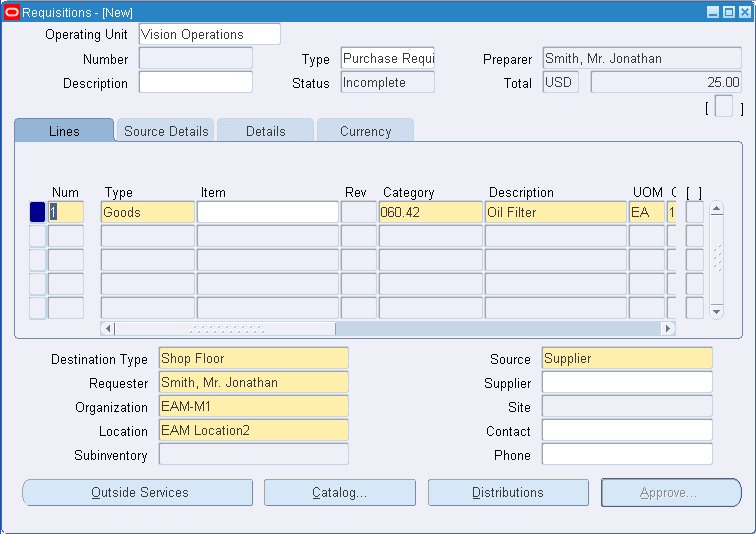
(オプション)購買依頼の摘要を入力します。
「明細」タブを選択します。
「品目タイプ」値リストから商品またはサービスを選択します。
(オプション)購買する品目を選択します。 選択できるのは、在庫管理で「在庫保有可能」チェック・ボックスの選択を解除して定義された品目です。 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の在庫属性グループに関する項を参照してください。
購買する品目の購買カテゴリを選択します。 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリの定義に関する項を参照してください。 作業指示にチャージする資材、労務または設備の勘定は、カテゴリを購買依頼明細に割り当てることで指定できます。 これにより、外注生産資源サービスが単発状態の場合は、外注加工の設定をバイパスできます。 発注には複数の原価要素を含めることができます。
品目の摘要を入力します。 この摘要は、品目の調達に使用されるため意味のある内容にしてください。 この品目が非在庫品目の場合、内部のメンバーは、この摘要によって、調達しようとしている品目を把握することになります。
単位を選択します。 単位は、発注明細に入力する数量を修飾します。 明細タイプを選択すると、デフォルトの単位がこのフィールドに移入されます。 品目を選択すると、そのデフォルトの単位によって明細タイプのデフォルトが上書きされます。 単位は、品目を受け入れ、請求または引き当てるまでは変更できます。
購買する数量を入力します。
希望入手日を選択します。
すべての直接品目および非在庫品目のeAM関連購買依頼に対して、「搬送先タイプ」値リストから「製造現場」を選択します。 「製造現場」搬送先タイプは、品目マスターで在庫可能として選択されていない購買可能品目すべてに対して選択できます(『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目の定義に関する項を参照)。
「製造現場」搬送先タイプを選択すると、eAMでは、このタイプが直接品目を保守作業指示に搬送するための要件として認識されます。
「搬送先タイプ」が「製造現場」の場合、「搬送先組織」値リストには、品目が在庫不可の組織が表示されます。
注意: このウィンドウの残りのフィールドすべての詳細は、『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買依頼明細の入力に関する項を参照してください。
「外部サービス」を選択します。 このウィンドウには、「購買依頼」、「発注」および「リリース」の各ウィンドウからアクセスできます。 アクセスできるのは、前の手順で「搬送先タイプ」を「製造現場」に指定した場合です。
外部サービス
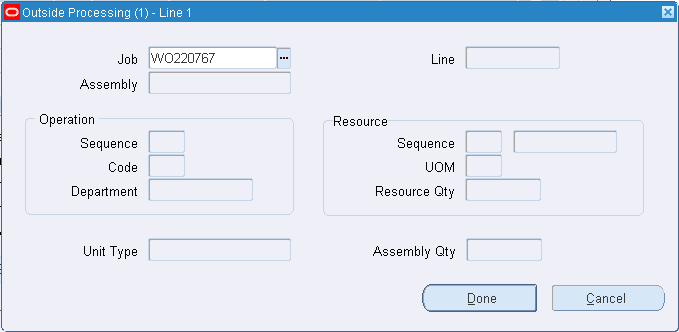
「製造オーダー」値リストから、作業指示を選択します。 選択できるのは、リリースされた保守作業指示です。 作業指示を選択すると、その作業指示に関連付けられたeAMプロジェクトおよびタスク情報が、購買依頼または発注の「配分」ウィンドウの「プロジェクト」タブ内の対応する「プロジェクト」および「タスク」フィールドにコピーされます。
工程連番を選択します。 購買した資材は、現在の作業指示のこの工程に関連付けられます。 購買管理には、工程のコードおよび部門が表示されます。
「完了」を選択します。
注意: 「外注加工」ウィンドウの残りのフィールドすべての詳細は、『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の外注加工情報の入力に関する項を参照してください。
作業内容を保存します。
購買依頼には承認が必要です(Oracle WorkflowガイドのOracle Workflow Builderでのプロセス定義の作成に関する項を参照)。 承認された購買依頼は、eAM作業指示に表示され、購買管理に表示されます。
関連項目
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買依頼ヘッダーの入力に関する項
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買依頼明細の入力に関する項
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買依頼配分の入力に関する項
購買依頼が作成および承認された後は、自動作成プロセスを実行して、発注を作成できます。
発注を作成する手順は、次のとおりです。
「購買依頼明細の検索」ウィンドウにナビゲートします(「購買管理」>「自動作成」)。
購買依頼明細の検索
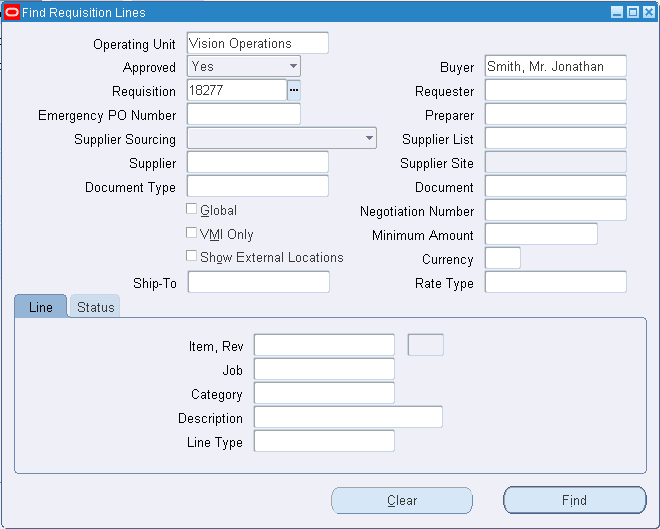
購買依頼番号を入力します。 この購買依頼は発注向けに作成されています。
「検索」を選択します。
「自動」を選択します。
新規文書
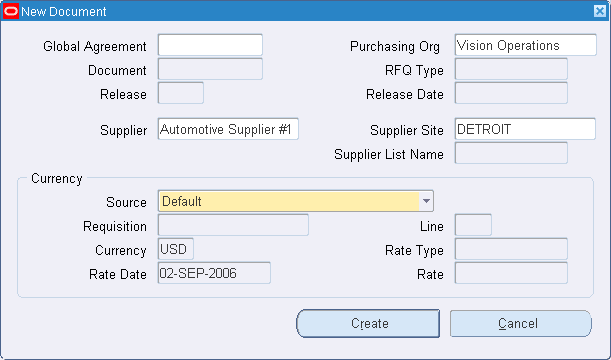
仕入先を選択します。
「作成」を選択し、作成された発注番号を書き留めます。
品目のタイプが「商品」であることを確認します。
「納入」を選択します。
「受入管理」を選択します。
受入経路を選択します。 これは、調達品目の割当先の受入経路(直送、標準受入または検査要)です。 『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の受入管理、オプションおよびプロファイルに関する項を参照してください。
「OK」を選択します。
「納入」ウィンドウから「配分」を選択します。 「搬送先タイプ」フィールドに「製造現場」が移入され、「保管場所」が空白であることを確認します。
「外部サービス」を選択します。 製造オーダーおよび工程連番を確認します。
注意: 「外注加工」ウィンドウの残りのフィールドすべての詳細は、『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の外注加工情報の入力に関する項を参照してください。
「完了」を選択します。
作業内容を保存します。
「承認」を選択します。
「文書の承認」ウィンドウで、「OK」を選択します。 発注が承認されると、購買管理内に発注が受け入れられます。
関連項目
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の発注配分の入力に関する項
直接品目の発注は、購買管理で作成できます。
複数の直接品目が必要な作業指示の購買依頼や発注は、手動で作成する必要があります。
Oracle Purchasingを介して直接品目の発注を入力する手順は、次のとおりです。
「発注」ウィンドウにナビゲートします。
発注
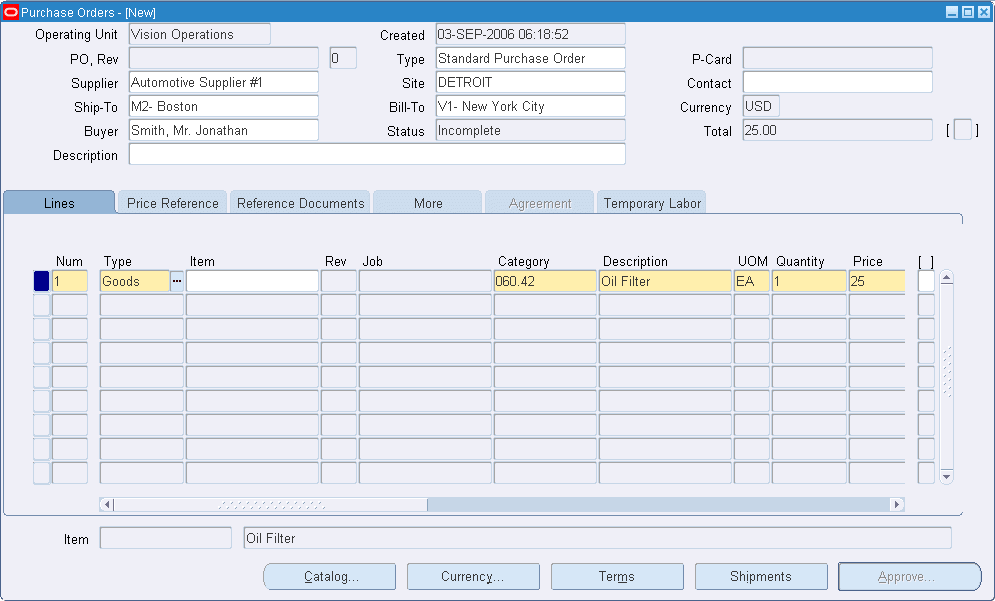
購買オプション(「採番」タブ)で自動発注の生成を選択しなかった場合は、一意のPO(発注)番号を入力します。 それ以外の場合は、作業内容の保存時に番号が生成されます。 『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買オプションの定義に関する項を参照してください。 番号の右に改訂が表示されます。
「タイプ」値リストから、「標準発注」を選択します。 文書タイプ名は、「文書タイプ」ウィンドウで変更できます(『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の文書タイプの定義に関する項を参照)。
(オプション)仕入先を選択します。 承認を得るためには、仕入先を指定する必要があります。
仕入先サイトを選択します。 承認を得るためには、サイトを指定する必要があります。 発注が承認された後、「PO: 仕入先サイトの変更」プロファイル・オプションが「Yes」に設定されている場合は、仕入先サイトを変更できます(『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』のPurchasingのプロファイル・オプションに関する項を参照)。
(オプション)担当者を選択します。 これは、仕入先サイトの担当者名です。
(オプション)発注の出荷先事業所と請求先事業所を入力します。 仕入先サイトを入力した場合は、仕入先または仕入先サイトに割り当てた事業所の値が、これらのフィールドにデフォルト設定されます。 『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の発注デフォルト・ルールに関する項を参照してください。
実施購買担当者名オプションが「Yes」に設定されている場合は、自分の名前が購買担当として表示されます。 それ以外の場合は、購買担当の名前を入力できます。 『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の管理オプションの定義に関する項を参照してください。
発注の摘要を入力します。 この摘要は発注には印刷されず、内部で使用されます。 必要な数のノートを追加する場合は、添付機能を使用します(『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の購買文書へのノートの添付に関する項を参照)。
「明細」タブを選択します。 新しい発注明細の場合、購買管理には、次に使用可能な明細連番が表示されます。 この番号を受け入れるか、他と重複しない明細番号を入力できます。 この番号は、このウィンドウのすべてのタブに使用されます。
商品またはサービスの明細タイプを選択します。 選択した明細タイプに基づいて、購買管理では、対応するデフォルト設定が自動的にコピーされます。 『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の明細タイプの定義に関する項を参照してください。
(オプション)購買する品目を選択します。 選択できるのは、在庫管理で「在庫保有可能」チェック・ボックスの選択を解除して定義された品目です。 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の在庫属性グループに関する項を参照してください。
購買する品目の購買カテゴリを選択します。 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリの定義に関する項を参照してください。
品目の摘要を入力します。 この摘要は、品目の調達に使用されるため意味のある内容にしてください。 この品目が非在庫品目の場合、内部のメンバーは、この摘要によって、調達しようとしている品目を把握することになります。
購買する数量を入力します。
単位を選択します。 単位は、発注明細に入力する数量を修飾します。 明細タイプを選択すると、デフォルトの単位がこのフィールドに移入されます。 前の手順で品目を選択した場合は、そのデフォルトの単位によって明細タイプのデフォルトが上書きされます。 単位は、品目を受け入れ、請求または引き当てるまでは変更できます。
品目の単価を入力します。
「納入」を選択して標準発注明細および計画発注明細に複数の納入を入力し、購買管理で自動的に作成された納入を編集します(『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の発注納入の入力に関する項を参照)。
「詳細」タブを選択します。
「納入」ウィンドウ
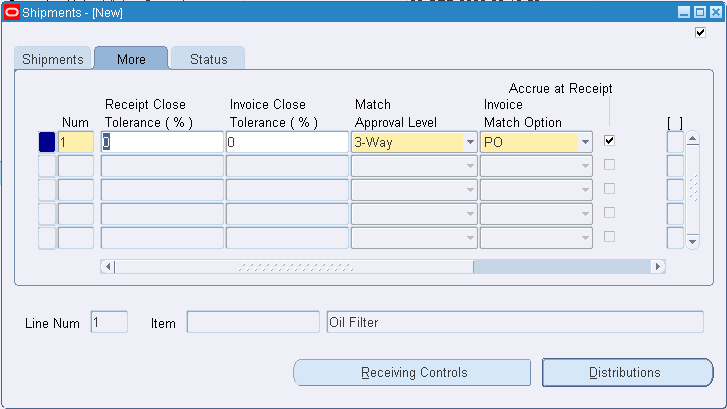
「受入時計上」チェック・ボックスを選択し、この発注明細の品目を受入時に計上することを指定します。
「配分」を選択して、発注納入に関する配分情報を入力するか、購買管理で自動的に作成された配分を表示します。 納入明細ごとに複数の配分を入力し、購買依頼文書に関する情報を入力できます(Oracle Procurementユーザーズ・ガイドの発注配分の入力に関する項を参照)。
「外部サービス」を選択して、この発注を保守作業指示に関連付けます。
「製造オーダー」値リストから、保守作業指示を選択します。 作業指示を選択すると、その作業指示に関連付けられたeAMプロジェクトおよびタスク情報が、購買依頼または発注の「配分」ウィンドウの「プロジェクト」タブ内の対応する「プロジェクト」および「タスク」フィールドにコピーされます。
工程連番を選択します。 購買した資材は、現在の作業指示のこの工程に関連付けられます。 購買管理には、工程のコードおよび部門が表示されます。
「完了」を選択します。
作業内容を保存します。
発注には承認が必要です(Oracle WorkflowガイドのOracle Workflow Builderでのプロセス定義の作成に関する項を参照)。 承認された発注は、eAM作業指示に表示され、購買管理に表示されます。
関連項目
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の発注ヘッダーの入力に関する項
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の外注加工情報の入力に関する項
『Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド』の発注明細の入力に関する項
直接品目(非在庫および摘要基準)は、発注カテゴリを選択することで、選択した適切な購買原価要素にチャージできます。 外注生産資源サービスが単発のイベントである理由から、外注加工の設定をバイパスするには(「外部処理の設定」を参照)、カテゴリを購買依頼明細に割り当てて(「直接品目に対する発注カテゴリ関連の設定」を参照)、労務、設備および資材の各勘定を作業指示にチャージできます。
「製造現場」搬送先タイプ(外注加工に関連しない)のすべての購買依頼または発注の配分明細については、eAM作業指示の資材勘定に金額(数量 * 購買価格 * 換算レート)がチャージされます。
受入プロセスでは、次の会計仕訳が作成されます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 受入検査 | XXX | - |
| 買掛金/未払金経過 | - | XXX |
資材搬送プロセスでは、次の仕訳が作成されます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 作業指示資材 | XXX | - |
| 受入検査 | - | XXX |
![]()
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.