リリース12
E06049-01
目次
前へ
次へ
| Oracle Assetsユーザー・ガイド リリース12 E06049-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この章のトピックは、次のとおりです。
この項では、Oracle Assetsの設定の完了に必要な各タスクの概要について説明します。
関連項目
Oracle Assetsを実装するには、次の各ステップを実行する必要があります。これらのステップについては、該当するOracle製品のユーザー・ガイドの設定に関する項に詳細が記載されています。次の表に、関連する製品の設定ステップを示します。
基礎となるOracle Applicationsテクノロジを設定するには、次のような様々な追加設定ステップを完了する必要があります。
コンカレント・マネージャやプリンタの構成など、システム全体の設定タスクの実行
ビジネス・データの特定セットへのアクセスを可能にし、取引の特定セットを完了する責任の設定を含むデータ・セキュリティの管理と、個人別のユーザーの1つ以上をこれらの責任への割当
Oracle Workflowの設定
次の設定ステップを完了する手順は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』のGeneral Ledgerの設定に関する項を参照してください。
| ステップ |
|---|
| 元帳の定義 関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の元帳の定義に関する項 注意: Oracle General Ledgerを実装していない場合は、Oracle Assetsの「元帳」ウィンドウを使用して元帳を定義できます。 |
| 追加仕訳ソースの定義 関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の仕訳ソースの定義に関する項 注意: Oracle General Ledgerを実装していない場合は、Oracle Assetsの「仕訳ソース」ウィンドウを使用して仕訳ソースを定義できます。 |
| 追加仕訳カテゴリの定義 関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の仕訳カテゴリの定義に関する項 注意: Oracle General Ledgerを実装していない場合は、Oracle Assetsの「仕訳カテゴリ」ウィンドウを使用して仕訳カテゴリを定義できます。 |
次の設定ステップを完了する手順は、『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のOracle Inventoryの設定に関する項を参照してください。
| ステップ |
|---|
| 単位区分の定義 関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位区分の定義に関する項 注意: Oracle Inventoryを実装していない場合は、Oracle Assetsの「単位区分」ウィンドウを使用して単位区分を定義できます。 |
| 単位の定義 関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位の定義に関する項 注意: Oracle Inventoryを実装していない場合は、Oracle Assetsの「単位」ウィンドウを使用して単位を定義できます。 |
次の設定ステップを完了する手順は、『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』を参照してください。
| ステップ |
|---|
| 従業員の定義 関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の新しい個人レコードの作成に関する項 注意: Oracle Human Resourcesを実装していない場合は、Oracle Assetsの「個人情報入力」ウィンドウを使用して従業員を定義できます。 |
次の設定ステップを完了する手順は、『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』のOracle Payablesの設定に関する項を参照してください。
| ステップ |
|---|
| 仕入先および従業員の採番方式の定義 関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項 注意: Oracle Payablesを実装していない場合は、Oracle Assetsの「会計オプション」ウィンドウを使用して仕入先および従業員の採番方式を定義できます。 |
次の設定ステップを完了する手順は、『Internet Supplier Portalインプリメンテーション・ガイド』を参照してください。
| ステップ |
|---|
| 仕入先の定義 関連項目: 『Internet Supplier Portalインプリメンテーション・ガイド』の仕入先の入力に関する項 注意: Oracle Payablesを実装していない場合は、Oracle Assetsの「仕入先」ウィンドウを使用して仕入先を定義できます。 |
関連項目
『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』
『Oracle Workflowガイド』
このフローチャートおよびチェックリストで概略が示されるステップの中には、必須のものと、任意のものがあります。デフォルト値のある必須ステップは、データベースでのあらかじめ提供されたデフォルト値を伴って実行される設定機能を指しますが、これらのデフォルト値を検討し、個々のビジネス・ニーズに適合するよう変更するかどうかを決定する必要があります。それらが必要な場合、または変更が必要な場合は、それぞれの設定ステップを実行してください。 関連する機能を使用したり、ある種のビジネス機能を完成する計画がある場合にのみ、オプションのステップを実行する必要があります。
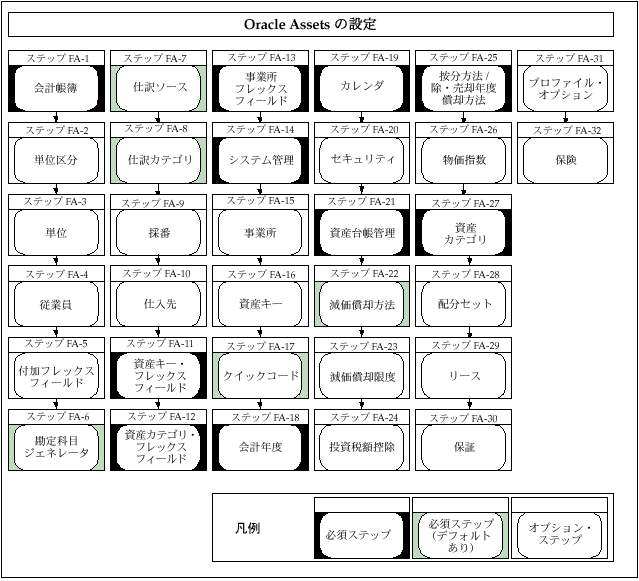
次の表は、Oracle Assetsの設定ステップとそのステップがオプションであるか必須であるかを示しています。Oracle Applicationsにログオンした後、これらのステップを完了して、Oracle Assetsを実装してください。
| ステップ番号 | 必須 | ステップ | |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 必須 | 元帳の定義 | |
| ステップ2 | オプション | 単位区分の定義 | |
| ステップ3 | オプション | 単位の定義 | |
| ステップ4 | オプション | 従業員の定義 | |
| ステップ5 | オプション | 付加フレックスフィールドの定義 | |
| ステップ6 | オプション | Oracle Subledger Accountingの設定 | |
| ステップ7 | オプション | 勘定科目ジェネレータの使用方法の決定 | |
| ステップ8 | 必須(デフォルトあり) | 追加仕訳ソースの定義 | |
| ステップ9 | 必須(デフォルトあり) | 追加仕訳カテゴリの定義 | |
| ステップ10 | オプション | 仕入先および従業員の採番方式の定義 | |
| ステップ11 | オプション | 仕入先の定義 | |
| ステップ12 | 必須 | 資産キー・フレックスフィールドの定義 | |
| ステップ13 | 必須 | 資産カテゴリ・フレックスフィールドの定義 | |
| ステップ14 | 必須 | 事業所フレックスフィールドの定義 | |
| ステップ15 | 必須 | システム管理の定義 | |
| ステップ16 | オプション | 事業所の定義 | |
| ステップ17 | オプション | 資産キーの定義 | |
| ステップ18 | 必須(デフォルトあり) | 標準資産摘要および他のクイックコード値の定義 | |
| ステップ19 | 必須 | 会計年度の定義 | |
| ステップ20 | 必須 | カレンダの定義 | |
| ステップ21 | オプション | 台帳別セキュリティの設定 | |
| ステップ22 | 必須 | 台帳管理の定義 | |
| ステップ23 | 必須(デフォルトあり) | その他の減価償却方法および償却率の定義 | |
| ステップ24 | オプション | 償却費計上限度額の定義 | |
| ステップ25 | オプション | 投資税額控除の定義 | |
| ステップ26 | 必須 | 按分方法および除・売却年度償却の定義 | |
| ステップ27 | オプション | 物価指数の定義 | |
| ステップ28 | 必須 | 資産カテゴリの定義 | |
| ステップ29 | オプション | 配分セットの定義 | |
| ステップ30 | オプション | リースの入力 | |
| ステップ31 | オプション | 保証の定義 | |
| ステップ32 | オプション | プロファイル・オプションの設定 | |
| ステップ33 | オプション | 資産保険の定義 |
各ステップには、一連のタスク、元帳、在庫組織、HR組織または複数組織の異なる営業単位ごとにステップを繰り返す必要があるかどうかを示すコンテキスト部があります。
Oracle Assetsを実装して使用するには、事前に元帳を少なくとも1つ定義しておく必要があります。
元帳には、会計カレンダ、元帳通貨および勘定科目体系が含まれます。勘定科目はGL勘定科目体系を定義します。元帳を設定する際に勘定科目を定義しなかった場合は、勘定科目体系と一致するように勘定科目を定義して、費用、現預金、買掛/未払金負債の各勘定科目に対して有効な値を指定する必要があります。
別のOracle Financials製品の設定を介して元帳がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
単一のインストールで、元帳が複数あるOracle Assetsを使用できます。関連項目: 元帳が複数あるOracle Assets
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: 『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の元帳の定義に関する項
Oracle InventoryまたはOracle Purchasingをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「単位区分」ウィンドウを使用して単位区分を定義します。生産高の測定に使用する単位区分は、累計生産高比例法を使用する資産に対して定義できます。
別のOracle Applications製品の設定を介して単位区分がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
重要: 単位区分を定義する前に組織を設定する必要があります。関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の組織の作成に関する項
重要: 組織を設定する前にプロファイル・オプション「HR: ユーザー・タイプ」を定義する必要があります。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のユーザー・プロファイル・オプションの設定に関する項
デフォルト - このステップをスキップした場合、単位区分にはOracle InventoryまたはOracle Purchasingのデフォルト設定が使用されます。Oracle InventoryまたはOracle Purchasingのいずれもインストールされていない場合は、単位区分を使用できません。
コンテキスト: それぞれの在庫組織について、このステップを1回実行します。
関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位区分の定義に関する項
Oracle InventoryまたはOracle Purchasingをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「単位」ウィンドウを使用して単位を定義します。生産高の測定に使用する単位は、累計生産高比例法を使用する資産に対して定義できます。
重要: 単位を定義する前に組織を設定する必要があります。関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の組織の作成に関する項
重要: 組織を設定する前にプロファイル・オプション「HR: ユーザー・タイプ」を定義する必要があります。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のユーザー・プロファイル・オプションの設定に関する項
別のOracle Applications製品の設定を介して単位がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合、単位にはOracle InventoryまたはOracle Purchasingのデフォルト設定が使用されます。Oracle InventoryまたはOracle Purchasingのいずれもインストールされていない場合は、単位を使用できません。
コンテキスト: それぞれの在庫組織について、このステップを1回実行します。
関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位の定義に関する項
Oracle Personnel、Oracle Payroll、Oracle PurchasingまたはOracle Payablesをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「個人情報入力」ウィンドウを使用して従業員を定義します。従業員に資産を割り当てるには、事前に従業員を入力しておく必要があります。Oracle Assetsでは、従業員名、番号および退職日のみが使用されます。
別のOracle Applications製品の設定を介して従業員がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、従業員名による資産の追跡を実行できません。
コンテキスト: それぞれのビジネス・グループについて、このステップを1回実行します。
関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の新しい個人レコードの入力に関する項
付加フレックスフィールドを設定して、追加の情報を追跡できます。たとえば、各資産カテゴリに対して付加フレックスフィールドを設定し、業務に関連する情報を収集できます。たとえば、車についてはナンバープレートの番号を追跡し、建物については床面積を追跡する場合があります。この場合は、新しい資産をカテゴリに割り当てるときに追加情報を入力できます。
Oracle Assetsにはその他にも多数の付加フレックスフィールドがあります。たとえば、取引に関する追加情報を格納するための付加フレックスフィールドを設定できます。
注意: リースGUI付加フレックスフィールドまたは除・売却GUI付加フレックスフィールドの設定方法は、『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の付加フレックスフィールド体系の定義に関する項を参照してください。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、資産を追跡するための追加の摘要情報を入力できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: 資産カテゴリ付加フレックスフィールドの定義
Oracle Subledger Accountingの設定(条件により必須)
注意: このステップは、「FA: ワークフロー勘定科目生成の使用」プロファイル・オプションが「No」に設定されている場合は必須です。
Oracle Assetsでは、Oracle Subledger Accountingを使用して仕訳が作成されます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、「FA: ワークフロー勘定科目生成の使用」プロファイル・オプションのデフォルト値である「No」が使用され、Subledger Accountingを介して仕訳が作成されます。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 『Oracle Subledger Accountingインプリメンテーション・ガイド』のSubledger Accountingオプションの設定の概要に関する項
Oracle Assetsでは、勘定科目ジェネレータを使用して仕訳用の会計フレックスフィールドの組合せが生成されます。Oracle Assetsで使用されるデフォルトの処理をレビューして、会計処理要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。定義した元帳ごとに、必要に応じて勘定科目ジェネレータをカスタマイズできます。勘定科目ジェネレータを使用するには、Oracle Workflowを設定する必要があります。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、デフォルトの勘定科目ジェネレータの設定を使用して会計フレックスフィールド・コードの組合せが作成されます。
コンテキスト: 各エンティティ(組織営業単位、ビジネス・グループ、法的エンティティなど)について、このステップを1回実行します。
Oracle General Ledgerをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「仕訳ソース」ウィンドウを使用して追加の仕訳ソースを定義します。仕訳ソースは仕訳取引の起点を識別するために使用されます。
Oracle General Ledgerの設定を介して仕訳ソースがすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、Oracle General Ledgerの仕訳ソース設定が使用されます。
コンテキスト: 営業単位ごとに1回ずつこのステップを実行してください。
関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の仕訳ソースの定義に関する項
Oracle General Ledgerをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「仕訳カテゴリ」ウィンドウを使用して追加の仕訳カテゴリを定義します。仕訳カテゴリは仕訳の目的またはタイプを表します。
Oracle General Ledgerの設定を介して仕訳カテゴリがすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、Oracle General Ledgerの仕訳カテゴリ設定が使用されます。
コンテキスト: 営業単位ごとに1回ずつこのステップを実行してください。
関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の仕訳カテゴリの定義に関する項
Oracle PurchasingまたはOracle Payablesをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「会計オプション」ウィンドウを使用して仕入先および従業員の採番方式を定義します。仕入先および従業員の採番方式は、仕入先または従業員を入力する前に指定する必要があります。
別のOracle Applications製品の設定を介して仕入先および従業員の採番方式がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、従業員およびアサイメントに対する資産割当の追跡を実行できません。
コンテキスト: 営業単位ごとに1回ずつこのステップを実行してください。
関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項
Oracle iSupplierをインストールしていない場合は、Oracle Assetsの「設定」 > 資産システム > 「会計」 > 「仕入先」を使用して、仕入先を定義します。資産の入力または仕入先からの一括追加の取得を実行するには、事前に仕入先を入力しておく必要があります。
別のOracle Applications製品の設定を介して仕入先がすでに定義されている場合は、次のステップに進みます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、特定の仕入先に割り当てられている資産の追跡を実行できません。
コンテキスト: 営業単位ごとに1回ずつこのステップを実行してください。
関連項目: 『Internet Supplier Portalインプリメンテーション・ガイド』の仕入先の入力に関する項
資産キー・フレックスフィールドを使用して資産キーを定義できます。資産キーを定義すると、資産に名称を指定したり、資産をグループ化できるため、資産番号なしで資産を検索できるようになります。資産キーは資産をグループ化できる点で資産カテゴリと似ていますが、資産キーは会計には影響を与えません。
このフレックスフィールドでは、類似する資産を検索できるように複数の資産に同じ名称を割り当てることができます。フレックスフィールドに追加の付加データを指定することで、資産をプロジェクト別または機能グループ別にグループ化できます。建設仮勘定(CIP)資産を追跡する際は、このフレックスフィールドを使用できます。資産キー・フレックスフィールドは、他のキー・フレックスフィールドの場合と同じ設定ウィンドウを使用して作成します。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: 資産キー・フレックスフィールド
資産カテゴリ・フレックスフィールドを使用して、資産カテゴリおよび補助カテゴリを定義できます。たとえば、コンピュータ機器用に資産カテゴリを作成し、さらにパーソナル・コンピュータ、端末、プリンタおよびソフトウェア用に各補助カテゴリを作成できます。主カテゴリ・セグメント・クオリファイアをカテゴリ・フレックスフィールドの単一のセグメントに割り当てる必要があります。主カテゴリ・セグメントを使用することで資産購買予算編成が容易になります。その他のセグメントはすべてオプションです。資産カテゴリ・フレックスフィールドは、他のキー・フレックスフィールドの場合と同じ設定ウィンドウを使用して作成します。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: カテゴリ・フレックスフィールド
事業所フレックスフィールドを使用して、正確な資産所在地の指定と追跡を実行できます。都道府県セグメント・クオリファイアを事業所フレックスフィールドの単一のセグメントに割り当てる必要があります。都道府県セグメントを使用することで固定資産税レポートの作成が容易になります。その他のセグメントはすべてオプションです。事業所フレックスフィールドは、他のキー・フレックスフィールドの場合と同じ設定ウィンドウを使用して作成します。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: 事業所フレックスフィールド
システム管理を設定します。「システム管理」ウィンドウで、企業名、資産採番方式およびキー・フレックスフィールド体系を指定します。資産の最も古い事業供用日も指定します。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: このステップは、インストールごとに1回実行する必要があります。
関連項目: システム管理の指定
有効な事業所を定義します。事業所フレックスフィールドの組合せによって、企業の有効な事業所が判断されます。事業所は、資産の追跡と固定資産税レポートの作成を実行する際に使用されます。
「事業所」ウィンドウは、事業所フレックスフィールドの動的挿入がオフになっている場合に有効な組合せを定義できる唯一のウィンドウです。動的挿入がオンになっている場合は、「資産割当」ウィンドウに入力した値で「事業所」ウィンドウが自動的に更新されます。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 事業所の定義
有効な資産キーを定義します。資産のこれらの組合せを入力する際は、値リストを使用して選択できます。
「資産キー」ウィンドウは、資産キー・フレックスフィールドの動的挿入が使用不可に設定されている場合に有効な組合せを定義できる唯一のウィンドウです。動的挿入が使用可能に設定されている場合は、資産を追加する際に入力した値で「資産キーの定義」ウィンドウが自動的に更新されます。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 資産キーの定義
標準資産摘要および他のクイックコード値の定義(必須、デフォルトあり)
クイックコード値は、資産の入力と保守を行う際に値リストから選択できる値です。次の項目に対してクイックコード値を定義できます。
標準資産摘要
仕訳
一括追加キュー名
資産タイプ
除・売却
資産カテゴリ
資産補助カテゴリ
デフォルト - このステップをスキップした場合は、資産を保守する際に表示される値リストにはデフォルト値がシードされます。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: クイックコードの入力
「会計年度」ウィンドウを使用して、創業以来の各会計年度の開始と終了を定義できます。
会計年度は会計期間をグループ化したものです。最も古い事業供用日からの各会計年度の開始日と終了日を定義する必要があります。4-4-5カレンダを使用している場合、開始日と終了日は毎年変化します。会計年度は、最も古い事業供用日から現会計年度より少なくとも1つ後の会計年度まで作成します。現会計年度が最終会計年度の場合、減価償却は失敗となります。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 会計年度の作成
「カレンダ」ウィンドウを使用して、必要な数の減価償却カレンダおよび按分用カレンダを設定します。カレンダは、会計年度を会計期間に分割するものです。カレンダには必要に応じていくつかの期間を定義します。
各減価償却台帳に対して按分用カレンダと減価償却カレンダをそれぞれ1つ定義します。複数の減価償却台帳で同じカレンダを共有してもかまいません。必要な場合は、同じカレンダを減価償却と按分用の両方のカレンダとして使用することもできます。
減価償却カレンダ: 償却費期間配分フラグを使用して、年間減価償却額に対する各期間への割当を決定します。
按分用カレンダ: 事業供用日を使用して、減価償却率表から選択される償却率を決定します。
各減価償却台帳ごとに異なるカレンダを設定できます。たとえば、会計レポートには月次カレンダを設定し、税務レポートには四半期カレンダを設定できます。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: カレンダ期間の日付の指定
複数の減価償却台帳がある場合は、各台帳ごとにセキュリティを設定する必要があります。たとえば、米国、欧州およびアジアで事業を行う場合は、その国の通貨と税法に従って、各国別に元帳および付随する減価償却台帳を準備しておきます。様々な理由により、それぞれのサイトのスタッフには別のサイトの減価償却情報が表示されないようにする場合があります。
各台帳は、一定の個人のみが情報を表示できるようにアクセスを制限できます。そのためには、資産組織および組織階層を作成して、特定の減価償却台帳にアクセスできる組織を決定します。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、全ユーザーがすべての資産減価償却台帳にアクセスできるようになります。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 台帳別セキュリティの設定
「資産台帳管理」ウィンドウを使用して減価償却台帳を設定します。独立した減価償却台帳をいくつでも作成できます。各台帳には、特有な固定資産の会計処理方針を編成して実装できるように、独自の会計基準と勘定科目を指定できます。
税務台帳を定義する場合は、対応する会計用台帳を指定する必要があります。資産および取引は、ソース台帳から税務台帳に一括コピーできます。現オープン期間を指定して初期一括コピーを実行すると、会計用台帳の該当する会計年度末時点の会計用台帳から税務台帳に各資産がコピーされます。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
元帳のセキュリティを設定するには、次のステップを完了する必要があります。
組織の定義。関連項目: 資産組織の概要
組織階層の定義。関連項目: Oracle Assetsの組織階層
セキュリティ・プロファイルの定義。関連項目: セキュリティ・プロファイル
セキュリティ・リスト保守処理の実行。関連項目: セキュリティ・リスト保守処理
職責の定義。関連項目: 職責の定義
ユーザーへの職責の割当。関連項目: ユーザーへの職責の割当
「FA: セキュリティ・プロファイル」プロファイル・オプションの設定。関連項目: 「FA: セキュリティ・プロファイル」の設定
関連項目: 減価償却台帳の定義
その他の減価償却方法および償却率の定義(必須、デフォルトあり)
減価償却方法は、資産取得価額の配分方法を示します。Oracle Assetsには多数の標準減価償却方法がありますが、必要に応じて「方法」ウィンドウで方法をさらに定義できます。
耐用年数ベースの減価償却方法: Oracle Assetsには標準耐用年数に基づいた減価償却方法と償却率が組み込まれていますが、耐用年数ベースの方法をさらに定義できます。
定率減価償却方法: 減額値などの定率方法をさらに定義できます。減価償却の計算方法は、純帳簿価額または資産取得価額を使用して定義できます。
ボーナス償却ルール: 「ボーナス償却ルール」ウィンドウを使用して、定率減価償却のボーナス・レートを入力します。ボーナス・ルールを使用すると、資産の耐用期間の早期年度に追加の減価償却を計上できます。
累計生産高比例法: 累計生産高比例法を定義すると、期間の実際の累計生産高または使用に基づいて資産の減価償却を計算できます。
算式ベースの減価償却: 資産について年間減価償却率を導出する特定の算式を定義できます。表ベース、定率、計算または単位による減価償却方法のかわりに、ユーザー定義によるこれらの減価償却算式を使用できます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、Oracle Assetsに組み込まれている標準減価償却方法のみを使用できます。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: その他の減価償却方法の定義、算式ベースの減価償却方法の定義およびボーナス償却ルールの定義
償却費計上限度額は、資産に対して適用できる減価償却費を制限します。資産に対して適用できる減価償却費の年額を制限するには、減価償却費限度額を設定します。あるいは、減価償却費計上限度額を設定して資産の償却対象額を制限します。
減価償却費限度額: 「限度」ウィンドウを使用して減価償却費限度額を定義します。米国税法が適用される場合は、高級車に対して償却費計上限度額を設定する必要があります。
減価償却費計上限度額: 計上限度額を必要とする国(オーストラリアなど)で事業を行う場合は、Oracle Assetsでの減価償却計算に使用する計上価額を制限できます。計上限度額を使用すると、計上限度額と資産取得価額のうち少ない減価償却費に基づいて減価償却が計算されます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、償却費計上限度額による減価償却費の制限は適用されません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 償却費計上限度額の設定
投資税額控除(ITC)率、回収率および限度を設定します。投資税額控除(ITC)を使用して、資産の償却対象額を減額できます。
投資税額控除率: 投資税額控除の対象となる資産の投資税額控除率(ITC率)を設定できます。ITC率によって、資産の投資税額控除額(ITC額)が決まります。
投資税額控除回収率: 投資税額控除のある資産の投資税額控除回収率(ITC回収率)を設定できます。ITC回収率によって、資産を早期に除・売却した場合に回収する必要がある投資税額控除部分が決定されます。
関連項目: 投資税額控除率の定義
投資税額控除限度額: 投資税額控除限度額(ITC限度額)を定義できます。ITC限度額は資産のITC額を制限します。米国税法が適用される場合は、高級車に対してITC限度額を設定する必要があります。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、投資税額控除を使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 償却費計上限度額の設定
「按分方法」ウィンドウを使用して按分方法および除・売却年度償却を設定します。按分方法および除・売却年度償却を定義することで、資産の事業供用日に基づいて資産の初年度および最終年度の減価償却費が決まります。Oracle Assetsでは按分方法および除・売却年度償却を必要に応じていくつでも設定できます。
按分方法: 資産に対する初年度の減価償却費が決まります。
除・売却年度償却: 除・売却に対して加算以外の按分方法を使用する必要がある国で事業を行う場合は、除・売却年度償却を設定する必要があります。除・売却日に基づいて資産に対する最終年度の減価償却費が決まります。
按分方法は年度全体に対して設定する必要があります。会計年度の最終期間に減価償却プログラムを実行すると、次の会計年度の日付が自動的に生成されます。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 按分方法の日付の指定
物価指数を使用すると、取得時の価額ではなく現行価額で除・売却の損益を計算できます。取得時の価額ではなく現行価額に基づいて損益を計算する必要がある国で事業を行う場合は、除・売却時に資産の損益を計算できるように、Oracle Assetsを使用して物価指数を設定できます。物価指数を定義したカテゴリおよび台帳に割り当てた資産を除・売却する場合は、再評価資産除・売却レポートを実行できます。このレポートでは損益計算に再評価後の資産取得価額が使用されます。
各資産カテゴリに別の指数を使用したり、全カテゴリに同じ指数を使用できます。「資産カテゴリ」ウィンドウの「物価指数」フィールドに物価指数名を入力することで、指数を資産カテゴリに関連付けます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、除・売却や保険などの機能で物価指数を使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 物価指数の定義
資産カテゴリを使用して、減価償却方法や按分方法など、単一カテゴリ内のすべての資産に共通する情報を定義できます。この情報を使用してデフォルト値が提供されるため、資産を速やかに入力できるようになります。
デフォルト - これは必須ステップです。このステップをスキップした場合、Oracle Assetsは使用できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 資産カテゴリの設定
事前定義の配分セットを使用して、新しい資産または一括追加に対して配分を迅速かつ正確に自動で割り当てることができます。デフォルトの配分セットは、「資産割当」ウィンドウの「配分セット」ポップリストに表示されます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、配分セットを使用して配分を新規資産取得に自動的に割り当てることはできません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 配分セットの定義
「リース詳細」ウィンドウでリースを定義します。「リース詳細」ウィンドウでは、1つ以上の資産にリースを割り当てることができます。また、「リース詳細」ウィンドウで一般会計原則に従ってリースをテストして、「リース支払」ウィンドウを使用して代替リース戦略を分析することもできます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、リースを資産に割り当てることはできません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
製造業者および仕入先保証書の記載情報の定義と追跡を実行します。保証情報は「資産保証」ウィンドウで定義します。「資産詳細」ウィンドウでは、以前に定義した保証に対して資産を割り当てます。同じ保証に資産をいくつでも割り当てることができます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、製造業者および仕入先保証の記載情報を追跡できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 資産保証の定義
プロファイル・オプションでは、Oracle Assetsによるデータ・アクセスとデータ処理の管理方法を指定します。一般的に、プロファイル・オプションは、サイト、アプリケーション、職責およびユーザーのうち、1つ以上のレベルで設定できます。
Oracle Assetsのユーザーは、「個別プロファイル値」ウィンドウで、ユーザー・レベルでのみのプロファイル・オプションを設定します。システム管理者は、「システム・プロファイル・オプションの更新」ウィンドウで、サイト、アプリケーション、職責およびユーザーのレベルのプロファイル・オプションを設定します。
Oracle Assetsでは、次のプロファイル・オプションを設定または表示できます。この表には、Oracle Assetsで使用される他のApplicationsからのプロファイル・オプションも含まれています。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、Oracle Assetsでのアクセス管理およびデータ処理が最適な設定では実行されません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のユーザー・プロファイルの概要に関する項、およびユーザー・プロファイル・オプションの設定に関する項
「固定資産保険」ウィンドウを使用して、資産の保険情報(保険証券情報や保険計算方法など)を定義できます。異なる保険カテゴリに対して資産の保険証券を複数入力できます。ここに入力する保険情報は、資産の現行保険価額の計算に使用されます。
デフォルト - このステップをスキップした場合は、資産の保険情報の追跡を実行できません。
コンテキスト: 各元帳について、このステップを1回実行します。
関連項目: 資産保険の概要
単一のOracle Assetsインストールで、元帳が複数あるOracle Assetsを使用できます。
2つの異なる方法で複数の企業を処理できます。単一の元帳で複数の企業を処理することも、それぞれ個別の元帳を使用して複数の企業を処理することもできます。採用する方法に関係なく、使用する各元帳に対して少なくとも1つの減価償却台帳を作成します。
例: Global Computersは、3社の子会社を持つ親会社です。次の図表を参照してください。
| Global Computers | G/L元帳1 |
| Real Estate | G/L元帳2 |
| Research & Development | G/L元帳3 |
| Distribution | G/L元帳3 |
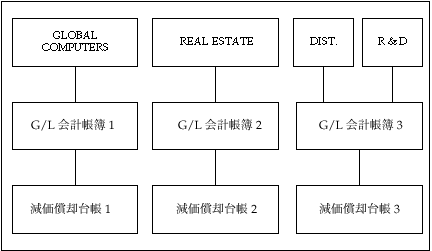
Global Computersと子会社Real Estateは元帳が異なるため、個別の減価償却台帳が必要です。子会社Research & DevelopmentとDistributionは元帳が同じであるため、両社で1つの減価償却台帳を設定することも、各社に個別の減価償却台帳を設定することもできます。
複数の元帳を実装するには、Oracle Assetsのコピーが1つのみ必要です。自動インストールを使用して単一のコピーをインストールします。
Oracle Assetsをインストールした後は、「資産台帳管理」ウィンドウを使用して、必要な数の減価償却台帳を設定します。各減価償却台帳ごとに、仕訳が適切な元帳に作成されるように選択します。
「資産台帳管理」ウィンドウを使用して減価償却台帳を設定する前に、次の設定を完了しておく必要があります。
各元帳に関連する勘定科目体系(勘定体系)を設定します。
Oracle General Ledgerを使用して必要な元帳を設定します。Oracle General Ledgerを使用していない場合は、Oracle Assetsの「元帳」ウィンドウを使用して元帳を設定できます。
Oracle Assetsによる複数元帳の実装には、次の制限があります。
異なる会計用減価償却台帳にある資産を移動する場合は、一方の減価償却台帳で資産を除・売却し、もう一方の減価償却台帳に資産を追加する必要があります。
すべての台帳が同じ会計フレックスフィールド体系の場合は、1度に複数の台帳に対して減価償却見積計算を実行できます。会計フレックスフィールド体系が異なる場合は、個別に見積計算を実行する必要があります。
関連項目
『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の元帳の定義に関する項
資産カテゴリ付加フレックスフィールドを設定し、資産カテゴリに基づいて追加情報を格納できます。資産カテゴリ付加フレックスフィールドは、「追加」と「資産クイック登録」の両方のフォームに表示されます。
付加フレックスフィールド体系がカテゴリ・フレックスフィールド(キー・フレックスフィールド)の値に基づくように、ATTRIBUTE_CATEGORY_CODEを参照フィールドとして入力します。関連項目: カテゴリ・フレックスフィールド
コンテキスト・フィールド値(体系名)は、連結カテゴリ・フレックスフィールドの組合せと正確に一致するように定義します。たとえば、主カテゴリ値がBUILDING、補助カテゴリ値がOFFICEの場合、カテゴリ・フレックスフィールドの組合せはBUILDING.OFFICEとなります。したがって、BUILDING.OFFICEをコンテキスト値(体系名)として定義します。同様にして、別のコンテキスト値にはVEHICLE.DELIVERYを定義できます。セグメント・セパレータ、綴りおよび大/小文字の表記は、カテゴリ・フレックスフィールドの組合せと正確に一致する必要があります。
付加フレックスフィールド体系は、カテゴリ・フレックスフィールドの各組合せに対して定義する必要はありません。追加情報(ナンバー・プレートの番号、保険証書番号など)を取得する必要があるカテゴリに対してのみ定義します。
レポートにフレックスフィールド・ビューを使用する予定がある場合は、コンテキスト依存セグメントの異なる体系の間で、セグメント名(セグメント・プロンプトと同一とはかぎりません)を共有する必要があることに注意してください。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のフレックスフィールド・ビューの概要に関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のセグメントの命名規則に関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の付加フレックスフィールド・ビューの例に関する項
この項では、Oracle Assetsのデフォルトの勘定科目生成処理の使用方法とカスタマイズ方法について説明します。
Oracle Assetsの勘定科目ジェネレータはOracle Workflowを利用します。勘定科目生成処理は、Oracle Workflow Builderを介して表示およびカスタマイズできます。関連項目: 『Oracle Workflow Developer Guide』のOracle E-Business Suite組込みの事前定義済ワークフローに関する項、および『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の勘定科目ジェネレータの概要に関する項
Oracle Assetsでは、勘定科目ジェネレータを使用して仕訳の会計フレックスフィールドの組合せが生成されます。勘定科目ジェネレータを使用することで、Oracle Assetsが仕訳を作成する勘定科目の各セグメントに特定のソースを指定できます。勘定科目ジェネレータには、要件に従って仕訳を作成する柔軟性があります。仕訳を作成するための詳細を指定したり、各台帳と勘定科目タイプの詳細レベルを指定できます。
たとえば、資産取得価額の仕訳を作成するときに、コスト・センター・セグメントの元データは、「資産割当」ウィンドウで資産に対して入力した配分明細の減価償却費勘定であることを指定できます。あるいは、コスト・センターの元データは、減価償却台帳に定義したデフォルト値であることを指定できます。
減価償却台帳を設定すると、デフォルトの割当を使用して仕訳が作成されるように勘定科目ジェネレータが設定されます。
Oracle Assetsには、2つの勘定科目生成処理がシードされています。
「デフォルト勘定科目を生成」処理
「分配詳細勘定科目を生成」処理
「デフォルト勘定科目を生成」処理は、減価償却費を除いて、コスト・センター・レベルの詳細なしで仕訳を作成します。この処理ではデフォルトの割当が使用され、「資産割当」ウィンドウの配分明細からの貸借一致セグメントを使用して仕訳が作成されます。勘定科目セグメントは、勘定科目タイプに従って資産カテゴリまたは台帳から作成されます。その他のセグメントは、台帳に入力したデフォルトのセグメント値から取得されます。デフォルトの勘定科目生成処理を変更して、別の詳細レベルに仕訳が作成されるようにできます。
「分配詳細勘定科目を生成」処理は、コスト・センター・レベルの詳細がある仕訳を作成します。この処理では、勘定科目セグメント以外のすべてのセグメント値に対して減価償却費勘定を使用して仕訳が作成されます。勘定科目セグメントは、勘定科目タイプに従って資産カテゴリまたは台帳から作成されます。デフォルトの勘定科目生成処理を変更して、別の詳細レベルに仕訳が作成されるようにできます。
ヒント: この項の説明に従ってデフォルトの処理を変更する必要があるのは、勘定科目ジェネレータを使用して異なる詳細レベルに仕訳を転記する場合のみです。
重要: 減価償却費勘定とボーナス減価償却費勘定では、デフォルトの処理が異なることに注意してください。デフォルトの処理を使用すると、減価償却費については完全な詳細仕訳が作成されます。減価償却費の場合は、「資産割当」ウィンドウで資産に対して入力した配分明細からの全セグメントを使用して仕訳が作成されます。ボーナス減価償却費の場合は、資産カテゴリからの勘定科目セグメントと配分明細からのその他のセグメントを使用して仕訳が作成されます。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の勘定科目ジェネレータの概要に関する項
リリース10では、Oracle Applicationsの複数の製品で、特定の勘定取引に対して勘定科目コードの組合せを導出する際にフレックスビルダーが使用されていました。リリース11では、フレックスビルダーから勘定科目ジェネレータに移行され、卓越した柔軟性とOracle Workflowとの優れたユーザー・インタフェースが提供されるようになりました。
リリース10からアップグレードしていて、フレックスビルダーを使用していた場合は、この設定ステップに相当する手順をアップグレードの一環として実行する必要があります。関連項目: 『Oracle Applicationsのアップグレード』の「フレックスビルダー」の章
Oracle Assetsを初めて実装している場合は、会計フレックスフィールド・コードの組合せの作成に対する勘定科目ジェネレータの使用方法をレビューする必要があります。固有の会計フレックスフィールド体系を使用する各元帳ごとに、デフォルトの勘定科目生成処理が適切かどうかをレビューします。各体系と元帳ごとに、次のいずれかの手段を選択できます。
「デフォルト勘定科目を生成」処理を使用します。
「分配詳細勘定科目を生成」処理を使用します。
デフォルトの勘定科目生成処理をカスタマイズします。
この選択によって、実装チームが実行する必要がある設定ステップが決まります。
注意: 勘定科目ジェネレータを新規に作成することはできません。ただし、前述されているようにデフォルトの勘定科目ジェネレータをカスタマイズできます。
Oracle Assetsの本番データベースで勘定科目ジェネレータを使用して会計フレックスフィールドの組合せを生成する前に、次のことを実行する必要があります。
各元帳に対して会計フレックスフィールド体系を定義します。
フレックスフィールド・セグメント値と検証ルールを定義します。
Oracle Workflowを設定します。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』
デフォルトの勘定科目生成処理を使用するか、会計処理のニーズにあわせて勘定科目ジェネレータをカスタマイズするかを選択します。
各元帳に対して次のいずれかを行います。
デフォルトの勘定科目生成処理を使用することを選択します。
デフォルトの勘定科目生成処理をカスタマイズして、カスタマイズをテストし、必要に応じてフレックスフィールド体系に対してその処理を選択します。
関連項目
Oracle Assetsの勘定科目ジェネレータのカスタマイズ
デフォルトの勘定科目生成処理が会計処理要件を満たしているかどうかを評価します。デフォルトの処理を使用するために必要な設定ステップはありません。デフォルトの処理は、変更の必要性に従って後で更新することもできます。重要度の低い変更については、デフォルトの処理名を変更せずに付加できます。
注意: リリース10でフレックスビルダーを使用していて、その際にデフォルトの構成をカスタマイズしていなかった場合は、リリース11のデフォルトの勘定科目生成処理を使用できます。このデフォルトの処理を使用して、フレックスビルダーのデフォルトの割当と同じ結果が得られます。
勘定科目ジェネレータの各ワークフローは項目タイプと呼ばれます。Oracle Assetsには、次の勘定科目ジェネレータ項目タイプが付属しています。
FA勘定科目ジェネレータ
FA勘定科目ジェネレータには、次のワークフロー・プロセスが組み込まれています。
デフォルト勘定科目を生成
分配詳細勘定科目を生成
フレックスビルダー・ルールを使って科目を生成
「デフォルト勘定科目を生成」処理は、資産レベル、台帳レベルおよびカテゴリ・レベルの勘定科目を生成します。デフォルトの設定を使用するか、必要に応じて設定をカスタマイズできます。
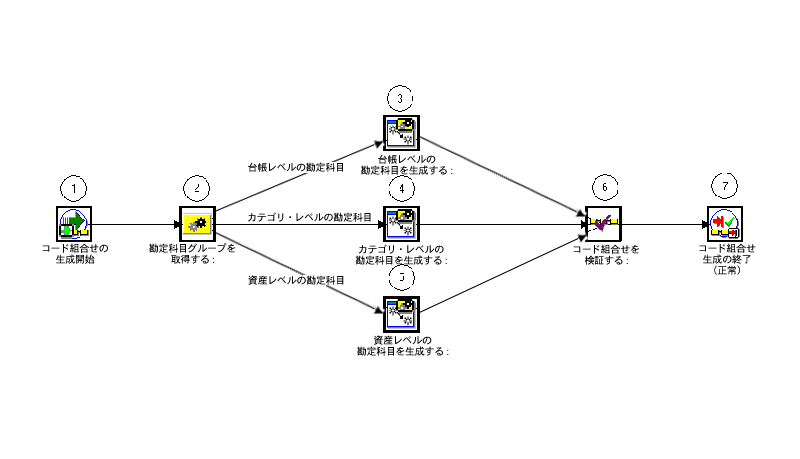
これはプロセスの開始をマークする標準アクティビティです。
勘定科目が属するグループを台帳レベル、カテゴリ・レベルまたは資産レベルで戻します。
台帳レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
撤去費用精算
撤去費用差益
撤去費用差損
繰延償却費用
繰延償却累計額
償却累計額修正
会社間買掛/未払金
会社間売掛/未収金
純帳簿価額除・売却差益
純帳簿価額除・売却差損
売却価額精算
売却価額差益
売却価額差損
再評価償却累計額差益
再評価償却累計額差損
カテゴリ・レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
資産精算
資産取得価額
ボーナス減価償却費
ボーナス償却累計額
建設仮勘定精算
建設仮勘定費用
償却累計額
再評価償却
再評価償却累計額
資産レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
減価償却費
FA勘定科目ジェネレータによって、生成されたコード組合せが検証されます。
勘定科目生成処理では、この機能が必ず最後に実行されます。
「分配詳細勘定科目を生成」処理は、資産レベル、台帳レベルおよびカテゴリ・レベルの勘定科目を生成します。デフォルトの設定を使用するか、必要に応じて設定をカスタマイズできます。
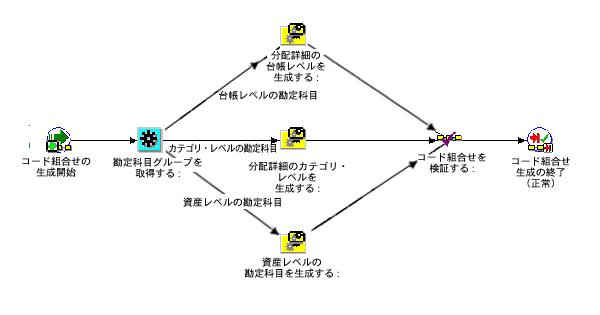
これはプロセスの開始をマークする標準アクティビティです。
勘定科目が属するグループを台帳レベル、カテゴリ・レベルまたは資産レベルで戻します。
台帳レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
撤去費用精算
撤去費用差益
撤去費用差損
繰延償却費用
繰延償却累計額
償却累計額修正
会社間買掛/未払金
会社間売掛/未収金
純帳簿価額除・売却差益
純帳簿価額除・売却差損
売却価額精算
売却価額差益
売却価額差損
再評価償却累計額差益
再評価償却累計額差損
カテゴリ・レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
資産精算
資産取得価額
ボーナス減価償却費
ボーナス償却累計額
建設仮勘定精算
建設仮勘定費用
償却累計額
再評価償却
再評価償却累計額
資産レベルの勘定科目についてコード組合せID(CCID)を生成します。FA勘定科目ジェネレータによって、コード組合せを生成している勘定科目名が検索されます。該当する勘定科目名は、次のとおりです。
減価償却費
FA勘定科目ジェネレータによって、生成されたコード組合せが検証されます。
勘定科目生成処理では、この機能が必ず最後に実行されます。
以前のリリースでフレックスビルダーを使用して勘定科目の組合せを生成していた場合は、「フレックスビルダー・ルールを使って科目を生成」処理を使用して、事前定義のフレックスビルダー・ルールを変更することなく、勘定科目ジェネレータもカスタマイズせずに、フレックスビルダーの設定を自動的に複製できます。「フレックスビルダー・ルールを使って科目を生成」処理には、リリース10からリリース11へのアップグレードの際に生成された機能が含まれています。
リリース10からアップグレードしている場合は、『Oracle Applicationsのアップグレード』の「フレックスビルダー」の章のガイドラインに従ってください。
ある特定の状況では、仕訳を作成する勘定科目を決定する際に勘定科目ジェネレータが使用されないことがあります。一括追加を使用して追加された資産に対する精算勘定を決定する場合や、資産組替後の減価償却費勘定を決定する場合がこれに該当します。
一括追加を使用して資産を追加すると、勘定科目ジェネレータが使用されずに、買掛管理システムが資産を計上した会計用台帳の資産精算勘定または建設仮精算勘定が精算されます。
資産を組み替えると、勘定科目ジェネレータが使用されずに、すべての台帳の減価償却費勘定が、新しい資産カテゴリの勘定科目セグメント、または「資産割当」ウィンドウで資産に指定した配分からの勘定科目セグメントに変更されます。
勘定科目の生成を実行すると、必要なすべての勘定科目が生成され、勘定科目の検証に合格した場合はfa_distribution_accountsに格納されます。
勘定科目の組合せがfa_distribution_accountsにすでにある場合、その勘定科目の組合せは再度検証せずに使用されます。
関連項目
Oracle Assetsには、勘定科目を生成する際に使用できる2種類のデフォルトの処理が用意されています。デフォルトの処理では会計処理要件を満たさない場合は、Oracle Workflow Builderを使用して、デフォルトの処理をカスタマイズするか、新しい処理を作成できます。
独自の会計処理要件を満たすように新しい処理を作成する場合は、Oracle Workflow Builderを使用して新しい処理を作成するか、既存のデフォルトの処理をコピーし、処理名を変更してから様々な変更を加えます。
勘定科目ジェネレータによる勘定科目の組合せの生成方法を指定することで、仕訳が作成される詳細レベルを定義できます。勘定科目の組合せの各セグメント値に対して、Oracle Assetsでソースを指定できます。
重要: クオリファイアなしでセグメントの詳細レベルに仕訳を作成すると、償却累計額元帳レポートでは、総勘定元帳への直接的な消込は実行されません。Oracle Assetsのほとんどのレポートでは、クオリファイアのないセグメント詳細はレポートの対象になりません。
Oracle Assetsの標準レポートには、配分明細からの貸借一致セグメントと、資産カテゴリまたは台帳からのコスト・センターと勘定科目が表示されます。これらの値は、異なるセグメント値を使用して仕訳を作成するように勘定科目生成処理を変更した場合も表示されます。
FA勘定科目ジェネレータには、デフォルトの処理で使用される機能に加え、いくつかの独特な機能が組み込まれています。これらの機能は、標準機能および標準フレックスフィールド・ワークフロー機能とともに使用して、FA勘定科目ジェネレータをカスタマイズできます。
注意: この項に記載されている機能はいずれも削除または変更できません。
資産台帳の勘定科目名を取得。台帳レベルの勘定科目を1つのみ戻します。
資産台帳区分を取得。台帳の資産台帳区分(会計、税金、予算のいずれか)を決定します。
台帳タイプ・コードを取得。ワークフロー・プロセスで使用される台帳タイプ・コードを戻します。処理でこの機能を使用するには、次の準備が必要です。
新しい参照タイプ「資産台帳」を定義します。
定義してある参照コードを参照タイプ「資産台帳」に追加します。参照コードには、「資産台帳管理」ウィンドウで定義した有効な台帳タイプ・コード(例: MYCORP、MYTAX)を指定する必要があります。
「台帳タイプ・コードを取得」プロパティの「結果タイプ」フィールドに、「資産台帳」と入力します。
次の表に、各セグメントのデフォルト・セグメント・ソースを示します。
| セグメント名 | デフォルト・セグメント・ソース |
|---|---|
| 会社 | 配分CCID |
| コスト・センター | デフォルトCCID |
| 勘定科目 | 勘定科目セグメント値 |
| 製品 | デフォルトCCID |
| 補助科目 | デフォルトCCID |
勘定科目ジェネレータでは、様々なソースを使用して仕訳を作成する勘定科目の組合せを入力します。
会計用台帳のカテゴリ・レベルの全勘定科目について仕訳をコスト・センター・レベルに作成するには、勘定科目ジェネレータが配分明細属性のコスト・センター・セグメント値を使用するように指定します。
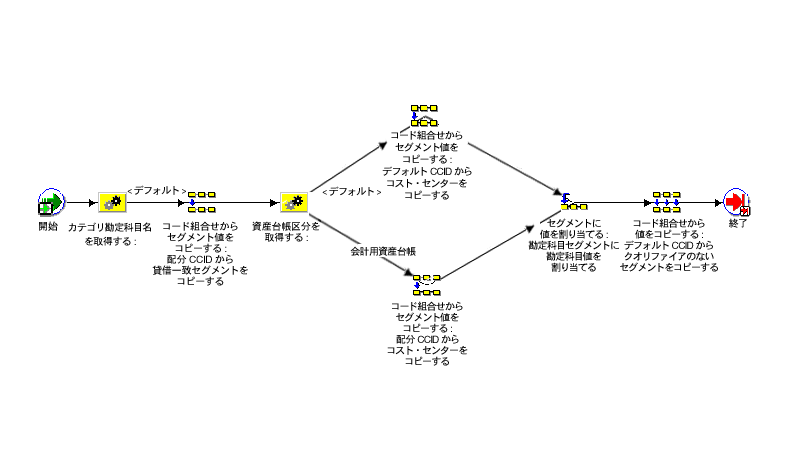
これらの属性を使用して、配分明細からの貸借一致セグメントとコスト・センター・セグメントを使用して仕訳が作成されます。勘定科目セグメントは資産カテゴリから取得され、その他のセグメントは台帳に入力したデフォルトから取得されます。
変更した勘定科目生成処理は、本番データベースで使用する前にテストする必要があります。
仕入先請求書の勘定科目を生成する処理は、SQLスクリプトfaxagtst.sqlを実行することでテストできます。システム・プロンプトで、次のように入力します。
$FA_TOP/admin/sql/faxagtst.sql
次のパラメータ値の入力を要求するプロンプトが表示されます。
account_type(例: asset_cost、asset_cost_clearing)
book
distribution_ccid
account_segment
default_ccid
account_ccid
FA勘定科目ジェネレータ項目タイプの勘定科目生成処理をカスタマイズし、新しい処理名を割り当てた場合は、「勘定科目生成処理」ウィンドウを使用して新しい処理名を適切な会計フレックスフィールド体系および項目タイプに関連付けます。
処理名を変更せずにデフォルトの処理をカスタマイズした場合は、このステップを実行する必要はありません。
「勘定科目生成処理」ウィンドウにナビゲートします。
このウィンドウは、システム管理者職責では、「アプリケーション」 > 「フレックスフィールド」 > 「キー」 > 「勘定科目」のナビゲータ・パスを介して表示されます。Oracle Assets職責では、「設定」 > 「フレックスフィールド」 > 「キー」 > 「勘定科目」で表示されます。
処理を割り当てる体系を選択します。行の値リストからアプリケーション、フレックスフィールド・タイトルおよび摘要を選択できます。
FA勘定科目ジェネレータ項目タイプを指定します。
勘定科目の生成に使用する処理を指定します。
デフォルトでは、「デフォルト勘定科目を生成」処理が指定されます。「分配詳細勘定科目を生成」処理などの別の処理を使用する場合は、使用する処理名を入力します。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の勘定科目ジェネレータのカスタマイズに関する項
Oracle Assetsでは、資産キー・フレックスフィールドを使用して資産を非財務情報別にグループ化します。必要な情報が記録されるように資産キー・フレックスフィールドを設計します。次に、資産番号なしで資産を検索できるように、資産キーで資産をグループ化します。
警告: フレックスフィールドは慎重に計画してください。フレックスフィールドを使用して資産の入力を開始した後は、フレックスフィールドを変更できません。
| 所有者 | Oracle Assets |
|---|---|
| フレックスフィールド・コード | キー番号 |
| 表名 | FA_ASSET_KEYWORDS |
| 列数 | 10 |
| 列幅 | 30 |
| 動的挿入可/不可 | 可 |
| 一意ID列 | CODE_COMBINATION_ID |
| 体系列 | なし |
資産キー・フレックスフィールドを使用して資産をグループ化します。資産は非財務情報に従ってグループ化します。類似する資産を簡単に検索できるように、同じ資産キーを複数の資産に割り当てることができます。Oracle Assetsのすべての取引フォームでは、問合せに資産キーを使用できるため、資産番号を指定せずに資産を検索できます。
資産キー・フレックスフィールド体系は、組織固有のニーズを満たすように定義します。資産キー・フレックスフィールドのセグメント数、各セグメントの長さ、および各セグメントの名称と順序を選択します。資産キー・セグメントは10個まで定義できます。このキー・フレックスフィールドは、1つの体系のみをサポートします。
資産キーを使用して資産を追跡するように選択しない場合は、少なくとも1つのセグメント資産キー・フレックスフィールドを検証なしで定義する必要があります。
資産をグループ化して問い合せる方法を検討します。資産キー体系に必要なレベル(セグメント)数を決定する必要があります。
資産キー体系の各セグメントには値セットが必要です。これらの値セットには、資産のグループ化に使用した条件を値として入力します。
ヒント: 資産キー名(すべてのセグメントが連結された名称)はフォームおよびレポートに表示されますが、表示される文字数には制限があります。簡潔な資産キー・セグメント値を指定してください。
値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを作成します。別のセグメントに依存するセグメントを設定する場合は、ユーザーが最初に入力するセグメントには独立値セットを作成し、入力された値によって決まるセグメントには依存値セットを作成します。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の値セットの各ウィンドウに関する項
あるいは、カテゴリ・フレックスフィールドの値セットに対してカスケード依存を設定できます。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の$FLEX$構文の例に関する項
新しい資産キー・セグメントは、キー・セグメントの定義フォームを使用して定義します。キー・フレックスフィールドを再コンパイルした後は、資産を追加する前に再度Oracle Assetsにログインする必要があることに注意してください。
有効なすべての組合せを定義して、ユーザーが資産を入力する際は追加の組合せを作成できないようにする場合は、「動的挿入の許可」の選択を解除します。有効な組合せを制限する必要がない場合は、「動的挿入の許可」を選択します。有効な組合せは、「資産キー・フレックスフィールド組合せの定義」フォームで定義できます。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のキー・フレックスフィールド・セグメントに関する項
各セグメントの有効な値リストは、「セグメント値」ウィンドウを使用して作成します。フォームおよびレポートに表示できる資産キー・フレックスフィールドの文字数には制限があるため、簡潔な値を指定してください。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の「セグメント値」ウィンドウに関する項
定義したセグメントを使用する組合せを入力するには、「資産キー・フレックスフィールド組合せの定義」フォームを使用します。「動的挿入の許可」を選択した場合は、このフォームを使用して組合せを定義する必要はありません。
関連項目: 資産キーの定義
2つのセグメント資産キー・フレックスフィールドを使用することに決定しました。典型的な資産キーの組合せは「JET 10.ENGINE」です。資産キー・フレックスフィールドを設定するには、値セットの設定、セグメントの有効化、および有効なセグメント値の入力を実行する必要があります。
最初に、値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを設定します。たとえば、「プロジェクト」および「構成要素」値セットを作成します。
次に、「キー・フレックスフィールド・セグメント」ウィンドウを使用して、セグメントを有効にします。「セグメント」ウィンドウで、検証する各セグメントと値セットを入力します。
「セグメント値」ウィンドウを使用して、各資産キー・セグメントに対して有効な値を入力します。たとえば、「プロジェクト」セグメントに有効な値として「JET 10」を入力します。
これで、資産を入力する際に資産キーとして「JET 10.ENGINE」を指定できるようになりました。「動的挿入の許可」が選択されているため、その組合せがない場合は自動的に作成されます。「資産キー・フレックスフィールド組合せの定義」フォームを使用して、組合せを明示的に作成することもできます。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のフレックスフィールド名別キー・フレックスフィールドに関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の所有アプリケーション別キー・フレックスフィールドに関する項
Oracle Assetsでは、カテゴリ・フレックスフィールドを使用して資産を財務情報別にグループ化します。必要な情報が記録されるようにカテゴリ・フレックスフィールドを設計します。次に、カテゴリ別に資産をグループ化し、そのカテゴリの資産に一般的に共通するデフォルト情報を用意します。
警告: フレックスフィールドは慎重に計画してください。フレックスフィールドを使用して資産の入力を開始した後は、フレックスフィールドを変更できません。
| 所有者 | Oracle Assets |
|---|---|
| フレックスフィールド・コード | CAT番号 |
| 表名 | FA_CATEGORIES |
| 列数 | 7 |
| 列幅 | 30 |
| 動的挿入可/不可 | 不可 |
| 一意ID列 | CATEGORY_ID |
| 体系列 | なし |
カテゴリ・フレックスフィールドは、資産のグループ化方法にあわせて定義します。カテゴリ・フレックスフィールドを使用して資産をグループ化します。資産は減価償却ルールに従ってグループ化します。カテゴリ名を標準化することで、資産をより簡単に追跡できるようになります。
カテゴリ・フレックスフィールド体系は、組織固有のニーズを満たすように定義します。主カテゴリ・セグメント値を定義する必要があります。また、補助カテゴリ・セグメントは6個まで定義できます。このキー・フレックスフィールドは、1つの体系のみをサポートします。
警告: 組合せは資産カテゴリ付加フレックスフィールドのコンテキスト・フィールド値として使用されるため、セグメント値のセパレータを付加したセグメント値の組合せは、30文字以下にする必要があります。たとえば、VEHICLE.DELIVERYは有効な組合せであり、セグメント・セパレータを含めて16文字です。
入力された主カテゴリ値に基づいて補助カテゴリ・セグメントの有効な値が決まるように、カテゴリ・フレックスフィールドを設定できます。依存するセグメントがある場合、そのセグメントの値リストには有効な値のみが表示されます。
新しい資産には、資産カテゴリに基づいて資産財務情報のデフォルト値を設定できます。各台帳のカテゴリ・フレックスフィールドの各組合せに対して、デフォルト減価償却ルールを入力できます。資産を台帳に追加すると、資産カテゴリから減価償却ルールがデフォルト設定されます。必要な場合は、異なる事業供用日範囲に対して異なるデフォルト減価償却ルールを指定できます。
各カテゴリについて予算額に対する実際の支出を追跡できます。予算情報は、資産カテゴリに基づいて入力します。各期間の各カテゴリに対して予算金額を入力し、予算計上された資産取得に対して減価償却見積計算を実行します。また、予算に対する実際の支出を比較したり、予算額を入力しなかったカテゴリの資産取得を表示するレポートを実行できます。
付加フレックスフィールドを設定して、資産カテゴリに基づいてその他の情報を格納できます。資産カテゴリ・フレックスフィールドを参照フィールドとして入力し、連結カテゴリ・セグメントをその付加フレックスフィールド体系のコンテキスト・フィールド値として入力します。
資産をグループ化する方法を検討します。按分方法や減価償却方法などの減価償却情報を共有する資産を決定します。カテゴリ体系に必要なレベル(セグメント)数を決定する必要もあります。さらに、最上位レベル(主カテゴリ・セグメント)を決定します。
カテゴリは、勘定体系にあわせて設定してください。各勘定体系には主カテゴリを定義します。主カテゴリ内で区別できるように少なくとも1つの補助カテゴリ・セグメントを定義します。
ヒント: 資産カテゴリ・フレックスフィールドには最大7個のセグメントを定義できます。フォームおよびレポートに表示できる文字数には制限があるため、場合によっては2または3個のセグメントのみを使用して、セグメントがすべて表示されるようにしてください。また、減価償却ルールはカテゴリ・フレックスフィールドの各組合せに対して定義する必要があるため、セグメント数が増加すると、より多くの設定と保守作業が必要になります。
カテゴリ体系の各セグメントには値セットが必要です。これらの値セットには、資産のグループ化に使用した条件を値として入力します。
ヒント: カテゴリ名(すべてのセグメントが連結された名称)はフォームおよびレポートに表示されますが、表示される文字数には制限があります。簡潔なカテゴリ・セグメント値を指定してください。
事前に入力したセグメントの値に依存して有効な値が決まる補助カテゴリ・セグメントを設定するには、依存値セットを作成します。値セットに関する各ウィンドウを使用して、最初のセグメントに対して独立値セットを作成します。次に、依存セグメントに対して依存値セットを作成します。独立値セットの名称を入力し、依存値セットが有効になるために入力する必要がある値を指定します。
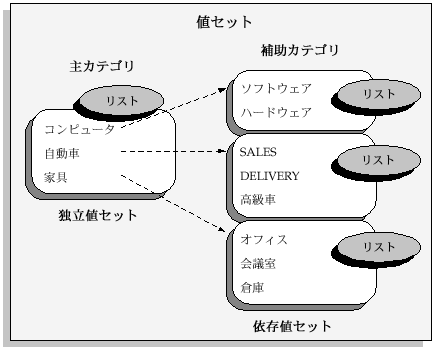
補助カテゴリ・セグメントに有効な値は、主カテゴリ・セグメントの値に依存します。
あるいは、カテゴリ・フレックスフィールドの値セットに対してカスケード依存を設定できます。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の$FLEX$構文の例に関する項
カテゴリ・フレックスフィールドを設定する場合は、主カテゴリ・セグメントを必ず1つ定義する必要があります。主カテゴリとなるセグメントを指定するには、キー・セグメントの定義フォームの主カテゴリ・クオリファイアに「Yes」を入力します。主カテゴリには資産購買予算編成情報を入力できます。
値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを作成します。別のセグメントに依存するセグメントを設定する場合は、ユーザーが最初に入力するセグメントには独立値セットを作成し、入力された値によって決まるセグメントには依存値セットを作成します。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の値セットの各ウィンドウに関する項
新しい資産カテゴリ・セグメントは、キー・セグメントの定義フォームを使用して定義します。主カテゴリ・セグメントには、「主カテゴリ」クオリファイアの「有効」を選択します。キー・フレックスフィールドを再コンパイルした後は、資産を追加する際に再度Oracle Assetsにログインする必要があることに注意してください。
カテゴリ・フレックスフィールドを使用する場合は、各資産カテゴリに依存値を入力し、そのカテゴリを少なくとも1つの台帳に割り当てる必要があるため、Oracle Assetsの動的挿入は使用できません。「キー・フレックスフィールド・セグメント」ウィンドウの「動的挿入の許可」チェック・ボックスの選択が解除されていること、およびフレックスフィールドの登録(「キー・フレックスフィールド」ウィンドウ)が動的挿入の可用性を変更するように編集されていないことを確認します。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のキー・フレックスフィールド・セグメントに関する項
各セグメントの有効な値リストは、「セグメント値」ウィンドウを使用して作成します。フォームおよびレポートに表示できる資産カテゴリ・フレックスフィールドの文字数には制限があるため、簡潔な値を指定してください。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の「セグメント値」ウィンドウに関する項
ヒント: 資産カテゴリを参照するための資産を追加するフォームで付加フレックスフィールドを設定している場合は、すべての値を大文字で入力してください。付加フレックスフィールド体系を適用する連結カテゴリ・フレックスフィールド・セグメント値を入力する場合は、セグメント値をセグメント・セパレータで区切って大文字のみで入力できます。
「資産カテゴリ」フォームを使用して、定義したセグメントを使用して資産カテゴリ名を入力します。資産カテゴリのデフォルト情報も入力します。そのカテゴリと台帳に関して資産を入力するには、事前に「資産カテゴリ」フォームを使用して台帳のカテゴリを定義する必要があります。
関連項目: 資産カテゴリの設定
依存セグメントを伴う2つのセグメント・カテゴリ・フレックスフィールドを使用することに決定しました。典型的なカテゴリの組合せは「COMPUTER.HARDWARE」です。「HARDWARE」は、最初のセグメントの値が「COMPUTER」の場合にのみ、2番目のセグメントに有効な値です。カテゴリ・フレックスフィールドを設定するには、値セットの設定、セグメントの有効化、有効なセグメント値の入力、およびカテゴリの設定を実行する必要があります。
最初に、値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを設定します。たとえば、「主」および「補助コンピュータ」値セットを作成します。「補助コンピュータ」値セットは「主」値セットに依存するように設定するため、「主」には独立値セットを作成し、「補助コンピュータ」には依存値セットを作成します。「補助コンピュータ」の依存先となる独立値セットは「主」で、依存値のデフォルトは「COMPUTER」です。
次に、キー・フレックスフィールド・セグメントに関する各ウィンドウを使用して、セグメントを有効にします。「セグメント」ウィンドウで、検証する各セグメントと値セットを入力します。主カテゴリ・セグメントには、「主カテゴリ」クオリファイアの「有効」を選択します。
「セグメント値」ウィンドウを使用して、各補助カテゴリ・セグメントに対して有効な値を入力します。たとえば、「補助コンピュータ」セグメントに有効な値として「HARDWARE」を入力します。
最後に、「資産カテゴリ」ウィンドウを使用して、資産カテゴリ名および情報を入力します。
カテゴリ・フレックスフィールドには、主カテゴリ・セグメントを必ず1つ定義する必要があります。主カテゴリ・セグメントは、資産購買予算編成に使用されます。
関連項目
Oracle Assetsの資産カテゴリ付加フレックスフィールド
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のフレックスフィールド名別キー・フレックスフィールドに関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の所有アプリケーション別キー・フレックスフィールドに関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の付加フレックスフィールド・セグメントに関する項
Oracle Assetsでは、事業所フレックスフィールドを使用して資産を物理的な所在地別にグループ化します。必要な情報が記録されるように事業所フレックスフィールドを設計します。次に、事業所別に資産をレポートできます。グループとして事業所情報を共有する資産を振り替えることもできます(オフィスを新しい事業所に移動する場合など)。
警告: フレックスフィールドは慎重に計画してください。フレックスフィールドを使用して資産の入力を開始した後は、フレックスフィールドを変更できません。
| 所有者 | Oracle Assets |
|---|---|
| フレックスフィールド・コード | LOC番号 |
| 表名 | FA_LOCATIONS |
| 列数 | 7 |
| 列幅 | 30 |
| 動的挿入可/不可 | 可 |
| 一意ID列 | LOCATION_ID |
| 体系列 | なし |
事業所フレックスフィールドは、資産事業所の追跡方法にあわせて定義します。事業所フレックスフィールドを使用して、資産の物理的な所在地を追跡します。たとえば、国際的に事業を行っている(または将来に向けて計画している)場合は、資産の所在国を追跡する必要があります。追跡対象とする他のセグメントとしては都道府県、郡市区およびサイトがあります。資産事業所をより詳細に追跡する場合は、バーコード用などに、建物および部屋番号のセグメントを追加することもできます。
事業所フレックスフィールド体系は、組織固有のニーズを満たすように定義します。事業所フレックスフィールドのセグメント数、各セグメントの長さ、および各セグメントの名称と順序を選択します。都道府県セグメントを定義する必要があります。また、その他の事業所セグメントは6個まで定義できます。
都道府県レベルで資産税レポートを実行できます。資産税レポートでは、都道府県クオリファイアが「Yes」に設定されている事業所セグメントで資産がソートされます。
関連項目: 資産税レポート
グループとして事業所情報を共有する資産を振り替えることができます。あるいは、従業員間またはGL費用勘定間で資産を移動する際の選択基準として事業所を使用できます。
関連項目: 資産の振替
資産事業所を追跡する方法を検討します。事業所体系に必要なレベル(セグメント)数を決定する必要があります。都道府県セグメントも決定します。
事業所体系の各セグメントには値セットが必要です。これらの値セットには、資産事業所の記述に使用した条件を値として入力します。
ヒント: 事業所名(すべてのセグメントが連結された名称)はフォームおよびレポートに表示されますが、表示される文字数には制限があります。簡潔な事業所セグメント値を指定してください。
事業所フレックスフィールドを設定する場合は、都道府県セグメントを必ず1つ定義する必要があります。都道府県セグメントは、「セグメント」ウィンドウで「都道府県」クオリファイアの「有効」を選択することで指定します。都道府県レベルで資産税レポートを実行できます。
値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを作成します。別のセグメントに依存するセグメントを設定する場合は、ユーザーが最初に入力するセグメントには独立値セットを作成し、入力された値によって決まるセグメントには依存値セットを作成します。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の値セットの各ウィンドウに関する項
あるいは、カテゴリ・フレックスフィールドの値セットに対してカスケード依存を設定できます。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の$FLEX$構文の例に関する項
新しい事業所セグメントは、キー・セグメントの定義フォームを使用して定義します。都道府県セグメントには、「都道府県」クオリファイアの「有効」を選択します。キー・フレックスフィールドを再コンパイルした後は、資産を追加する際に再度Oracle Assetsにログインする必要があることに注意してください。
有効なすべての事業所を定義して、ユーザーが資産を入力する際は追加の事業所を作成できないようにする場合は、「動的挿入の許可」の選択を解除します。有効な事業所を制限する必要がない場合は、「動的挿入の許可」を選択します。有効な事業所フレックスフィールドの組合せは、「事業所」フォームで定義できます。
事業所フレックスフィールドに短縮別名を定義する場合は、「フレックスフィールド短縮入力」の「有効」を選択します。この設定によって、「短縮別名」ウィンドウでは事業所を表す別名を設定できるようになります。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のキー・フレックスフィールド・セグメントに関する項、および短縮別名に関する項
各セグメントの有効な値リストは、「セグメント値」フォームを使用して作成します。フォームおよびレポートに表示できる事業所フレックスフィールドの文字数には制限があるため、簡潔な値を指定してください。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の「セグメント値」ウィンドウに関する項
定義したセグメントを使用する事業所名を入力するには、「事業所」フォームを使用します。「動的挿入の許可」を選択した場合は、このフォームを使用して事業所を定義する必要はありません。
関連項目: 事業所の定義
3つのセグメント事業所フレックスフィールドを使用することに決定しました。典型的な事業所の組合せは「UK.OXFORDSHIRE.BDG3」です。事業所フレックスフィールドを設定するには、値セットの設定、セグメントの有効化、有効なセグメント値の入力、および事業所の設定を実行する必要があります。
最初に、値セットに関する各ウィンドウを使用して各セグメントの値セットを設定します。たとえば、「国」、「地方」および「サイト」値セットを作成します。
次に、キー・フレックスフィールド・セグメントに関する各ウィンドウを使用して、セグメントを有効にします。「セグメント」ウィンドウで、検証する各セグメントと値セットを入力します。「地方」セグメントには、「都道府県」クオリファイアの「有効」を選択します。
「セグメント値」ウィンドウを使用して、各セグメントに対して有効な値を入力します。たとえば、「国」セグメントに有効な値として「UK」を入力します。
最後に、「事業所」ウィンドウを使用して、事業所フレックスフィールドの組合せ「UK.OXFORDSHIRE.BDG3」を入力します。
事業所フレックスフィールドには、都道府県セグメントを必ず1つ定義する必要があります。都道府県セグメントは、資産税レポートに使用されます。
関連項目
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のフレックスフィールド名別キー・フレックスフィールドに関する項
『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の所有アプリケーション別キー・フレックスフィールドに関する項
このフォームを使用して、会社名、資産採番方式およびキー・フレックスフィールド体系を指定します。
前提条件
カテゴリ・フレックスフィールド、事業所フレックスフィールドおよび資産キー・フレックスフィールドを設定します。関連項目: 資産カテゴリ・フレックスフィールドの設定、資産キー・フレックスフィールドの設定および事業所フレックスフィールドの設定
「システム管理」ウィンドウをオープンします。
レポートに表示する企業名を入力します。
最も古い事業供用日を入力します。これによって、資産を事業に供用する有効日とカレンダの開始日が制御されます。
このフィールドを変更した場合、システム内の既存の資産に影響はありませんが、新規の資産は、新しい日付より前に事業に供用することはできません。
注意: 減価償却台帳にカレンダを割り当てると、「最も古い事業供用日」は更新できなくなります。
資産の自動採番を開始する開始番号を入力します。一部の資産番号はスキップされることがあります。
ヒント: 別のシステムから変換している場合は、変換した資産に対して以前のシステムと同じ番号が使用されるように、変換対象の資産数より大きい開始番号を入力してください。たとえば、75,000件の資産を変換する場合は、100,000の開始番号を入力して、1から100,000までの番号を資産の手動採番用に確保してください。75,000件の資産を追加すると、番号は自動的に75,000番増分されます(自動採番される資産は175,001で開始します)。
自動採番は一連の番号であるため、文字を使用する資産番号は自動採番用に確保されないことに注意してください。
自動採番を使用している場合は、「システム管理」ウィンドウの開始資産番号より小さい番号を手動採番に割り当てる必要があります。2,000,000,000を超える資産番号はサポートされません。
使用する事業所フレックスフィールド、カテゴリ・フレックスフィールドおよび資産キー・フレックスフィールドの体系を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
キー・セグメントの定義フォームの「動的挿入の許可」を選択した場合は、有効な事業所を定義する必要はありません。資産をアサイメントに割り当てると、事業所は自動的に作成されます。
前提条件
使用する事業所フレックスフィールド体系を指定します。関連項目: システム管理の指定
「事業所」ウィンドウをオープンします。
有効な事業所フレックスフィールドの組合せを入力します。
組合せを有効にするかどうかを選択します。
作業内容を保存します。
関連項目
キー・セグメントの定義フォームの「動的挿入の許可」を選択した場合は、有効な資産キーを定義する必要はありません。
前提条件
使用する資産キー・フレックスフィールド体系を指定します。関連項目: システム管理の指定
「資産キー」ウィンドウをオープンします。
有効な資産キー・フレックスフィールドの組合せを入力します。
組合せを有効にするかどうかを選択します。
作業内容を保存します。
関連項目
このウィンドウを使用して、提供されているクイックコード値以外の値を入力します。これらの値は、Oracle Assetsの各値リストに表示されます。
「クイックコード」ウィンドウをオープンします。
値を定義するクイックコード名を問い合せます。
クイックコード・タイプの値を入力します。
次の表に、クイックコード・タイプとその値を示します。
| クイックコード・タイプ | クイックコード値 |
|---|---|
| 資産摘要 | 資産の摘要を標準化する値(PERSONAL COMPUTER、DELIVERY VEHICLEなど)を入力します。 |
| 仕訳 | 新規の仕訳値は入力できませんが、摘要を変更できます。 |
| キュー名 | 一括追加の保留キューを説明する値(ACCOUNT HOLD、LOCATION HOLDなど)を入力します。DELETE、ON HOLDおよびPOSTの値は変更できません。 |
| 資産タイプ | 資産を説明する値(PERSONAL、REAL、RESIDENTIALなど)を入力します。 |
| 除・売却 | 除・売却を説明する値(EXTRAORDINARY、SALEなど)を入力します。 |
| 資産カテゴリ | 主要な資産カテゴリを説明する値(AUTO、COMPUTERなど)を入力します。資産カテゴリに表ベースの検証を使用している場合は、「クイックコード」ウィンドウで主カテゴリ値を入力します。 |
| 資産補助カテゴリ | 資産補助カテゴリを説明する値(SALES、DELIVERYなど)を入力します。たとえば、これらの値を使用してAUTO.SALESやAUTO.DELIVERYの資産カテゴリを作成できます。資産カテゴリに表ベースの検証を使用している場合は、「クイックコード」ウィンドウで補助カテゴリ値を入力します。 |
| 未計画減価償却タイプ | UNPLANNED DEPRNに加え、異なる未計画減価償却修正タイプを説明する値を入力できます。 |
| リース複利頻度 | リース複利頻度に使用可能な値は、「月次」、「四半期」、「半期」および「年次」です。既存のリース複利頻度の変更や新規の入力はできませんが、既存の摘要を変更できます。 |
| リース支払タイプ | 「年金」、「最終支払」、「割安購入選択権」および「割安更改オプション」に加え、リース支払タイプを入力できます。 |
ヒント: 階層型の資産カテゴリ・フレックスフィールド・セグメント値を作成する場合は、「値セットの定義」、キー・セグメントの定義およびキー・セグメント値の定義ウィンドウを使用して、資産カテゴリ・フレックスフィールドを定義します。次に、主要なセグメント値に依存する補助セグメント値を設定するために、主要なセグメントの値に依存する補助セグメントの値セットを定義します。
階層型の資産カテゴリ値を作成する場合は、カテゴリ・クイックコード値および補助カテゴリ・クイックコード値を入力する必要はありません。
ヒント: 入力した値は「値リスト」ウィンドウに表示されますが、12文字を超える部分は表示されません。値は12文字までの範囲で指定してください。
クイックコード値の摘要を入力します。
必要に応じて失効日を入力します。失効日を経過すると、この値は値リストに表示されなくなります。
作業内容を保存します。
関連項目
会計年度名の各会計年度の開始日と終了日を指定します。会計年度は、最も古い事業供用日から現会計年度より少なくとも1つ後の会計年度まで作成します。現会計年度が最終会計年度の場合、減価償却は失敗となります。
このウィンドウで複数の会計年度を設定できます。様々な会計年度を異なる会計用台帳に割り当てることができます。税務台帳のカレンダには、関連する税務台帳のカレンダと同じ会計年度名を使用する必要があります。
前提条件
最も古い事業供用日を指定します。関連項目: システム管理の指定
「資産会計年度」ウィンドウをオープンします。
会計年度名と摘要を入力します。名称が異なる複数の会計年度を設定できます。
ヒント: 入力した名称は「値リスト」ウィンドウに表示されますが、30文字を超える部分は表示されません。名称は30文字までの範囲で指定してください。
各会計年度の開始日と終了日を入力します。
定義している会計年度を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
カレンダは必要に応じていくつでも設定できます。設定する各台帳には、減価償却カレンダと按分用カレンダが必要です。減価償却カレンダによって1会計年度内の会計期間数が決まり、按分用カレンダによって会計年度の按分期間数が決まります。1つのカレンダを複数の減価償却台帳に使用することも、台帳に対して1つのカレンダを減価償却カレンダと按分用カレンダの両方として使用することもできます。
会計用台帳は同じカレンダを共有できます。税務台帳には、対応する会計用台帳とは異なるカレンダを指定できます。税務台帳のカレンダは、関連する税務台帳のカレンダと同じ会計年度名を使用する必要があります。
減価償却プログラムは、按分用カレンダを使用して減価償却率の選択に使用される按分期間を判断します。このプログラムでは、減価償却カレンダと償却費期間配分フラグを使用して、各期間に割り当てる年間減価償却費が決定されます。たとえば、四半期の減価償却費カレンダがある場合は、減価償却を実行するたびに年間減価償却の4分の1が計算されます。
最初に、最も古い事業供用日に対応する期間から現期間までのすべてのカレンダ期間を設定する必要があります。現期間より前の期間を少なくとも1つ設定する必要があります。各会計年の年度末には、次の会計年度の期間が自動的に設定されます。
重要: この減価償却カレンダを総勘定元帳の仕訳を作成するソースとなる減価償却台帳で使用する場合は、総勘定元帳に設定した期間と同じ期間名にする必要があります。
カレンダはどのようにでも定義できます。たとえば、4-4-5カレンダを定義するには、異なる開始日と終了日を使用して会計年度、減価償却カレンダおよび按分用カレンダを設定し、不規則な期間を入力します。各期間の日数に従って年間減価償却を相応に分割するには、「資産台帳管理」ウィンドウの「償却費期間配分」フィールドに日数を入力します。
前提条件
「資産カレンダ」ウィンドウをオープンします。
カレンダの名称を入力します。
ヒント: 入力した名称は「値リスト」ウィンドウに表示されますが、15文字を超える部分は表示されません。名称は15文字までの範囲で指定してください。
会計期間名に会計年度またはカレンダ年を付加するには、「会計」または「カレンダ」を選択します。会計年度またはカレンダ年が自動的に付加されないようにするには、「なし」を選択します。
たとえば、会計年度が6月1日から翌年5月31日までの場合、現在日が1995年7月15日とすると、カレンダ年は1995年、会計年度は1996年です。「会計」を指定すると、期間名は「JUL-96」となります。「カレンダ」を指定すると、期間名は「JUL-95」になります。
このカレンダに使用する会計年度名を入力します。
このカレンダの会計年度の期間数を入力します。
注意: 1年に対して365を超える期間数は入力できません。
この期間の名称を入力します。
期間に年が含まれていて、サフィックス・デリミタにハイフン(-)を使用している場合は(JAN-1995など)、2または4桁の年サフィックスを使用する必要があります。年を未入力にしておくと、期間名の最後に4桁の年が自動的に追加されます。このようにしない場合は、2桁の年サフィックスを入力できます。
この減価償却カレンダを総勘定元帳の仕訳を作成するソースとなる減価償却台帳で使用する場合は、総勘定元帳に設定した期間と同じ期間名にする必要があります。
この期間の開始日と終了日を入力します。
作業内容を保存します。
注意: この手順は、GL期間に対応させるために、すでに作成されている期間を変更する必要がある場合に使用します。変更できるのは、先日付の期間名のみです。
「資産カレンダ」ウィンドウをオープンします。
期間名を変更するカレンダを問い合せ、最終期間までスクロールします。
「メイン」メニューから「編集」 > 「レコードの削除」を選択します。期間名を変更する期間をすべて削除します。
削除した期間を正しい名称を指定して再度入力します。
関連項目
『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の(Oracle General Ledgerでの)カレンダの定義に関する項
Oracle Assetsでは、組織および階層の情報をOracle Human Resourcesと共有します。現在、Oracle Human Resourcesを使用していない場合は、Oracle Assetsに用意されているOracle Human Resourcesの各ウィンドウを使用して、このデータを定義します。
Oracle Human Resourcesがすでに実装されている場合は、この項の多くのステップをスキップできます。Oracle Human Resourcesで定義した組織および階層がOracle Assetsで使用するデータに対応していることを確認してください。
組織とは、事業を行う係、課、部、会社またはその他の組織的な単位です。
次の図は、ABC Corporationの組織体系を示しています。組織には3つのレベルがあります。ABC Corporationは最上位レベルの組織で、Americas、EuropeおよびAsia/Pacificの3つの下位組織があります。これらの各下位組織にも複数の下位組織があります。たとえば、Americas組織には、US、CanadaおよびBrazilの下位組織があります。
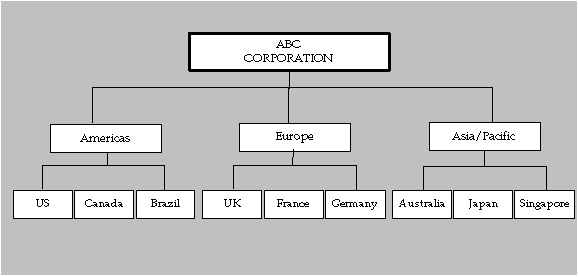
ABC Corporationでは、次の情報を使用してデフォルトのレポート組織階層を定義します。
| 名称 | Oracle Assets |
| バージョン | 1 |
| 組織名 | ABC Corporation |
ビジネス・グループは、組織の最上位レベルであり、レポート可能な最大の従業員グループです。
Oracle Human Resourcesには、「ビジネス・グループの設定」という事前定義組織が付属しています。ビジネス・グループは、新規に作成するのではなく、この事前定義のビジネス・グループの定義を変更することをお薦めします。事前定義の「ビジネス・グループの設定」を変更せずに、新規のビジネス・グループを定義する場合は、新規ビジネス・グループのセキュリティ・プロファイルを示すように「HR: セキュリティ・プロファイル」プロファイル・オプションを設定する必要があります。Oracle Human Resourcesでは、新規ビジネス・グループを定義すると、そのビジネス・グループ名でセキュリティ・プロファイルが自動的に作成されます。指定する他のすべての組織は、定義したビジネス・グループに組み入れられます。関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』
「組織」ウィンドウを使用して、事前定義の「ビジネス・グループの設定」を取得します。次に、「ビジネス・グループの設定」の名称を変更して独自のビジネス・グループを作成します。ここで定義したビジネス・グループは、「HR: セキュリティ・プロファイル」プロファイル・オプションを設定する際、値リストに表示されます。
注意: Oracle Human Resourcesをすでに使用している場合は、Human Resourcesで定義したビジネス・グループと同じグループを引き続き使用することをお薦めします。Human Resourcesの共有インストールを使用している場合は、事前定義の「ビジネス・グループの設定」を使用することをお薦めします。
ビジネス・グループは組織の特別な分類であり、その組織タイプ、事業所、および内部組織か外部組織かを指定する必要があります。Oracle Human Resourcesが正しく機能するためには、ビジネス・グループに対して正しい国別仕様コードを選択することも重要です。従業員をビジネス・グループに入力した後は、国別仕様コードを変更できません。関連項目: 『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』のビジネス・グループ情報の入力に関する項
重要: 従業員、組織および他のエンティティは、ビジネス・グループ別に分割されます。複数のビジネス・グループを設定すると、データは相応に分割されます。また、ビジネス・グループとして分類した組織は元に戻せません。ビジネス・グループは慎重に設定してください。詳細は、『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』を参照してください。
Oracle AssetsまたはOracle Human Resourcesの「組織」ウィンドウを使用して、社内の全組織を指定します。このウィンドウの「その他」ボタンを選択することで、特定の組織の会計用台帳および税務台帳を設定できます。
Oracle Human Resourcesでは、組織分類を使用して、設定する組織のタイプが決定されます。Oracle Assetsで組織を使用することを示すには、「資産組織」分類を使用可能に設定します。
資産組織とは、Oracle Assetsの特定の会計用減価償却台帳に対して資産に関連する活動を実行できる組織です。Oracle Assetsでは、資産組織として指定されている組織のみが使用されます。
その他のタイプの組織分類が必要な場合は、『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』を参照してください。
関連項目
『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の組織の作成に関する項
組織階層は、会社の組織間の報告ラインおよびその他の階層関係を示しています。
「組織階層」ウィンドウを使用して、組織階層を指定します。
階層の最上位の組織と、それに従属する組織を少なくとも1つ定義する必要があります。
関連項目
『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』の組織階層に関する項
セキュリティ・プロファイルを使用すると、管理者が作成してシステムのユーザーに割り当てた職責を介してOracle Assetsへのアクセスを制御できます。ユーザーは、付与された職責を介してのみOracle Assetsにサインオンできます。職責によって、ユーザーがシステムで表示および実行できる内容が制御されます。
職責には、組織階層などの作業体系に関連付けるセキュリティ・プロファイルが常に含まれています。
『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』のセキュリティ・プロファイルに関する項
この処理により、セキュリティ・プロファイルの保持者がアクセスできる、組織、職階、従業員および応募者のリストが保守されます。この処理は、1日のうちに行われた変更を記録するため、毎晩実行するようにスケジュール調整する必要があります。この処理が実行されている間に、停電などの事故が発生した場合、「要求の発行」ウィンドウから、手動で再起動できます。
『Oracle HRMSユーザーズ・ガイド(日本仕様)』のセキュリティ処理に関する項
職責とはOracle Applicationsにおける権限のレベルです。ユーザーは職責を使用して、組織内での各自のロールに適したOracle Applicationsの機能とデータにのみアクセスできます。各職責によって、特定のアプリケーション、元帳、ウィンドウ、機能およびレポートへのアクセスが許可されます。
関連項目
『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の職責の定義に関する項
『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のOracle Applicationsのセキュリティの概要に関する項
Applicationsユーザーの定義時に、各ユーザーに職責を割り当てる必要があります。そのためには、システム管理者職責で「ユーザー」ウィンドウにナビゲートします。
関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の「ユーザー」ウィンドウに関する項
「FA: セキュリティ・プロファイル」プロファイル・オプションは、セキュリティ・プロファイルに定義されている組織のみにアクセスを制限します。「FA: セキュリティ・プロファイル」に使用可能なオプションは、事前に定義したセキュリティ・プロファイル値です。
たとえば、ABC Corporationにセキュリティ・プロファイルを設定します。組織とセキュリティ・プロファイル間には1対1の対応があるため、セキュリティ・プロファイル値の論理的な命名基準には、組織名と組織識別番号が含まれます。この場合、組織ABC CorporationにはABC_Corporation_100というセキュリティ・プロファイル値、組織AmericasにはAmericas_200というプロファイル値を設定できます。
関連項目
プロファイル・オプションおよびプロファイル・オプション・カテゴリの概要
『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のユーザー・プロファイル・オプションの設定に関する項
会計用減価償却台帳、税務減価償却台帳および予算減価償却台帳を定義できます。減価償却台帳を定義してから、資産を台帳に追加する必要があります。異なる元帳に対してまたは同一の元帳に仕訳を作成する複数の会計用減価償却台帳を設定できます。いずれの場合も、各減価償却台帳に対して償却を実行し、仕訳を作成する必要があります。各会計用減価償却台帳には、複数の税務減価償却台帳と予算減価償却台帳を関連付けることができます。
前提条件
システム管理を指定します。関連項目: システム管理の指定
カレンダを定義します。関連項目: カレンダ期間の日付の指定
勘定科目セグメント値および組合せを設定します。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の勘定科目の定義に関する項
仕訳書式を設定します。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の仕訳ソースの定義に関する項、および仕訳カテゴリの定義に関する項
「資産台帳管理」ウィンドウをオープンします。
定義する台帳の名称を入力します。
台帳名には特殊文字を使用できません。また、数字で始まる名称も指定できません。
ヒント: 入力した名称は「値リスト」ウィンドウに表示されますが、15文字を超える部分は表示されません。名称は15文字までの範囲で指定してください。
台帳に関する簡潔な一意の摘要を入力します。
「会計用」、「税金」または「予算」の台帳区分を選択します。
台帳のカレンダ情報を入力します。
台帳の会計基準を入力します。
台帳の勘定科目を入力します。
台帳の税務処理基準を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
「資産台帳管理」ウィンドウで、「カレンダ」タブ・リージョンを選択します。
必要に応じて、減価償却台帳の失効日を入力します。
注意: 失効した台帳は再度有効にはできません。
台帳のパージを許可するかどうかを選択します。
仕訳を作成する元帳を入力します。この台帳に対して仕訳を作成する場合は「GL転記の許可」を選択します。予算資産台帳に対する総勘定元帳転記は許可されません。
対応する会計用台帳の元帳とは異なる税務台帳の元帳を入力できます。異なる元帳は、会計用台帳に割り当てられている元帳の副元帳であること、および次の条件を満たすことが必要です。
Oracle Subledger Accountingが使用可能で、副元帳設定の会計オプションで「主要元帳金額の使用」が「No」に設定されている必要があります。
Oracle Subledger Accountingの副元帳に関してOracle Assetsが使用可能になっている必要があります。
この台帳に使用する減価償却カレンダの名称を入力します。
この台帳に使用する按分用カレンダの名称を入力します。
減価償却率を決定するために必要な、期間サイズまたは分割が最も小さい按分用カレンダを使用します。たとえば、四半期単位の減価償却カレンダを使用する税務台帳では、月次按分用カレンダを使用して、複数の月次の按分と方法の組合せごとに年間減価償却額を詳細に制御できます。
この台帳の現オープン期間の名称を入力します。
注意: 現期間より前に少なくとも1期間について減価償却カレンダを設定する必要があります。関連項目: カレンダ期間の日付の指定
この台帳の会計年度で、期間全体の年間減価償却額を分割する方法を入力します。
各期間で減価償却を均等に分割する場合は「均等」を選択します。
各期間で日数に基づいて相応に分割する場合は「日付別」を選択します。
取得した初年度に除・売却される資産をこの台帳で減価償却するかどうかを選択します。
この台帳について減価償却を最後に実行した日付を入力します。この日付は、減価償却を実行すると更新されます。
台帳の会計基準を入力します。
関連項目
『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の元帳の定義に関する項
「資産台帳管理」ウィンドウで、「会計」タブ・リージョンを選択します。
「仕訳の作成」プログラムの実行時に会社間仕訳が作成されるようにする場合は、「会社間貸借一致エントリの作成」チェック・ボックスを選択します。
この台帳で償却済変更を許可する場合は、「償却済変更の許可」チェック・ボックスを選択します。
この台帳で一括変更を許可する場合は、「一括変更の許可」を選択します。
注意: 未計画減価償却を入力した資産の一括変更は許可されません。関連項目: 未計画減価償却
資産を除・売却する場合に、その資産がキャピタル・ゲインとしてレポートされるために、資産を保持する必要がある最小時間を入力します。資産の除・売却で、すべての資産を対象としてキャピタル・ゲインがレポートされるようにするには、0(ゼロ)のキャピタル・ゲイン保留期間を入力します。
キャピタル・ゲイン保留期間より資産を保持している期間が短い場合、それらの資産は通常所得としてレポートされます。
「再評価の許可」を選択した場合は、再評価基準を指定します。
償却累計の再評価: 償却累計を再評価しない場合、償却累計は再評価の際に再評価償却累計額勘定に移動します。
年償却累計の再評価: 年償却累計を再評価する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
再評価引当金取崩: 再評価償却累計額を取り崩す場合は、このチェック・ボックスを選択します。
再評価引当金償却: この台帳での再評価償却累計額の償却を許可する場合は、このチェック・ボックスを選択します。関連項目: 高インフレ経済における資産管理(再評価)
償却済資産の再評価: 償却済資産を再評価する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
再評価限定: この台帳の資産で償却済として再評価する最大回数を入力します。このフィールドを空白のままにすると、償却済として資産を再評価できる回数は制限されません。
耐用年数延長要因: この台帳の全償却資産の耐用年数延長要因を入力します。資産の当初の耐用年数に耐用年数延長要因を乗算して、延長された新しい耐用年数が決まります。
耐用年数延長限度: 耐用年数延長限度は、全償却資産を再評価する際の減価償却修正を制限します。
この台帳でグループ資産を追加できるようにするには、「グループ減価償却の許可」を選択します。グループ減価償却を許可するように選択した場合は、次のグループ減価償却ルールを指定します。
グループ資産の建設仮勘定減価償却の許可: メンバー建設仮勘定の資産取得価額を減価償却できるようにする場合は、このチェック・ボックスを選択します。
会社間メンバー資産割当の許可: グループ資産とそのメンバー資産に異なる貸借一致セグメント値を指定できるようにする場合は、このチェック・ボックスを選択します。チェック・ボックスの選択が解除されている場合、グループ資産とその各メンバー資産には同じ貸借一致セグメント値が必要です。
「資産台帳管理」ウィンドウで、「勘定科目」タブ・リージョンを選択します。
除・売却勘定科目を入力します。
損益金額の各構成要素に対する個別の仕訳を、独立した勘定科目または純損益の単一の勘定科目に作成するように、損益の勘定科目を設定できます。
繰延償却累計額勘定および繰延減価償却勘定を入力します。
償却累計額修正を実行する際に、償却累計額に対する仕訳の相殺勘定として使用するGL勘定科目を入力します。
この台帳の仕訳に対する勘定科目ジェネレータのデフォルト・セグメント値を入力します。
デフォルトでは、減価償却費勘定以外のすべての勘定科目に対して、コスト・センター・レベルの詳細なしで仕訳が作成されます。デフォルトの割当を使用すると、勘定科目タイプに従って、「資産割当」ウィンドウの費用勘定からの貸借一致セグメントおよび資産カテゴリまたは台帳からの勘定科目セグメントを使用して、仕訳が作成されます。その他のセグメントは、このフィールドで台帳に対して入力したデフォルト・セグメント値から使用されます。
関連項目
「税務処理基準」タブ・リージョンは税務台帳の場合にのみ使用可能になります。「資産台帳管理」ウィンドウの「区分」フィールドで「税金」を選択しなかった場合、このタブ・リージョンは表示されません。
「資産台帳管理」ウィンドウで、「税務処理基準」タブ・リージョンを選択します。
税務台帳の償却累計額を変更できるようにする場合は、「償却累計額修正の許可」を選択します。
減価償却台帳では、取得価額限度または減価償却費限度の使用を許可できます。ただし、減価償却台帳の同じ資産に対して取得価額限度と減価償却費限度を適用することはできません。
建設仮勘定資産を会計用台帳に追加すると、その建設仮勘定資産が税務台帳に自動的に追加されるようにする場合は、「建設仮勘定資産の許可」を選択します。
この税務台帳の「一括コピーの許可」を選択した場合は、コピーする取得、修正、除・売却または残存価額(あるいはその組合せ)を選択します。
この税務台帳へのグループ資産の一括コピーを許可する場合は、「グループ資産取得」フィールドで「コピー」を選択します。デフォルト値は「コピーしない」です。
注意: 一括コピーでは、メンバー資産のグループ割当を変更するときに実行されるグループ資産組替取引はコピーされません。また、グループ修正のタイプ(グループ償却累計額振替、グループ除・売却調整、グループ未計画減価償却など)もコピーされません。
この税務台帳へのメンバー資産のグループ資産割当の一括コピーを許可する場合は、「メンバー資産割当」フィールドで「コピー」を選択します。デフォルト値は「コピーしない」です。
台帳の勘定科目を入力します。
関連項目
使用を開始した償却方法は更新できません。異なる償却率が必要な場合は、別の方法を入力します。
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
減価償却方法の名称および摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「計算済」を選択します。
計算基準単位が「取得価額」に自動的にデフォルト設定されます(「純帳簿価額」は計算済償却方法には使用できません)。
この減価償却方法で、資産が除・売却される年の減価償却を許可するかどうかを選択します。
この方法で減価償却基準から残存価額を除外する場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。
資産の耐用期間(年月)を入力します。
作業内容を保存します。
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
減価償却方法の名称および摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「表」を選択します。
「計算基準単位」ポップリストから「取得価額」または「純帳簿価額」を減価償却計算基準として選択します。
この減価償却方法で、資産が除・売却される年の減価償却を許可するかどうかを選択します。
この方法で減価償却基準から残存価額を除外する場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。
この方法が定額法かどうかを選択します。
資産の耐用期間(年月)を入力します。
この方法で使用する1年当たりの按分期間数を入力します。
年間償却率を入力します。
資産の耐用期間全体で資産を完全に減価償却する償却率を入力する必要があります。「取得価額」の計算基準単位ルールを指定している場合は、各期間の年間償却率すべての合計が1になるようにします。「純帳簿価額」の計算基準単位ルールを指定している場合は、各期間の耐用最終年度の償却率が1で、その他すべての償却率は0(ゼロ)から1の間であることが必要です。
重要: 表ベースの方法の場合、各按分期間に入力する年率は、資産が事業に供用された会計年度の部分を反映する必要があります。償却率は、その年の期間数と按分方法に基づいて按分する必要があります。
作業内容を保存します。
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
減価償却方法の名称および摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「生産高」を選択します。
計算基準単位が「取得価額」に自動的にデフォルト設定されます(「純帳簿価額」は累計生産高比例法には使用できません)。
この方法で減価償却基準から残存価額を除外する場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。
作業内容を保存します。
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
減価償却方法の名称および摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「定率」を選択します。
「計算基準単位」ポップリストから「取得価額」または「純帳簿価額」を減価償却計算基準として選択します。
この減価償却方法で、資産が除・売却される年の減価償却を許可するかどうかを選択します。
「減価償却基準ルール」フィールドで、ポップリストから減価償却基準ルールを選択します。
この方法で減価償却基準から残存価額を除外する場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。残存価額を除外できるのは、計算基準として純帳簿価額を使用する定率方法の場合のみです。
該当する場合は「ポーランドの修正計算基準単位」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスは、ポーランド税減価償却に基づいて減価償却する資産にマイナスの取得価額修正を作成する際の計算に影響します。関連項目: ポーランド税減価償却取引の修正
注意: このチェック・ボックスは、いずれかのポーランド税減価償却基準ルールを減価償却基準ルールとして選択した場合にのみ使用可能になります。
普通償却率を入力します。
修正率または負荷係数を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
Oracle Assetsでは、年間減価償却率を計算する減価償却算式を定義できます。
減価償却算式を定義するには、「減価償却算式」ウィンドウを使用します。算式を定義した後は、「算式のテスト」タブ・リージョンを使用して算式をテストすることをお薦めします。
注意: 減価償却算式を定義するには、SQLに関する多少の知識が必要です。関連項目: 『Oracle8i SQLリファレンス』
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
減価償却方法の名称および摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「算式」を選択します。
「計算基準単位」ポップリストから「取得価額」または「純帳簿価額」を減価償却計算基準として選択します。
減価償却の計算基準として「純帳簿価額」を選択した場合は、次のいずれかの減価償却基準ルールを必要に応じて選択します。
期首残高
期末平均
関連項目: 減価償却基準ルールの定義
この減価償却方法で、資産が除・売却される年の減価償却を許可するかどうかを選択します。
この方法で減価償却基準から残存価額を除外する場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。残存価額を除外できるのは、計算基準として純帳簿価額を使用する定率方法の場合のみです。
この方法が定額法かどうかを選択します。
耐用期間(年月)を入力します。
「減価償却算式」ウィンドウで「算式」ボタンを選択し、減価償却算式を定義します。
「算式の定義」タブ・リージョンで、算式に要素を挿入するボタンをクリックして算式を入力します。
必要に応じて「算式のテスト」タブを選択し、算式をテストします。
算式を保存します。
「減価償却算式」ウィンドウで、「算式のテスト」タブ・リージョンに移動します。
必要に応じてパラメータ(耐用年数、残存価額など)を入力します。
資産が正しく減価償却されることをテスト結果で確認します。
算式を保存します。
「減価償却算式」ウィンドウには、クリックして算式に要素を挿入するボタンを備えた電卓が組み込まれています。
重要: 表示フィールドには算式を直接入力できません。算式を更新する唯一の手段はボタンをクリックすることです。
定数および演算子を表示フィールドに直接入力する標準の電卓キーに加えて、「減価償却算式: 方法内容」ウィンドウには、特別なキーとして「変数」、「機能」および「算式」があります。
Oracle Assetsには変数のポップリストが用意されています。これらの変数のいずれかを選択すると、その変数が減価償却する資産の値に挿入されます。たとえば、1/<Salvage Value>と入力すると、この算式を使用して特定の資産の減価償却を実行したときに、減価償却の計算で資産の残存価額が取得されます。
関連項目: 短期課税年度における減価償却のOracle Assetsによる計算方法
「機能」ポップリストには、SIGN、ROUND、DECODEなど、SQL関数の演算子が表示されます。
「算式」ポップリストには、事前に定義した算式が表示されます。「算式」ポップリストを使用して、既存のユーザー定義算式を表示フィールドに挿入します。
企業によって、一定の償却率で資産を減価償却するほうが都合がよい場合と、特定の時点で異なる償却率で資産の減価償却を開始したほうがよい場合があります。Oracle Assetsでは、指定した時点で減価償却率を変更する減価償却算式を定義できます。そのためには、SQL関数DECODEおよびSIGNの組合せを使用する算式を定義します。
SQLの詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してください。
耐用年数が15年の資産があります。この資産の残り耐用期間が10年を超える間は、0.05の償却率で資産を減価償却する必要があると仮定します。関連項目: 短期課税年度における減価償却のOracle Assetsによる計算方法
資産の残り耐用期間が10年の場合は、資産を0.07で減価償却します。資産の残り耐用年数が10年未満の場合は、資産を0.08の償却率で減価償却します。これを実行するには、次の算式を「減価償却算式」ウィンドウに入力します。
DECODE(SIGN(<Remaining Life2> - 10), 1, 0.05, 0, 0.07, -1, 0.08)
償却率に従って、一方の減価償却方法から別の方法に切り替えることができます。
GREATEST(1 / <Life> * 2, 1 / <Remaining Life1>)
次の表に、使用可能な関数の使用例を示します。
| 関数 | 例 | 結果 |
|---|---|---|
| Decode | Decode(Remaining Life 1, 3, 0.3, 2, 0.2, 0.1) | Remaining Life 1が3の場合は0.3の値が戻ります。Remaining Life 1が2の場合は0.2の値が戻ります。それ以外の場合は0.1の値が戻ります。 |
| Greatest | Greatest(2/Life, 0.5) | Lifeで除算した2と0.5のうち大きい値が戻ります。 |
| Least | Least(2/Life, 0.5) | Lifeで除算した2と0.5のうち小さい値が戻ります。 |
| Power | Power(0.5, 3) | 0.5の3乗(0.125)が戻ります。 |
| Round | Round(2.33333, 4) | 小数点第4位に端数処理して2.3333の値が戻ります。 |
| Sign | Sign(Life - 5) | Life - 5が正数の場合は1の値が戻ります。Life - 5が0(ゼロ)の場合は0(ゼロ)の値が戻ります。それ以外の場合は-1の値が戻ります。 |
| Sqrt | Sqrt(25) | 25の平方根(5)が戻ります。 |
算式ベースの減価償却を使用する場合は、カスタム減価償却方法を作成して特定のニーズに柔軟に対応できます。ただし、資産が正しく減価償却されるようにカスタム減価償却算式を計画し、十分にテストすることが重要です。減価償却算式を周到に検討しないと、予想外の誤った減価償却率になる可能性があります。
注意: カスタム減価償却算式は、Oracle Assetsでは検証されません。
次の例は、十分な検討を怠った減価償却算式を示しています。
100 / <Salvage Value> + 0.01
資産の残存価額が100を超える場合は、期待される償却率(0から100までの間)で資産が減価償却されます。しかし、資産の残存価額が100以下の場合は、時間が経過するに従って資産が実質的に高くなります。
また、資産の残存価額がゼロの場合は、残存価額で除算した金額が自動的にゼロに設定されます(100 / 0 = 0)。この場合、前述の減価償却算式を使用した償却率は、常に0.01になります。
最後に、資産の残存価額がNULLに設定された場合、値は自動的に0(ゼロ)に設定されます。したがって、この場合も前述の減価償却算式を使用した償却率は、常に0.01になります。
関連項目
ボーナス・ルールには、資産の耐用期間の各年に対して異なるボーナス・レートを指定できます。現行および将来の会計年度のレートはいつでも変更できます。
ボーナス・ルールは、税務台帳に加え、会計用台帳でも使用できます。ボーナス・レートによって、定率、定額、表ベースおよび算式ベースの減価償却方法を使用する資産の年間減価償却費を増額できます。マイナスのボーナス・レートを設定してボーナス償却累計額を償却することもできます。
ボーナス年およびレートは、レポートを作成する目的で0(ゼロ)に設定できます。この場合、ボーナス減価償却費は計算されません。
「一時減価償却」チェック・ボックスを使用して、ボーナス・ルールを単一の会計年度に制限できます。
「ボーナス償却ルール」ウィンドウをオープンします。
ボーナス・ルール名および摘要を入力します。
該当する場合は、「一時減価償却」チェック・ボックスを選択します。
ボーナス・レートを適用する資産耐用年数の会計年度範囲を入力します。
各会計年度範囲に対してボーナス・レートを入力します。
ポーランド税減価償却で使用するボーナス・ルールを設定している場合は、減価償却ファクタと代替減価償却ファクタを入力します。減価償却ファクタまたは代替減価償却ファクタのいずれかを入力すると、「率(%)」フィールドの値は自動的に0%に設定されます。
注意: 減価償却ファクタおよび代替減価償却ファクタが適切に設定されていることを確認する必要があります。ファクタが所定の範囲内にあるかどうかの検証はOracle Assetsでは実行されません。
作業内容を保存します。
関連項目
Oracle Assetsには、2002年雇用創出と労働者支援活動に関する法律によって提供される初年度の追加償却控除を利用する際に役立つ特別な減価償却方法が用意されています。
2002年雇用創出と労働者支援活動に関する法律では、米国における通常の課税と代替最小課税の両方を対象として追加の減価償却控除が提供されます。この法律によって、控除対象資産の減価償却基準の30パーセントに相当する初年度減価償却控除額が追加されます。購入年およびそれ以降の年の資産の減価償却基準と減価償却控除額は、初年度の追加償却控除額を反映するように修正されます。遵守については、2002年雇用創出と労働者支援活動に関する法律を参照してください。
次の表は、Oracle Assetsが提供する表ベースの減価償却方法を示しています。これらの償却方法は、2002年雇用創出と労働者支援活動に関する法律による初年度の追加償却控除を利用する際に役立ちます。
| 方法 | 耐用期間 | 方法の説明 | 基礎となる方法 |
|---|---|---|---|
| MACRS 30B HY | 3、5、7、10、15、20年 | MACRS: Half-Year按分方法 - 30%ボーナス | MACRS HY |
| MACRS 30B MQ | 3、5、7、10、15、20年 | MACRS: Mid-Quarter按分方法 - 30%ボーナス | MACRS MQ |
| MACRS STL30B | 27.5、39年 | MACRS: 定額法Mid-Month按分方法 - 30%ボーナス | MACRS STL MM |
| AMT 30B HY | 2.5から20年 | 代替最小課税: Half-Year按分方法 - 30%ボーナス | AMT HY |
| AMT 30B MQ | 2.5から20年 | 代替最小課税: Mid-Quarter按分方法 - 30%ボーナス | AMT MQ |
| STL 30B | 3年 | 定額法 - 30%ボーナス(Mid-Month按分方法に適用) | 該当なし |
重要: 表ベースによるこれらの償却方法は、Oracle Assetsに以前に組み込まれていた方法の修正版です。これらのベースとなる方法は「基礎となる方法」列に記載されています。現在、税減価償却方法にカスタマイズした償却率表を使用している場合は、償却率表を相応に変更する必要があります。
2002年6月1日に、取得価額100万ドルの控除対象資産を取得して事業に供用します。この企業は、30万ドルの初年度追加償却控除額を適用できます。減価償却計算は、次の表に従って計算されます。
| フィールド | 値 |
| 資産取得価額: | 100万ドル |
| 事業供用日: | 2002年6月1日 |
| 按分基準日: | 2002年1月1日 |
| 耐用年数: | 5年 |
| 期間: | 12月31日で終了する年次カレンダ |
| 減価償却方法: | MACRS 30B HY |
| 按分方法: | Half-Year |
次の表に、年次減価償却を示します。
| 期間 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | MACRS 30B HYによる償却率 - 5年間 | MACRS HYによる償却率 - 5年間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 1,000,000 | 440,000 | 440,000 | 44% | 20% |
| 2003年度 | 1,000,000 | 224,000 | 664,000 | 22.4% | 32% |
| 2004年度 | 1,000,000 | 134,400 | 798,000 | 13.44% | 19.2% |
| 2005年度 | 1,000,000 | 80,640 | 879,040 | 8.064% | 11.52% |
| 2006年度 | 1,000,000 | 80,640 | 959,680 | 8.064% | 11.52% |
| 2007年度 | 1,000,000 | 40,320 | 1,000,000 | 4.032% | 5.76% |
減価償却は次のように計算されます。
2002年度 = 44% * 1,000,000 = 440,000
2003年度 = 22.4% * 1,000,000 = 224,000
2004年度 = 13.44% * 1,000,000 = 134,400
2005年度 = 8.064% * 1,000,000 = 80,640
2006年度 = 8.064% * 1,000,000 = 80,640
2007年度 = 4.032% * 1,000,000 = 40,320
MACRS 30B HY - 5年間の償却率は、次に示すようにMACRS HY - 5年間の表の償却率から変更されます。
2002年度 = 30% + 20% * (1 - 30%) = 44%
2003年度 = 32% * (1 - 30%) = 22.4%
2004年度 = 19.2% * (1 - 30%) = 13.44%
2005年度 = 11.52% * (1 - 30%) = 8.064%
2006年度 = 11.52% * (1 - 30%) = 8.064%
2007年度 = 5.76% * (1 - 30%) = 4.032%
既存の資産の減価償却方法を変更して、初年度の追加償却控除額を取得できます。以前の期間の減価償却方法の変更を実行し、減価償却方法の変更を費用処理済修正として実行できます。遡及償却費は、方法を変更した現期間に適用されます。
資産の減価償却方法は資産ワークベンチを介して変更できます。影響を受ける資産の範囲に対して、一括変更を使用して償却方法の変更を実行します。関連項目: 財務情報と減価償却情報の変更
資産に対して修正額償却を以前に実行した場合は、費用処理済修正を実行できません。
注意: 前会計年度の償却累計額を修正する必要がある場合は、減価償却方法を変更する前に、資産の償却累計額修正を実行する必要があります。
2001年9月10日以降に事業に供用した資産には、初年度追加償却控除が遡及的に適用されますが、多くのユーザーは、初年度追加償却控除が利用可能になる前に、前会計年度をクローズした可能性があります。
前年度の納税申告の修正を申請する必要がある場合は、償却累計額修正を使用して、税務台帳の前会計年度の1つ以上の資産について減価償却を修正できます。
関連項目: 税務台帳の償却累計額の修正
Oracle Assetsには、2004年米国雇用創出法によって提供される、控除対象となる事業およびレストラン用建物付属設備に対する初年度の追加償却控除を利用する際に役立つ特別な減価償却方法が用意されています。
2004年米国雇用創出法では、2004年10月22日から2005年12月31日までの間に事業に供用した控除対象となる事業およびレストラン用建物付属設備が、15年にわたって定額法を使用して減価償却されます。これらの付属設備を2004年12月31日以前に事業に供用した場合は、50パーセントのボーナス償却の対象になります。
50パーセントのボーナス償却では、控除対象資産の減価償却基準の50パーセントに相当する初年度減価償却控除額が追加されます。購入年およびそれ以降の年の資産の減価償却基準と減価償却控除額は、初年度の追加償却控除額を反映するように修正されます。
米国における控除対象資産に対する通常の課税と代替最小課税(AMT)の両方に同じ減価償却方法、耐用年数および按分方法を使用して、控除対象資産が償却されます。
次の表は、Oracle Assetsが提供する表ベースの減価償却方法を示しています。これらの償却方法は、2004年米国雇用創出法による初年度の追加償却控除を利用する際に役立ちます。控除対象資産に対する通常の課税と代替最小課税(AMT)の両方に同じ減価償却方法、耐用年数および按分方法が適用されます。
| 方法 | 耐用期間 | 方法の説明 | 基礎となる方法 |
|---|---|---|---|
| STL 50B HY | 15年 | 定額法による50%ボーナス償却付きHalf-Year按分方法 | MACRS STL HY |
| STL 50B MQ | 15年 | 定額法による50%ボーナス償却付きMid-Quarter按分方法 | MACRS STL MQ |
重要: 表ベースによるこれらの償却方法は、Oracle Assetsに以前に組み込まれていた方法の修正版です。これらのベースとなる方法は「基礎となる方法」列に記載されています。現在、税減価償却方法にカスタマイズした償却率表を使用している場合は、償却率表を相応に変更する必要があります。
2004年12月1日に、取得価額100万ドルの控除対象資産を取得して事業に供用します。この企業では、50万ドルの初年度追加減価償却控除を適用できます。減価償却計算は、次の表に従って計算されます。
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 資産取得価額 | 100万ドル |
| 事業供用日 | 2004年12月1日 |
| 按分基準日 | 2004年7月1日 |
| 耐用年数 | 15年 |
| 期間 | 12月31日で終了する年次カレンダ |
| 減価償却方法 | STL 50B HY |
| 按分方法 | Half-Year |
前述の減価償却方法、耐用年数および按分方法は、控除対象資産に対する通常の課税と代替最小課税(AMT)の両方に使用されます。
次の表に、年次減価償却を示します。
| 期間 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | STL 50B HYによる償却率 - 15年間 | MACRS STL HYによる償却率 - 15年間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 1,000,000 | 516,665 | 516,665 | 51.6665% | 3.333% |
| 2005年度 | 1,000,000 | 33,335 | 550000 | 3.3335% | 6.667% |
| 2006年度 | 1,000,000 | 33,335 | 583,335 | 3.3335% | 6.667% |
| 2007年度 | 1,000,000 | 33,330 | 616,665 | 3.333% | 6.666% |
| 2008年度 | 1,000,000 | 33,335 | 650,000 | 3.3335% | 6.667% |
| 2009年度 | 1,000,000 | 33,335 | 683,335 | 3.3335% | 6.667% |
| 2010年度 | 1,000,000 | 33,330 | 716,665 | 3.333% | 6.666% |
| 2011年度 | 1,000,000 | 33,335 | 750,000 | 3.3335% | 6.667% |
| 2012年度 | 1,000,000 | 33,335 | 783,335 | 3.3335% | 6.667% |
| 2013年度 | 1,000,000 | 33,330 | 816,665 | 3.333% | 6.666% |
| 2014年度 | 1,000,000 | 33,335 | 850,000 | 3.3335% | 6.667% |
| 2015年度 | 1,000,000 | 33,335 | 883,335 | 3.3335% | 6.667% |
| 2016年度 | 1,000,000 | 33,330 | 916,665 | 3.333% | 6.666% |
| 2017年度 | 1,000,000 | 33,335 | 950,000 | 3.3335% | 6.667% |
| 2018年度 | 1,000,000 | 33,335 | 983,335 | 3.3335% | 6.667% |
| 2019年度 | 1,000,000 | 16,665 | 1,000,000 | 1.6665% | 3.333% |
減価償却は次のように計算されます。
2004年度 = 51.6665% * 1,000,000 = 516,665
2005年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2006年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2007年度 = 3.333% * 1,000,000 = 33,330
2008年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2009年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2010年度 = 3.333% * 1,000,000 = 33,330
2011年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2012年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2013年度 = 3.333% * 1,000,000 = 33,330
2014年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2015年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2016年度 = 3.333% * 1,000,000 = 33,330
2017年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2018年度 = 3.3335% * 1,000,000 = 33,335
2019年度 = 1.6665% * 1,000,000 = 16,665
STL 50B HY - 15年間の償却率は、次に示すようにMACRS STL HY - 15年間の表の償却率から変更されます。
2004年度 = 50% + 3.333% * (1 - 50%) = 51.6665%
2005年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2006年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2007年度 = 6.666% * (1 - 50%) = 3.333%
2008年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2009年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2010年度 = 6.666% * (1 - 50%) = 3.333%
2011年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2012年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2013年度 = 6.666% * (1 - 50%) = 3.333%
2014年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2015年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2016年度 = 6.666% * (1 - 50%) = 3.333%
2017年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2018年度 = 6.667% * (1 - 50%) = 3.3335%
2019年度 = 3.333% * (1 - 50%) = 1.6665%
既存の資産の減価償却方法を変更して、初年度の追加償却控除額を取得できます。以前の期間の減価償却方法の変更を実行し、減価償却方法の変更を費用処理済修正として実行できます。遡及償却費は、方法を変更した現期間に適用されます。
資産の減価償却方法は資産ワークベンチを介して変更できます。影響を受ける資産の範囲に対して、一括変更を使用して償却方法の変更を実行します。関連項目: 財務情報と減価償却情報の変更
資産に対して修正額償却を以前に実行した場合は、費用処理済修正を実行できません。
注意: 前会計年度の償却累計額を修正する必要がある場合は、減価償却方法を変更する前に、資産の償却累計額修正を実行する必要があります。
Oracle Assetsには、「取得価額」または「純帳簿価額」計算基準単位タイプでは要件を満たさない減価償却方法の設定に対応するための減価償却基準ルール機能があります。減価償却基準ルールと減価償却方法の組合せで、減価償却基準の導出方法が決まります。
必要な減価償却基準ルールは、減価償却方法を設定する際に選択します。取引を作成すると、「減価償却基準ルール」フィールドに指定した減価償却基準ルールに基づいて資産の減価償却基準が計算されます。
注意: 減価償却基準ルールと組み合せて使用できるのは、定率ベースの方法のみです。ただし、期首残高と期末平均は、算式ベースの方法にも使用できるという例外があります。
償却対象額の使用
取引期間基準の使用
会計年度期首基準の使用
定率法延長
期末残高
期首残高
期末平均
年累計平均残高
Half-Yearルールを使用した年累計平均
年度末残高
控除額が正の年度末残高
Half-Yearルールを使用した年度末残高
次の減価償却基準ルールは、ポーランド税減価償却に対してのみ適用可能です。関連項目: ポーランド税減価償却基準ルール
注意: いずれかのポーランド税減価償却基準ルールを使用する場合は、「方法タイプ」を「定率」に、「計算基準単位」を「取得価額」に設定する必要があります。
古典的および定率法への減価切替を伴うポーランド30%
定率法への切替を伴うポーランド30%
古典的および定率法の減価切替を伴うポーランド変更減価
定率法への切替を伴うポーランド変更減価
定率法への切替を伴うポーランド標準減価
減価償却基準ルールでは、次の各計算が提供されます。
「償却対象額の使用」ルールを使用すると、減価償却基準は新規の償却対象額、つまり取得価額から残存価額を差し引いた額になります。この減価償却基準ルールは、取得価額基準の定率法に対してのみ使用できます。
「償却対象額の使用」ルールによる現期間の減価償却費 = (取得価額 - 残存価額) * 年間償却率 / 年度内期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 減価償却方法: | 取得価額基準の減価償却基準ルール「償却対象額の使用」を使用する定率法 |
| 償却率: | 30% |
| 残存価額: | 20% |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
| 償却カレンダ: | 月次 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産Aの取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| 資産Aの減価償却基準 | 24,000 | 24,000 | 32,000 | 32,000 |
| 資産Aの減価償却費 | 600 | 600 | 800* | 800 |
| 資産Aの償却累計額 | 600 | 1,200 | 2,000 | 2,800 |
* 2000年3月の減価償却費 = 32,000 * 30% / 12 = 800
この減価償却基準は、純帳簿価額基準の定率法に対してのみ使用できます。純帳簿価額基準は、取得価額から残存価額を引き、さらに償却累計額を差し引いた額になります。基準は各会計年度末に再設定されます。修正額償却を実行すると、純帳簿価額基準は償却日時点で再設定されます。
取引期間基準の使用 = (取得価額 - 残存価額) - 償却累計額
この減価償却基準ルールは、純帳簿価額基準の定率法に対してのみ使用できます。純帳簿価額基準は、取得価額から残存価額を引き、さらに会計年度期首時点の償却累計額を差し引いた額になります。この基準は各会計年度末に再設定されます。
会計年度期首基準の使用 = (取得価額 - 残存価額) - 会計年度期首時点の償却累計額
修正を実行すると、純帳簿価額基準は次のように再設定されます。
会計年度期首基準の使用 = 現在の取得価額 - 現在の残存価額 - 再計算された会計年度期首時点の償却累計額
このルールは、純帳簿価額基準の定率法から、日本において法的に義務付けられている取得価額基準の定率法への減価償却方法の変更をサポートしています。
純帳簿価額基準の定率法から取得価額基準の定率法に減価償却方法を変更すると、修正額が償却されます。減価償却基準は、償却開始日に取得価額から純帳簿価額に変わります。
このルールを純帳簿価額基準の定率減価償却方法に適用すると、減価償却基準ルールが「会計年度期首基準の使用」に設定されている場合と同じ動作になります。このルールは、取得価額または純帳簿価額基準の定率減価償却方法にのみ適用できます。
グループ資産では、「グループ金額の配賦」オプションによってメンバー資産追跡が有効になっている場合は、償却済メンバー資産の減価償却基準がグループ・レベルの減価償却基準から削除されます。メンバー資産追跡が「メンバー資産金額の計算」オプションによって有効になっており、取得価額を使用する減価償却方法が選択されている場合は、償却済メンバー資産の減価償却基準がグループ・レベルの減価償却基準から削除されます。
次に、定率法延長の例を示します。
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 方法タイプ | 定率法 |
| 計算基準単位 | 純帳簿価額 |
| 償却率 | 20% |
| 残存価額を除く | オン |
| 減価償却基準ルール | 会計年度期首基準の使用 |
| 期間 | 1998年第1四半期 |
| 計算基準単位/率 | 純帳簿価額、20% |
| 取得価額 | 1,000,000 |
| 活動 | 新規資産の追加 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 方法タイプ | 定率法 |
| 計算基準単位 | 取得価額 |
| 償却率 | 25% |
| 残存価額 | 10% |
| 残存価額を除く | オフ |
| 減価償却基準ルール | 定率法延長 |
| 期間 | 2000年第1四半期 |
| 計算基準単位/率 | 取得価額、25% |
| 取得価額 | 1,000,000 |
| 活動 | 修正額償却: 方法変更に伴う償却開始日: 2000年1月1日(2000年第1四半期) |
次の表に、修正後に計算された減価償却を示します。
| 期間 | 取得価額 | 減価償却基準 | 減価償却費 | 償却累計額 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年第4四半期 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50,000 | 200,000 |
| 1999年第1四半期 | 1,000,000 | 800,000 | 40,000 | 240,000 |
| 1999年第2四半期 | 1,000,000 | 800,000 | 40,000 | 280,000 |
| 1999年第3四半期 | 1,000,000 | 800,000 | 40,000 | 320,000 |
| 1999年第4四半期 | 1,000,000 | 800,000 | 40,000 | 360,000 |
| 2000年第1四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 393,750 |
| 2000年第2四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 427,500 |
| 2000年第3四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 461,250 |
| 2000年第4四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 495,000 |
| 2001年第1四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 528,750 |
| 2001年第2四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 562,500 |
| 2001年第3四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 596,250 |
| 2001年第4四半期 | 1,000,000 | 540,000 | 33,750 | 630,000 |
2000年第1四半期の計算は、次のようになります。
減価償却基準 = (1,000,000 - 残存価額) - 償却累計額 + 年償却累計額
= (1,000,000 - 1,000,000*10%) - 360,000 - 0 = 540,000
減価償却費 = 減価償却基準 * 償却率 * (1/ 期間)
= 540,000 * 0.25 * (1/4) = 33,750
「期末残高」ルールを使用すると、現期間の減価償却は次のように計算されます。
「期末残高」ルールによる現期間の減価償却費 = (グループ資産期末残高 * 年間償却率) / 年度内期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1、資産2 |
| 減価償却方法: | 取得価額基準の定率減価償却基準ルール: 期末残高 |
| 償却率: | 30% |
| 償却カレンダ: | 月次 |
| グループ資産事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループA取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA減価償却基準 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA減価償却費 | 750 | 750 | 1,000* | 1,000 |
| グループA償却累計額 | 750 | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
* 2000年3月のグループ減価償却費 = (グループ資産減価償却基準 * 年間償却率) / 年度内期間数 = (40,000 * 30%) / 12 = 1,000
「期首残高」ルールを使用すると、現期間の減価償却は次のように計算されます。
「期首残高」ルールによる現期間の減価償却費 = (グループ資産期首残高 * 年間償却率)/ 年度内期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1、資産2 |
| 減価償却方法: | 取得価額基準の定率減価償却基準ルール: 期首残高 |
| 償却率: | 30% |
| 償却カレンダ: | 月次 |
| グループ資産事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループA取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA減価償却基準 | 0 | 30,000 | 30,000 | 40,000 |
| グループA減価償却費 | 0 | 750 | 750 | 1,000* |
| グループA償却累計額 | 0 | 750 | 1,500 | 2,500 |
* 2000年4月のグループ減価償却費 = (グループ資産減価償却基準) * 年間償却率 / 年度内期間数 = 40,000 * 30% / 12 = 1,000
「期末平均」ルールを使用すると、現期間の減価償却は次のように計算されます。
「期末平均」ルールによる現期間の減価償却費 = (現期末残高 + 前期末残高) /2 * 償却率 / 年度内期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1、資産2 |
| 減価償却方法: | 取得価額基準の定率減価償却基準ルール: 期末平均 |
| 償却率: | 30% |
| 償却カレンダ: | 月次 |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループA取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA減価償却基準 | 15,000 | 30,000 | 35,000* | 40,000 |
| グループA減価償却費 | 375 | 750 | 875** | 1,000 |
| グループA償却累計額 | 375 | 1,125 | 2,000 | 3,000 |
* 2000年3月のグループ資産減価償却基準 = (現期末残高 + 前期末残高) / 2 = (40,000 + 30,000) / 2 = 35,000
** 2000年3月のグループ資産減価償却費 = グループ資産減価償却基準 * 年間償却率 / 年度内期間数 = 35,000 * 30% / 12 = 875
「年累計平均残高」ルールを使用すると、現期間の減価償却は次のように計算されます。
「年累計平均残高」ルールによる現期間の減価償却費 = (現期末残高 + 前年度末残高) / 2 * 償却率 / 年度内期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1 - 2000年3月に修正された取得価額、資産2 - 2000年2月に修正された取得価額 |
| 減価償却方法: | 取得価額基準の定率減価償却基準ルール: 年累計平均残高 |
| 償却率: | 30% |
| 償却カレンダ: | 月次 |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 20,000 |
| 実行期間: | 2000年2月 |
| 償却開始日: | 2000年2月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA取得価額 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| グループA減価償却基準 | 15,000 | 25,000* | 30,000** | 30,000 |
| グループA減価償却費 | 375 | 625 | 750*** | 750 |
| グループA償却累計額 | 375 | 1,000 | 1,750 | 2,500 |
* 2000年2月のグループ資産減価償却基準 = (現期末残高 + 前年度末残高) / 2 = (50,000 + 0) / 2 = 25,000
** 2000年3月のグループ資産減価償却基準 = (現期末残高 + 前年度末残高) / 2) = (60,000 + 0) / 2 = 30,000
*** 2000年3月のグループ資産減価償却費 = (グループ資産減価償却基準 * 年間償却率) / 年度内期間数 = (30,000 * 30%) / 12 = 750
この減価償却基準ルールは、取得価額基準の定率法に対してのみ使用できます。「Half-Yearルールを使用した年累計平均」ルールを使用すると、現期間の減価償却は次のように計算されます。
「Half-Yearルールを使用した年累計平均」ルールによる現期間の減価償却費 = (((当期末残高 + 前年度末残高) / 2 * 償却率) - 年償却累計額) / 会計期間内の残り期間数
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1 資産2 |
| 減価償却方法: | 取得価額基準の定率減価償却基準ルール: Half-Yearルールを使用した年累計平均 |
| 償却率: | 30% |
| 償却カレンダ: | 月次 |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2000年3月 |
| 償却開始日: | 2000年3月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 20,000 |
| 実行期間: | 2000年2月 |
| 償却開始日: | 2000年2月1日 |
次の表に、資産および2000年の最初の4期間について計算した金額を示します。
| 2000年1月 | 2000年2月 | 2000年3月 | 2000年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループA取得価額 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| グループA減価償却費 | 375* | 647.73** | 797.73*** | 797.73 |
| グループA償却累計額 | 375 | 1,022.73 | 1,820.46 | 2,618.19 |
| グループA年償却累計額 | 375 | 1,022.73 | 1,820.46 | 2,618.19 |
* 2000年1月のグループA減価償却費 = (((当期末残高 + 前年度末残高) / 2) x 年間償却率 - 年償却累計額) / 年度内の残り期間数 = (((30,000 + 0) / 2) x 30% - 0) / 12 = 375
** 2000年2月のグループA減価償却費 = (((当期末残高 + 前年度末残高) / 2) x 年間償却率 - 年償却累計額) / 年度内の残り期間数 = (((50,000 + 0) / 29 x 30% - 3759 / 11 = 647.73
*** 2000年3月のグループA減価償却費 = (((当期末残高 + 前年度末残高) / 2) x 年間償却率 - 年償却累計額) / 年度内の残り期間数 = (((60,000 + 0) / 2) x 30% - 1,022.73) / 10 = 797.73
現会計年度末の残高です。この減価償却基準ルールは、純帳簿価額基準の定率法に対してのみ使用できます。
「年度末残高」ルールによる現期間の減価償却費 = 現期間の年償却累計額 - 前期間の年償却累計額
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1: 2002年度に修正された取得価額 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 減価償却方法: | 純帳簿価額基準の定率減価償却基準ルール: 年度末残高 |
| 償却率: | 30% |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
| 減価償却カレンダ: | 年次 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2002年度 |
| 償却開始日: | 2002年1月1日 |
次の表に、資産および4年間について計算した金額を示します。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループ資産A取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループ資産A減価償却基準 | 30,000 | 21,000 | 24,700* | 17,290 |
| グループA減価償却費 | 9,000 | 6,300 | 7,410** | 5,187 |
| グループA償却累計額 | 9,000 | 15,300 | 22,710 | 27,897 |
* 2002年度のグループ資産A減価償却基準 = 取得価額 - 残存価額 - 償却累計額 = 40,000 - 15,300 - 24,700
(取得 + / - 修正) - (売却価額 - 撤去費用) > 0
** 2002年度のグループ資産減価償却費 = 減価償却基準 * 年間償却率 = 24,700 * 30% = 7,410
このルールは、取得価額または純帳簿価額基準の定率法に適用できます。「控除率」フィールドは、グループ資産およびメンバー資産の場合のみ使用可能で、スタンドアロン資産には使用できません。
カナダでは、グループ資産の指定の期間で、次の計算が0(ゼロ)より大きい場合は、グループ減価償却額を計算する際に、超過金額の半額を減価償却基準から控除する必要があります。計算は次のとおりです。
(取得 + / - 修正) - 売却価額 - 撤去費用 > 0
ただし、一部のグループは50%ルールを免除されます。カナダの50%ルールに対応させるには、グループ資産の減価償却方法に対して「控除額が正の年度末残高」減価償却基準ルールを選択し、グループ資産に50%の控除率を入力する必要があります。
この減価償却基準ルールをグループ資産の減価償却方法に設定した場合は、グループ資産の控除率を入力できます。
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1: 2002年度に修正された取得価額、資産2 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 減価償却方法: | 純帳簿価額基準の定率減価償却基準ルール: 控除額が正の年度末残高 |
| 償却率: | 30% |
| 控除率: | 50% |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
| 減価償却カレンダ: | 年次 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 取得価額修正: | 10,000 |
| 実行期間: | 2002年度 |
| 償却開始日: | 2002年1月1日 |
次の表に、資産および4年間について計算した金額を示します。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループ資産A取得価額 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| グループ資産A減価償却基準 | 15,000* | 25,500** | 22,850*** | 20,995 |
| グループA減価償却費 | 4,500 | 7,650 | 6,855**** | 6,298.50 |
| グループA償却累計額 | 4,500 | 12,150 | 19,005 | 25,303.50 |
* 2000年度のグループA減価償却基準 = 取得価額 - 残存価額 - 償却累計額 - 控除額 = 30,000 - (30,000 * 50%) = 15,000
** 2001年度のグループA減価償却基準 = 30,000 - 4,500 = 25,500
*** 2002年度のグループA減価償却基準 = 40,000 - 12,150 - 10,000 * 50% = 22,850
**** 2002年度のグループA減価償却費 = 減価償却基準 * 年間償却率 = 22,850 * 30% = 6,855
「Half-Yearルールを使用した年度末残高」ルールは、純帳簿価額基準の定率法に適用できます。「控除率」フィールドは、グループ資産およびメンバー資産の場合のみ使用可能で、スタンドアロン資産には使用できません。
インドでは、会計年度の後半にメンバー資産を取得した場合は、そのメンバー資産の減価償却率が50%削減されます。会計年度の前半にメンバー資産を事業に供用した場合は、減価償却率の100%を使用できます。
インドの50%ルールに対応させるには、グループ資産の減価償却方法に対して「Half-Yearルールを使用した年度末残高」減価償却基準ルールを選択し、グループ資産に50%の控除率を入力する必要があります。また、「会計年度」設定ウィンドウで「半期 開始日」を入力する必要があります。
事業供用日が年度の前半にある場合は、グループ減価償却率の100%を使用します。
事業供用日が年度の後半にある場合は、グループ減価償却率の50%を使用します。
この減価償却基準ルールをグループ資産の減価償却方法に設定した場合は、グループ資産の控除率を入力できます。
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| グループ資産: | グループA |
| メンバー資産: | 資産1のDPIS(事業供用日): 2000年1月1日、資産2のDPIS(事業供用日): 2000年8月1日 |
次の表に、この例で使用する資産設定情報を示します。
| 資産設定項目 | 資産設定情報 |
|---|---|
| 減価償却方法: | 純帳簿価額基準の定率減価償却基準ルール: Half-Yearルールを使用した年度末残高 |
| 償却率: | 30% |
| 控除率: | 50% |
| グループ事業供用日/按分基準日: | 2000年1月1日 |
| 減価償却カレンダ: | 年次 |
| 半期 開始日: | 2000年7月1日 |
次の表に、資産および4年間について計算した金額を示します。
| 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資産2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| グループ資産A取得価額 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| グループ資産A減価償却基準 | 20,000* | 24,000*** | 16,800 | 11,760 |
| グループA減価償却費 | 6,000** | 7,200 | 5,040 | 3,528 |
| グループA償却累計額 | 6,000 | 13,200 | 18,240 | 21,768 |
* 2000年度のグループA減価償却基準 = 取得価額 - 残存価額 - 償却累計額 - 控除額 = 30,000 - (20,000 * 50%) = 20,000
** 2000年度のグループA減価償却費 = 減価償却基準 * 年間償却率 = 20,000 * 30% = 6,000
*** 2001年度のグループA減価償却基準 = 30,000 - 6,000 = 24,000
「減価償却方法」ウィンドウにナビゲートします。
「方法」フィールドに減価償却方法の名称を入力します。
「摘要」フィールドに減価償却方法の摘要を入力します。
「方法タイプ」ポップリストから「定率」を選択します。
「計算基準単位ルール」ポップリストから、減価償却を計算する基準として取得価額を使用するか純帳簿価額を使用するかを選択します。
減価償却基準ルールを選択します。
注意: 「方法タイプ」フィールドで「定率」を選択すると、「減価償却基準ルール」フィールドは必須になります。デフォルト設定されている値は更新可能です。
除・売却年に償却が計算されるようにする場合は、「除・売却年の償却」チェック・ボックスを選択します。
この方法による取得価額から残存価額を差し引く計算で、残存価額を計算に含めない場合は、「残存価額を除く」チェック・ボックスを選択します。
「償却率」ウィンドウで「率」ボタンを選択し、償却率を入力します。
普通償却率を入力します。
修正率または負荷係数を入力します。
作業内容を保存します。
Oracle Assetには、ポーランド税減価償却要件をサポートする5種類の減価償却基準ルールがシードされています。この5種類の各減価償却基準ルールは、様々なポーランド税減価償却方法で構成されます。これらのポーランド税減価償却方法は、事前に定義された順序または条件に従った順序で有効になります。たとえば、3種類のポーランド税減価償却方法で構成されている減価償却基準ルールでは、第1のポーランド税減価償却方法は第1会計年度に対して有効で、第2のポーランド税減価償却方法は第2会計年度から第4会計年度まで有効で、第3のポーランド税減価償却方法は資産がすべて償却されるまでの残りの会計年度に対して有効になります。
ポーランド税減価償却方法は、個別に設定または使用して資産を減価償却できないこと以外は他の減価償却方法と同じです。つまり、ポーランド税減価償却方法の1つを使用して減価償却するように資産を割り当てることはできません。
注意: ポーランド税減価償却方法を使用する場合は、減価償却見積計算を使用して将来の減価償却を判断することはできません。かわりに、What-If減価償却を使用できます。
ポーランド税減価償却方法は、次のとおりです。
30%定率: 追加期間には30パーセントの償却率で資産が減価償却され、会計年度の残りの期間は減価償却が中断されます。
古典的減価: 定義された定率に減価償却ファクタを乗算した償却率で資産が減価償却されます。このポーランド税減価償却方法が減価償却基準ルールで使用される場合、この方法は常に第2会計年度に開始されます。
変更減価: 定義された定率に代替減価償却ファクタを乗算した償却率で資産が減価償却されます。
標準減価: 定義された定率に減価償却ファクタを乗算した償却率で資産が減価償却されます。
定率法: 定義された定率で資産が減価償却されます。
ポーランド税減価償却基準ルールは、これらのポーランド税減価償却方法の2つ以上でそれぞれ構成されます。ポーランド税減価償却の減価償却基準ルールは、次のとおりです。
古典的および定率法への減価切替を伴うポーランド30%
定率法への切替を伴うポーランド30%
古典的および定率法の減価切替を伴うポーランド変更減価
定率法への切替を伴うポーランド変更減価
定率法への切替を伴うポーランド標準減価
「減価償却方法」ウィンドウで新しい減価償却方法を定義します。関連項目: その他の減価償却方法の定義
「減価償却基準ルール」値リストからポーランド税減価償却基準ルールのいずれか(「定率法への切替を伴うポーランド30%」など)を選択します。関連項目: ポーランド税減価償却基準ルール
「償却率」ウィンドウにナビゲートし、定率を入力します。
作業内容を保存します。
「ボーナス償却ルール」ウィンドウにナビゲートし、ボーナス・ルールを定義します。関連項目: ボーナス償却ルールの定義
減価償却ファクタおよび代替減価償却ファクタを入力します。関連項目: ボーナス償却ルールの定義
「資産台帳」ウィンドウにナビゲートし、方法およびボーナス・ルールを資産に割り当てます。関連項目: 財務情報の入力(詳細追加の続き)
資産カテゴリに方法を割り当てることもできます。関連項目: カテゴリのデフォルト減価償却ルールの入力
Oracle Assetsには、5種類のポーランド税減価償却基準ルールがシードされています。
この減価償却基準ルールでは、第1会計年度には30%定率のポーランド税減価償却方法が使用されます。追加期間には30パーセントの固定償却率で資産が減価償却されます。その後、会計年度の残りの期間は減価償却が中断されます。30パーセントの減価償却を計上した後に、第1会計年度の後続する期間に修正が付加された場合も、減価償却は遡及されません。
第2会計年度は、古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用して減価償却率が計算されます。古典的減価のポーランド税減価償却方法で使用される算式は、「ボーナス償却ルール」ウィンドウで定義した減価償却ファクタで定率を乗算して計算されます。
古典的減価のポーランド税減価償却方法で使用される減価償却率の計算に使用される算式は、次のとおりです。
定率 * 減価償却ファクタ
たとえば、定率が20パーセントで減価償却ファクタが2の場合、このポーランド税減価償却方法に使用される償却率は、次のようになります。
20% * 2 = 40%
第2会計年度の減価償却は、常に取得価額に基づいて計算されます。後続する(古典的減価のポーランド税減価償却方法が使用される)会計年度の減価償却は、次の基準に従って計算されます。
取得価額 - 償却累計額 + 初年度償却額
第2会計年度の終了後、すべての会計年度の開始時にはテストが実行され、古典的減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率に基づいて計算された減価償却見積額以下であるかどうかが検証されます。
古典的減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率(「定率法」の減価償却基準は常に取得価額基準)に基づいて計算された減価償却見積額以下の場合は、その会計年度以降の減価償却方法を「定率法」に切り替える必要があります。それ以外の場合は、引き続き古典的減価のポーランド税減価償却方法で償却を実行します。
| 月 | 第1年: 30%(3000.00) | 第2年: 20% * 2(4000.00) | 第3年: 20% * 2(2400.00) | 第4年: 20%(600.00) |
|---|---|---|---|---|
| 第1月 | 3000.00 | 333.33 | 200.00 | 166.67 |
| 第2月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | 166.67 |
| 第3月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | 166.67 |
| 第4月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | 99.99 |
| 第5月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第6月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第7月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第8月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第9月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第10月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第11月 | 0.00 | 333.33 | 200.00 | -- |
| 第12月 | 0.00 | 333.37 | 200.00 | -- |
この例について考えてみます。
資産取得価額は10,000ドルです。
第1年は、10,000の減価償却基準による30%定率のポーランド税減価償却方法を使用します。
第2年は、10,000の減価償却基準による古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第3年は6000の減価償却基準による古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
注意: ここでは、基準が取得価額から償却累計額を差し引いて初年度償却額を加えた額に変更されています。
第4年は、10,000の減価償却基準による定率法を使用します。
各年度末の償却累計額は、次のとおりです。
第1年: 3000.00
第2年: 7000.00
第3年: 9400.00
第4年: 10,000.00
この減価償却基準ルールでは、第1会計年度には30%定率のポーランド税減価償却方法が使用されます。追加期間には30パーセントの固定償却率で資産が減価償却されます。その後、会計年度の残りの期間は減価償却が中断されます。
第2会計年度は、この減価償却基準ルールが30%定率のポーランド税減価償却方法から「定率法」に自動的に切り替わります。
| 月 | 第1年: 30%(3000.00) | 第2年: 20%(2000.00) | 第3年: 20%(2000.00) | 第4年: 20%(2000.00) | 第5年: 20%(1000.00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1月 | 3000.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第2月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第3月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第4月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第5月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第6月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.65 |
| 第7月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第8月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第9月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第10月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第11月 | 0.00 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第12月 | 0.00 | 166.63 | 166.63 | 166.63 | -- |
この例について考えてみます。
資産取得価額は10,000ドルです。
第1年は、10,000の減価償却基準による30%定率のポーランド税減価償却方法を使用します。
第2年から第5年は、10,000の減価償却基準による定率法を使用します。
各年度末の償却累計額は、次のとおりです。
第1年: 3000.00
第2年: 5000.00
第3年: 7000.00
第4年: 9000.00
第5年: 10,000.00
この減価償却基準ルールを使用すると、第1会計年度は変更減価のポーランド税減価償却方法に基づいて減価償却されます。変更減価のポーランド税減価償却方法で使用される償却率は、代替減価償却ファクタで定率を乗算して取得されます。
変更減価のポーランド税減価償却方法で使用される減価償却率の計算に使用される算式は、次のとおりです。
定率 * 代替減価償却ファクタ
たとえば、定率が20パーセントで代替減価償却ファクタが3の場合、償却率は次のようになります。
20% * 3 = 60%
第2会計年度の開始時に、ポーランド税減価償却方法は、変更減価のポーランド税減価償却方法から古典的減価のポーランド税減価償却方法に自動的に切り替わります。償却率は、古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用して計算されます。
古典的減価のポーランド税減価償却方法で使用される減価償却率の計算に使用される算式は、次のとおりです。
定率 * 減価償却ファクタ
たとえば、定率が20パーセントで減価償却ファクタが2の場合、このポーランド税減価償却方法に使用される償却率は、次のようになります。
20% * 2 = 40%
第2会計年度の減価償却は、常に取得価額に基づいて計算されます。後続する(古典的減価のポーランド税減価償却方法が使用される)会計年度の減価償却は、次の基準に従って計算されます。
取得価額 - 償却累計額 + 初年度償却額
第2会計年度の後、すべての会計年度の開始時にはテストが実行され、古典的減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率に基づいて計算された減価償却見積額以下であるかどうかが検証されます。
古典的減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率に基づいて計算された減価償却見積額以下の場合は、その会計年度以降の減価償却方法を「定率法」に変更する必要があります。それ以外の場合は、引き続き古典的減価のポーランド税減価償却方法で償却を実行します。
| 月 | 第1年: 20% * 2.5(5000.00) | 第2年: 20% * 2(4000.00) | 第3年: 20% * 2(1000.00) |
|---|---|---|---|
| 第1月 | 416.67 | 333.33 | 200.00 |
| 第2月 | 416.67 | 333.33 | 200.00 |
| 第3月 | 416.67 | 333.33 | 200.00 |
| 第4月 | 416.67 | 333.33 | 200.00 |
| 第5月 | 416.67 | 333.33 | 200.00 |
| 第6月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第7月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第8月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第9月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第10月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第11月 | 416.67 | 333.33 | -- |
| 第12月 | 416.63 | 333.37 | -- |
この例について考えてみます。
資産取得価額は10,000ドルです。
第1年は、10,000の減価償却基準による変更減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第2年は、10,000の減価償却基準による古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第3年は6000の減価償却基準による古典的減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
注意: ここでは、基準が取得価額から償却累計額を差し引いて初年度償却額を加えた額に変更されています。
各年度の償却累計額は、次のとおりです。
第1年: 5000.00
第2年: 9000.00
第3年: 10,000.00
第1会計年度の償却方法には、変更減価のポーランド税減価償却方法が使用されます。計算方法は「古典的および定率法の減価切替を伴うポーランド変更減価」減価償却基準ルールの第1会計年度の計算と同じです。関連項目: 古典的および定率法の減価切替を伴うポーランド変更減価
第2会計年度は、減価償却方法が自動的に定率法に切り替わり、資産がすべて償却されるまで引き続き定率法を使用して資産が償却されます。
| 月 | 第1年: 20% * 2.5(5000.00) | 第2年: 20%(2000.00) | 第3年: 20%(2000.00) | 第4年: 20%(1000.00) |
|---|---|---|---|---|
| 第1月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第2月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第3月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第4月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第5月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
| 第6月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | 166.65 |
| 第7月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第8月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第9月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第10月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第11月 | 416.67 | 166.67 | 166.67 | -- |
| 第12月 | 416.63 | 166.63 | 166.63 | -- |
この例について考えてみます。
資産取得価額は10,000ドルです。
第1年は、10,000の減価償却基準による変更減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第2年から第4年は、10,000の減価償却基準による定率法を使用します。
各年度末の償却累計額は、次のとおりです。
第1年: 5000.00
第2年: 7000.00
第3年: 9000.00
第4年: 10,000.00
第1会計年度の償却方法には、標準減価のポーランド税減価償却方法が使用されます。償却率は、減価償却ファクタで定率を乗算して導出されます。
標準減価のポーランド税減価償却方法で使用される減価償却率の計算に使用される算式は、次のとおりです。
定率 * 減価償却ファクタ
たとえば、定率が20パーセントで減価償却ファクタが3の場合、償却率は次のようになります。
20% * 3 = 60%
第2会計年度の後、すべての会計年度の開始時にはテストが実行され、標準減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率に基づいて計算された減価償却見積額以下であるかどうかが検証されます。
標準減価のポーランド税減価償却方法に基づいて計算された減価償却見積額が、定率に基づいて計算された減価償却見積額以下の場合は、その会計年度以降の減価償却方法を「定率法」に変更する必要があります。それ以外の場合は、引き続き標準減価のポーランド税減価償却方法で償却を実行します。標準減価のポーランド税減価償却方法の減価償却は、常に純帳簿価額が基準となります。
| 月 | 第1年: 20% * 2(4000.00) | 第2年: 20% * 2(2400.00) | 第3年: 20%(2000.00) | 第4年: 20%(1600.00) |
|---|---|---|---|---|
| 第1月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第2月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第3月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第4月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第5月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第6月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第7月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第8月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第9月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 166.67 |
| 第10月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | 99.97 |
| 第11月 | 333.33 | 200.00 | 166.67 | -- |
| 第12月 | 333.37 | 200.00 | 166.63 | -- |
この例について考えてみます。
資産取得価額は10,000ドルです。
第1年は、10,000の減価償却基準による標準減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第2年は、6000の減価償却基準による標準減価のポーランド税減価償却方法を使用します。
第3年と第4年は、10,000の減価償却基準による定率法を使用します。
各年度末の償却累計額は、次のとおりです。
第1年: 4000.00
第2年: 6400.00
第3年: 8400.00
第4年: 10,000.00
ポーランド税減価償却取引を使用して減価償却している資産に対して、取得価額修正を実行できます。取得価額修正では、プラスの金額(取得価額の引上げ)またはマイナスの金額(取得価額の引下げ)を指定できます。現期間の修正(現期間のいずれかの日付に修正が適用されることを意味する)または過去の期間の修正を実行できます。
関連項目
マイナスの取得価額修正は、資産の取得価額を現在の取得価額から引き下げる場合に発生します。マイナスの取得価額修正を実行すると、「ポーランドの修正計算基準単位」チェック・ボックスの選択状態に従って減価償却が計算されます。
注意: 「ポーランドの修正計算基準単位」チェック・ボックスは、マイナスの取得価額修正にのみ適用されます。
このチェック・ボックスが選択されている場合は、新しい減価償却基準を計算する特別なルールが使用されます。新しい減価償却基準は、次の算式を使用して計算されます。
旧取得価額 - 修正金額の純帳簿価額
修正金額の純帳簿価額を計算するために、最初に償却累計額の割合が計算されます。次の算式を使用して計算されます。
旧償却累計額 * 修正金額/旧取得価額
次に、計算された償却累計額の割合を使用して、修正金額の純帳簿価額が計算されます。次の算式を使用して計算されます。
修正金額 - 計算された償却累計額の割合
たとえば、旧取得価額が20,000、旧償却累計額が10,800、修正金額が8,000と仮定します。最初に、償却累計額の割合が計算されます。
10,800 * 8,000/20,000 = 4,320
次に、修正金額の純帳簿価額が計算されます。
8,000 - 4,320 = 3,680
最後に、新しい減価償却基準が計算されます。
20,000 - 3,680 = 16,320
このチェック・ボックスの選択が解除されている場合は、次の算式を使用して新しい減価償却基準が計算されます。
旧基準 - 旧基準 * 修正金額/旧取得価額
たとえば、旧取得価額が20,000、旧基準が12,000、修正金額が8,000と仮定します。新しい基準は次のように計算されます。
12,000 - 12,000 * 8,000/20,000 = 7,200
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、マイナスの取得価額修正が第2年第8月に発生します。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
注意: この表および後に続く各表の端数処理は概算です。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 |
| 8 | 12,000.00 | 544.00 | 11,344.00 | 16,320.00 |
| 9 | 12,000.00 | 544.00 | 11,888.00 | 16,320.00 |
| 10 | 12,000.00 | 544.00 | 12,432.00 | 16,320.00 |
| 11 | 12,000.00 | 544.00 | 12,976.00 | 16,320.00 |
| 12 | 12,000.00 | 544.00 | 13,520.00 | 16,320.00 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000.00 | 272.00 | 13,792.00 | 16,320.00 |
| 2 | 12,000.00 | 272.00 | 14,064.00 | 16,320.00 |
| 3 | 12,000.00 | 272.00 | 14,336.00 | 16,320.00 |
| 4 | 12,000.00 | 272.00 | 14,608.00 | 16,320.00 |
| 5 | 12,000.00 | 272.00 | 14,880.00 | 16,320.00 |
| 6 | 12,000.00 | 272.00 | 15,152.00 | 16,320.00 |
| 7 | 12,000.00 | 272.00 | 15,424.00 | 16,320.00 |
| 8 | 12,000.00 | 272.00 | 15,696.00 | 16,320.00 |
| 9 | 12,000.00 | 272.00 | 15,968.00 | 16,320.00 |
| 10 | 12,000.00 | 272.00 | 16,240.00 | 16,320.00 |
| 11 | 12,000.00 | 80.00 | 16,320.00 | 16,320.00 |
| 12 |
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、マイナスの取得価額修正が第3年第7月に発生しますが、修正は第2年第8月に適用されます。第3年第7月に表示される624.00の減価償却額には、現期間の272.00と遡及減価償却が含まれています。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 400.00 | 11,200.00 | 12,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 400.00 | 11,600.00 | 12,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 400.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 400.00 | 12,400.00 | 12,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 400.00 | 12,800.00 | 12,000.00 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 333.33 | 13,133.33 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 333.33 | 13,466.67 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 333.33 | 13,800.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 333.33 | 14,133.33 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 333.33 | 14,466.67 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 333.33 | 14,800.00 | 20,000.00 |
| 7 | 12,000.00 | 624.00 | 15,424.00 | 16,320.00 |
| 8 | 12,000.00 | 272.00 | 15,696.00 | 16,320.00 |
| 9 | 12,000.00 | 272.00 | 15,968.00 | 16,320.00 |
| 10 | 12,000.00 | 272.00 | 16,240.00 | 16,320.00 |
| 11 | 12,000.00 | 80.00 | 16,320.00 | 16,320.00 |
| 12 |
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、20,000.00から12,000.00へのマイナス修正が第2年第8月に発生します。新しい減価償却基準は7,200.00です。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 |
| 8 | 12,000.00 | 240.00 | 11,040.00 | 7,200.00 |
| 9 | 12,000.00 | 240.00 | 11,280.00 | 7,200.00 |
| 10 | 12,000.00 | 240.00 | 11,520.00 | 7,200.00 |
| 11 | 12,000.00 | 240.00 | 11,760.00 | 7,200.00 |
| 12 | 12,000.00 | 240.00 | 12,000.00 | 7,200.00 |
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、20,000.00から12,000.00へのマイナス修正が第3年第7月に発生しますが、修正は第2年第8月に適用されます。第3年第7月の償却金額として表示されるマイナス2,800.00には、超過償却額および遡及される償却累計額が含まれています。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 400.00 | 11,200.00 | 12,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 400.00 | 11,600.00 | 12,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 400.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 400.00 | 12,400.00 | 12,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 400.00 | 12,800.00 | 12,000.00 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 333.33 | 13,133.33 | 20,000.00 |
| 2 | 20,000.00 | 333.33 | 13,466.67 | 20,000.00 |
| 3 | 20,000.00 | 333.33 | 13,800.00 | 20,000.00 |
| 4 | 20,000.00 | 333.33 | 14,133.33 | 20,000.00 |
| 5 | 20,000.00 | 333.33 | 14,466.67 | 20,000.00 |
| 6 | 20,000.00 | 333.33 | 14,800.00 | 20,000.00 |
| 7 | 12,000.00 | (2800.00) | 12,000.00 | 7,200.00 |
プラスの取得価額修正は、資産の取得価額を現在の取得価額から引き上げる場合に発生します。
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、10,000.00から20,000.00へのプラスの取得価額修正が第3年第7月に発生します。
注意: この例では、減価償却が第3年のみに表示されていますが、減価償却はその後も資産が完全に償却されるまで続きます。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 333.33 | 333.33 | 10,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 333.33 | 666.67 | 10,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 333.33 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 333.33 | 1,333.33 | 10,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 333.33 | 1,666.67 | 10,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 333.33 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 333.33 | 2,333.33 | 10,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 333.33 | 2,666.67 | 10,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 333.33 | 3,000.00 | 10,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 333.33 | 3,333.33 | 10,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 333.33 | 3,666.67 | 10,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 333.33 | 4,000.00 | 10,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 200.00 | 4,200.00 | 6,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 200.00 | 4,400.00 | 6,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 200.00 | 4,600.00 | 6,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 200.00 | 4,800.00 | 6,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 200.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 200.00 | 5,200.00 | 6,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 200.00 | 5,400.00 | 6,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 200.00 | 5,600.00 | 6,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 200.00 | 5,800.00 | 6,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 200.00 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 200.00 | 6,400.00 | 6,000.00 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 166.67 | 6,566.67 | 10,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 166.67 | 6,733.33 | 10,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 166.67 | 6,900.00 | 10,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 166.67 | 7,066.67 | 10,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 166.67 | 7,233.33 | 10,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 166.67 | 7,400.00 | 10,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 333.33 | 7,733.33 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 333.33 | 8,066.67 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 333.33 | 8,400.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 333.33 | 8,733.33 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 333.33 | 9,066.67 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 333.33 | 9,400.00 | 20,000.00 |
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、10,000.00から20,000.00へのプラスの取得価額修正が第3年第7月に発生しますが、影響は第2年第7月から始まります。第3年第7月に表示される1,333.33の償却金額には、現期間の減価償却費333.33と遡及減価償却が含まれています。第2年第7月から第3年2月までの遡及減価償却の金額は1,000.00です。
注意: この例では、減価償却が第3年のみに表示されていますが、減価償却はその後も資産が完全に償却されるまで続きます。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 333.33 | 333.33 | 10,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 333.33 | 666.67 | 10,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 333.33 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 333.33 | 1,333.33 | 10,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 333.33 | 1,666.67 | 10,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 333.33 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 333.33 | 2,333.33 | 10,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 333.33 | 2,666.67 | 10,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 333.33 | 3,000.00 | 10,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 333.33 | 3,333.33 | 10,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 333.33 | 3,666.67 | 10,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 333.33 | 4,000.00 | 10,000.00 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 200.00 | 4,200.00 | 6,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 200.00 | 4,400.00 | 6,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 200.00 | 4,600.00 | 6,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 200.00 | 4,800.00 | 6,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 200.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 200.00 | 5,200.00 | 6,000.00 |
| 7 | 10,000.00 | 200.00 | 5,400.00 | 6,000.00 |
| 8 | 10,000.00 | 200.00 | 5,600.00 | 6,000.00 |
| 9 | 10,000.00 | 200.00 | 5,800.00 | 6,000.00 |
| 10 | 10,000.00 | 200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11 | 10,000.00 | 200.00 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 12 | 10,000.00 | 200.00 | 6,400.00 | 6,000.00 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000.00 | 166.67 | 6,566.67 | 10,000.00 |
| 2 | 10,000.00 | 166.67 | 6,733.33 | 10,000.00 |
| 3 | 10,000.00 | 166.67 | 6,900.00 | 10,000.00 |
| 4 | 10,000.00 | 166.67 | 7,066.67 | 10,000.00 |
| 5 | 10,000.00 | 166.67 | 7,233.33 | 10,000.00 |
| 6 | 10,000.00 | 166.67 | 7,400.00 | 10,000.00 |
| 7 | 20,000.00 | 1,333.33 | 8,733.33 | 20,000.00 |
| 8 | 20,000.00 | 333.33 | 9,066.67 | 20,000.00 |
| 9 | 20,000.00 | 333.33 | 9,400.00 | 20,000.00 |
| 10 | 20,000.00 | 333.33 | 9,733.33 | 20,000.00 |
| 11 | 20,000.00 | 333.33 | 10,066.67 | 20,000.00 |
| 12 | 20,000.00 | 333.33 | 10,400.00 | 20,000.00 |
Oracle Assetsには、5種類のポーランド税減価償却方法のいずれかを使用して資産を部分除・売却する特別な処理は用意されていません。他の部分除・売却取引の場合と同様に、新規の償却累計額、減価償却基準および新しい取得価額が計算されます。
新しい基準の計算は、修正金額が部分除・売却金額に置換されること以外は、「ポーランドの修正計算基準単位」チェック・ボックスの選択が解除されている場合の取得価額のマイナス修正と同じです。
旧基準 - 旧基準 * 部分除・売却金額/旧取得価額
たとえば、旧取得価額が20,000、旧基準が12,000、部分除・売却金額が8,000の場合、新しい基準は次のように計算されます。
12,000 - 12,000 * 8,000/20,000 = 7,200
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、8,000の部分除・売却が第2年第8月に発生します。新しい償却累計額は次のように計算されます。
旧償却累計額 + 現期間減価償却 - 旧償却累計額 * 除・売却金額/旧取得価額
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 8 | 12,000.00 | 240.00 | 6,720.00 | 7,200.00 | 標準減価 |
| 9 | 12,000.00 | 240.00 | 6,960.00 | 7,200.00 | 標準減価 |
| 10 | 12,000.00 | 240.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 標準減価 |
| 11 | 12,000.00 | 240.00 | 7,440.00 | 7,200.00 | 標準減価 |
| 12 | 12,000.00 | 240.00 | 7,680.00 | 7,200.00 | 標準減価 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000.00 | 200.00 | 7,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 2 | 12,000.00 | 200.00 | 8,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 3 | 12,000.00 | 200.00 | 8,280.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 4 | 12,000.00 | 200.00 | 8,480.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 5 | 12,000.00 | 200.00 | 8,680.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 6 | 12,000.00 | 200.00 | 8,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 7 | 12,000.00 | 200.00 | 9,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 8 | 12,000.00 | 200.00 | 9,280.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 9 | 12,000.00 | 200.00 | 9,480.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 10 | 12,000.00 | 200.00 | 9,680.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 11 | 12,000.00 | 200.00 | 9,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 12 | 12,000.00 | 200.00 | 10,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
次の例について考えてみます。
減価償却基準ルール: 定率法への切替を伴うポーランド標準減価
定率: 20パーセント
ファクタ: 2
減価償却方法の切替を判断するテスト: 第1年は実行せず、それ以降のすべての年には実行
この例では、8,000の部分除・売却が第2年第12月に発生します。第2年第12月に表示されるマイナス400.00の償却金額には、現期間の減価償却費240.00と、第2年第8月から第2年第11月までに遡及された超過償却額640.00が含まれています。
次の表に、第1年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 666.67 | 666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 2 | 20,000.00 | 666.67 | 1,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 3 | 20,000.00 | 666.67 | 2,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 4 | 20,000.00 | 666.67 | 2,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 5 | 20,000.00 | 666.67 | 3,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 6 | 20,000.00 | 666.67 | 4,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 7 | 20,000.00 | 666.67 | 4,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 8 | 20,000.00 | 666.67 | 5,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 9 | 20,000.00 | 666.67 | 6,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 10 | 20,000.00 | 666.67 | 6,666.67 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 11 | 20,000.00 | 666.67 | 7,333.33 | 20,000.00 | 標準減価 |
| 12 | 20,000.00 | 666.67 | 8,000.00 | 20,000.00 | 標準減価 |
次の表に、第2年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000.00 | 400.00 | 8,400.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 2 | 20,000.00 | 400.00 | 8,800.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 3 | 20,000.00 | 400.00 | 9,200.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 4 | 20,000.00 | 400.00 | 9,600.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 5 | 20,000.00 | 400.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 6 | 20,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 7 | 20,000.00 | 400.00 | 10,800.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 8 | 20,000.00 | 400.00 | 11,200.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 9 | 20,000.00 | 400.00 | 11,600.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 10 | 20,000.00 | 400.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 11 | 20,000.00 | 400.00 | 12,400.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
| 12 | 12,000.00 | (400.00) | 7,680.00 | 12,000.00 | 標準減価 |
次の表に、第3年の減価償却情報を示します。
| 月 | 取得価額 | 減価償却 | 償却累計額 | 減価償却基準 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000.00 | 200.00 | 7,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 2 | 12,000.00 | 200.00 | 8,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 3 | 12,000.00 | 200.00 | 8,280.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 4 | 12,000.00 | 200.00 | 8,480.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 5 | 12,000.00 | 200.00 | 8,680.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 6 | 12,000.00 | 200.00 | 8,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 7 | 12,000.00 | 200.00 | 9,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 8 | 12,000.00 | 200.00 | 9,280.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 9 | 12,000.00 | 200.00 | 9,480.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 10 | 12,000.00 | 200.00 | 9,680.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 11 | 12,000.00 | 200.00 | 9,880.00 | 12,000.00 | 定率法 |
| 12 | 12,000.00 | 200.00 | 10,080.00 | 12,000.00 | 定率法 |
減価償却、取得価額および投資税額控除(ITC)の限度額を設定またはレビューできます。減価償却限度額または取得価額限度額のいずれかを資産カテゴリに関連付けることができます。米国税法が適用される場合は、高級車に対して償却費計上限度額を設定する必要があります。
「資産限度額」ウィンドウをオープンします。
設定する限度額のタイプ(「取得価額」、「減価償却」または「投資税額控除」)を選択します。
限度額の名称および摘要を入力します。
減価償却費限度額を定義する通貨を入力します。
限度額が有効になる開始日と終了日を入力します。「終了日」フィールドを空白のままにすると、限度額は無期限に有効になります。
「減価償却」タイプの限度額を定義している場合は、限度額が適用される資産の耐用期間の会計年度を入力します。
限度額を入力します。
減価償却: 資産の耐用期間の各年に対する年間減価償却最大許容額を入力します。以降は、各年について最後に設定した限度額が使用されます。
作業内容を保存します。
関連項目
投資税額控除(ITC)率および回収率を設定してレビューできます。控除率および控除回収率は、年度順および耐用年数順に昇順で表示されます。投資税額控除対象資産を償却が完了する前に除・売却すると、資産の投資税額控除部分が自動的に回収されます。控除率を設定した後は、資産に対して投資税額控除を申告できます。
「投資税額控除率」ウィンドウをオープンします。
ITC率を有効にする年を入力します。
ITC回収率を適用する課税年度すべてにITC回収率を設定する必要があります。
このITC率を適用する耐用期間を入力します。
ITC率をパーセントで入力します。資産のITC基準は、資産の当初の取得価額とITC限度額(使用される場合)のいずれか少ない額になります。
作業内容を保存します。
「投資税額控除回収率」ウィンドウをオープンします。
回収率を有効にする課税年度を入力します。
回収率を適用する耐用期間(年月)を入力します。
回収率を適用する除・売却年を入力します。耐用期間内のこの年に資産を除・売却する場合は、この回収率に従って処理されます。
回収率をパーセントで入力します。この回収率を使用して、除・売却時に回収する投資税額控除額が決定されます。
作業内容を保存します。
関連項目
「按分方法」ウィンドウでは、按分および除・売却年度償却方法を設定またはレビューできます。
最初に、最も古い事業供用日に対応する期間から現会計年度の終了まで、すべての按分方法を設定する必要があります。各会計年の年度末には、次の会計年度の按分方法が自動的に設定されます。
前提条件
最も古い事業供用日を設定します。関連項目: システム管理の指定
会計年度を設定します。関連項目: 会計年度の作成
減価償却カレンダおよび按分用カレンダを設定します。関連項目: カレンダ期間の日付の指定
「按分方法」ウィンドウをオープンします。
方法名および摘要を入力します。
この方法を設定する会計年度名を入力します。
按分基準日に対応する期間のかわりに、事業供用日に対応する会計期間で減価償却を開始する場合は、「事業供用開始期間の償却」チェック・ボックスを選択します。
このオプションは、年間の減価償却額を配分する期間数を決定します。計算済(定額)法を使用する資産の場合、このオプションは無視され、常に按分基準日に対応する会計期間に減価償却が開始されます。
事業供用日が開始日から終了日までにある資産の日付範囲および対応する按分基準日を入力します。
注意: 按分方法には、会計年度内のすべて日付が指定されている必要があります。そうでない場合は減価償却が適切に計算されません。
作業内容を保存します。
関連項目
Oracle Assetsでは、按分方法を使用して、資産の事業供用日に基づいて資産の耐用期間に対する初年度および最終年度の減価償却費が決定されます。資産は期間内のいつでも取得できるため、あらゆる場合に対応して減価償却費を決定する方法が必要です。按分基準日は、按分方法と事業供用日によって決定されます。
注意: 資産を適切に償却するために、按分方法には、会計年度のすべての日付を含める必要があります。
按分用カレンダにおける按分期間は、按分基準日を使用して決定されます。完全に償却する前に資産を除・売却した場合は、除・売却年度償却方法の按分基準日を使用して、資産が存在した期間の最終年度の減価償却費が決定されます。
資産を完全に償却する前に除・売却した場合は、除・売却年度償却方法を使用して、除・売却日に基づいて資産が存在した期間の最終年度の減価償却費が決定されます。
重要: 減価償却額の生成では、按分方法、除・売却年度償却方法および減価償却方法が連携して作用します。償却率は、各按分期間に対して設定する必要があります。
Oracle Assetsでは、独自の按分方法を作成できます。
この例では、Half-Quarterという按分方法を作成します。この按分方法は、各四半期を2つの期間に分割します。この按分方法には、合計8個(各四半期に対して2個)の按分期間を作成する必要があります。
| 按分方法 | 期間 | 按分基準日 | 按分期間数 |
|---|---|---|---|
| Half-Quarter | 1998年1月1日から1998年2月15日 | 1998年2月15日 | 8 |
| Half-Quarter | 1998年2月16日から1998年3月31日 | 1998年3月31日 | 8 |
この例では、Following Half-Yearという按分方法を作成します。この按分方法は、按分基準日が次の期間の初日になります。
| 按分方法 | 期間 | 按分基準日 | 按分期間数 |
|---|---|---|---|
| Following Half Year | 1998年1月1日から1998年6月30日 | 1998年7月1日 | 2 |
| Following Half Year | 1998年7月1日から1998年12月31日 | 1999年1月1日 | 2 |
この例では、Mid-Half-Yearというもう1つの半年の按分方法を作成します。この按分方法は、按分基準日が期間の中間日になります。
| 按分方法 | 期間 | 按分基準日 | 按分期間数 |
|---|---|---|---|
| Mid-Half Year | 1998年1月1日から1998年6月30日 | 1998年3月31日 | 2 |
| Mid-Half Year | 1998年7月1日から1998年12月31日 | 1998年9月30日 | 2 |
月極は、按分方法やカレンダ設定として最も一般的です。ここでは、次のことを前提とします。
減価償却カレンダと按分用カレンダは同一で、異なる月ごとに各期間が設定されている標準的な12か月カレンダを使用します。
特定の月の任意の時点に事業供用日がある資産は、その期間の1か月分すべての減価償却が割り当てられます。
「資産カレンダ」ウィンドウで減価償却カレンダを設定します。次のように、各月に1つの減価償却期間を入力します。
| 期間 | 日付 |
| 減価償却期間1 | 1月1日から1月31日 |
| 減価償却期間2 | 2月1日から2月28日 |
| 減価償却期間3 | 3月1日から3月31日 |
| 減価償却期間4 | 4月1日から4月30日 |
| ... | ... |
次に、按分用カレンダを設定します。按分用カレンダと減価償却カレンダは同じであるため、減価償却カレンダと按分用カレンダの両方に同じカレンダ名を入力できます。
資産を追加する場合は、「資産台帳」ウィンドウで当月の按分方法を選択します。
この場合、按分基準日は期間の最終日になります。次に例を示します。
| 期間 | 期間日 | 按分基準日 |
| 期間1 | 1月1日から1月31日 | 1月31日 |
| 期間2 | 2月1日から2月28日 | 2月28日 |
| 期間3 | 3月1日から3月31日 | 3月31日 |
| ... | ... | ... |
半月按分方法を使用すると、資産の耐用期間の最初と最後の期間に1か月の半分の減価償却が割り当てられます。半月按分方法では、半月の期間の按分用カレンダを設定する必要があります。
月単位の期間の減価償却カレンダを設定します。
半月単位の24期間の按分用カレンダを設定します。次に例を示します。
| 期間 | 日付 |
| 按分期間1 | 1月1日から1月15日 |
| 按分期間2 | 1月16日から1月31日 |
| 按分期間3 | 2月1日から2月15日 |
| 按分期間4 | 2月16日から2月28日 |
| ... | ... |
半月単位で24期間が指定されている半月按分方法を設定します。
按分基準日に対応する期間のかわりに、事業供用日に対応する会計期間で減価償却を開始する場合は、「事業供用開始期間の償却」チェック・ボックスを選択します。このオプションは、年間の減価償却額を配分する期間数を決定します。定額法の減価償却資産については、常に按分基準日に対応する会計期間に減価償却が開始されます。
資産を追加する場合は、カテゴリのデフォルトの按分方法を上書きして、設定した半月按分方法を使用します。「資産台帳」ウィンドウの「デフォルト償却基準」リージョンで、按分方法を半月に変更します。
| 期間 | 期間日 | 按分基準日 |
| 期間 | 期間日 | 按分基準日 |
| 期間1 | 1月1日から1月15日 | 1月15日 |
| 期間2 | 1月16日から1月31日 | 1月31日 |
| 期間3 | 2月1日から2月15日 | 2月15日 |
| 期間4 | 2月16日から2月28日 | 2月28日 |
| 期間5 | 3月1日から3月15日 | 3月15日 |
| ... | ... | ... |
この例で、資産の事業供用日が1月の前半(1998年1月4日など)にある場合は、資産を取得した期間に対して1か月分すべての減価償却が割り当てられます。減価償却は、第1按分期間(1998年1月1日から1998年1月15日)と第2按分期間(1月16日からの期間)に計上されます。
減価償却期間の前半に資産を除・売却すると、減価償却は、その資産が存在した最後の減価償却期間には割り当てられません。つまり、1年後の1999年1月4日に資産を除・売却すると、減価償却は1999年1月の減価償却期間には計上されません。資産をその耐用期間の最終減価償却期間の後半に除・売却した場合は、半月分の減価償却が計上されます。たとえば、1998年1月18日に資産を除・売却すると、減価償却は、1998年1月1日から1998年1月15日の按分期間には計上されますが、1998年1月16日から1998年1月31日の按分期間には計上されません。
1月の後半(1998年1月18日など)に資産を事業に供用すると、半月分の減価償却が取得した期間(1998年1月16日から1998年1月31日)に計上されます。
減価償却期間の前半に資産を除・売却すると、減価償却は、その資産が存在した最後の減価償却期間には割り当てられません。つまり、1999年1月4日に資産を除・売却すると、減価償却は1999年1月の減価償却期間には計上されません。資産をその耐用期間の最終減価償却期間の後半に除・売却した場合は、半月分の減価償却が計上されます。たとえば、1999年1月18日に資産を除・売却すると、減価償却は、1999年1月1日から1999年1月15日の按分期間には計上されますが、1999年1月16日から1999年1月31日の按分期間には計上されません。
減価償却を1日単位で実行する必要がある場合は、日次減価償却カレンダおよび日次按分用カレンダ(365の期間数)を設定する必要があります。
次のような日次減価償却カレンダを設定します。
| 期間 | 日付 |
| 減価償却期間1 | 1月1日から1月1日 |
| 減価償却期間2 | 1月2日から1月2日 |
| 減価償却期間3 | 1月3日から1月3日 |
| 減価償却期間4 | 1月4日から1月4日 |
| ... | ... |
日次按分用カレンダを設定します。
「按分方法」ウィンドウで、設定した按分用カレンダと同じ日次期間を使用して「日次」という按分方法を設定します。
この按分方法を使用する必要がある資産を追加する場合は、「資産台帳」ウィンドウで「日次」按分方法を選択します。
関連項目
「資産カテゴリ」ウィンドウで物価指数を資産カテゴリや資産台帳に割り当てるには、事前に物価指数を設定する必要があります。同一または異なる資産台帳の複数の資産カテゴリに対して単一の物価指数を使用できます。あるいは、各減価償却台帳の各資産カテゴリに異なる物価指数を指定できます。
再評価資産除・売却レポートでは、物価指数を使用して再評価後の資産取得価額が決定されます。この資産取得価額を使用して除・売却資産の損益が計算されます。物価指数リストを実行することで、定義したすべての物価指数をレビューできます。
台帳にある資産の取得価額を実際に再評価する場合は、資産またはカテゴリを再評価する必要があります。
「物価指数」ウィンドウをオープンします。
定義する指数の名称を入力します。
ヒント: 入力した名称は「値リスト」ウィンドウに表示されますが、40文字を超える部分は表示されません。名称は40文字までの範囲で指定してください。
指数値をパーセントで入力します。
指数値を有効にする日付を入力します。「日付:至」を空白のままにすると、指数は無期限に有効になります。
作業内容を保存します。
関連項目
カテゴリ情報は、資産のグループに共通の情報です。Oracle Assetsでは、資産を追加する際にこれらの減価償却ルールがデフォルトとして使用されるため、資産を速やかに追加できます。個別の資産に適さないデフォルトの大半は、「資産詳細」または「資産台帳」ウィンドウで上書きできます。デフォルト値は、各台帳のカテゴリごとに設定します。カテゴリに対して設定するデフォルト減価償却ルールは、指定する事業供用日の範囲によっても異なります。
前提条件
カテゴリ・フレックスフィールドを設定します。関連項目: 資産カテゴリ・フレックスフィールドの設定
勘定科目セグメント値と組合せを設定します。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の勘定科目の定義に関する項
減価償却台帳を設定します。関連項目: 減価償却台帳の定義
クイックコード値を設定します。関連項目: クイックコードの入力
按分方法を設定します。関連項目: 按分方法の日付の指定
減価償却方法を設定します。関連項目: その他の減価償却方法の定義
「資産カテゴリ」ウィンドウをオープンします。
設定する資産カテゴリを識別するカテゴリ名と摘要を入力します。
ヒント: 入力した名称は連結されてフィールドに表示されますが、20文字を超える部分は表示されません。名称は20文字までの範囲で指定してください。
このカテゴリを使用する場合は「使用可能」を選択します。
このカテゴリの品目について支払を行う際に資産勘定に計上する場合、およびこのカテゴリの品目を減価償却する場合は、「資産計上」を選択します。
このカテゴリの資産を実地棚卸比較の対象とする場合は、「実地棚卸」を選択します。
「カテゴリ・タイプ」ポップリストから「リース」、「建物付属設備」または「ノン・リース」を選択します。
資産を「リース」カテゴリ・タイプに割り当てた場合のみ、「資産詳細」ウィンドウにリース情報を入力します。
「所有権」ポップリストから「所有」または「リース」を選択します。
このカテゴリの資産が一般的に属するプロパティ・タイプと区分を入力します。
「クイックコード」ウィンドウで、プロパティ・タイプに対してクイックコード値を設定します。米国における資産の場合は、動産には1245、不動産には1250を入力します。
カテゴリのGL勘定科目を入力します。関連項目: カテゴリのGL勘定科目の入力
カテゴリが定義されている各減価償却台帳に対してデフォルト減価償却ルールを入力します。関連項目: カテゴリのデフォルト減価償却ルールの入力
作業内容を保存します。
関連項目
ヒント: 勘定科目が有効な組合せでない可能性があるため、相互検証ルールを一時的に使用不可にし、勘定科目体系の動的挿入を許可して、これらの勘定科目を入力できるようにする必要があります。
重要: 「資産カテゴリ」ウィンドウに入力した組合せの勘定科目に加え、他のセグメントを使用して仕訳を作成する場合は、勘定科目ジェネレータのデフォルト値を変更して、カテゴリからセグメントを入力する必要があります。
「資産カテゴリ」ウィンドウで、この資産カテゴリを設定する台帳を入力します。
このカテゴリと台帳の組合せについて資産取得価額勘定を入力します。
この勘定科目を使用して、資産取得価額が総勘定元帳に消し込まれます。資産の取得、除・売却、取得価額変更、再評価、振替、組替および資産計上を反映するように、この勘定科目の仕訳が作成されます。
このカテゴリと台帳の組合せについて資産精算勘定を入力します。
手動による資産取得および取得価額修正では、この勘定科目を使用して買掛管理システムおよびOracle Assetsが消し込まれます。
一括追加では、買掛管理システムを使用して資産取得または取得価額修正を消し込む際に、一括追加明細とともに取得した完全な勘定科目の組合せが使用されます。
このカテゴリと台帳の組合せの資産に対して減価償却を計上するGL減価償却費セグメントを入力します。この値は、「資産割当」ウィンドウで、減価償却費勘定の勘定科目セグメントに対するデフォルト値として表示されます。
ボーナス・レートを設定した場合は、ボーナス減価償却費勘定を入力します。このフィールドに値を入力しなかった場合、この勘定には減価償却費勘定がデフォルト設定されます。
このカテゴリと台帳の組合せについて償却累計額勘定を入力します。この勘定科目は、このカテゴリの資産取得価額勘定に対する相手勘定です。
ボーナス・レートを設定した場合は、ボーナス償却累計額勘定を入力します。このフィールドに値を入力しなかった場合、この勘定には償却累計額勘定がデフォルト設定されます。
このカテゴリと台帳の組合せについて再評価償却累計額勘定を入力します。この勘定科目は、償却累計額を再評価する場合に、再評価によって純帳簿価額を変更する際に使用されます。
このカテゴリと台帳の組合せについて再評価償却勘定を入力します。この勘定科目は、再評価償却累計額を償却する場合に、再評価の後に資産の残り耐用期間で再評価償却累計額を償却する際に使用されます。
このカテゴリと台帳の組合せについて建設仮勘定取得価額勘定を入力します。この勘定科目は、建設仮勘定取得価額勘定を総勘定元帳に消し込む際に使用されます。
カテゴリが定義されている各減価償却台帳に対してデフォルト減価償却ルールを入力します。
カテゴリが定義されている各減価償却台帳に対してデフォルト減価償却ルールを入力します。関連項目: カテゴリのデフォルト減価償却ルールの入力
関連項目
「デフォルト償却基準」ウィンドウで、これらのカテゴリのデフォルトが有効になる事業供用日の範囲を入力します。資産を追加すると、資産、カテゴリおよび台帳の事業供用日に従って減価償却ルールがデフォルト設定されます。
デフォルト減価償却ルールの範囲は必要に応じていくつでも指定できます。終了日を空白のままにすると、その減価償却ルール・セットが無期限に使用されます。有効な減価償却ルールに新しい範囲を追加するには、終了日を追加して現レコードを終了し、メニューから「編集」 > 「新規レコード」を選択します。
この台帳とカテゴリの組合せの資産に対する減価償却を通常行う場合は「償却費計上」を選択します。
注意: このフィールドに入力したデフォルト値に関係なく、費用処理済資産は減価償却されません。
この台帳とカテゴリの組合せの資産に対して通常使用する減価償却方法を入力します。
耐用年数ベースの方法を入力した場合は、資産の耐用期間(年月)を入力する必要があります。入力する方法には、この台帳の按分用カレンダと同じ期間数が定義されている必要があります。
定率法を入力した場合は、この台帳とカテゴリの組合せの資産を減価償却する際に通常使用する普通償却率と割増後償却率のデフォルト値を入力する必要があります。税務台帳に対してこのカテゴリを定義している場合は、ボーナス・ルールも入力できます。
累計生産高比例法を入力した場合は、この台帳とカテゴリの組合せの資産を減価償却する際に通常使用する単位(UOM)と生産能力を入力する必要があります。税務台帳に対してこのカテゴリを定義している場合は、会計用台帳に入力した単位と生産能力を入力します。
この台帳とカテゴリの組合せの資産に対して通常使用するボーナス・ルールを入力します。ボーナス・ルールは、UOM(単位)以外のあらゆる減価償却方法を使用する会計用台帳および税務台帳に使用できます。
この台帳とカテゴリの組合せの資産に通常割り当てる按分方法と除・売却年度償却方法を入力します。
この台帳の「資産台帳管理」ウィンドウで、「残存価額」ポップリストから「デフォルト % 使用」を選択した場合は、このカテゴリ、台帳および事業供用日の範囲に対するデフォルトの残存価額率を入力できます。関連項目: 資産台帳の会計基準の入力および資産残存価額の取得価額率としてのデフォルト設定
たとえば、残存価額を取得価額の10%にデフォルト設定する場合は、このフィールドに10を入力します。資産取得価額に影響する取引を実行すると、次の算式に従って、このデフォルト・パーセントを使用して残存価額が計算されます。
残存価額 = 取得価額 * デフォルト率
税務台帳に対してこのカテゴリを定義している場合は、必要に応じて減価償却費限度額または取得価額限度を入力できます。
親資産の耐用期間に基づいて従属資産のデフォルト耐用期間を決定する際に使用する従属資産耐用ルールのデフォルトを入力します。
次のいずれかのルールを選択します。
なし(フィールドを空白のままにする): 従属資産と親資産の耐用期間に関連性はありません。従属資産の耐用期間は資産カテゴリからデフォルト設定されます。
同一終了日(従属資産の耐用期間下限の指定なし): 従属資産は、親資産と同日またはカテゴリのデフォルト耐用期間の終了のいずれか早い時点で完全に償却されるようになります。従属資産のデフォルト耐用期間は、親資産の耐用期間とカテゴリのデフォルト耐用期間の終了に基づきます。親資産が完全に償却されている場合、従属資産には1か月のデフォルト耐用期間が設定されます。
同一終了日(従属資産の耐用期間下限の指定あり): 親資産の耐用期間が指定した耐用期間下限以上の場合、従属資産は親資産と同日に完全に償却されるようになります。従属資産の耐用期間は、親資産の耐用期間、カテゴリのデフォルト耐用期間および従属資産の耐用期間下限の終了に基づきます。親資産の残りの耐用期間とカテゴリのデフォルト耐用期間の両方が、入力した耐用期間下限未満の場合は、従属資産の耐用期間下限が使用されます。そうでない場合は、親資産の残り耐用期間とカテゴリのデフォルト耐用期間のいずれか短い期間が使用されます。
同一耐用期間: 従属資産には親資産と同じ耐用期間が使用されます。同じ期間総数で減価償却されます。親資産より後に従属資産を取得した場合は、親資産の耐用期間の終了日以降も減価償却が処理されます。
「同一終了日」従属資産耐用ルールを選択した場合は、従属資産の耐用期間下限を指定できます。
親資産の残り耐用期間とカテゴリのデフォルト耐用期間の両方が、入力した耐用期間下限未満の場合は、従属資産の耐用期間下限が使用されます。そうでない場合は、親資産の残り耐用期間とカテゴリのデフォルト耐用期間のいずれか短い期間が使用されます。
税務台帳で資産区分1250の資産カテゴリを設定している場合は、「除却損益計算のための定額法」を選択します。これによって、1250動産(不動産)の除・売却による損益を判断する際に定額減価償却方法が使用されます。
「除却損益計算のための定額法」を選択した場合は、1250動産の処理からの収益レポートに対して使用する定額減価償却方法と耐用期間を入力します。この方法は、「除・売却」ウィンドウの資産および一括コピーを使用する際の税務台帳の資産に対するデフォルトの償却方法になります。
耐用年数を超えて資産を減価償却する場合は、「償却限度の使用」チェック・ボックスを選択します。デフォルトの償却限度はパーセントまたは金額で入力できます。関連項目: 耐用年数を経過した資産の償却費の計上
除・売却する資産がキャピタル・ゲインとしてレポートされるために、その資産を保有している必要がある最小時間を入力します。
資産の除・売却で、このカテゴリのすべての資産を対象としてキャピタル・ゲインがレポートされるようにするには、0(ゼロ)のキャピタル・ゲイン保留期間を入力します。最低1年間保有した資産についてキャピタル・ゲインをレポートする場合(アメリカ合衆国の連邦税フォーム4797用にレポートする場合など)は、「年数」フィールドに1、「月数」フィールドに0(ゼロ)を入力します。様々な事業供用日にそれぞれ異なるキャピタル・ゲイン保留期間が必要な場合(アメリカ合衆国の連邦税フォーム4797の場合など)は、資産カテゴリを事業供用日の異なる範囲ごとに複数回設定してください。
税務台帳に対してこのカテゴリを定義している場合は、このカテゴリの資産が投資税額控除(ITC)に適格かどうか、およびこのカテゴリの資産に投資税額控除限度を使用するかどうかを指定します。
このカテゴリの資産を一括資産の取扱い対象に追加する場合は、「一括資産適用」チェック・ボックスを選択します。
「グループ資産」フィールドに、このカテゴリに追加されるすべての資産を割り当てるグループ資産を入力します。このフィールドにグループ資産番号を入力すると、このカテゴリを使用する資産計上資産および建設仮勘定資産すべてが、入力したグループ資産に自動的に割り当てられます。
作業内容を保存します。
関連項目
『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位の定義に関する項
このウィンドウを使用して、デフォルトの配分セットを定義します。詳細追加または一括追加処理を使用して新しい資産を追加するときは、「資産割当」ウィンドウのポップリストから事前定義済の配分セットを選択し、新しい資産に適切な配分を速やかに割り当てることができます。
配分セットを定義すると、様々な減価償却費勘定科目、事業所および従業員に対する資産単位の比率を割り当てることができます。1つのセットには、1つ以上の配分を定義できます。配分セットの配分情報は、いつでも変更できます。
重要: 配分セットの配分情報を変更しても、その配分セットにすでに割り当てられている資産への影響はありません。
「配分セット」ウィンドウにナビゲートします。
定義する配分セットの一意の名称と摘要を入力します。
配分セットの会計用台帳を入力します。
注意: 税務台帳または予算資産台帳には、配分セットを割り当てることはできません。
必要に応じて、この配分セットが有効である事業供用日範囲を入力します。配分セットを無期限に有効にする場合は、終了日を空白のままにします。
セット内の各配分について、単位パーセント、減価償却費勘定科目および事業所を入力します。従業員名または従業員番号も必要に応じて入力できます。
単位パーセント: この配分に割り当てる資産の比率を入力します。1つの配分に100%を入力することも、複数の配分に比率を分割することもできます。配分セットの比率の合計は100%にする必要があります。
作業内容を保存します。
関連項目
Oracle Assetsでは、リース資産を資産計上して減価償却するかどうかを決定するために、一般会計原則に従ってリース資産をテストできます。
注意: 財務会計基準委員会(FASB)によって、リースの資産計上の適格性を判断する際に使用する一定の基準が定義されました。他の多くの国でも同様のテスト基準が使用されます。
また、代替リース戦略を分析して、ビジネス要件に最も適合するようにリースを体系化できます。
多くの国では、次の4つの基準のいずれかを満たす場合は、リース資産の資産計上および減価償却が必要です。
リース終了時点で賃借人への資産所有の振替がある(テスト1)
割安購入選択権が存在する(テスト2)
賃貸借契約期間がリース資産の経済的耐用期間の75%を超える(テスト3)
リース開始時点での最低リース支払額の現在値が資産の公正市場価格の90%を超える(テスト4)
支払計画の現在値をOracle Assetsで自動的に計算する際に使用する情報や、前述のいずれかの基準を満たしているかどうかを判断する際に使用する情報は、リースを設定するときに入力できます。リースが4種類のいずれかのテストに適合する場合は、リース・タイプが「資産計上」にデフォルト設定され、資産取得価額は、リースに割り当てられた資産に対する支払計画の公正値と現在値のいずれか少ない額にデフォルト設定されます。
支払計画の現在値を定義して計算できます。Oracle Assetsは、通常の年金、最終支払、割安購入選択権、割安更改オプション、保証残余価額、ペナルティ、スキップ支払、重複支払など、あらゆるタイプのリース支払体系とリース支払タイプに対応しています。
リース契約のインプリシット実効金利に基づいて、利息と元本間に資産型リースの支払を配賦する償却計画を作成できます。
Oracle Assetsでは、情報提供の観点から、いずれの基準にも適合しないオペレーティング(短期)リースでの支払が追跡されます。この情報を使用して、オペレーティング・リースに基づく将来の最小支払額の計画を作成できます。この情報は財務諸表の脚注で開示する必要があります。
Oracle Assetsでは、変数(定期的なリース支払、最終支払、支払日、資産の公正値など)を操作することで代替リース戦略を評価できます。
Coastal Landscapesは、1993年3月1日にMarine Technologiesとの5年の設備リースに加入しています。設備の公正値は100,000ドルです。賃借人の限界借入利率は12%です。最低リース支払額は、月々の1,900ドルの支払で構成されます。リース開始時には3か月分を支払うことになっています。初回の定期支払は1996年4月1日に予定されています。割安購入選択権はありません。また、リース終了時に所有がCoastal Landscapesに振り替えられることもありません。資産の経済的耐用期間は6年です。
資産をリースに追加する前に、次の情報を「リース詳細」ウィンドウに入力し、リースを設定する必要があります。
| リース番号 | 325 |
| 摘要 | 設備リース |
| 賃貸人 | Marine Technologies |
| 支払計画 | Marine Lease |
| 通貨 | USD |
| 所有の振替 | なし |
| 割安購入選択権 | なし |
| リース・タイプ | 資産計上 |
| 賃貸借契約期間 | 60 |
| 資産耐用期間 | 72 |
| 公正値 | 100,000 |
注意: 「リース詳細」ウィンドウでは、事前定義の支払計画を選択してリースに添付できます。
リースの支払計画を定義していない場合は、「リース詳細」ウィンドウの「支払計画」ボタンを選択して、この資産に対する支払計画情報を入力し、支払計画の現在値を計算します。次の支払計画情報を入力します。
| 支払計画 | Marine Lease |
| 通貨 | USD |
| 現在値 | |
| リース(開始)日 | 93年3月1日 |
| 利率 | .12 |
| 複利頻度 | 月次 |
| 開始日 | 支払金額 | 回数 | 支払タイプ | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 93年3月1日 | 5,700ドル | 1 | ||
| 93年4月1日 | 1,900ドル | 57 | 年金 | 97年12月1日 |
この時点で「計算」ボタンを選択し、支払計画の現在値を決定できます。この例では、現在値は87,945.53ドルになります。87,945.53ドルは100,000ドル(公正値)未満であるため、4種類のテストのいずれかに適合する場合、これは資産計上の取得価額でもあります。
計算を実行すると、次のようにリース情報が更新されます。
| 支払計画 | Marine Lease |
| 現在値 | 87,945.53 |
| リース(開始)日 | 93年3月1日 |
| 利率 | .12 |
| 開始日 | 支払金額 | 回数 | 期間 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 93年3月1日 | 5,700ドル | 1 | ||
| 93年4月1日 | 5,700ドル | 57 | 月次 | 97年12月1日 |
現在値を計算した後は、「リース支払」ウィンドウの「償却の表示」ボタンを選択して償却計画を作成できます。この例では、支払計画の現在値は87,945.53ドルになります。リースで支払われる総額は114,000ドルです。26,054.47ドルの差異は、リース期間全体で認識される支払利息を表します。この例を次の表に示します。
| 開始日 | 支払額 | 支払に占める利息(12%/年)部分 | 元本の控除 | リース債務負担 |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | ||
| 93年3月1日 | 87,945.53 | |||
| 93年3月1日 | 5,700.00 | 0 | 5,700.00 | 82,245.53 |
| 93年4月1日 | 1,900.00 | 822.46 | 1,077.54 | 81,167.99 |
| 93年5月1日 | 1,900.00 | 811.68 | 1,088.32 | 80,079.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 97年11月1日 | 1,900.00 | 37.44 | 1,862.56 | 1,881.19 |
| 97年12月1日 | 1,900.00 | 18.81 | 1,900.00 | 0 |
| 合計: | 114,000 | 26,054.47 | 87,945.53 | 0 |
(a)時間が経過していないために金利が発生しない93年3月1日の支払以外は、前期間のリース債務負担に期間ごとの利率(この例では12%/12=1%)を乗じた金額
(b)(a)を差し引いた支払金額
(c)前期間の金額(c)から現期間の金額(b)を差し引いた金額
支払計画を保存すると、自動的に「リース詳細」ウィンドウに戻ります。先ほど定義した計画をこのウィンドウでリースに添付できます。
注意: 支払計画をリースに添付するには、償却計画も保存する必要があります。
「リース詳細」ウィンドウの「現在値」フィールドは、添付された支払計画からデフォルト設定されます。90%テストの要件は満たしていませんが、経済的耐用期間テストの要件は満たしているため、リースは引き続き資産計上に適格です。資産計上の取得価額は、支払計画の現在値と公正値のうち少ない額である87,945.53ドルになります。このリースを資産に添付すると、「資産台帳」ウィンドウには、資産計上の取得価額がリース資産の取得価額のデフォルト値として表示されます。この値は、必要に応じて変更できます。
Fremont Corporationは、1990年1月1日付けでリース基本契約に加入しました。賃貸借契約期間は5年で、各年の初めに20,000ドルのレンタル料を支払う必要があります。設備の公正値は100,000ドルで、経済的耐用期間は10年です。リースには5,000ドルの割安購入選択権が付帯しています。賃借人の限界借入利率は10%です。
| 支払計画 | 支払1 |
| 現在値 | |
| リース(開始)日 | 90年1月1日 |
| 利率 | .10 |
| 複利頻度 | 年次 |
| 開始日 | 支払金額 | 回数 | 支払タイプ | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 90年1月1日 | 20,000ドル | 5 | 年金 | 94年1月1日 |
| 95年1月1日 | 5,000ドル | 1 |
支払計画の現在値は86,501.92です。
CDI Technologyでは、チップ製造設備のリースに資金を融通する目的で18,000ドルが積み立てられています。CDIには4年間の設備リースが必要です。現在、資金は半年複利で10%の金利が得られる口座に預金されています。今日(90年1月1日)から6か月後に初回の支払となるリースを即時に開始することを希望しています。最終回の支払まで資金が尽きることなく今後4年間にわたって半年ごとにリース支払を履行できる最大額を考えます。
| 支払計画 | チップ価額 |
| 通貨 | USD |
| 現在値 | 18,000ドル |
| リース(開始)日 | 90年1月1日 |
| 利率 | .10 |
| 複利頻度 | 半期 |
| 開始日 | 支払金額 | 回数 | 支払タイプ | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 90年7月1日 | 2,784.99 | 8 | 年金 | 94年1月1日 |
Oracle Assetsで現在値が計算された後は、「リース支払」ウィンドウの「償却の表示」ボタンを選択して予測の償却計画を作成できます。この例では、支払計画の現在値は、18,000ドルになります。リースで支払われる総額は、22,279.22ドルです。4,279.92ドルの差異は、リース期間全体で認識される支払利息を表します。この例を次の表に示します。
| 開始日 | 支払額 | 支払に占める利息(10%/年)部分 | 元本の控除 | リース債務負担 |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | ||
| 90年1月1日 | 18,000.00 | |||
| 90年7月1日 | 2,784.99 | 900.00 | 1,884.99 | 16,115.01 |
| 91年1月1日 | 2,784.99 | 805.75 | 1,979.24 | 14,135.77 |
| 91年7月1日 | 2,784.99 | 706.79 | 2,078.20 | 12,057.57 |
| 92年1月1日 | 2,784.99 | 602.88 | 2,182.11 | 9,875.46 |
| 92年7月1日 | 2,784.99 | 493.77 | 2,291.22 | 7,584.24 |
| 93年1月1日 | 2,784.99 | 379.21 | 2,405.78 | 5,178.46 |
| 93年7月1日 | 2,784.99 | 258.92 | 2,526.07 | 2,652.39 |
| 94年1月1日 | 2,784.99 | 132.60 | 2,652.39 | 0 |
| 合計: | 22,279.92 | 4,279.92 | 18,000.00 | 0 |
(a)時間が経過していないために金利が発生しない90年1月1日の支払以外は、前期間のリース債務負担に期間ごとの利率(この例では10%/2=5%)を乗じた金額
(b)(a)を差し引いた支払金額
(c)前期間の金額(c)から現期間の金額(b)を差し引いた金額
関連項目
「リース詳細」ウィンドウおよび「リース支払」ウィンドウを使用して、次のタスクを実行します。
リースの入力
支払計画の入力
償却計画の作成
新規リースを定義するには、「リース詳細」ウィンドウおよび「リース支払」ウィンドウを使用します。使用中のリースの更新または削除は実行できません。
リースを資産計上し、割り当てた資産を償却するかどうかを判断するために、Oracle Assetsでリースをテストする場合は、「リース詳細」ウィンドウの「資産計上テスト」リージョンに情報を入力します。リースの支払計画をすでに定義している場合は、「リース詳細」ウィンドウで支払計画をリースに添付します。定義していない場合は、「リース支払」ウィンドウにナビゲートして、支払計画を定義し、リース支払の現在値を計算できます。資産計上リース資産が償却され、オペレーティング・リース資産が費用処理されます。次のいずれかの基準を満たす場合は、リース資産の資産計上と減価償却が処理されます。
テスト1: リース終了時点で賃借人への資産所有の振替がある
テスト2: 割安購入選択権が存在する
テスト3: 賃貸借契約期間がリース資産の経済的耐用期間の75%を超える
テスト4: リース開始時点での最低リース支払額の現在値が資産の公正市場価格の90%を超える
詳細追加処理を使用してリース資産を追加する場合は、事前に定義したリースに資産を追加できます。同じリースに複数の資産を割り当てることができます。
指定された一連のリース支払の現在値をOracle Assetsで計算する際に使用する情報を入力したり、代替リース体系を分析するには、「リース支払」ウィンドウを使用します。支払計画を保存した後は、「リース詳細」ウィンドウで定義したリースに支払計画を添付できます。
リース契約のインプリシット実効金利に基づいて、利息と元本間に資産型リースの支払を配賦する償却計画を作成します。
「リース詳細」ウィンドウをオープンします。
リース番号および摘要を入力します。
賃貸人を入力します。
賃貸人サイトを入力します。賃貸人サイトとは支払の送付先所在地です。このフィールドは、Oracle Payablesへのリース支払のエクスポートを計画している場合は必須です。
「資産計上」または「オペレーティング」のリース・タイプを選択します。このリリースに対して資産計上テストをすでに実行した場合は、このフィールドを使用して、テストの判定フィールドに表示されたテスト結果を手動で上書きできます。Oracle Payablesへの自動リース支払を設定できるのは、資産計上リースのみです。
このリースに添付する計画を事前定義の支払計画のリストから選択するか、このフィールドを空白のままにし、「支払計画」ボタンを選択して、このリースの計画を定義できます。関連項目: 支払計画を定義する手順
リース開始日以降に既存のリース支払を変更する場合は、新規リースを入力するか、個別の支払明細を手動で修正して既存のリースを変更する必要があります。
支払勘定を入力します。このフィールドは、Oracle Payablesへのリース支払のエクスポートを計画している場合は必須です。
支払勘定を入力するには、事前に賃貸人サイトを入力しておく必要があります。これは、賃貸人サイトによって営業単位が決まり、それによって勘定科目体系が決まるためです。
必要に応じて支払条件を入力します。
注意: Oracle Payablesで即時支払条件を設定し、Oracle Assetsのリース支払のエクスポート機能を使用するリースに対し、その即時支払条件を適用することをお薦めします。支払条件を設定しなかった場合は、Oracle Payablesによって、賃貸人サイトに関連付けられている支払条件がデフォルト設定されます。その結果、支払が遅れて発行される可能性があります。関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の支払条件に関する項
このリースに使用している通貨を入力します。
このリースの資産計上についてテストする場合は、次の情報を「資産計上テスト」リージョンに入力します。
リース終了時に資産の所有を賃借人に振り替える場合は、「所有の振替」を選択します。
このリースに割安購入選択権が含まれている場合は、「割安購入選択権」を選択します。
リース資産の賃貸借契約期間および資産耐用期間を月数で入力します。「基準適合」チェック・ボックスは、賃貸借契約期間がリース資産の経済的耐用期間の75%を超えるかどうかを示します。
リース資産の公正値を入力します。
リース資産の現在値をOracle Assets外部で事前に計算してある場合は、必要に応じてリース資産の現在値を入力します。値を入力しなかった場合は、リースの支払計画を選択したときに、このフィールドに値が自動的に移入されます。「基準適合」チェック・ボックスは、最低リース支払額の現在値が公正市場価格の90%を超えるかどうかを示します。
このリースの支払計画を定義する必要がある場合は、「支払計画」ボタンを選択します。関連項目: 支払計画を定義する手順
テストの判定フィールドに資産計上テストの結果が表示されます。リースが資産計上に適格な場合は、「資産計上の取得価額」フィールドに、資産の公正値と最低リース支払額の現在値のいずれか少ない額が自動的に移入されます。また、この金額は、資産取得を実行する際に「資産台帳」ウィンドウに資産の取得価額として表示されます。
作業内容を保存するには、「完了」を選択します。
「リース詳細」ウィンドウで新規リースを定義している場合は、「支払計画」ボタンを選択します。あるいは、ナビゲータ・ウィンドウから「リース支払」ウィンドウを直接オープンします。
リース開始日を入力します。この日付は、月の初日と一致する必要があります。
利率を入力します。利率は、賃借人の限界借入利率とリース契約のインプリシット金利のいずれか低い利率になります。
この支払計画に使用している通貨を入力します。
使用する複利頻度を入力します。年金イベントの場合は、「月次」、「四半期」、「半期」または「年次」の支払期間を選択します。
複利頻度を変更すると、各支払明細の終了日が自動的に再計算されます。開始日は変更されません。
支払計画について1つ以上の支払明細を入力します。一括リース支払と年金(一連の均等リース支払)のあらゆる組合せを入力できます。
開始日: この支払の日付を入力します。支払日には月の初日を指定する必要があります。
金額: 各リース支払の金額を入力します。
支払明細の金額については、このフィールドを空白のままにしておき、Oracle Assetsで金額が計算されるようにできます。このフィールドを空白のままにする場合は、「現在値」フィールドに支払計画の現在値を指定する必要があります。
回数: このイベントの一環として履行する支払回数を入力します。
支払タイプ: 「年金」、「最終支払」、「割安購入選択権」または「割安更改オプション」の支払タイプを選択します。
終了日: 入力した複利頻度、開始日および支払回数から終了日が決まります。
支払計画を定義した後、「計算」ボタンを選択します。入力した支払明細の現在値が計算されます。
支払計画を保存して「リース詳細」ウィンドウに戻り、支払計画をリースに添付します。支払計画をリースに添付した後に、支払計画を変更することはできません。
作業内容を保存します。
リース支払計画を計算した後は、「償却の表示」ボタンを選択してリースの償却計画を作成します。最低リース支払額の現在値とリースで支払う総額との差異は、資産の使用期間全体で認識される支払利息を表します。
Oracle Assetsを使用して、リース支払をOracle Payablesに自動的に送信できます。そのためには、「リース支払をPayablesへエクスポート」ウィンドウでOracle Payablesに送信するリース支払明細を選択し、「エクスポート」を選択して「リース支払をPayablesへエクスポート」コンカレント処理を実行します。「リース支払をPayablesへエクスポート」処理によって、Oracle Payablesインタフェース表AP_INVOICES_INTERFACEおよびAP_INVOICE_LINES_INTERFACEに、リース支払データがインポートされます。
Oracle Payablesへのエクスポートでは、すべてのリース支払明細をエクスポートするか、特定のリース支払明細のみをエクスポートするかを選択するオプションがあります。たとえば、最初の2か月分を支払うが、最終支払は別のパーティが支払う場合は、Oracle Payablesで処理するリース支払明細のみを選択できます。
ナビゲータ・ウィンドウから「設定」 > 「資産システム」 > 「リース」 > 「Payablesへのリース支払」を選択します。
Oracle Payablesにエクスポートするリース支払を問い合せます。
「リース支払をPayablesへエクスポート」ウィンドウで、Oracle Payablesにエクスポートする各リース支払に対応する「エクスポート」チェック・ボックスを選択します。「エクスポート」チェック・ボックスを選択すると、「ステータス」フィールドは「転記」に更新されます。「エクスポート」チェック・ボックスの選択を解除すると、「ステータス」フィールドは「新規」に再設定されます。すべてのリース支払を選択するには、「編集」メニューから「全て選択」を選択します。リース支払を誤って選択した場合は、「編集」メニューから「全て選択解除」を選択します。
支払期日、支払金額、リース番号および賃貸人の名称を確認します。
賃貸人サイトを入力、確認または変更します。Oracle Payablesにリース支払をエクスポートするには、賃貸人サイトが必要です。
請求書番号を確認または変更します。Oracle Payablesにリース支払をエクスポートするには、請求書番号が必要です。
支払勘定を入力、確認または変更します。Oracle Payablesにリース支払をエクスポートするには、支払勘定が必要です。
必要に応じて支払条件を入力または変更します。
注意: Oracle Payablesで即時支払条件を設定し、Oracle Assetsのリース支払のエクスポート機能を使用するリースに対し、その即時支払条件を適用することをお薦めします。支払条件を設定しなかった場合は、Oracle Payablesによって、賃貸人サイトに関連付けられている支払条件がデフォルト設定されます。その結果、支払が遅れて発行される可能性があります。関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の支払条件に関する項
必要に応じて「計画の表示」を選択し、償却計画を表示します。
注意: 償却計画は、「リース支払をPayablesへエクスポート」ウィンドウでは変更できません。
必要に応じて「保存」を選択し、明細をOracle Payablesにエクスポートせずに変更内容を保存します。
支払明細をOracle Payablesに送信する準備が整った場合は、「エクスポート」を選択し、Oracle Payablesインタフェース表AP_INVOICES_INTERFACEおよびAP_INVOICE_LINES_INTERFACEを移入します。
関連項目
製造業者および仕入先保証書の摘要情報の定義と追跡を実行できます。保証情報は「資産保証」ウィンドウで定義します。「資産詳細」ウィンドウでは、事前に定義した保証に対して資産を割り当てます。同じ保証に資産をいくつでも割り当てることができます。資産が割り当てられている保証は更新または削除できません。資産は、いつでも異なる保証に割り当てることができます。
「資産保証」ウィンドウにナビゲートします。
一意の保証番号と保証の摘要を入力します。
必要に応じて開始日と終了日を入力します。一方の日付を入力した場合は、もう一方の日付も入力する必要があります。開始日と終了日を指定した場合、この保証に割り当てる資産には、ここで指定した開始日から終了日の範囲内の事業供用日が必要です。
通貨コードを入力します。保証の通貨コードは、保証に割り当てる資産と同じ通貨コードであることが必要です。
0(ゼロ)以上の取得価額を入力します。
保証を更改可能にする場合は、「更新可能」チェック・ボックスを選択します。デフォルトでは、「更新可能」チェック・ボックスの選択は解除されています。終了日を指定していない場合は、「更新可能」チェック・ボックスが使用不可になります。
必要に応じて従業員情報を入力します。
仕入先情報を入力します。
作業内容を保存します。
「資産の検索」ウィンドウにナビゲートします。
保証に割り当てる資産を問い合せます。
「資産詳細」ウィンドウで、事前に定義した保証番号を入力するか、値リストから保証番号を選択します。
作業内容を保存します。
Oracle Assetsには、資産に対する保険価額や保険に関するその他の情報を管理する際に役立つウィンドウとレポートが用意されています。資産の保険情報を表示して情報を入力したり、複数の種類の保険を資産に割り当てることができます。資産保険情報には、保険カテゴリ、現行保険価額、および保険価額に影響するオプションの更新情報(取得、除・売却など)が含まれます。
Oracle Assetsでは、3種類の方法を使用して資産の保険価額を計算します。
新規値 - この方法では、取得価額または生産原価に基づいて資産の基準保険価額が計算されます。この価額にその年の物価指数を適用して、現行保険価額を提供します。資産価額に影響する取引の物価スライド価額を組み込むこともできます。
市価 - この方法では、資産の現行市価が計算されます。資産の純帳簿価額、組み込まれている物価スライド・ファクタおよび資産価額に影響する取引の物価スライド価額から現行価額が自動的に計算されます。
手動値 - この方法を使用して、資産の保険価額を手動で入力できます。通常は保険会社との合意により入力します。この計算方法を使用して、資産保険価額に更新情報を手動で入力することもできます。資産の保守日(オプション)を入力すると、現行保険価額のみが自動的に更新されます。
資産の一部を除・売却すると、保険計算処理によって、部分除・売却に対して取得価額が減額される割合と同じ割合で資産の保険価額が減額されます。
スイスの商習慣では、特定の種類の資産(建物など)を対象として、保険会社で保険価額が再査定され、手動で再定義される場合があります。その後、保険価額の物価スライドは、この時点から再開されます。自動計算された保険価額に対する手動更新は、スイスでのこのような特別な資産のみを対象として許可されます。その場合は、「資産保険」ウィンドウでフラグを設定する必要があります。
Oracle Assetsには、資産保険情報をレビューする2種類のレポートがあります。資産保険データ・レポートには、資産の保険証券データすべてが表示されます。資産保険価額レポートには、保険価額、現行保険価額および保険補償計算が表示されます。
「固定資産保険」ウィンドウを使用して、保険証券情報や計算方法など、資産に関する保険情報を入力します。様々な保険カテゴリについて、資産に対して複数の保険証券を入力できます。ここに入力した保険情報を使用して、資産の現行保険価額が計算されます。
前提条件
Oracle Payablesで仕入先タイプを「保険会社」に設定して仕入先を入力します。
必要に応じて、資産物価指数を設定します。
保険カテゴリ・クイックコード(火災、暴風、盗難など)を設定します。関連項目: 「固定資産保険証券明細」ウィンドウ・リファレンス
危険度区分クイックコードを設定します。関連項目: 「固定資産保険証券明細」ウィンドウ・リファレンス
スイス特別資産(スイスの建物など)を入力する予定がある場合は、プロファイル・オプション「FA: スイス特別資産の許可」を「Yes」に設定します。
「固定資産保険」ウィンドウにナビゲートします。
保険情報を入力する資産を問い合せます。
「保険証券」リージョンで、保険情報(保険証券番号、保険会社など)を入力します。
この資産保険に使用する計算方法として「新規値」、「市価」または「手動値」のいずれかを入力します。
資産がスイス特別資産の場合は、「特別スイス資産」チェック・ボックスを選択します。
「基準指数日」フィールドに、物価スライドの基準日として使用する日付を入力します。
「保険指数」フィールドに、年次修正保険価額の計算に使用する物価指数の名称を入力します。
「基準保険価額」フィールドに、保険証券に定義されている資産の基準保険価額を入力します。
「手動値」計算方法を選択した場合、または資産をスイス特別資産として指定した場合は、現行保険価額を入力します。それ以外の場合は、資産の現行保険価額が自動的に計算され、このフィールドに表示されます。
「保険金額」フィールドに、その保険証券で資産が保険契約されている金額を入力します。
「固定資産保険」ウィンドウで、「明細」ボタンを選択して保険証券明細情報を表示します。
「固定資産保険証券明細」ウィンドウで、保険証券情報(保険証券明細番号、保険カテゴリ、危険区分など)を入力します。
「注釈」フィールドに、その他の注釈を入力します。
作業内容を保存します。
「固定資産保険」ウィンドウで、「保守」ボタンを選択します。
「固定資産保険証券保守」ウィンドウで、変更が必要な情報を更新します。
変更内容を保存します。
資産番号。問い合せた資産の資産番号が表示されます。
摘要。問い合せた資産の摘要が表示されます。
現品票番号。問い合せた資産の現品票番号が表示されます。
資産キー。問い合せた資産の資産キーが表示されます。
資産台帳問い合せた資産の資産減価償却台帳が表示されます。
保険証券番号。保険証券番号を入力します。
保険会社。有効な保険会社名を入力します。このフィールドの値リストには、Oracle Payablesで仕入先タイプを「保険会社」に設定した仕入先のみが表示されます。
仕入先サイト。保険会社の仕入先サイトを入力します。
所在地。仕入先サイトの会社所在地が自動的に表示されます。
計算方法。この資産保険に使用する計算方法を入力します。
新規値 - 基準保険価額。毎年物価スライドされます。
市価 - 現行市価。基準保険価額から減価償却分を差し引いて計算されます。毎年物価スライドされます。
手動値 - 手動で入力した価額。この計算方法を使用する場合は「現行価額」フィールドが更新可能になります。
注意: 既存の保険レコードと同じ保険証券番号と保険会社を使用して別の資産が補償されるように、重複する保険証券を入力すると、計算方法は、既存の保険証券に定義されている方法に自動的にデフォルト設定されます。同じ保険証券でのすべての発生事項には、同一の計算方法が使用される必要があります。
特別スイス資産。資産がスイス特別資産の場合は、「特別スイス資産」チェック・ボックスを選択します。プロファイル・オプション「FA: スイス特別資産の許可」が「Yes」に設定されていない場合は、このフィールドを使用できません。関連項目: Oracle Assetsのユーザー・プロファイル
資産がスイス特別資産として設定されている場合は、保険会社による保険価額の再査定が反映されるように、資産の現行保険価額、保険指数および基準指数日を更新できます。
資産に適用するための一連の新しい物価スライド・ファクタが保険会社から提供されることがあります。提供された情報は、新しい物価指数を定義して「保険指数」フィールドを更新することで記録できます。
「現行価額」フィールドを更新し、この新しい評価の有効日を「基準指数日」フィールドに記録することで、保険会社から提供された新しい保険価額を記録します。「基準指数日」に将来の日付を設定した場合は、その日付になるまで保険価額が再び物価スライドされることはありません。この日付までの期間は、資産の手動保守期間を表します。この期間中の資産価額に影響する修正または除・売却は、自動保険計算が再開する際に新しい保険価額には組み込まれません。
基準指数日。物価指数の基準日として使用する日付を入力します。基準指数日は、次のいずれかであることが必要です。
新規資産の場合は、資産の事業供用日を入力します。
中古で購入した資産の場合は、資産の当初の建設日を入力します。
計算方法が「手動値」の場合は、保守日を入力します。これは、手動値によるオプションの物価スライドが開始する日付を表します。
スイス資産の更新の場合は、保険価額の自動物価スライドを再開する日付を記録します。この日付になるまでは、保険価額を手動で保守する必要があります。
保険指数。年次修正済の保険価額の計算に使用する物価指数の名称を入力します。保険計算処理で取得価額修正、除・売却などが自動的に計上されるようにし、物価スライド修正ファクタを使用しない場合は、「基準指数日」フィールドに値を入力します。保険指数は入力しないでください。
基準保険価額。資産の基準保険価額を保険証券に定義されているとおりに入力します。次のいずれかを入力します。
新規資産については、資産の現行取得価額が表示されます。この新規資産の計算方法が「新規値」の場合は、このデフォルト価額を別の価額で上書きできます。資産の計算方法が「市価」の場合は、このフィールドに表示される価額は変更できません。この資産保険計算では基準保険価額は使用されないため、かわりに、資産の純帳簿価額から保険価額が導出されます。資産の計算方法が「手動値」の場合は、基準保険価額を使用せずに現行価額を手動で入力するため、「基準保険価額」フィールドは使用不可になります。
中古で購入した資産については、資産の当初の建設価額を入力します。
現行価額。「手動値」計算方法を選択していない場合および資産がスイス特別資産として指定されていない場合は、自動的に計算された資産の現行保険価額がこのフィールドに表示されます。
価額は、次のように計算方法に従って表示されます。
「新規値」方法の場合は、物価スライド方式の基準保険価額が表示されます。この価額は、資産価額に影響する取引(修正、除・売却など)が計上される際も更新されます。
「市価」方法の場合は、物価スライド方式の資産の純帳簿価額(当初取得価額から減価償却分を差し引いた価額)が表示されます。この価額は、資産価額に影響する取引(修正、除・売却など)が計上される際も更新されます。
「手動値」方法の場合は、表示された価額を更新できます。「基準指数日」フィールドに資産の保守日を入力した場合は、この日付で手動価額の物価スライドが開始され、その後は「新規値」計算方法の場合と同様になります。
「新規値」計算方法が指定されているスイス資産の場合は、他のすべての資産の場合と同様に計算された値が表示されます。「市価」計算方法が指定されているスイス資産の場合は、「新規値」計算方法に従って保険価額が計算された後、この価額が資産の耐用期間全体に対する残り耐用期間の割合(残り耐用期間 / 耐用期間全体)を使用して修正され、「現行価額」フィールドに表示されます。スイス資産の場合は、計算された現行価額を手動で更新することもできます。
保険金額。その保険証券で資産が保険契約されている金額を入力します。このフィールドは、情報を提供することが目的であり、Oracle Assetsでの計算には使用されません。
最終物価スライド日。このフィールドには、物価スライド処理が最後に実行されたクローズ済償却期間の最終日が表示されます。
保守。「保守」ボタンを使用して、「固定資産保険証券保守」ウィンドウを起動します。
明細。「明細」ボタンを使用して、「固定資産保険証券明細」ウィンドウを起動します。
関連項目
明細。保険証券で補償される保険カテゴリの保険証券明細番号を入力します。保険証券番号と保険証券明細番号の組合せは一意であることが必要です。同じ保険証券で多数の資産を補償する複数の発生事項がある場合も、同一の保険証券に対して重複する明細番号は入力できません。
保険カテゴリ。保険カテゴリを入力します。資産が複数の保険証券で補償される場合も、資産が保険契約できるのは保険の各カテゴリごとに1つのみです。参照タイプFA_INS_CATEGORYの保険カテゴリ参照値を事前に定義しておく必要があります(アプリケーション開発者: 「アプリケーション」 > 「検証」 > 「クイックコード」 > 「特別」)。
危険度区分。この保険証券明細に割り当てる危険度区分を入力します。参照タイプFA_INS_HAZARDの危険度区分参照値を事前に定義しておく必要があります(アプリケーション開発者: 「アプリケーション」 > 「検証」 > 「クイックコード」 > 「特別」)。
注釈。「注釈」フィールドには追加注釈を入力します。
関連項目
「固定資産保険証券保守」ウィンドウを使用して、複数の資産を補償する保険証券について情報を更新します。「固定資産保険証券保守」ウィンドウでの保険証券情報の変更は、その保険証券によって補償されるすべての資産に適用されます。
保険証券番号。このフィールドは、現行の保険証券レコードの保険証券番号にデフォルト設定されます。この保険証券の保険会社および仕入先サイトを更新できます。この保険証券によって補償される資産に対して自動保険計算ルーチンが実行されていない場合は、計算方法も更新できます。
保険会社。このフィールドには、保険証券番号に対する現在の保険会社が表示されます。このウィンドウでは、保険会社を更新できます。
仕入先サイト。このフィールドには、保険証券番号に対する現在の仕入先サイトが表示されます。このウィンドウでは、この保険証券に対する仕入先サイトを更新できます。
計算方法。このフィールドには、保険証券番号に対する現在の計算方法が表示されます。この保険証券によって補償される資産に対して自動保険計算ルーチンが実行されていない場合は、このウィンドウから計算方法を更新できます。
関連項目
資産の現行保険価額を自動的に更新するには、「保険計算ルーチン」プログラムを使用します。「保険計算ルーチン」プログラムでは、物価スライド・ファクタや資産価額に影響する取引(取得価額修正、除・売却など)が考慮されます。
通常は、「保険計算ルーチン」プログラムを年ベースで実行し、すべての資産保険価額を更新する必要があります。
1年を通してプログラムを実行すると、その年の最後にクローズした期間の期末(つまり、減価償却が実行された最終期間)まで計算処理が実行されます。最終実行日以降に新規の取得価額修正、除・売却または再稼働が組み込まれた場合は、その年のさらに後の時点で処理を再実行できます。最終実行日以降にファクタが変更された場合、再実行では新規物価スライド・ファクタが使用されます。
「保険計算ルーチン」プログラムでは出力は生成されません。プログラムが終了すると、選択したすべての資産の保険価額が更新されます。新しい保険価額は、「資産保険」ウィンドウで、または資産保険価額レポートを実行して検証できます。関連項目: 保険価額詳細レポート
前提条件
「資産保険」ウィンドウを使用して、保険証券の詳細を設定します。関連項目: 資産保険の概要
処理を実行している年の少なくとも1つの期間に対して減価償却を実行します。関連項目: 減価償却の実行
処理を実行している年の物価スライド・ファクタを設定します。その年の物価スライド・ファクタを定義しなかった場合は、使用可能な物価スライド・ファクタの中で最新のファクタが使用されます。関連項目: 物価指数の定義
「資産」 > 「保険」 > 「保険計算ルーチン」の順にナビゲートし、「要求の発行」ウィンドウをオープンします。
関連項目: 『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の要求の発行に関する項
「パラメータ」ウィンドウで、減価償却台帳を入力します。
レポートの会計年度を入力します。
減価償却期間のすべてがクローズしていない年度に対して処理を実行すると、年度内の最後にクローズした期間の期末まで処理が実行されます。保険計算処理を実行する前に、処理を実行する年の少なくとも1つの期間に対して減価償却が実行されている必要があります。現在オープンしている年度より前の数年間を対象として処理を実行することはできません。
必要に応じて保険会社を入力します。
値を入力しなかった場合は、すべての保険会社について保険契約されている資産がレポートの対象となります。このフィールドの値リストには、Oracle Payablesで仕入先タイプを「保険会社」に設定した仕入先が表示されます。
必要に応じて資産番号の範囲を入力します。
Oracle Assetsには、保険情報の監視に役立つ2種類のレポートが用意されています。
資産の保険の詳細を検討し、保険レコードの割当が正しいことを確認するには、「保険データ・レポート」を使用します。「保険データ・レポート」には、選択した資産のすべての保険詳細が印刷されます。
選択した資産の保険でカバーされる金額の計算を検討するには、「保険価額詳細レポート」を使用します。「保険価額詳細レポート」には、選択した資産の全保険金額が印刷され、「貸借一致セグメント」レベル、「保険計算方法」レベル、「保険会社」レベルおよび「保険証券番号」レベルでの合計が表示されます。保険でカバーされる金額の計算では、保険金額と現在の保険価額の差異が示されます。
関連項目