リリース12
E05999-01
目次
前へ
次へ
| Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド リリース12 E05999-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
連結は、連結元の財務結果を連結先会社と結合して、単一の結合された財務結果諸表を作成する期末プロセスです。グローバル連結システム(GCS)には、会社の構成に関係なく連結ニーズを管理するのに役立つ柔軟性があります。
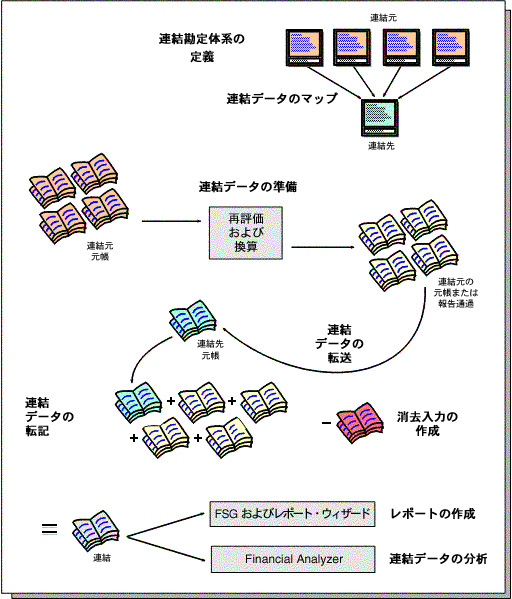
グローバル連結システム(GCS)の柔軟性により、会社の構成に合せて財務情報を管理できます。会計構造が同じかどうかに関係なく、複数の会社を保守し、その結果を連結して財務レポートを作成できます。予算残高と実績残高を連結できます。
注意: 会社が業務会計のために単一元帳を共有している場合、GCSを使用する必要はありません。「財務諸表生成プログラム」(FSG)を使用して連結財務レポートを作成できます。
組織に次のいずれかが当てはまる場合は、GCSを使用してください。
会社に異なる勘定体系が必要な場合。たとえば、ある会社が6つのセグメント勘定体系を必要とし、別の会社が4つのセグメント勘定体系のみを必要としている場合。
会社が異なる会計カレンダを使用している場合。たとえば、ある会社が週次カレンダを使用し、別の会社が月次カレンダを使用している場合。
独自の各国通貨の使用を必要とする国で、会社が運営されている場合。
注意: 平均日次残高が使用可能に設定されている元帳間で平均残高を連結する場合は、連結先元帳の「平均残高連結使用可」オプションを使用可能にしておく必要があります。関連項目: 元帳の定義
Oracle Applicationsで連結結果を得るために使用できる方法は2つあります。
レポート連結: 単一の元帳に格納されているデータの連結または同じアプリケーション・インスタンス上の異なる元帳間でのデータの合計を行うFSGレポートを定義します。
データ転送連結: 複数元帳または複数のアプリケーション・インスタンスを持つグローバル企業を処理します。データ転送連結では、財務データを多様な元帳とデータ・ソースから単一連結元帳に転送します。この連結元帳から、連結財務情報をレポートおよび分析できます。
実績と同様に、予算金額を1度に1つの期間に連結できます。同じカレンダ期間または開始/終了期間(あるいはその両方)を共有していない予算を連結することもできます。予算残高の連結には、次の制限が適用されます。
ソース予算とターゲット予算が同じカレンダを共有していない場合、特定の期間を特定の期間に連結する必要があります。
ソース予算とターゲット予算が同じ開始期間を共有していない場合、特定の期間を特定の期間に連結する必要があります。
ソース予算とターゲット予算が同じカレンダと開始期間を共有している場合、すべての期間または特定の期間を特定の期間に連結できます。
GCSを使用すれば、どんなビジネス分野でも、任意の詳細レベルで任意の観点から連結することができます。
任意の連結元: 勘定元帳、データベース、Oracle Applicationsおよび非Oracle applicationsを含む任意の連結元からのデータをGCSで連結できます。Oracle Applicationsでは、クロス・インスタンス・データ転送を使用して、リモート・インスタンスの連結先に、連結データを転送します。非Oracle Applicationsでは、カスタマイズ可能なスプレッドシート・フロントエンドまたはオープン連結インタフェースを使用して、データをGCSにアップロードします。
任意の勘定体系: 連結元は、連結先から独立した勘定体系を使用して、固有の運用会計処理に対処し、国内の法定要件を満たすことができます。GCSを使用すると、多様な勘定体系間を連結できます。
任意のカレンダ: 連結元は、連結先と異なる会計カレンダを使用できます。GCSを使用すると、カレンダ間を連結できます。
任意の通貨: 連結元は、連結先の元帳通貨とは異なる元帳通貨を使用できます。GCSは、すべての連結元残高を再評価および換算し、一貫した連結結果を保証します。
詳細レベル: 詳細取引、詳細残高および要約残高を連結します。
連結元帳の詳細情報にアクセスし、連結残高に対して増分更新を実行できるようにする必要がある場合は、取引を連結します。
選択した勘定科目のみの勘定科目詳細の振替を行うには、残高を連結します。
集計勘定残高のみを連結元帳に振り替える場合は、要約残高を連結します。この方法では、必要なリソースが比較的少ないため、処理パフォーマンスが向上します。
残高タイプ: 実績残高、平均残高、換算済残高、予算残高および統計残高含む、任意の残高タイプを連結します。
平均残高を連結する場合は、ダブル・カウントを防ぐために、現期間で前期間の連結を逆仕訳する必要があります。期間平均残高は、期間ごとの単独の残高を表し、同じ期間内の各日の残高は同じです。逆仕訳の調整を加えない場合、前期間の平均残高が現期間の平均残高に誤って含まれることになります。
たとえば、1月1日および2月1日に対して、PATD残高を使用して期間平均連結を実行するとします。1月1日を連結した後、2月1日を連結する前に、2月1日時点での1月1日のPATD平均連結仕訳を逆仕訳する必要があります。これによって、2月1日のPATD残高は0に設定されます。次に、2月1日に対してPATD平均連結を実行できます。
QATD連結およびYATD連結でも、同じ逆仕訳調整が必要です。現在の連結を実行する前に、現在の四半期の初日に前四半期のQATD平均連結を逆仕訳する必要があります。YATD平均連結では、現在の連結を実行する前に、現在の年度の初日に前年のYATD平均連結を逆仕訳する必要があります。
各期間に対してPATD平均連結を実行すると、QATDおよびYATD平均連結残高が自動的に使用可能になります。この方法で正しいQATDおよびYATD残高を検討するには、四半期または年度の末日の日付を選択する必要があります。範囲内の他のすべての日付の場合、残高は不正確になります。
選択する連結は、グローバル会計処理の要件を満たすために使用する元帳の数によって異なります。
元帳には、元帳通貨、会計カレンダ、勘定体系および会計処理基準という4つの構成要素が含まれています。
すべての子会社が親会社と同じ元帳を共有している場合、または同じ勘定体系およびカレンダを共有していて同じアプリケーション・インスタンスに常駐する場合は、「財務諸表生成プログラム」レポート・エンジンを使用して財務結果を連結できます。
複数元帳を使用した会計処理には、次のようなシナリオがあります。
単一アプリケーション・インスタンス
複数アプリケーション・インスタンス
連結元が独自の元帳を使用している場合は、グローバル連結システムを使用してデータ転送連結を実行し、連結プロセスを管理する必要があります。
連結元が、別個のインスタンスで、Oracle Applicationsおよび異なる元帳を使用して会計処理を管理している場合は、グローバル連結システムを使用して連結データを転送し、連結処理を管理できます。これは、クロス・インスタンス・データ転送を使用して、社内イントラネットを通じて行います。関連項目: Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
注意: 一部の連結元が、非Oracle Applicationsを使用して会計を管理している場合は、Interface Data Transformer、Applications Desktop IntegratorまたはSQL Loaderを使用して連結データをインポートできます。関連項目: 非Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
すべての会社は、財務結果を連結するために共通の連結手順を完了する必要があります。次の表に、各連結実装オプションの詳細を示します。
| 連結手順 | レポートのみ (単一元帳) | データ転送 (複数元帳)単一インスタンス | データ転送 (複数元帳)複数インスタンス |
|---|---|---|---|
| 1. 元帳の定義 | すべての連結元が単一元帳を共有し、各元帳に同じ勘定体系、会計カレンダ、通貨および会計処理基準を使用します。 報告通貨用に連結先の勘定体系とカレンダを共有する連結元に対して、レポート連結を実行することもできます。 | 複数の子会社と親会社を共通の勘定体系、会計カレンダおよび通貨に連結する場合は、これらの会社で同じ元帳を共有できます。子会社と親会社は、異なる貸借一致セグメント値を使用して個別IDを保持できます。 または、各子会社と親会社は、業務会計またはローカル会計のニーズを満たすために独自の元帳を使用することもできます。 | 単一インスタンスと同じ。 また、他のOracle Applicationインスタンスからのデータ転送の場合は、ターゲットの連結先元帳と同じ通貨、カレンダおよび勘定体系を共有するソース・インスタンス上で元帳を作成します。 |
| 2. 連結元データの準備 | 外貨残高を再評価します。オプションで、レポート作成のために元帳通貨金額を外貨に換算します。 | 外貨残高を再評価します。必要な場合は、残高を連結先に転送する前に、勘定残高を連結先の元帳通貨に換算します。注意: 仕訳または補助元帳レベルの報告通貨を使用する場合は、連結元の報告通貨から連結先元帳に直接連結することで換算ステップをバイパスできる場合があります。関連項目: 連結元データの準備 | 単一インスタンスと同じ。 |
| 3. 連結および勘定体系マッピングの作成 | 処理は不要。 勘定科目マッピングは勘定体系に暗黙指定されています。 | 必須。 独自の元帳を使用している連結元については、連結元の勘定科目値を連結後の連結先の値にマップする連結定義および勘定体系マッピングを作成して、連結元残高を連結先に積み上げる方法を決定します。 | 単一インスタンスと同じ。 |
| 4. データの転送 | 処理は不要。 すべての連結元の取引と残高は、すでに同じ元帳で保守されています。 | 必須。 Oracle以外のシステムにデータを格納している連結元については、インタフェース・データ・トランスフォーマ、Application Desktop IntegratorまたはSQL*Loaderを使用して、データを連結先元帳(データが連結先元帳と同じ通貨建ての場合)または連結元元帳に直接インポートできます。独自の元帳を使用している連結元については、連結データ転送プログラムを実行して、連結元から連結先元帳に残高または取引を転送します。転送ごとに、連結先元帳に連結仕訳が作成されます。注意: 連結仕訳を自動的にインポートして転記するように、連結実行オプションを変更できます。 | 必須。 単一インスタンスと同じ。さらに、「データベースリンク」ウィンドウを使用して、連結先データベース・インスタンスへのデータベース・リンクを定義します。「連結データの転送」または「連結データ・セットの転送」ウィンドウで、「実行オプション」ウィンドウを使用してリモート・インスタンス・サインオン・パラメータを入力および検証します。 |
| 5. 残高の消去 | 自動会社間消去機能を使用して、消去セットを生成します。算式ベースの消去の場合は、定型仕訳も使用できます。 | レポートのみの方法と同じ。 | レポートのみの方法と同じ。 |
| 6. レポート | 連結元を合算して連結結果を生成するためのメカニズムとして「財務諸表生成プログラム」(FSG)を使用します。 Application Desktop Integrator(ADI)を使用して、レポートをスプレッドシート環境に拡張します。ADIを使用すると、連結レポートをHTML形式で作成し、インターネットまたは社内イントラネットに公開できます。 | FSGレポートを使用して連結結果レポートを作成します。 Application Desktop Integrator(ADI)を使用して、レポートをスプレッドシート環境に拡張します。ADIを使用すると、連結レポートをHTML形式で作成し、インターネットまたは社内イントラネットに公開できます。 | 単一インスタンスと同じ。 |
| 7. 分析 | 全ドリルダウン機能を使用して、連結残高から連結元の仕訳明細および補助元帳詳細にドリルダウンします。 データをオンライン分析処理(OLAP)アプリケーションであるOracle Financial Analyzerに直接リンクして、連結残高を分析し、経営チームによる業務分析および財務分析の準備を行います。 | GCSを使用すると、連結先元帳の連結残高から同じインスタンス内の連結元元帳へと直接ドリルできます。 連結元の換算残高と当初残高の間でもドリルできます。また、GCSには、要約勘定、詳細勘定および元の仕訳から補助元帳詳細へのドリルダウン機能も用意されています。 | オンライン照会を使用して、必要な勘定科目、仕訳または連結の残高を検討します。Application Desktop IntegratorまたはOracle Financial Analyzerを使用して、データをさらに分析します。同じ方法を連結元元帳インスタンスで使用して、連結元データを分析します。 |
関連項目
連結ワークベンチにより、各連結元の連結ステータスについての情報が供給され続けるとともに、連結元を無制限に連結するための中核管理機能が連結先会社に提供されます。また連結元のデータが連結先元帳にすでに転送された後に発生する連結元のすべての勘定残高の変更も、ワークベンチにより監視されます。
連結ワークベンチにナビゲートすると、「連結プロセス検索」ウィンドウがオープンされます。このウィンドウを使用して、連結および消去プロセスを問い合せます。問合せ結果は、連結ワークベンチに表示されます。フィールドをいくつでも入力して、問合せを限定できます。
注意: 連結ワークベンチから連結または消去を問い合せるには、データ・アクセス・セットによって、連結元元帳または連結先元帳への読取りアクセス権が提供されている必要があります。
連結を問い合せた後に実行する連結元の処理は、定義アクセス・セット権限によって制御されます。たとえば、連結定義に対して表示権限のみが付与されている場合は、ワークベンチから連結データを転送できません。連結に対して使用権限のみが付与されている場合は、ワークベンチから連結定義を表示できません。
連結先: 値リストから連結先を選択します。データ・アクセス・セットによって、その連結先元帳への読取りアクセス権が提供されている必要があります。
連結先期間: 連結期間を入力するか、値リストから選択します。
残高タイプ: 「実績」、「予算」または「全て」から選択します。
注意: 連結先元帳へのアクセス権があるユーザーは、連結元元帳から連結データを表示できます。
準備/振替リージョン
「連結セット」、「連結」、「連結元」および「ステータス」の各フィールドの値リストから選択して、連結元の連結を問い合せます。
消去リージョン
このリージョンの「消去セット」フィールドと「ステータス」フィールドに入力して、消去セットを検索します。
「連結プロセスの検索」ウィンドウを連結ワークベンチとともに使用します。連結仕訳を生成、転記または逆仕訳するときに、「連結プロセスの検索」ウィンドウにナビゲートし、「検索」ボタンを選択して、連結ワークベンチに表示されているデータをリフレッシュします。あるいは、メニュー・バーから「表示」 > 「すべて検索」を選択します。
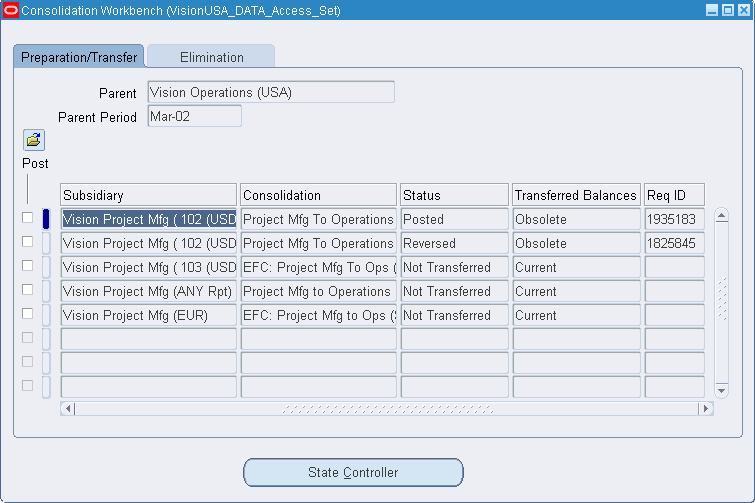
連結ワークベンチは、すべての連結元の活動を監視して、発行する各プロセスのステータスを表示します。次の表に、ステータス列に表示される連結プロセスで可能なステータスをすべてリストします。
| ステータス | 摘要 |
|---|---|
| 仕訳削除 | 連結仕訳は削除された。 |
| インポート済 | 連結仕訳はインポートされた。 |
| インポート失敗 | 連結仕訳のインポートは失敗した。 |
| インポート | 連結仕訳をインポート中。 |
| 転送データなし | 転送する連結元残高がない。 |
| インポート・データなし | インタフェース表にインポート対象のエントリがない。 |
| 振替しない | データは連結元から連結先に振り替えられなかった。 |
| 転記済 | 連結仕訳は正常に転記された。 |
| 転記に失敗 | 連結仕訳は転記に失敗した。 |
| 転記 | 連結仕訳を転記中。 |
| 転記分選択 | 転記する連結仕訳が選択されている。 |
| 逆仕訳済 | 連結仕訳が逆仕訳された。 |
| 振替済 | 連結残高が連結先に振り替えられた。 |
| 転送失敗 | 連結転送処理は失敗した。 |
| 換算 | 連結元残高を振替中。 |
| 転送分選択 | 転送する連結プロセスが選択されている。 |
また、「振替済残高」列には、発行する各連結プロセスについて次のステータスがリストされます。
現行: 連結元から連結先への連結データが現行です。連結が振り替えられる前のステータスは、必ず現行になります。
廃止: 連結元データを連結先に転送した後で、連結元の勘定残高が変更されました。
注意: 特定の連結が、連結元の部分的な勘定科目範囲のみに対するものであっても、連結元でいずれかの勘定科目が更新されると、その連結プロセスのステータスは「古い」になります。
「古い」ステータスにより、連結元残高が、連結先に以前に振り替えられた残高と一致しなくなったことがわかります。オリジナルの連結プロセスを逆仕訳してから、別の連結振替を開始する必要があります。新しい振替のステータスは「現行」になります。
連結元の連結プロセスを逆仕訳すると、次の条件がすべて満たされていれば、そのプロセスの「ステータス」列に「逆仕訳済」と表示されます。
オリジナルの連結仕訳を転記する必要があります。
オリジナルの連結仕訳の逆仕訳を生成する必要があります。
生成された逆仕訳連結仕訳を転記する必要があります。
連結ワークベンチから、連結プロセスをガイドするナビゲーション・ツールである、ステータス制御にアクセスします。
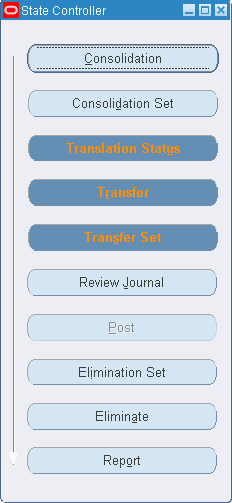
ステータス制御から、実行する連結ステップがすばやく選択できます。ステータス制御のそれぞれのボタンは、次の表にリストするように連結のそれぞれの機能ステップに対応しています。
| 機能ステップ | ステータス制御の各ボタン |
|---|---|
| 連結勘定体系の定義 | なし |
| 連結データのマップ | 連結および連結セット |
| 連結元データの準備 | 換算ステータス |
| データの転送 | 転送および転送セット |
| 連結データの結合 | 仕訳の検討および転記 |
| 消去入力の作成 | 消去および消去セット |
| 連結残高のレポート | レポート |
| 連結データの分析 | なし |
関連項目
「ステータス制御」ボタンを選択すると、書込みの必要がある連結ステップに関するOracle General Ledgerのウィンドウがオープンします。次の項では、連結ステップの機能の概要、連結ステップを完了するために実行する必要がある、「ステータス制御」の関連処理の概略およびそれぞれの処理の詳細なタスクを記載した関連項目について述べます。
連結ステップを完了するためのガイドとして、「ステータス制御」ボタンが3色のうちのいずれか1色で表示されます。
青: 推薦されたステップを表します。
グレー: 推薦されないステップを表します。オプションとして、ボタンが灰色で表示されるかわりに無効化される場合があります。
赤: 警告を表します。たとえば、赤色の「換算ステータス」ボタンは連結元の換算済残高は失効していることを示します。
連結ワークベンチから連結元を選択すると、その連結元に対して実行したステップまたは実行する必要があるステップに基づいて、「ステータス制御」ボタンのラベルの色が変わります。「ステータス制御」ボタンの色は、連結ステップを正常に完了した後、現在ステータスを反映するために変わる場合があります。たとえば、「仕訳の検討」ボタンは連結元データを連結先に転送し、連結仕訳をインポートするまでは灰色です。これらのステップが正常に完了した後は、青色に変わり、連結仕訳の検討が、推奨される現在のステップであることを示します。
連結元と連結先の勘定体系は慎重に計画してください。これは、連結プロセスの簡略化に役立ちます。
連結先元帳に連結する各連結元元帳の連結定義を定義(または必要に応じて変更)するには、「ステータス制御」の「連結」ボタンを選択します。連結定義を定義する際は、連結方法を選択します。実績、平均、換算、予算または統計の各残高を連結できます。連結元の元帳から実績仕訳の取引詳細を連結することもできます。関連項目: 勘定体系のマッピング
注意: 平均残高処理が使用可能な場合は、選択した連結方法によって、連結先が連結元帳になるか、非連結元帳になるかが決定します。
ルールを選択して、勘定科目の各連結元から連結先へのマップ方法を指定します。関連項目: 元帳と異なる勘定体系との連結
(オプション)すべての連結元の連結定義およびマッピングを定義した後は、「ステータス制御」の「連結セット」ボタンを選択して、それらの連結定義を連結セットにグループ化します。連結セットを使用すると、一度に1つの転送ではなく、連結元のグループを同時に転送できるため、連結元データを迅速に転送できます。関連項目: データの転送
元帳のどれかに、外貨による貸借対照表勘定がある場合は、残高を再評価して、換算レート変更による影響を反映します。結果の再評価仕訳を転記します。関連項目: 連結元データの準備
連結元換算の現在のステータスをチェックするには「ステータス制御」の「換算ステータス」ボタンを選択します。元帳通貨が連結先と異なる連結元元帳の勘定残高を換算します。連結先元帳の元帳通貨に換算します。関連項目: 連結元データの準備
連結先元帳の通貨を使用して、各連結元元帳の残高試算表レポートを実行します。このレポートは、連結元から連結先への調整に役立ちます。
連結で使用する連結先元帳の会計期間をオープンします。関連項目: 会計期間のオープンおよびクローズ(『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』)
連結セットを使用した場合、複数の連結元から連結データを同時に転送するには、「ステータス制御」の「転送セット」ボタンを選択します。関連項目: 連結セットの転送
連結セットを使用しなかった場合は、「ステータス制御」の「移動」ボタンを選択して、連結データを転送します。GCSは、未転記の連結仕訳を連結先元帳に作成します。関連項目: 連結先への連結元データの転送
連結データの転送時に監査モードを使用する場合は、連結監査レポートを検討します。
監査モードを使用する場合、連結に関連した監査詳細が不要になった際は、削除するために連結監査レポート・データをパージします。関連項目: 連結監査レポート・データのパージ
注意: Oracle以外のアプリケーションから連結先元帳に連結元データを直接インポートする場合は、その連結元に関するデータの転送は不要です。
未転記の連結仕訳バッチを検討または修正するには、「ステータス制御」の「仕訳の検討」ボタンを選択します。関連項目: 連結元データの転記
連結先元帳に連結バッチを転記するには「ステータス制御」の「転記」ボタンを選択します。関連項目: 連結元データの転記
標準リストと会計レポートを要求するか、FSGレポートを実行して連結結果を検討します。
連結相殺消去のために連結先元帳に、必要な消去仕訳を作成するには、「ステータス制御」の「消去セット」ボタンを選択します。関連項目: 消去入力の作成
「消去」を選択して消去入力を生成します。
消去入力を転記します。連結ワークベンチに、消去ステータスが「消去転記済」として表示されます。
連結済および連結中のレポートを実行するには、「ステータス制御」の「レポート」ボタンを選択します。財務諸表生成プログラムまたはApplications Desktop Integratorのレポート定義ツールを使用して標準レポートを実行し、連結先元帳のカスタム連結レポートを定義することもできます。
関連項目: 財務諸表生成プログラムの概要
関連項目: 『Oracle Applications Desktop Integrationユーザーズ・ガイド』
注意: 各元帳が同じ勘定体系とカレンダを共有し、同一インスタンスにある場合は、同じレポートで複数の元帳についてレポートできます。
監査モードを使用する場合、連結に関連した監査詳細が不要になった際は、削除するために連結監査レポート・データをパージします。関連項目: 連結監査レポート・データのパージ
「勘定科目照会」フォームにナビゲートし、連結残高から連結元残高に直接ドリルします。GCSをOracle運用会計システムの直接連結機能拡張として使用している場合は、補助元帳詳細にさらにドリル・ダウンできます。連結元が連結先会社とは異なる通貨で運営されている場合は、各連結元の換算済残高と入力済残高の間もドリルできます。要約勘定、詳細勘定および完全仕訳明細の間もドリルできます。
連結データを、Oracle Financial Analyzerなどのオンライン分析処理(OLAP)ツールにリンクします。連結レポートを検討および分析し、管理チームに対し、運用分析と財務分析を準備できます。
関連項目
グローバル連結システムを使用すると、企業のイントラネットによって、連結元データをリモート連結先インスタンスに転送できます。オプションで、転送結果のリモート・インスタンスについてユーザーに通知することもできます。また、連結仕訳を自動的にインポートおよび転記することもできます。クロス・インスタンス・データ転送を設定し、中心となる連結データベース・インスタンスの特定のオブジェクトのみにアクセスが制限されたユーザーを設定することで、セキュリティを強化できます。
グローバル連結システムでは、社内イントラネットを通じて、リモート連結先インスタンスへの連結元データの転送がサポートされています。
セキュリティのため、中心となる連結データベース・インスタンスの特定のオブジェクトのみにアクセスが制限されたデータベース・ユーザー名を設定する方法を次に説明します。リモート連結元から中心となる連結データベース・インスタンスへのデータベース・リンクを定義するときに、このデータベース・ユーザー名を使用します。
データベース・ユーザー名を作成するには、次の手順を実行します。
中心となる連結データベース・インスタンスで、システム管理者としてSQL*Plusにログインして、データベース・ユーザー名を作成し、データベース・ユーザー名に次の権限を付与します。
SQL>CONNECT system/manager@target_databasenameSQL>CREATE user IDENTIFIED BY password;SQL>GRANT CREATE SESSION TO user;SQL>GRANT CREATE TABLE TO user;SQL>GRANT CREATE SYNONYM TO user;SQL>COMMIT;SQL>EXIT;中心となる連結データベース・インスタンスで、データベース・ユーザーとしてSQL*Plusにログインして、APPLSYSスキーマのfnd_oracle_userid表のシノニムを作成します。
SQL>CONNECT user/user@target_databasenameSQL>CREATE SYNONYM fnd_oracle_userid FORapplsys.fnd_oracle_userid;SQL>COMMIT;SQL>EXIT;中心となる連結データベース・インスタンスで、APPSユーザーとしてSQL*Plusにログインして、データベース・ユーザー名に次の権限を付与します。
SQL>CONNECT apps/apps@target_databasenameSQL>GRANT EXECUTE ON GL_CI_REMOTE_INVOKE_PKG TO user;SQL>GRANT EXECUTE ON GL_JOURNAL_IMPORT_PKG TO user;SQL>GRANT SELECT ON gl_je_batches TO user;SQL>GRANT SELECT ON fnd_oracle_userid TO user;SQL>COMMIT;SQL>EXIT; リモート連結元データベース・インスタンスで、Oracle ApplicationsユーザーとしてOracle Applicationsにログインし、作成したデータベース・ユーザー名を使用して、中心となる連結データベース・インスタンスへのデータベース・リンクを定義します。
注意: グローバル連結システムのクロス・インスタンス・データ転送機能を使用して、Oracle RDBMS 9iR2以上を実装していないターゲット・データベースに連結データを転送している場合、ターゲット職責にあわせて「MO: 分散環境」プロファイル・オプションを「Yes」、「FND: デバッグ・ログ使用可能」プロファイル・オプションを「No」に設定する必要があります。Oracle RDBMS 9iR2以上を実装していないターゲット・データベースに連結データを転送する場合、転送先インスタンスへの自動インポートおよび仕訳の転記は実行できません。
転送元インスタンスで、「データベース・リンクの定義」ウィンドウを使用して、リモート連結先データベースへのデータベース・リンクを定義します。
(N)「設定」>「システム」>「データベース・リンク」
転送先インスタンスで、クロス・インスタンス転送プロセスを開始する転送元インスタンスのユーザーと同じユーザー名とパスワードを持つアプリケーション・ユーザーを作成します。転送元インスタンスのユーザーに、連結先元帳を含む職責を割り当てます。
(オプション)転送元インスタンスで、「システム・プロファイル値」ウィンドウにナビゲートします。「プロファイル」フィールドで、プロファイル・オプション「GL連結: クロス・インスタンス・ワークフロー通知担当」に問い合せます。「アプリケーション」、「職責」または「サイト」の各フィールドに、ステップ2で入力した転送先インスタンスのユーザー名を入力し、作業内容を保存します。
転送先インスタンスで、ステップ2で入力したユーザー名に対して「ユーザー」ウィンドウに有効なEメール・アドレスがあることを検証します。
転送先インスタンスの連結先元帳と同じ通貨、カレンダおよび勘定体系を共有している転送元インスタンスで連結先元帳を定義します。
「連結データの転送」ウィンドウまたは「連結データ・セットの転送」ウィンドウにナビゲートします。ウィンドウのパラメータを指定します。
「連結実行オプション」ボタンを選択します。
使用するオプション、「仕訳インポートの実行」、「監査モード」、「要約仕訳の作成」および「自動転記」を使用可能にします。
リモート・インスタンス連結先のデータベースを選択します。
リモート・インスタンス連結先の職責を入力します。このフィールドには大/小文字区別があります。連結先元帳には、職責に割り当てられたデータ・アクセス・セットのデフォルト元帳を使用する必要があります。
「検証」ボタンを選択して、転送元データベースと転送先データベースの連結先元帳が同じカレンダ、通貨および勘定体系を共有していることを検証します。
「OK」を選択します。
General Ledgerのオープン・インタフェース表には、完全に独立した非Oracle会計システムなどの外部ソースから、GCS連結元データをインポートするための便利なインタフェースがあります。非Oracleソースからデータを収集するために使用可能なオプションは3つあります。
インタフェース・データ・トランスフォーマ機能を使用して、非OracleシステムからGCSシステムにインポート可能な形式にロー・データを変換できます。ソース・データが転送先元帳と同じ通貨の場合、IDTオプションを実行できます。
Applications Desktop Integrator(ADI)を使用して、スプレッドシート環境で作業できます。単に外部システムからADIの仕訳ワークシートに連結元情報を転送します。次に、ターゲット・インスタンスに転記できるGCSシステムにエントリをアップロードします。連結元データの形式によっては、このインスタンス内で連結元用のダミー元帳の作成が必要になる場合があります。
SQL*Loaderを使用して、様々なソースからGLのオープン・インタフェース表GL_INTERFACEにデータをロードします。
SQL*Loaderまたは別のローダー・プログラムを使用して、データをGL_INTERFACE表にロードする準備をします。
GL_INTERFACE表とその列の詳細は、「仕訳のインポート」を参照してください。
各システムのデータを対応するダミー元帳にロードします。
各連結元ダミー元帳について仕訳インポートを実行し、取引をインポートします。仕訳インポートは、データを検証して、連結元ダミー元帳の転記可仕訳にデータを変換します。
各連結元ダミー元帳内の仕訳を転記して、残高を更新します。
これで、連結定義とマッピング・ルールを使用して各ダミー元帳からGCS連結先に勘定科目値をマッピングするためのデータの準備ができました。
関連項目
『Oracle Applications Desktop Integrationユーザーズ・ガイド』
異なる主要通貨、会計カレンダまたは勘定体系が設定された複数の元帳を連結するには、最初に、連結元の勘定体系を連結先の勘定体系にマップする必要があります。
勘定体系マッピングは、勘定科目または勘定科目セグメント全体を、連結元勘定体系から連結先勘定体系にマップするための一連の指示です。この勘定体系マッピングは、連結データを連結元元帳から連結先元帳に転送するための連結定義に割り当てることができます。
勘定体系マッピングを定義するには、「異なる勘定体系がある複数元帳の連結」を参照してください。
連結先勘定体系の各セグメントに、セグメント・ルール動作を定義する必要があります。各親セグメントに、1つ以上の動作は定義できません。
次の理由から、勘定科目ルールよりセグメント・ルールの使用をお薦めします。
セグメント・ルールを使用すると、連結の作成がすばやく、簡単に行えます。たとえば、連結先勘定科目に3つしかセグメントがない場合、連結元の勘定体系全体を3つのセグメント・ルールのみでマップできます。
セグメント・ルールに基づいた連結は、より早く処理されます。
ヒント: 連結元勘定科目がセグメント・ルールでは正確にマップできない特定の例外にのみ、勘定科目ルールを使用します。
矛盾がある場合、セグメント・ルールは勘定科目ルールにより上書きされます。
勘定体系内の従属セグメント用にセグメント・ルールを定義する場合、従属セグメント値の値リストが重複入力を含んで表示されることがあります(同じ従属値と摘要を複数の独立したセグメント値に定義した場合)。適切な値のある入力を選択します。グローバル連結システムでは、摘要は使用されません。
「連結定義」ウィンドウにナビゲートし、「マッピング」ボタンを選択します。
勘定体系マッピングを入力するか、問い合せます。
「セグメント・ルール」ボタンを選択します。
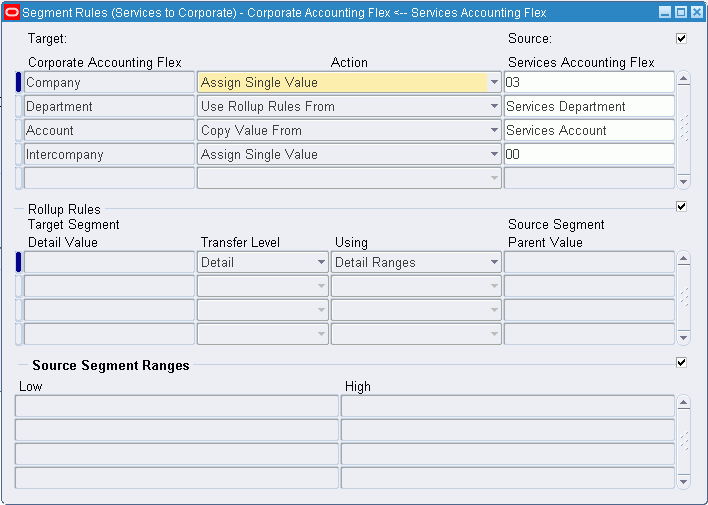
マップされるソース・セグメントごとに、マップ先となるターゲット・セグメント名、処理およびソース・セグメント名を入力します。各ターゲット・セグメントに使用できる処理は1つのみです。可能な処理には、次が含まれます。
値のコピー: ソース・セグメント内のすべての値を、ターゲット・セグメント内の同じ値にコピーします。セグメントでは同じ値セットを使用する必要はありませんが、同じセグメント値を使用する必要があります。
注意: 大きい連結元セグメントを小さい親セグメントにコピーすることはできません。たとえば、連結元値101を、最大長が2の親値セットにコピーすることはできません。
単一値の割当: ターゲット・セグメントに使用する特定の値を1つ割り当てます。連結先勘定体系で使用する値を入力する必要があります。
ヒント: 連結先勘定科目のセグメントが連結元勘定科目より多い場合が、この処理を使用します。
積上ルールの使用: 「積上ルール」リージョンで指定したルールを使用して、ソース・セグメントの値をターゲット・セグメントにマップします。
前のステップで「積上ルールの使用」処理を選択した場合は、「積上ルール」リージョンにマッピング・ルールを入力します。
作業内容を保存します。
注意: 作業内容を保存した後は、ターゲットとソース・セグメント詳細値の変更以外に、積上ルールを変更することはできません。積上ルールを変更するには、それを削除してから、新しいルールを作成します。
「連結定義」ウィンドウにナビゲートし、「マッピング」ボタンを選択します。
勘定体系マッピングを入力するか、問い合せます。
「勘定科目ルール」ボタンを選択します。
連結する「ソース勘定科目」を入力します。複数の範囲を入力する場合は、重複しないようにしてください。
各連結元勘定科目範囲のマップ先となる「ターゲット勘定科目」を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
元帳の定義(『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』)
勘定体系のマッピング(『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』)
連結定義は連結データを連結元元帳から連結先元帳に転送するために使用します。連結定義を作成するときに、連結元および連結先の元帳および各元帳勘定体系がマップされた勘定体系マッピングを指定します。
次に連結元から連結先に金額を転送するときに、General Ledgerにより未転記の連結仕訳バッチが連結定義に基づいて連結先元帳に作成されます。
注意: 連結元の連結先への連結方法を変更する場合は、データを転送する前に連結元の勘定体系マッピングを変更します。
連結定義を定義すると、複数の連結定義を連結セットにグループ化できます。次に、各連結元データを別々に転送するかわりに、連結セットを連結先に転送できます。関連項目: 連結セットの作成
前提条件
連結元と連結先の勘定体系をマップするために勘定体系マッピングを定義します。詳細は、「異なる勘定体系での元帳の連結」を参照してください。
連結先と連結元の元帳を定義します。平均残高処理が有効な場合は、連結先元帳が連結元帳または非連結元帳である必要があるかどうかを決定します。
連結定義を定義するには、次の手順を実行します。
「連結定義」ウィンドウにナビゲートします。
連結名と摘要を入力します。
「連結属性」リージョンで、連結先元帳名を入力します。
連結に使用する通貨を次のように入力します。
残高を連結する場合は、連結先の元帳通貨を入力します。オプションとして、「STAT」を入力し、統計残高を連結します。
取引を連結する場合は、連結先の通過を入力します。この通貨は連結元の元帳通貨と同じである必要があります。
注意: 連結元の元帳通貨が連結先元帳と異なる場合、連結元元帳の(仕訳または補助元帳レベル)報告通貨を使用して、データを報告通貨から連結先元帳に直接転送できます。
連結している連結元元帳名を入力します。
勘定体系マッピングを選択します。
連結方法を選択します。
残高: 実績、平均、換算済、予算または統計残高を連結します。この方法には、仕訳入力の詳細は含まれません。平均残高処理を使用可能にしてある場合は、連結先は平均残高処理が使用可能な連結元帳として定義してください。平均残高を連結しようとしていることに注意してください。
取引: 連結元元帳からの実績仕訳入力の詳細を連結します。両方の元帳が同じ元帳通貨の場合のみ、この方法を使用できます。この方法は予算には使用できません。平均残高処理を使用可能にしてある場合は、連結先は平均残高処理が使用可能な非連結元帳として定義してください。連結元元帳からの詳細を連結した後は、平均残高処理を行うことに注意してください。
平均残高処理が使用可能になっている場合は、ポップリストからデフォルト使用タイプを選択します。
標準: 標準残高のみが連結先元帳に転送されます。
平均残高のみが連結先元帳に転送されます。
標準および平均: 標準残高および平均残高の両方が、連結先元帳に移動されます。
注意: 標準残高と平均残高には、別々の連結定義を作成できます。これは異なる勘定体系マッピングを使用して、異なるレベルの詳細を得る場合に便利です。たとえば、各会社内のコスト・センターごとの連結合計を表示できるように、標準残高をマップする場合などです。ただし、各コスト・センターの連結詳細を表示できるように、平均残高をマップする場合もあります。
注意: 連結方法として「取引」を選択すると、「標準」が使用タイプとして入力されます。連結元データの転送時には、これを上書きできません。
連結実行オプションを選択します(関連項目: 連結実行オプション)。連結元データの転送時に、これらを上書きできます。
(オプション)「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択して定義アクセス・セットのセキュリティを連結定義に適用します。
定義アクセス・セットはGeneral Ledger定義へのアクセス権限を管理可能にするオプションのセキュリティ機能です。たとえば、連結定義に連結セットを割り当てるか連結定義を使用して連結データを転送するときに、特定のユーザーがその連結定義を表示、変更または使用するのを禁止できます。
セキュリティを使用可能にしない場合は、すべてのユーザーが連結定義を使用、表示、変更および削除できます。
ユーザーの職責でアクセスの割当機能を使用できる場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが使用可能になります。「アクセスの割当」ボタンを選択すると、該当する権限のある1つ以上の定義アクセス・セットに定義が割り当てられます。詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。
作業内容を保存します。
次では、連結定義に関連する使用、表示および変更アクセス権の意味を説明します。
使用アクセス: 次の操作について、特定のユーザーが連結定義を使用できるようにします。
「連結データの転送」ウィンドウを使用した連結データの転送。
「連結セット」ウィンドウを使用した、連結セットへの連結の割当。
「連結監査レポート・データのパージ」ウィンドウを使用した、連結監査データのパージ。
「連結-監査レポート」、「連結例外レポート-連結先勘定科目無効」、「連結例外レポート-マップ取消連結元勘定科目」といったレポートからの連結監査データの表示。
表示アクセス: 特定のユーザーが「連結定義」ウィンドウから連結定義のみ表示できるようにします。表示アクセスを持つユーザーが、連結定義の変更、連結セットへの定義の割当、またはデータの転送を実行することはできません。
変更アクセス: 特定のユーザーが連結定義を表示し、変更できるようにします。「アクセスの割当」ボタンが有効な場合は、定義アクセス・セットも変更できます。
連結定義または連結セットを作成するときは、次にリストされている4つの実行オプションのいずれかを選択して、連結仕訳を連結先元帳に転送できます。これらの選択内容は、連結元データを連結先に転送するときに上書きできます。
仕訳インポートの実行: このオプションを選択すると、連結元データの転送後に仕訳インポートが起動します。これによって、連結先元帳内に未転記連結バッチが自動的に作成されます。このバッチには、<日付> <連結名>連結<要求ID>: <残高タイプ> <グループID>の形式で名称が設定されます(例: 31-JAN-95 US to Global Consolidation 50835:A 534)。バッチ処理を後で実行する場合、連結データを異なるコンピュータまたはデータベースにまたがって転送する場合は、仕訳インポートを実行しないでください。
仕訳インポートを実行しないように選択すると、あとで仕訳インポートを実行できるように、転送処理によってGL_INTERFACE表が移入されます。
要約仕訳の作成: このオプションを選択すると、同じ勘定科目コード組合せに影響を与えるすべての仕訳明細が連結先元帳の1つの明細に要約されます。これは、要約処理であるため、Oracle General Ledgerでは、各勘定科目の組合せに対して借方と貸方を示す1つの仕訳明細が作成されます。
監査モード: このオプションを選択すると、連結元元帳の勘定科目を連結先元帳の勘定科目にマップした方法が記録されます。次に、「連結監査レポート」、「連結先勘定科目無効」レポートおよび「マップ取消連結元勘定科目」レポートを実行すると、連結監査情報を表示できます。
ヒント: 定義内容が適切であること、および元帳の勘定体系が予定どおりにマッピングされていることを確認するには、新規連結に監査モードを使用してください。一度検証した後は、監査モードを無効にしてパフォーマンスを向上させることができます。
連結元データが転送され、監査レポートを要求した後で、「連結監査データのパージ」ウィンドウを使って連結監査レポート・データをパージします。
自動転記: このオプションを選択すると、連結先元帳の連結仕訳が自動的に転記されます。詳細は、「自動転記」を参照してください。
次のフィールドに入力し、「検証」ボタンを選択して、連結元インスタンスから連結先インスタンスに、連結データを転送できます。連結先インスタンスは、同じ社内イントラネット上にある必要があります。
データベース: リモート・インスタンスのデータベースを選択します。
職責: 連結データをリモート連結先インスタンスに転送することを許可するリモート・インスタンスの職責を入力します。
「検証」ボタンを選択して、ソース・インスタンスとターゲット・インスタンスの連結先元帳が同じカレンダ、通貨および勘定体系を共有していることを検証します。
注意: 「リモート・インスタンス・サインオン」の実行オプションは、「連結データの転送」および「連結データ・セットの転送」の各ウィンドウの「実行オプション」ウィンドウのみに表示されます。
関連項目
複数連結元の連結データを同時に転送するには、連結セットを作成します。
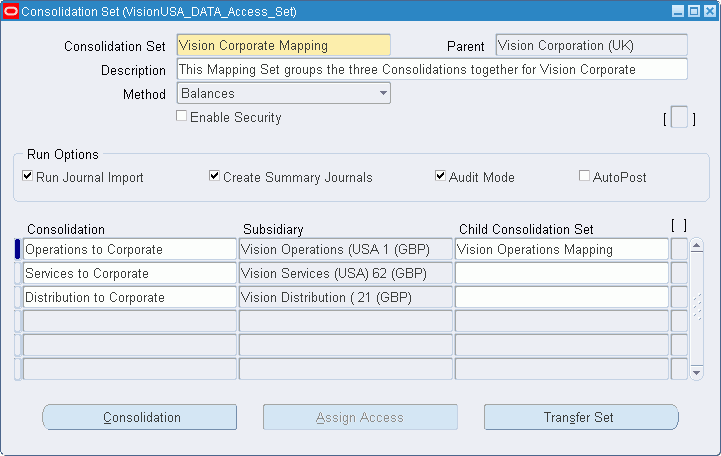
「連結セット」ウィンドウにナビゲートします。
連結セットの連結セット名、連結先元帳および摘要を入力します。
連結方法を選択します。
連結実行オプションを選択します。
連結セットに含める連結元と連結先の連結ごとに、連結定義を入力します。この連結定義には、前述の手順で選択した内容と同じ連結先元帳と連結方法を使用する必要があります。
(オプション)既存の連結定義を表示または変更する場合、あるいは新規連結定義を作成する場合は、「連結」ボタンを選択します。関連項目: 連結定義の定義
(オプション)連結定義の入力を終了した後は、「転送セット」ボタンを選択して「連結データ・セットの転送」ウィンドウをオープンします。このウィンドウから転送セット・パラメータを入力すると、連結元から連結先元帳へのデータ転送処理を開始できます。ここでデータを転送しない場合は、次のステップに進みます。
(オプション)定義アクセス・セットのセキュリティを連結セットに適用する場合は、「セキュリティ使用可能」チェックボックスを選択します。
定義アクセス・セットは、Oracle General Ledgerの各定義へのアクセスを制御できるオプションのセキュリティ機能です。たとえば、特定のユーザーが、連結セットを表示または変更できないように、あるいは連結セットを使用して連結データを転送できないようにすることができます。
セキュリティが無効な場合は、すべてのユーザーが連結セットを使用、表示、変更および削除できます。
職責にアクセス権の割当機能がある場合は、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが有効になります。この「アクセスの割当」ボタンを選択し、必要な権限を使用して定義を1つ以上の定義アクセス・セットに割り当てます。定義アクセスセットの詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。
作業内容を保存します。
次に、連結セットに関連する使用、表示および変更の各アクセス権について説明します。
使用アクセス権: ユーザーは、連結セット・データを「転送セット」ウィンドウから転送できます。使用アクセス権のみのユーザーは、連結セットを「連結セット」ウィンドウから問い合せできません。
表示アクセス権: ユーザーは、連結セット定義を「連結セット」ウィンドウから表示できます。
変更アクセス権: ユーザーは、連結セットを表示して変更できます。「アクセスの割当」ボタンが有効な場合、この変更には、定義アクセス・セットへの変更が含まれます。
関連項目
残高を連結先に転送する前に、残高の再評価と換算を行って連結元データを準備します。
連結元元帳のいずれかに外貨建ての貸借対照表勘定科目がある場合は、残高を再評価して、換算レートの変化による影響を反映します。再評価仕訳の結果を転記します。
関連項目: 残高の再評価
連結元元帳のいずれかで連結先と異なる元帳通貨が使用されている場合は、連結元データを連結先転送する前に、勘定科目残高を換算する必要があります。連結先元帳の通貨に換算します。
「グローバル連結システム」を使用して、すべての連結元元帳の換算ステータスをチェックします。「換算ステータス」ウィンドウでは、換算を再実行する要求を発行することもできます。
注意: 「連結ワークベンチ」から再実行できるのは、期間に対して少なくとも1度は実行されている換算のみです。新規の換算は発行できません。新換算を発行するには、「残高換算」ウィンドウを使用します。
関連項目: 残高の換算
報告通貨(仕訳または補助元帳レベル)を使用しているときに、連結元と連結先の両方が同じ通貨を共有している場合は、連結元の報告通貨(仕訳または補助元帳レベル)から連結先元帳に直接連結することで、換算ステップを省略できます。連結する前に、連結元元帳および報告通貨の再評価を実行する必要があります。
連結元の報告通貨(仕訳または補助元帳レベル)から直接連結するかどうかを決定する際には、次のことが重要となります。
どの会計ルールによって、連結先と連結元のビジネス環境を管理するのか。報告通貨は、SFAS #52(U.S.)などの複数の国内会計標準をモデルとしているため、これらの標準間の違いによって、連結元の報告通貨からの連結が非現実的な内容にならないかどうかを考慮してください。
「連結ワークベンチ」にナビゲートします。
換算ステータスをチェックする連結元の、連結定義を問い合せます。
「ステータス制御」の「換算ステータス」ボタンを選択します。
「換算ステータス」ウィンドウの情報を検討します。「換算ステータス」列には、換算が「現行」または「現行のものではない」で表示されます。「最終実行日」列には、換算が最後に実行された日付が表示されます。
「換算ステータス」ウィンドウから、「換算」チェック・ボックスを選択して、実行する換算を選択します。
「換算」ボタンを選択します。
関連項目
連結元元帳から連結先に連結する残高または取引を転送します。General Ledgerは、定義した勘定体系マッピングおよび連結ルールに基づいて、連結元情報を累計し、連結データをGL_INTERFACE表に移入します。
「実行オプション」ボタンを選択して、連結実行オプションを定義し、必要に応じてリモート・インスタンス・サインオン・パラメータを入力します。たとえば、連結元データの転送時に、仕訳インポートと自動転記を自動的に実行できます。
注意: 連結元から連結先への転送は、同じインスタンス内での転送の場合のみ連結元元帳または連結先元帳から開始できます。インスタンス間でデータを転送する場合、ソース・インスタンスはクロス・インスタンス・データの転送で開始する必要があります。
データ・アクセス・セット
連結データを正常に転送するには、連結転送のターゲットとして使用する、元帳や貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りアクセス権および書込みアクセス権が必要です。アクセス権が不十分な場合、連結転送は正常に完了しますが、仕訳インポート・プログラムがエラーとなり、連結仕訳は作成されません。
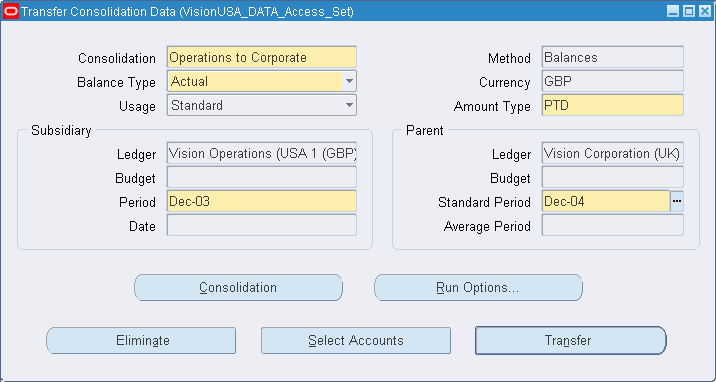
関連項目
前提条件
連結先に連結する連結元元帳のそれぞれに対し、連結定義を定義します。
連結元元帳への仕訳の入力と転記は通常の業務で行います。
外貨建の貸借対照表勘定科目がある元帳の残高を再評価します。
連結元元帳と連結先元帳に異なる元帳通貨が設定されている場合は、連結元元帳の残高を連結先元帳の通貨に換算します。
実際の残高を連結するには、次の手順を実行します。
「連結ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。
移動する連結定義を選択します。定義には必ず残高連結方法を使用します。
注意: 定義アクセス・セットを使用して連結定義を保護するには、残高を転送する定義に対する使用アクセス権が必要です。
「ステータス制御」から「移動」ボタンを選択します。
「連結データの転送」ウィンドウが表示され、この定義に定義されている方法、通貨および元帳の情報が表示されます。平均残高処理が有効な場合は、選択したデフォルトの使用タイプも表示されます。
「残高タイプ」に「実績」を選択します。
平均残高処理が有効な場合は、「使用」タイプを選択して連結する残高を示します。これには、「標準」、「平均」または「標準および平均」があります。
年度累計(YTD)や期間累計(PTD)など、連結する残高の「金額タイプ」を入力します。
連結する連結元の会計「期間」を入力します。
連結先元帳で連結する「標準期間」を入力します。オープンまたは先日付入力可能な任意の期間に連結できます。
平均残高処理が有効な場合は、連結する連結元平均残高の「日付」を入力します。
平均残高処理が有効な場合は、連結先元帳に連結する「平均期間」を入力します。
(オプション)「実行オプション」ボタンを選択して、連結実行オプションを変更します。リモート・インスタンスの連結先にデータを転送する場合は、リモート・インスタンス・サインオンのパラメータを指定します。関連項目: Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
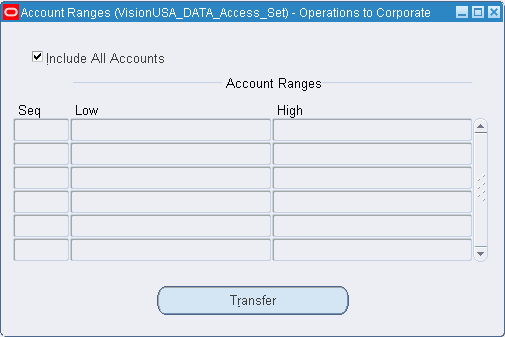
連結する勘定科目範囲を指定するには、「勘定科目の選択」ボタンを選択します。連結する範囲について「勘定科目 自」と「勘定科目 至」を入力します。
「仕訳インポートの実行」オプションが有効な状態で転送処理を発行すると、連結先元帳内に、範囲内の有効な連結元勘定科目をすべて含む未転記連結仕訳バッチが作成されます。連結範囲で連結元元帳から一部の勘定科目が除外されて、連結処理が監査モードで実行された場合は、「マップ取消連結元勘定科目」レポートで除外された勘定科目を検証できます。
この連結転送のために指定した範囲が、選択した連結定義を使用して次回データを転送する際のデフォルト範囲となります。
注意: 連結定義で使用する要約勘定科目が連結元元帳に定義されている場合、勘定科目範囲の転送は不要です。要約勘定科目は連結されません。
「移動」を選択して、連結元データを連結先に移動するコンカレント・プロセスを開始します。
「仕訳インポートの実行」オプションを転送用に選択しなかった場合、連結先元帳で連結仕訳バッチを作成するには、転送完了後に「仕訳のインポート」ウィンドウを使用します。
「連結ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。
移動する連結定義を選択します。定義には必ず残高連結方法を使用します。
「ステータス制御」から「移動」ボタンを選択します。
「残高タイプ」に「予算」を選択します。Oracle General Ledgerでは予算の平均残高情報が保守されないため、使用タイプが「標準」に変更されます。「日付」および「平均期間」フィールドも使用不可になります。
連結する予算残高の「金額タイプ」を入力します。年度累計(YTD)または期間累計(PTD)などがあります。
連結元元帳と連結先元帳の両方に対して「予算名」を指定します。両方の予算はオープンまたは現行である必要があります。連結先予算および連結元予算は同じ期間内にある必要があります。
連結する連結元予算「期間」と、連結先の「標準期間」を入力します。
予算内のすべての期間の予算残高を連結する場合は、デフォルト期間「全て」を選択します。全期間について連結する場合は、予算会計年度を入力する必要があります。
(オプション)必要に応じて、連結実行オプションを変更します。リモート・インスタンス連結先にデータを転送する場合は、リモート・インスタンス・サインオン・パラメータを指定します。関連項目: Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
連結する勘定科目範囲を指定するには、「勘定科目の選択」ボタンを選択します。連結する範囲について「勘定科目 自」と「勘定科目 至」を入力します。
注意: 連結定義で使用する要約勘定科目が連結元元帳に定義されている場合、勘定科目範囲の転送は不要です。要約勘定科目は連結されません。
「移動」を選択して、連結元データを連結先に移動するコンカレント・プロセスを開始します。
「仕訳インポートの実行」オプションを転送用に選択しなかった場合、連結先元帳で連結仕訳バッチを作成するには、転送完了後に「仕訳のインポート」ウィンドウを使用します。
関連項目
取引を連結できるのは、連結に「実績」の「残高タイプ」を使用している場合のみです。平均残高処理が有効な場合は、有効な平均残高を使用して非連結元帳に連結する必要があります。
「連結ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。
移動する連結定義を選択します。この定義には取引連結方法を使用する必要があります。
「ステータス制御」から「移動」ボタンを選択します。「連結データの転送」ウィンドウに、この定義に定義されている方法、通貨および元帳の情報が表示されます。
注意: 「残高タイプ」には「実績」が、「使用」タイプには「標準」が、「金額タイプ」には「期間」が自動的に入力されます。
連結する連結元会計「期間」を入力します。
連結先元帳で連結する「標準期間」を入力します。オープンまたは先日付入力可能な任意の期間に連結できます。
連結実行オプションを選択します。リモート・インスタンス連結先にデータを転送する場合は、「リモート・インスタンス・サインオン」パラメータを指定してください。関連項目: Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
「バッチの選択」ボタンを選択して、連結する仕訳バッチを指定します。
次の「バッチ問合せオプション」の中から選択します。
連結なし: 連結元元帳内で、まだ連結されたことがないバッチを問い合せる場合。
連結: すでに連結されたバッチを問い合せる場合。
全て: すでに連結されたバッチと、まだ連結されたことがないバッチの両方を問い合せる場合。
「移動」を選択して、連結元データを連結先に移動するコンカレント・プロセスを開始します。
「仕訳インポートの実行」オプションを転送用に選択しなかった場合、連結先元帳で連結仕訳バッチを作成するには、転送完了後に「仕訳のインポート」ウィンドウを使用します。
関連項目
連結セット内に連結定義が含まれている連結元のすべてまたは一部からデータを転送できます。これは、連結先に連結する連結元の数が多い場合に便利です。
前提条件
連結セットを定義します。
「連結ワークベンチ」にナビゲートします。
「ステータス制御」から「転送セット」ボタンを選択します。「連結データ・セットの転送」ウィンドウが表示されます。
連結セット名を入力するか、値リストから選択します。
連結セットの「残高タイプ」、「使用」、「通貨」、「方法」、「金額タイプ」および「連結先元帳」の名前が表示されます。
(オプション)連結先元帳に対して平均残高が有効なときに、残高連結方法を使用すると、「使用」を変更できます。「標準」、「平均」または「標準および平均」を選択します。
連結の「金額タイプ」を選択します。
連結先と連結元が同じ会計カレンダを使用している場合は、デフォルトの「連結元期間」と連結先「標準期間」を入力します。「使用」タイプに「平均」または「標準および平均」を選択した場合は、デフォルトの連結元「有効日」と連結先「平均期間」を入力します。
「連結の問合せ」ボタンを選択して、連結セットに含まれている連結を表示します。前述の手順で選択した他のオプションに基づいて、連結元期間および連結元日付も表示されます。
転送する連結定義名の左にあるチェック・ボックスを選択して、連結定義を選択します。すべての連結を転送するには、「全て選択」チェックボックスを選択します。
(オプション)連結元元帳と連結先元帳が同じカレンダを共有している連結に対してデフォルトの日付を適用するには、「デフォルトの適用」ボタンを選択します。カレンダが異なる場合、デフォルトの日付は適用されません。
(オプション)「実行オプション」ボタンを選択して、連結実行オプションを変更します。リモート・インスタンス連結先にデータを転送するには、「リモート・インスタンス・サインオン」パラメータを指定します。関連項目: Oracle Applicationsを使用した複数インスタンスからの連結元データの収集
注意: ここで定義した実行オプションは、連結セットの連結すべてに適用され、個別の連結定義で定義した実行オプションは上書きされます。
「移動」ボタンを選択して、連結元データを転送するコンカレント・プログラムを開始します。
関連項目
連結元データを連結先元帳に転送した後は、連結元データと連結先データを結合する必要があります。この結合には次のいくつかの手順が必要となります。
結合実行オプションの1つとして選択していない場合は、仕訳インポートを実行します。
転送および後続の仕訳インポートにより作成される未転記仕訳バッチを検討します。
連結先元帳で連結仕訳を転記します。
平均日次残高連結先元帳: 前月、前四半期または前年の入力は、連結先で平均日次残高が正確であるように、PATD/PTD、QATD/QTDおよびYATD/YTD金額タイプをADB連結元からADB連結先に連結する際に逆仕訳する必要があります。たとえば、7月の平均連結データを連結する前に、6月の平均連結仕訳を逆仕訳します。
「仕訳のインポート」ウィンドウで、ソースを「連結」とします。
関連項目: 仕訳のインポート
検討する仕訳バッチについての連結定義を選択します。
「ステータス制御」の「仕訳の検討」ボタンを選択します。
Oracle General Ledgerにより、連結バッチについての詳細情報が掲載されている「バッチ」ウィンドウが表示されます。ここから、仕訳についての追加情報の表示を選択できます。
「連結ワークベンチ」にナビゲートします。
連結定義に関連付けされている連結元の左側にある「転記」チェック・ボックスを選択して、転記する仕訳バッチの連結定義を選択します。
「ステータス制御」の「転記」ボタンを選択します。
Oracle General Ledgerによってコンカレント・プロセスが起動され、連結仕訳バッチが転記されます。
注意: 連結仕訳の各プロセスのステータスをチェックするには、「連結プロセス検索」ウィンドウの「検索」ボタンを選択します。ステータス結果が連結ワークベンチに表示されます。
関連項目
Oracle General Ledger自動会社間消去プログラムは、会社間残高を消去します。1つ以上の消去仕訳のバッチである消去セットを作成します。
「全消去」消去セットでは、オプションとして消去会社を使用して、一連の連結元の会社間消去入力のグループを完全に消去できます。
消去仕訳が貸借不一致の場合は、貸借一致オプションを指定して、貸借不一致の仕訳の作成を許可するか、代替勘定科目に貸借差引差異を転記できます。さらに、しきい値ルールを適用して、貸借差引差異が特定の金額、特定勘定科目の割合または合計仕訳の割合を超えた場合に貸借一致明細が作成されるのを防ぐことができます。
消去セットを毎期間生成して、消去仕訳を自動的に作成します。仕訳をこの時点で自動的に転記するか、検証するまで待ってから転記するかを選択できます。
連結ワークベンチを使用して、消去セットの消去ステータスを記録し、生成された消去セットを転記することもできます。
注意: 自動会社間消去プログラムを使用して平均残高を消去できません。
算式ベースの消去: 算式ベースの消去入力がある場合、または平均残高を消去する場合は、Oracle General Ledgerの定型仕訳機能を使用します。関連項目: 定型仕訳算式バッチの作成
ADIのスプレッドシート環境で、消去入力を作成できます。関連項目: 『Oracle Applications Desktop Integrationユーザーズ・ガイド』
自動会社間消去プログラムは、「消去勘定マッピングの定義」ウィンドウで指定されたルールに従って消去入力を自動的に生成します。
連結元元帳に消去入力を作成するには、Oracle General Ledgerの標準仕訳機能を使用します。入力消去の作成にはApplications Desktop Integratorの「仕訳ウィザード」も使用できます。関連項目: 『Oracle Applications Desktop Integrationユーザーズ・ガイド』
また、消去セットを作成するのに、Oracle General Ledgerの定型仕訳の一種であるグローバル連結システムを使用できます。消去セットを使用すると、会計期間ごとに発生する消去入力の作成を定義できます。
最初に消去セットを作成して消去入力を定義します。セットには単一の消去入力を含めることができます。または、関連する入力を同じ消去セットにグループ化することもできます。たとえば、特定の業務に関わるすべての連結元を論理的にグループ化できます。
「消去セット」ウィンドウにナビゲートします。
元帳を選択します。
データ・アクセス・セットと同じ勘定体系を共有する元帳に対して消去を定義できます。
消去セットのバッチ名を入力します。この名称は、特定の元帳の1つ以上の消去仕訳のバッチを表します。
消去セットの摘要を入力します。
(オプション)値リストから、消去会社を表す貸借一致セグメント値を選択します。この会社は、消去入力を記帳するときに、ターゲット会社として使用されます。会社の摘要は自動的に入力されます。
注意: 消去会社を使用しない場合は、このフィールドを空白のままにします。
(オプション)その期間にどの消去が完了したかを判断するために消去セットをチェックリストの一部に含める場合は、「消去ステータスの追跡」チェック・ボックスを選択します。
注意: 追跡がマークされ、少なくとも1回は生成された消去セットは、削除できません。
(オプション)有効日:自と至を入力し、消去セットがいつアクティブになるかを指定します。
「最終実行期間」フィールドがGeneral Ledgerによって移入され、消去セットが実行された最終期間を示します。
「勘定科目」ボタンを選択します。
この消去セットの消去仕訳を入力します。関連項目: 消去仕訳の作成
(オプション)消去セットに定義アクセス・セットのセキュリティを適用するには、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択します。
「定義アクセス・セット」は、General Ledger定義へのアクセス制御を可能にするオプションのセキュリティ機能です。たとえば、自分の消去セットについて、特定のユーザーによる表示、変更または消去入力作成のための使用を防止できます。
セキュリティを使用可能にしなければ、自分の消去セットをすべてのユーザーが使用、表示、変更または削除できます。
ユーザーの職責でアクセスの割当機能を使用できる場合は、「セキュリティ使用可能」チェック・ボックスを選択すると「アクセスの割当」ボタンが使用可能になります。「アクセスの割当」ボタンを選択すると、該当する権限のある1つ以上の定義アクセス・セットに定義が割り当てられます。詳細は、『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の定義アクセス・セットに関する項を参照してください。
作業内容を保存します。
「生成」ボタンを選択して、消去セットを生成し、消去入力を作成します。関連項目: 消去仕訳の生成
消去仕訳を検討して転記します。
消去セットに関連する使用、表示および変更アクセス権の意味は、次のとおりです。
使用アクセス権: 「消去の生成」ウィンドウで消去セットを生成できます。使用アクセス権を持つユーザーが「消去セット」ウィンドウで消去セットを問い合せることはできません。
表示アクセス権: 「消去セット」ウィンドウで消去セットの定義を表示できます。表示アクセス権のみが付与されているユーザーは、消去セットの生成や定義の変更はできません。
変更アクセス権: 消去セットを表示して変更できます。「アクセスの割当」ボタンが使用可能な場合、これには定義アクセス・セットの変更許可も含まれます。変更アクセス権のみが付与されているユーザーは、消去セットを生成できません。
各消去セットについて、無制限の数の消去仕訳を定義できます。消去入力は、ソース勘定科目からターゲット勘定科目への勘定残高を完全に消去する個々の明細から導出されます。
「消去勘定」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウには、「消去セット」ウィンドウで「勘定科目」ボタンを選択するとナビゲートできます。
消去入力の仕訳名を入力して、消去バッチ内の消去仕訳を一意に識別します。
「カテゴリ」は、自動的に「消去」として定義されます。
値リストから通貨を選択します。連結された連結元の元帳通貨とSTATの2つの選択肢があります。指定する通貨は、ソース勘定科目とターゲット勘定科目両方の通貨です。
「金額タイプ」フィールドで、消去を導出する残高タイプを入力します。入力できる値として、PTD、QTD、YTDおよびPJTDがあります。
注意: 平均残高は使用できません。
「勘定科目」リージョンで、ソースを指定します。ソース勘定科目残高は、ターゲット勘定科目と完全に相殺消去されます。各勘定科目セグメントについて、詳細勘定科目値または連結先勘定科目値を選択するか、セグメントを空白のままにします。
注意: 消去セットは、特定の親値に関連付けられている子値の変更に自動的に適応するので、親値を使用して保守を削減します。各子値の複数明細のかわりに親値を含む1つの消去明細を指定できるので、親値を使用すると消去セットの定義の時間が節約されます。親値を使用すると、消去機能がセグメントの各子値を自動的にループして消去仕訳のオフセットを作成します。
消去入力のターゲット勘定科目を指定します。各勘定科目セグメントについて、詳細勘定科目値を選択するか、セグメントを空白のままにします。
注意: 「消去セット」フォームで消去会社を指定する場合は、貸借一致セグメント値が自動的に設定されます。このデフォルトは上書きできません。
ただし、「消去セット」フォームで消去会社を指定しない場合は、ソース勘定科目の貸借一致セグメント値がターゲットの貸借一致セグメント値のデフォルトになります。このデフォルトは上書きできます。
作業内容を保存します。
次の例は、単一のセグメントであるコスト・センター・セグメントに対してマッピング・ルールがどのように機能するかを示しています。この例では、親コスト・センター値999には、100、200および300という3つの子があります。400のコスト・センター値には親がありません。
消去セグメント値のダイアグラム
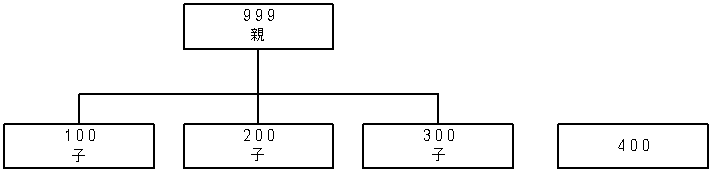
次の表には、コスト・センター・セグメントのマッピング・ルールの結果を示します。
| ソース勘定科目 | ターゲット勘定科目 | 結果 |
|---|---|---|
| NULL | NULL | ソース勘定科目100、200、300および400は、それぞれターゲット勘定科目100、200、300および400と相殺消去される。 |
| NULL | 100 | ソース勘定科目100、200、300および400は、単一のターゲット勘定科目100と相殺消去される。 |
| 200 | NULL | ソース勘定科目200は、ターゲット勘定科目と相殺消去される。 |
| 999 | NULL | ソース勘定科目100、200および300(999の子)は、それぞれターゲット勘定科目100、200および300と相殺消去される。 |
| 200 | 100 | ソース勘定科目200は、ターゲット勘定科目100と相殺消去される。 |
| 999 | 100 | ソース勘定科目100、200および300(999の子)は、ターゲット勘定科目100と相殺消去される。 |
注意: この例では1つのセグメント値を使用していますが、同じ概念が勘定体系のすべてのセグメントに適用されます。
生成された消去の貸借が一致していないときは、貸借一致オプションを定義して、貸借不一致を訂正できます。各消去セットに対して選択された貸借一致オプションは、その消去バッチに対して作成されたすべての仕訳に適用されます。
「貸借一致オプション」ウィンドウにナビゲートします。「消去セットの定義」ウィンドウで「貸借一致オプション」ボタンを選択します。
消去仕訳が貸借一致していない状況で使用する「貸借不一致オプション」を指定します。オプションには次のものがあります。
貸借不一致仕訳の許可: このオプションは、後で検討する貸借不一致仕訳を作成する場合に選択します。貸借不一致の仕訳の転記を決定した場合、または自動転記を設定してある場合は、元帳の仮勘定転記オプションが適用されます。
正味差異勘定との貸借一致: このオプションを選択して、差異が正味借方または正味貸方の場合に使用する勘定科目テンプレートを指定します。貸借不一致仕訳に複数の貸借一致セグメントが関係する場合、General Ledgerは貸借一致セグメント値によって仕訳明細をグループ化し、それらの各グループを個々に貸借一致させます。
しきいルールの使用: 正味差異勘定科目の使用オプションを選択した場合は、このオプションも選択できます。しきいルールの使用を選択すると、消去仕訳の正味借方および正味貸方金額が、指定されたしきい値を超えているかどうかをプログラムで検証できます。しきい値を超えていない場合、プログラムは検討できる貸借一致仕訳を作成します。しきい値を超えている場合は、検討できる貸借不一致仕訳が作成されます。
注意: 「残高不一致仕訳の許可」を選択した場合は、このオプションを使用できません。
正味差異勘定科目の使用オプションを選択した場合は、使用する正味差異借方勘定科目および正味差異貸方勘定科目を指定します。
正味差異勘定科目の使用およびしきいルールの使用オプションを選択した場合は、使用するしきい値ルールを割り当てます。次の表に示す3つのオプションがあります。
| しきい値ルール・オプション | 処理 |
|---|---|
| 一定金額 | 固定金額を指定する。 |
| 勘定科目のパーセント | 数値と勘定科目を入力する。数値は、指定された勘定科目コード組合せの期間累計残高のパーセンテージを表します。注意: 勘定科目は詳細勘定科目である必要があります。 |
| 仕訳のパーセント | 貸借不一致仕訳の少ない方の合計借方または合計貸方のパーセンテージを表す数値を入力する。 |
作業内容を保存します。
定義した消去仕訳の算式から未転記の仕訳バッチを作成するには、消去仕訳を生成する必要があります。生成後は、転記前に消去仕訳を検討または編集できます。
データ・アクセス・セット
消去仕訳を正常に生成するには、消去仕訳のソースおよびターゲットとして使用する元帳と貸借一致セグメント値または管理セグメント値への読取りおよび書込みアクセス権が必要です。
前提条件
消去セットに含まれる消去仕訳を定義します。
消去仕訳の貸借一致オプションを定義します。
「消去の生成」ウィンドウにナビゲートします。「消去セット」ウィンドウで「生成」ボタンを選択します。
各セット名の左にあるチェック・ボックスを選択して、生成する消去セットを選択します。
(オプション)「消去セット」ボタンを選択して「消去セットの定義」フォームをオープンし、消去定義を検討または変更します。
注意: 定義アクセス・セットで消去セットへの使用アクセス権のみが付与されている場合、「消去セット」ボタンは使用不可になっています。「消去セット」ボタンを使用して定義を表示できるようにするには、表示アクセス権が必要です。
期間を選択して消去セットを実行します。
「消去セット」フィールドに、選択した期間にアクティブな消去セットがすべて表示されます。
注意: 定義アクセス・セットを使用して消去セットへの使用、表示および変更アクセス権を保護している場合、消去セットを生成するには使用アクセス権が必要です。
「最終実行期間」フィールドには、消去セットが最後に実行された期間が表示されます。
消去セットが発行されると、「要求ID」フィールドに要求IDが表示されます。
「生成」ボタンを選択して、消去仕訳を作成します。選択した消去セットに基づいて未転記の仕訳バッチを作成するコンカレント・プロセスがOracle General Ledgerにより発行されます。コンカレント・プロセスに割り当てられた要求IDに注目してください。
連結先勘定科目の残高を更新するには、生成された消去仕訳バッチを転記します。
連結ワークベンチで特定の連結先期間の消去セットのステータスをチェックするには、「消去」タブを選択します。追跡を選択したすべてのアクティブな消去セットが、そのステータス、最終生成日および要求IDとともに表示されます。
注意: ワークベンチで消去のステータスを検討するには、データ・アクセス・セットで連結先元帳への読取りアクセス権が付与されている必要があります。
消去を問い合せた後に実行する処理は、定義アクセス・セットの権限により制御されます。たとえば、表示権限のみが付与されている場合、「ステータス制御」で「生成」ボタンを使用して消去セットを生成することはできません。使用権限のみが付与されている場合、「ステータス制御」で「消去セット」ボタンを使用して消去セットの定義を表示することはできません。
次の表には、消去セットの「ステータス」列に表示されるステータスを示します。
| ステータス | 摘要 |
|---|---|
| 生成用に選択 | 消去セットが生成用に選択された。 |
| 生成中 | 消去セットを生成中。 |
| 生成失敗 | 選択した消去セットの生成に失敗した。 |
| 生成済 | 消去セットが生成された。 |
| 削除済 | 消去セットが削除された。 |
| 転記分の選択 | 消去セットが転記用に選択された。 |
| 転記 | 消去セットの転記中。 |
| 転記済 | 消去セットが正常に転記された。 |
| 失敗 | 消去セットの転記に失敗した。 |
ワークベンチ・ウィンドウの「消去」タブを選択します。ウィンドウのこのビューには、消去ステータスの追跡がチェックされた、その期間のアクティブな消去セット、消去会社、消去セットのステータス、消去セットが最後に実行された日付および要求IDが表示されます。各消去セット定義は別々の行に表示されます。
消去ワークベンチは、消去仕訳の借方合計や貸方合計などの追加情報をリストするために使用可能になるフォルダでもあります。
消去ワークベンチは、次の表に示すように、有効なすべての消去セットの全ステータスを示します。これは、個々の消去セットのステータスではないので注意してください。
| ステータス | 摘要 |
|---|---|
| 未生成 | どの消去セットも生成されていません。 |
| 処理中 | 生成は開始していますが、すべての消去セットが生成され転記されたわけではありません。いずれかの消去セットの生成または転記に失敗した場合は、全ステータスが「処理中」を示します。 |
| 転記済 | すべての消去セットが生成され、転記されています。 |
| 確認済 | 「確認」ボタンを選択した場合に表示されるステータスです。消去プロセスがその期間に対して完了したことに満足してから、「確認」ボタンを選択できます。 全ステータスが「確認済」の場合は、「確認」ボタンのラベルが動的に「確認の取消」に変わります。確認を取り消すと、消去セットが前の状態または現在の適切なステータスに戻ります。 |
注意: 同じ期間に対して消去セットを再生成した場合は、ステータスが自動的に「処理中」に戻ります。
期間のクローズを選択し、消去が確認されていない場合は、「確認済」ステータスが自動的に設定されます。
期間を再オープンしても、確認を明示的に取り消さない限り、「消去確認済」ステータスは変わりません。
関連項目
Oracle General Ledgerには連結残高を検討してレポートするための強力なオンライン照会およびレポート機能があります。また、連結成果を分析するための洗練されたツールも提供されています。
連結済の連結先元帳からは、次の内容へドリルできます。
連結済および連結元エンティティ
詳細勘定科目および仕訳
要約および詳細勘定科目残高
仕訳および補助元帳取引
Oracle General Ledgerの「どこへでもドリルダウンできる」機能は、すべての連結元、勘定科目、仕訳、補助元帳取引に対する明瞭な見通しを即座に提供します。勘定科目残高にドリルダウンして連結仕訳を検討し、さらに連結元元帳にドリルダウンして連結元勘定科目残高を検討し、次に、連結元仕訳にドリルダウンして、連結元の補助元帳詳細にまでドリルダウンできます。
Oracle General Ledgerの照会およびドリルダウン機能の詳細は、次の項を参照してください。
グローバル連結システムから、Oracle General Ledgerの標準レポートおよび財務諸表生成プログラムにアクセスできます。これらのツールを使用して、経営陣の検討および分析用に、連結済および連結中のレポートを作成して実行します。Applications Desktop Integrator(ADI)のレポート定義ツールを使用して、スプレッドシート環境でレポートを作成して実行することもできます。
「連結ワークベンチ」ウィンドウにナビゲートします。
連結と消去を完了した期間を選択します。
「ステータス制御」から「レポート」ボタンを選択します。
「レポート」ウィンドウから、「財務」を選択してFSGレポートを実行するか、「標準」を選択して標準レポートおよびリストを実行します。
上記で選択したレポート・タイプに応じて、「財務レポートの実行」ウィンドウまたは「要求の発行」ウィンドウが表示されます。
関連項目: 標準レポートとびリストの実行および財務諸表生成プログラムの概要
Oracle Enterprise Planning and Budgeting(EPB)は、企業全体の計画、予算編成、予測、監視および分析に関するビジネス・プロセスを制御します。このEPBは、財務と業務の情報も含めたすべてのタイプのデータを収集した統合企業データ・モデルに基づいており、優れた可視性と情報の一貫性を提供して、ビジネスのより深い理解に役立ちます。
EPBでは、複数階層にわたる組織的な連結が処理され、明細項目と時間の集計が自動的に実行されます。
Oracle General LedgerのEPBとの統合によって、EPBが提供する強力な分析機能を使用して連結済の連結先データを分析できます。
関連項目
連結処理を監査モードで実行すると、「連結監査レポート」、「マップ取消連結元勘定科目」レポートおよび「連結先勘定科目無効」レポートを作成するための監査証跡が保守されます。これらのレポートを実行し終わったら、関連するソース・データをGL_CONSOLIDATION_AUDIT表からパージできます。
連結監査データをパージした後は、連結監査レポートを実行できません。ただし、連結仕訳バッチは連結先元帳で検討できます。
注意: 連結をパージするには、定義アクセス・セットによって、その連結に対して使用アクセス権が提供されている必要があります。
前提条件
監査モードで連結を実行します。
連結が問題なく完了したことを確認します。
必要な監査レポートをすべて実行します。
「連結監査データのパージ」ウィンドウにナビゲートします。
パージする連結名と期間を選択します。監査モードで実行した任意の連結をパージできます。
注意: 連結定義を保護するために定義アクセス・セットを使用している場合は、連結データをパージする定義に対して使用アクセス権が必要です。
「パージ」ボタンを選択し、選択した連結の連結監査データをパージします。
関連項目