リリース12
E06013-01
目次
前へ
次へ
| Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド リリース12 E06013-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この項では、Oracle Purchasingを設定するために実行する必要のある各ステップの概要を示します。
複数報告通貨
Oracle Purchasingで複数報告通貨(MRC)を使用する予定の場合は、追加の設定ステップが必要です。関連項目: 『Oracle Applicationsにおける複数報告通貨』
設定チェックリスト
この設定チェックリストのステップには「必須」と「オプション」があります。「デフォルトのある必須」は設定機能のデータベースにあらかじめデフォルト値を組み込んでありますが、作業のニーズに応じてデフォルト値を確認の上変更することもできます。変更が必要になった場合は、そのステップの設定を行ってください。「オプション」のステップを実行する必要があるのは、関連機能を使用する場合や、特定の業務を完了する場合のみです。
すでに共通アプリケーション設定(複数のOracle Applications製品の設定)を実行した場合は、実行する必要がない設定ステップもあります。
次の表に、Oracle Applicationsの設定ステップと参照先となるOracle Applicationsを示します。Oracle Applicationsにログオンした後、これらのステップを実行してOracle Purchasingを実装してください。
| ステップ番号 | 必須 | ステップ | アプリケーション |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 必須 | システム管理者の設定 | 共通アプリケーション |
| ステップ2 | 必須 | 会計キー・アプリケーションの定義 | 共通アプリケーション |
| ステップ3 | 必須 | カレンダ、通貨および元帳の設定 | 共通アプリケーション |
| ステップ4 | 必須 | Human Resourcesキー・フレックスフィールドの定義 | 共通アプリケーション |
| ステップ5 | 必須 | 事業所の定義 | Human Resources |
| ステップ6 | 必須 | 組織および組織関連の定義 | Human Resources |
| ステップ7 | 必須 | 複数組織アーキテクチャへの変換 | 共通アプリケーション |
| ステップ8 | 必須 | Inventoryキー・フレックスフィールドの定義 | 共通アプリケーション |
| ステップ9 | 必須 | 単位の定義 | Oracle Inventory |
| ステップ10 | オプション | 運送業者の定義 | Oracle Inventory |
| ステップ11 | デフォルトのある必須 | 品目属性、コードおよびテンプレートの定義 | Oracle Inventory |
| ステップ12 | 必須 | カテゴリの定義 | Oracle Inventory |
| ステップ13 | オプション | カタログ・グループの定義 | Oracle Inventory |
| ステップ14 | 必須 | 人事の設定 | Human Resources |
| ステップ15 | 必須 | Oracle Workflowの設定 | 共通アプリケーション |
| ステップ16 | 必須 | 勘定科目ジェネレータの使用方法の決定 | Oracle Purchasing |
| ステップ17 | 必須 | 在庫会計期間と購買会計期間のオープン | Oracle Purchasing |
| ステップ18 | オプション | 保管場所所在地の定義 | Oracle Inventory |
| ステップ19 | オプション | 相互参照タイプの定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ20 | オプション | 税金の定義 | Oracle E-Business Tax |
| ステップ21 | オプション | 支払条件の定義 | Oracle Payables |
| ステップ22 | 必須 | 承認情報の設定 | Oracle Purchasing |
| ステップ23 | デフォルトのある必須 | 参照と区分の定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ24 | オプション | 標準添付の定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ25 | 必須 | 購買オプションの定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ26 | 必須 | 購買担当の定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ27 | オプション | 品目の定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ28 | デフォルトのある必須 | 明細タイプの定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ29 | 必須 | 購買データベース管理の起動 | Oracle Purchasing |
| ステップ30 | 必須 | 会計オプションの定義 | Oracle Payables |
| ステップ31 | オプション | 取引事由の定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ32 | 必須 | 受入オプションの定義 | Oracle Purchasing |
| ステップ33 | 必須 | 取引マネージャと再発行間隔の設定 | Oracle Purchasing |
| ステップ34 | 必須 | 仕入先の定義 | Oracle Payables |
| ステップ35 | デフォルトのある必須 | ワークフロー・オプションの設定 | Oracle Purchasing |
| ステップ36 | 必須 | ワークフロー関連プロセスの発行 | Oracle Purchasing |
| ステップ37 | オプション | 付加フレックスフィールドの定義 | 共通アプリケーション |
| ステップ38 | オプション | 自動ソーシングの設定 | Oracle Purchasing |
| ステップ39 | 必須 | 追加のシステム管理者設定の実行 | 共通アプリケーション |
| ステップ40 | 必須 | 製造システムとユーザー・プロファイルの定義 | Oracle Purchasing |
「コンテキスト」の項は、元帳、タスク・セット、在庫組織、HR組織または複数組織における他の営業単位ごとに、影響を受けるステップを繰り返す必要があるかどうかを示します。
ステップ1: システム管理者の設定
このステップには、次のタスクが含まれます。
設定中にログオン名として使用するスーパーユーザーの作成と、そのスーパーユーザーに対する必須の設定職責の割当て。通常、必須の職責は次のとおりです(必須)。
Purchasing
システム管理者
プリンタの設定。この時点でプリンタをすべて設定する必要はありませんが、設定中に何かを印刷する場合はプリンタを1台設定しておくと便利です(オプション)。
関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のOracle Applications System Administratorの設定に関する項
ステップ2: 会計キー・フレックスフィールドの定義(必須)
会計上のキー・フレックスフィールドと相互検証ルールを設定します。すでにOracle General Ledgerをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合はこのステップを省略できます。関連項目: 『Oracle General Ledger インプリメンテーション・ガイド』の会計フレックスフィールドの設計に関する項。
重要: 他のOracle Applicationsをインストール中か、今後インストール予定の場合は、このステップでキー・フレックスフィールドを定義する前に、該当製品のフレックスフィールド設定と調整してください。フレックスフィールド・データの取得後にフレックスフィールドを変更することはお薦めしません。
キー・フレックスフィールドの設定方法は、『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』のキー・フレックスフィールドの計画と定義に関する項を参照してください。
ステップ3: カレンダ、通貨および元帳の設定(必須)
他のOracle Applications製品の設定中にカレンダ、通貨および元帳を定義した場合は、次のステップに進みます。
コンテキスト: Oracle Purchasingの複数組織インプリメンテーションを実行する場合は、必要に応じて複数のカレンダ、通貨または元帳を作成できます。関連項目: 『Oracle Applicationsにおける複数組織』。
このステップには、次のタスクが含まれます。
カレンダの設定。
期間タイプの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「期間タイプの定義」
会計カレンダの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「カレンダの定義」
注意: 特定のOracle Manufacturingアプリケーションをインストールする場合は、次の3つのオプション項目を定義できます。
取引カレンダの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の取引カレンダの定義に関する項。(オプション)
稼働日カレンダの定義。関連項目: 『Oracle Bills of Materialユーザーズ・ガイド』の稼働日カレンダの概要に関する項。(オプション)
例外テンプレートの定義。関連項目: 『Oracle Bills of Materialユーザーズ・ガイド』の稼働日カレンダの概要に関する項。(オプション)
通貨の定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「通貨の定義」
換算レート・タイプの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「換算レート・タイプの定義」
会計情報の定義。組織の主要元帳を1つ以上定義する必要があります。関連項目: 『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の元帳の定義に関する項。
現行職責への元帳の割当て。関連項目: 『Oracle General Ledgerインプリメンテーション・ガイド』の元帳勘定科目の割当てに関する項。
通貨レートの定義。
取引日レートの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の取引日レートの入力に関する項。
期間レートの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の期間レートの入力に関する項。
取得時レートの定義。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の取得時レートの入力に関する項。
会計コード組合せの設定。Oracle Purchasingインストールに対応する勘定体系についてコード組合せの動的入力を許可する場合、このタスクを実行する必要はありません。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』。
会計期間のオープンおよびクローズ。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「会計期間のオープンおよびクローズ」
ステップ4: Human Resourcesキー・フレックスフィールドの定義(必須)
すでにオラクル人事管理システムをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合は、このステップを省略できます。詳細は、『Oracle HRMSインプリメンテーション・ガイド』を参照してください。
重要: 他のOracle Applicationsをインストール中か、今後インストール予定の場合は、このステップでキー・フレックスフィールドを定義する前に、該当製品のフレックスフィールド設定と調整してください。フレックスフィールド・データの取得後にフレックスフィールドを変更することはお薦めしません。
後述の各キー・フレックスフィールドの設定方法は、『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』を参照してください。
Oracle Human ResourcesとOracle Payrollの次のキー・フレックスフィールドを定義します。
役職フレックスフィールド
職階フレックスフィールド
等級フレックスフィールド
原価割当フレックスフィールド
Peopleグループ・フレックスフィールド
個人特別情報フレックスフィールド
ステップ5: 事業所の定義(必須)
他のOracle Applicationsも設定している場合は、そのアプリケーションの設定時に事業所の定義を完了している場合があります。
このステップで事業所を1つ以上設定する必要があります。残りの事業所は、在庫組織と税金コードを定義した後で設定できます。
事業所を在庫組織にリンクする場合は、組織の設定後にこのステップの再実行が必要になることがあります。
関連項目: 事業所の定義
ステップ6: 組織および組織関連の定義(必須)
すでにOracle Inventoryをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合はこのステップを省略できます。
組織の設定に関連する次のタスクについては、『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』を参照してください。
ビジネス・グループの定義(デフォルトの「ビジネス・グループの設定」を使用せずに新規ビジネス・グループを定義する場合)。関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』のオラクル人事管理システム・ウィンドウを使用するアプリケーションのセキュリティの設定に関する項および『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』のビジネス・グループを使用した事業主の表示に関する項。
職責へのビジネス・グループの割当て。職責内でプロファイル・オプション「HR: ビジネス・グループ」がその職責に使用するビジネス・グループに設定されているかどうかを確認します。
重要: 後述の組織を定義する前に、「HR: ビジネス・グループ」プロファイル・オプションを使用予定のビジネス・グループに設定することが重要です。
法的エンティティ組織の定義。
営業単位の定義と法的エンティティへの割当て。
在庫組織の設定。在庫組織の設定に関連する次のタスクについては、『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』を参照してください。
在庫組織としての組織の分類。
在庫組織の会計情報の定義。
在庫組織パラメータの定義。
在庫組織の受入オプションの定義。このタスクについては、「受入オプションの定義」を参照してください。
人事組織の定義。
組織階層の定義。(オプション)
ステップ7: 複数組織アーキテクチャへの変換(必須)
この設定ステップはオプションですが、ビジネスが単一営業単位のみで構成されている場合にも実行することをお薦めします。このステップを実行すると、後で営業単位を柔軟に追加できます。
このステップには次のタスクが含まれます。
プロファイル・オプション「MO: 営業単位」および「HR: ユーザー・タイプ」の設定。
複数組織アーキテクチャへの変換ユーティリティの実行。このタスクにはシステム管理者を関与させることをお薦めします。
関連項目: 『Oracle Applicationsにおける複数組織』
自社が共有サービス運用モデルを実装している場合は、複数組織アクセス管理(MOAC)を使用するとビジネス取引をより効率的に処理できます。データ・セキュリティやシステム・パフォーマンスの面で妥協せずに、単一の職責から複数の営業単位にまたがるデータにアクセスし、処理してレポートを作成できます。
複数組織アクセス管理を使用するには、次のタスクを実行します。
複数組織セキュリティ・プロファイルを定義します。関連項目: 『Oracle HRMSインプリメンテーション・ガイド』のセキュリティ・プロファイルの定義に関する項。
「MO: セキュリティ・プロファイル」プロファイル・オプションを、複数の営業単位へのアクセスを必要とする各アプリケーション職責のセキュリティ・プロファイルに設定します。
「MO: デフォルト営業単位」プロファイル・オプションを、前述のステップで使用した職責のデフォルト営業単位に設定します。
ステップ8: Inventoryキー・フレックスフィールドの定義(必須)
すでにOracle Inventoryをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合は、このステップを省略できます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のOracle Inventoryフレックスフィールドに関する項。
重要: 他のOracle Applicationsをインストール中か、今後インストール予定の場合は、このステップでキー・フレックスフィールドを定義する前に、該当製品のフレックスフィールド設定と調整してください。フレックスフィールド・データの取得後にフレックスフィールドを変更することはお薦めしません。
後述の各キー・フレックスフィールドの設定方法は、『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』を参照してください。
Inventoryキー・フレックスフィールドを定義します。
システム品目フレックスフィールド。システム品目フレックスフィールドのコンパイル後に、「品目フレックスフィールド・ビュー」コンカレント要求が開始されます。
品目カテゴリ・フレックスフィールド。
発注品目カテゴリ・フレックスフィールド。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目カテゴリのフレックスフィールド体系に関する項。
品目カタログ・フレックスフィールド。
在庫保管棚フレックスフィールド。
勘定科目別名フレックスフィールド。
受注フレックスフィールド。
注意: Oracle Inventoryの取引(「品目の定義」ウィンドウなど)、照会およびレポートには確定済のフレックスフィールド定義が必要なため、前述のフレックスフィールドをまったく使用しない場合にも、フレックスフィールドごとにセグメントを1つ以上有効化してコンパイルする必要があります。
ステップ9: 単位の定義(必須)
すでにOracle Inventoryをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合は、このステップを省略できます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』。
このステップには、次のタスクが含まれます。
単位区分の定義。
単位の定義。
単位換算の定義。ニーズに応じて標準、区分内または区分間という3つの異なる換算タイプを定義できます。
ステップ10: 運送業者の定義(オプション)
仕入先が使用する運送業者を発注上で指定する場合は、運送業者を定義します。
関連項目: 『Oracle Order Managementインプリメンテーション・マニュアル』の運送業者および出荷方法の定義に関する項
コンテキスト: このステップは在庫組織ごとに実行する必要があります。
ステップ11: 品目属性、コードおよびテンプレートの定義
関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』
このステップには、次のタスクが含まれます。
品目属性管理の定義。(デフォルトのある必須)
デフォルト: ほとんどの品目属性グループは、品目マスター・レベルの管理にデフォルト設定されます。残りの品目属性グループは品目/組織レベルにデフォルト設定されます。
コンテナ・タイプ・クイックコードの定義。このクイックコードを使用して品目の物理属性を定義できます。(オプション)
ステータス・コードの定義。(デフォルトのある必須)
デフォルト: デフォルトのステータス・コードには、有効、無効、廃止およびプロトタイプなどの基本的なステータスが含まれています。
品目タイプ・クイックコードの定義。(デフォルトのある必須)
デフォルト: デフォルトのクイックコードには、完成品、オプション区分、キット、購買品目およびその他が含まれています。
顧客品目商品コードの定義。このコードを使用して顧客品目をグループ化できます。(オプション)
品目テンプレートの定義。多数の品目の多数の属性で同じ値が共有される場合は、品目テンプレートを定義できます。(オプション)
ステップ12: カテゴリの定義
Oracle Inventoryも設定している場合、このステップはOracle Inventoryの設定時に実行済の可能性があります。
このステップには、次のタスクが含まれます。
カテゴリ・コードの定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリの定義に関する項。(必須)
カテゴリ・セットの定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリ・セットの定義に関する項。(デフォルトのある必須)
デフォルト: カテゴリ・セットには「在庫」や「購買」などの例があります。
デフォルト・カテゴリ・セットの定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のデフォルト・カテゴリ・セットの定義に関する項。(デフォルトのある必須)
デフォルト: 各機能領域にはデフォルト・カテゴリ・セットが用意されています。
ステップ13: カタログ・グループの定義(オプション)
カタログ・グループは、タイプ、サイズまたは色などの値セットを割り当てる品目の付加要素で構成されます。Oracle Inventoryも設定している場合、このステップはOracle Inventoryの設定時に実行済の可能性があります。
関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目カタログ・グループの定義に関する項
ステップ14: 人事の設定
すでにオラクル人事管理システムをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合はこのステップを省略できます。次のステップの詳細は、『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』またはHRMSオンライン・ヘルプを参照してください。
このステップには、次のタスクが含まれます。
従業員クイックコードの定義。(デフォルトのある必須)
役職の定義。関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の役職と職階の表示に関する項。(必須)
職階の定義。職階承認階層を使用予定の場合は、職階を定義する必要があります。関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の役職と職階の表示に関する項。(オプション)
職階階層の定義。ニーズにあわせて職階階層を1つ以上定義できます。関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の「職階階層」ウィンドウに関する項。(オプション)
デフォルト: このタスクを省略すると、職階承認階層を使用できません。かわりに従業員/管理者承認方法を使用する必要があります。
「会計オプション」ウィンドウでの次の会計オプションの定義。関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項。(必須)
「従業員採番方法」
職階承認階層オプション(職階承認階層を使用するかどうか)
「在庫組織」
「ビジネス・グループ」(ビジネス・グループが指定されているかどうかを確認)
「仕入先採番方法」
従業員の定義。オラクル人事管理システムを使用せずにOracle Purchasingのみを使用する場合は、Oracle Purchasingの設定ウィンドウを使用して従業員を定義します。Oracle Purchasingをオラクル人事管理システムと併用する場合は、人事管理システム・アプリケーションの設定ウィンドウを使用して従業員を定義します。入力の詳細は、「個人情報入力」ウィンドウのオンライン・ヘルプを参照してください。関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の新しい個人レコードの作成に関する項。(必須)
注意: Oracle Purchasingユーザーのユーザー名を後の設定ステップで設定する必要があります。このOracle Purchasingユーザー名は従業員名にリンクする必要があります。
ステップ15: Oracle Workflowの設定(必須)
Oracle PurchasingではOracle Workflowテクノロジを使用して、文書承認、自動文書作成および勘定科目生成を勘定科目ジェネレータを介して実行するため、設定していない場合はOracle Workflowを設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflow管理者ガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
ステップ16: 勘定科目ジェネレータの使用方法の決定(必須)
Oracle Purchasingでは、勘定科目ジェネレータ・プロセスにより各発注、リリースおよび購買依頼配分に使用する借方勘定、予算勘定、経過勘定および差異勘定が、配分の「費用」、「在庫」または「製造現場」搬送先タイプに基づいて作成されます。Oracle Purchasingで会計要件を満たしているかどうかの確認に使用するデフォルト・プロセスを検討する必要があります。定義した元帳ごとに勘定科目ジェネレータをカスタマイズすることもできます。関連項目: Oracle Purchasingでの勘定科目ジェネレータの使用方法。
コンテキスト: このステップは営業単位ごとに実行する必要があります。
ステップ17: 在庫会計期間と購買会計期間のオープン(必須)
このステップには次のタスクが含まれます。
在庫会計期間のオープン。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の会計期間の管理に関する項。
コンテキスト: このタスクは在庫組織ごとに実行する必要があります。
購買会計期間のオープン。関連項目: 購買管理期間。
コンテキスト: このタスクは元帳ごとに実行する必要があります。
ステップ18: 保管場所所在地の定義(オプション)
検査、冷蔵または不合格-処分など、独自の保管場所所在地を定義できます。すでにOracle Inventoryをインストールして設定している場合は、このステップを省略できます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の保管場所の定義に関する項。
コンテキスト: このステップは在庫組織ごとに実行する必要があります。
ステップ19: 相互参照タイプの定義(オプション)
相互参照タイプの一例として、品目番号と仕入先が使用する部品番号の相互参照に使用するタイプがあります。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の相互参照タイプの定義に関する項。
ステップ20: 税金の定義(オプション)
税金を定義して控除率またはルールに割り当てます。Oracle Payablesをインストールして設定しているか、または共通アプリケーション設定を完了している場合は、このステップを省略できます。関連項目: 『Oracle E-Business Taxユーザー・ガイド』の税金の設定に関する項、または『Oracle E-Business Tax Implementation Guide』。
デフォルト: このステップを省略すると、購買依頼または発注に対する税金は計算されず、他の税金属性を選択またはデフォルト設定できません。
ステップ21: 支払条件の定義(オプション)
Oracle Payablesも設定している場合は、Oracle Payablesの設定時にこのステップを完了している可能性があります。30日満期1/10などの支払条件を設定できます。この支払条件は、請求書の期限が30日以内であることと、10日以内に支払うと1%の値引が適用されることを示します。
関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の支払条件に関する項
ステップ22: 承認情報の設定
すべての承認者は従業員で、「ステップ14: 人事の設定」で説明したログオン・ユーザー名を持つ必要があります。
注意: オフラインの承認者にもユーザー名が必要です。オフラインの承認者とは、Oracle Applicationsにログオンせずに「通知要約」ウィンドウを使用して購買文書を承認するユーザーです。オフラインの承認者を設定するには、「オフラインの承認者」を参照してください。承認者全員にユーザー名を割当済で、Oracle Workflowが設定済であれば、オフラインの承認者をいつでも設定できます。
すべての承認者を従業員として設定し、ユーザー名を指定して設定した後、次の承認設定を完了します。
コンテキスト: このステップは営業単位ごとに実行する必要があります。
承認グループの定義。関連項目: 承認グループの定義。(必須)
承認グループの割当て。関連項目: 承認グループの割当。(必須)
職階承認階層を定義した後の従業員階層の入力。関連項目: 従業員階層登録処理。職階承認階層を使用する場合は、従業員階層登録処理を実行する必要があります。(オプション)
文書タイプの定義。関連項目: 文書タイプの定義。(デフォルトのある必須)
デフォルト: 各購買文書(標準発注、包括購買契約、見積または購買依頼)には、標準のデフォルト設定があります。これらのデフォルトをセキュリティ上と承認上のニーズにあわせて更新してください。
ステップ23: 参照と区分の定義
このステップには、次のタスクが含まれます。
購買参照の定義。関連項目: 参照コードの定義。(デフォルトのある必須)
デフォルト: Oracle Purchasingには、「固定」価格タイプなどのデフォルト参照コードが用意されています。Oracle Purchasingに用意されている他のデフォルトのリストは、前述の項を参照してください。
検査コードの定義。関連項目: 品質検査コードの定義。(オプション)
デフォルト: このタスクを省略すると、受入時に検査コードを割り当てることができません。
危険度区分の定義。関連項目: 危険度区分の定義。(オプション)
デフォルト: このタスクを省略すると、品目または発注明細に危険度区分を割り当てることができません。
国連(UN)番号の定義。関連項目: 国連番号の定義。(オプション)
デフォルト: このタスクを省略すると、品目または発注明細に国連番号を割り当てることができません。
ステップ24: 標準添付の定義(オプション)
ここで標準添付を定義しない場合、後でいつでも定義できます。関連項目: 購買文書への注釈付け。関連項目: 購買文書へのノートの添付。
ステップ25: 購買オプションの定義(必須)
関連項目: 購買オプションの定義
コンテキスト: このステップは営業単位ごとに実行する必要があります。
ステップ26: 購買担当の定義(必須)
購買担当またはマネージャとしてOracle Purchasingを使用する従業員全員を購買担当として定義する必要があります。関連項目: 購買担当の定義。
ステップ27: 品目の定義(オプション)
品目はこのステップ以降のどの時点でも定義できますが、フレックスフィールドが正常に機能することを確認するために、品目を1つ以上設定することをお薦めします。
デフォルト: このステップを省略した場合、購買依頼または発注の作成時に入力できるのは品目摘要のみで、品目番号は入力できません。
コンテキスト: このステップは在庫組織ごとに実行する必要があります。
このステップには次のタスクが含まれます。
マスター・レベルでの品目の定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のマスター・レベルと組織レベルに関する項および品目の定義に関する項。「マスター品目」ウィンドウには、Oracle Inventoryが共有インストールではなく完全インストールされている場合にのみ使用可能な在庫フィールド(「シリアル番号」フィールドなど)が存在することに注意してください。
品目に割当済のデフォルト・カテゴリの更新。
組織レベルでの品目の割当て。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の組織レベル品目の更新に関する項。
品目関連の定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目関連の定義に関する項。
ステップ28: 明細タイプの定義(デフォルトのある必須)
関連項目: 明細タイプの定義
デフォルト: Oracle Purchasingには、「商品」、「サービス」および「外注加工費」(Oracle Work in Processがインストール済の場合)などのデフォルト明細タイプが用意されています。
ステップ29: 購買データベース管理の起動(必須)
関連項目: 購買データベース管理
ステップ 30: 会計オプションの定義(必須)
関連項目: 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項
コンテキスト: このステップは営業単位ごとに実行する必要があります。
ステップ31: 取引事由の定義(オプション)
取引事由コードを使用すると、受入取引ごとに事前定義済の説明を提供できます。梱包リストなし、不足、取消または仕入先エラーなどの取引事由コードを定義できます。Oracle Inventoryも設定している場合、このステップはOracle Inventoryの設定時に実行済の可能性があります。
関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の取引事由の定義に関する項
ステップ 32: 受入オプションの定義(必須)
「ステップ6: 組織および組織関連の定義」で受入オプションを定義した場合は、このステップを省略できます。関連項目: 受入オプションの定義。
コンテキスト: このステップは、すべての在庫組織に対して実行する必要があります。「購買管理」メニューの「組織の変更」機能を使用して、このステップを在庫組織ごとに実行します。
ステップ33: 取引マネージャと再発行間隔の設定
このステップには、次のタスクが含まれます。
次の取引マネージャの起動。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の「コンカレント・マネージャの管理」ウィンドウに関する項。(必須)
受入取引マネージャ
文書承認マネージャ
コンカレント・プロセスの再発行間隔の定義。このタスクのヘルプが必要な場合は、システム管理者に連絡してください。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のマネージャおよびマネージャの稼働シフトの定義に関する項。(オプション)
ステップ34: 仕入先の定義(必須)
すでにOracle Payablesをインストールし、共通アプリケーションの設定を行っている場合は、このステップを省略できます。関連項目: 『Oracle iSupplier Portal Implementation Guide』の仕入先情報の入力に関する項。
ステップ35: ワークフロー・オプションの設定(デフォルトのある必須)
Oracle Purchasingでは、Oracle Workflowテクノロジを使用して購買依頼と発注の承認、発注とリリースの自動作成、発注変更(特に変更に必要な追加承認)および受入確認を処理します。ワークフローはバックグラウンドで実行されます。これにより、文書を承認のために発行するか、購買依頼を作成するか、発注を変更すると、これらの調達アクティビティが自動化されます。
デフォルト: Oracle Purchasingでは、このようにOracle Workflowにより自動化されるプロセスにデフォルト機能が用意されています。たとえば、デフォルト機能の1つは、自動文書作成ワークフローで承認済購買依頼明細から発注を自動的に作成する機能です。このデフォルト機能が不要な場合は、Oracle Workflow Builderで容易に変更できます。
Oracle Purchasingに用意されている他のデフォルトの詳細は、「ワークフロー・オプションの選択」を参照してください。
ステップ36: ワークフロー関連プロセスの発行
以前のステップで開始していない場合、次のワークフロー関連プロセスを開始します。
「購買文書通知の発送」プロセス。関連項目: 購買文書通知の発送。(必須)
ワークフロー・バックグラウンド・エンジン。「ワークフロー・オプションの選択」で説明したように、このプロセスを発行する必要があるかどうかは、選択したオプションまたは受け入れたデフォルトに応じて異なります。ワークフロー・バックグラウンド・エンジンの発行手順は、『Oracle Workflowガイド』のワークフロー・バックグラウンド・エンジンの計画に関する項を参照してください。(デフォルトのある必須)
デフォルト: Oracle Purchasingに用意されているデフォルトのワークフロー・オプションを受け入れるように選択した場合は、ワークフロー・バックグラウンド・エンジンを起動する必要があります。
ステップ37: 付加フレックスフィールドの定義(オプション)
このステップで付加フレックスフィールドを定義しない場合は、いつでも定義できます。関連項目: 『Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイド』の付加フレックスフィールドの計画と定義に関する項。
ステップ38: 自動ソーシングの設定(オプション)
特定の品目と仕入先についてソース文書情報を購買契約またはカタログ見積から購買依頼または発注明細に自動的にデフォルト設定するように、Oracle Purchasingを設定できます。または、仕入先のみをデフォルト設定し、必要に応じて仕入先サイトをデフォルト設定することも可能です。関連項目: 自動ソーシングの設定。
自動ソーシングは、このステップで設定するか、後から設定できます。
ステップ39: 追加のシステム管理者設定の実行
このステップには、次のタスクが含まれます。
カスタム・メニューの定義。(オプション)
ビジネス・ニーズとセキュリティ・ニーズに基づく新規職責の定義。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』。(オプション)
ユーザー名の定義。Oracle Purchasingユーザーにはユーザー名が必要で、そのユーザー名を従業員名にリンクする必要があります。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の「ユーザー」ウィンドウに関する項。(必須)
プリンタの定義(未定義の場合)。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のプリンタの設定に関する項。(オプション)
ステップ40: 製造システムとユーザー・プロファイルの定義(必須)
関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』のユーザー・プロファイル・オプションの設定に関する項。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』の共通のユーザー・プロファイル・オプションに関する項。関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション。
コンテキスト: このステップは営業単位ごとに実行する必要があります。
「事業所」ウィンドウを使用して、購買文書に使用する出荷先事業所、受入事業所およびその他の事業所情報を定義します。
Oracle Purchasing用の事業所を設定する手順は、次のとおりです。
「事業所」ウィンドウにナビゲートします。
「名称」、「摘要」、「失効日」、「グローバル」および「住所詳細」フィールドに情報を入力します。『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の事業所の設定に関する項の指示に従うか、「事業所」ウィンドウのオンライン・ヘルプを参照してください。
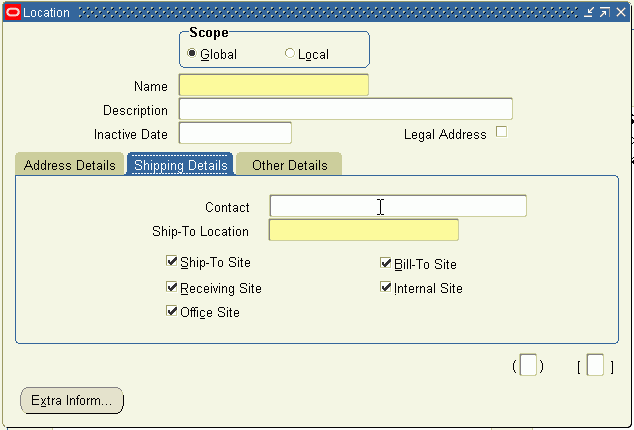
「出荷詳細」タブ・リージョンに情報を入力します。
注意: チェック・ボックスを選択すると、その事業所名が購買文書の値リスト内で有効な事業所となります。たとえば、「出荷先」を選択すると、その事業所名は購買ヘッダーの「出荷先」フィールドの値リストに有効な選択肢として表示されます。組織の「会計オプション」ウィンドウの「仕入先-購買」リージョンで定義したデフォルトの出荷先または請求先事業所が発注の事業所としてデフォルト設定されることに注意してください。ただし、そのデフォルトを変更する場合は、ここで定義して出荷先または請求先サイトとして有効化した事業所名は値リスト内で使用可能で、「出荷先」または「請求先」フィールドで選択できます。
連絡先: 事業所名のオプションの連絡先名。
出荷先事業所: 通常は事業所名と同じです。前に定義した別の出荷先事業所を選択することもできます。たとえば、オフィスAという事業所名を作成し、出荷先事業所として受入ドックAを指定できます。ただし、別の出荷先事業所を指定すると、その事業所名は出荷先サイトにできなくなることに注意してください。この例では、受入ドックAがオフィスAの出荷先サイトとなるため、オフィスA自体を出荷先サイトにすることはできません。
出荷先: 事業所名を発注または購買依頼上の有効な出荷先組織にするには、このオプションを選択します。
受入先: 事業所を受入または受入取引の作成時に有効な受入事業所にするには、このオプションを選択します。
受入先: 事業所を受入または受入取引の作成時に有効な受入事業所にするには、このオプションを選択します。
請求先: 事業所名を有効な請求先サイトにするには、このオプションを選択します。Oracle Payablesで使用される請求先サイトは、発注ヘッダーで指定します。
社内先: 事業所を社内購買依頼の作成時に有効な社内出荷先事業所にするには、このオプションを選択します。
必要に応じて「その他詳細」タブ・リージョンに情報を入力します。
在庫組織: この事業所を購買文書の値リストで使用可能にする在庫組織を選択します。在庫組織を選択しなければ、この事業所は全組織の購買文書で使用可能になります。
EDI事業所: 電子データ交換(EDI)を使用して事前出荷通知(ASN)または請求情報付きASN(ASBN)を受信するには、定義済の事業所を入力します。この事業所は、ASNまたはASBNで指定された出荷先事業所と一致する必要があります。関連項目: 事前出荷通知。
「その他情報」ボタンを使用してビジネスに必要な情報を追加入力する場合は、『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』のその他情報の入力に関する項、または該当するウィンドウのオンライン・ヘルプを参照してください。
「購買担当」ウィンドウを使用して、購買担当の定義と管理を行います。購買担当は「購買依頼」ウィンドウを使用してすべての購買依頼を検討でき、購買文書を入力、自動作成できるのは、購買担当だけです。文書へのアクセスを管理するルールについては、「文書タイプ」ウィンドウを参照してください。関連項目: 文書タイプの定義。
前提条件
このステップを実行する前に従業員を定義します。詳細は、「個人情報入力」ウィンドウのオンライン・ヘルプを参照してください。
このステップを実行する前に事業所を定義します。関連項目: 事業所の定義。
購買担当を定義する手順は、次のとおりです。
「購買担当」ウィンドウにナビゲートします。
新しい購買担当を定義する場合は、「購買担当」ウィンドウで「バイヤーの追加」をクリックします。既存の購買担当を変更するには、「検索」リージョンを使用して「購買担当」フィールドに購買担当名を入力するか、「カテゴリ」フィールドに購買担当に割り当てられたカテゴリを入力するか、または「納入先」フィールドに購買担当の納入先事業所を入力します。これらのフィールドの1つまたはすべてに入力した後、「進む」をクリックします。
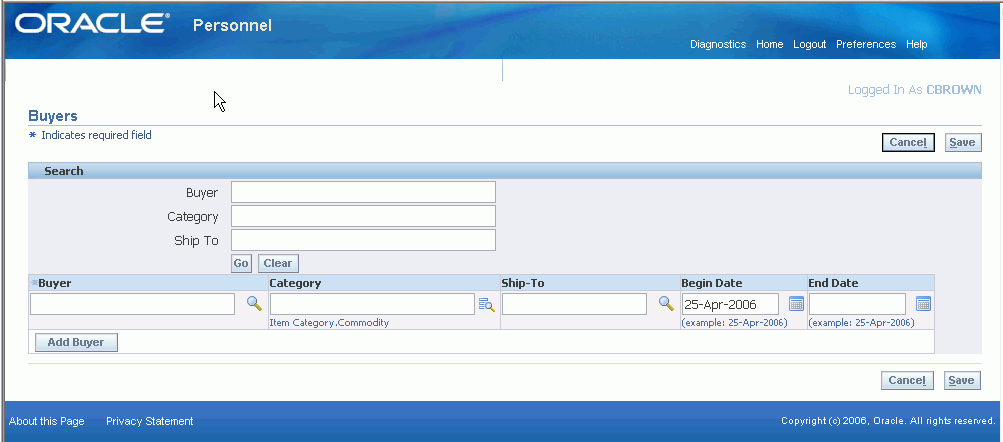
購買担当として定義する従業員の氏名を入力します。必要な氏名が値リストに表示されない場合は、「個人情報入力」ウィンドウを使用して、その個人を従業員として入力します。
購買担当が通常発注する商品のデフォルト購買カテゴリを入力します。Oracle Purchasingで文書を自動作成する際に、この値が「カテゴリ」フィールドにデフォルト設定されます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリの定義に関する項。
購買担当が発注の作成に通常使用する出荷先事業所の名称を入力します。Oracle Purchasingでは、この値が文書の自動作成時にデフォルト設定されます。
購買担当の職責を開始する開始日を入力します。デフォルトは現在の日付です。
終了日を入力します。この日付の後は、その従業員は購買担当でなくなります。
「保存」をクリックします。
「承認グループ」ウィンドウを使用して、承認グループの定義と更新を行います。ここで定義した承認グループを使用して、「承認割当」ウィンドウで役職または職階に承認機能を割り当てることができます。有効な割当てで使用中の承認グループは削除できません。承認グループ全体を有効化または無効化したり、各承認ルールの無効日を個別に入力できます。
前提条件
このステップを実行する前に従業員を定義します。詳細は、「個人情報入力」ウィンドウのオンライン・ヘルプを参照してください。
このウィンドウで選択した内容が承認経路にどのように影響するかを検討します。関連項目: 承認処理権限ルールの定義。
承認グループを定義する手順は、次のとおりです。
「承認グループ」ウィンドウにナビゲートします。
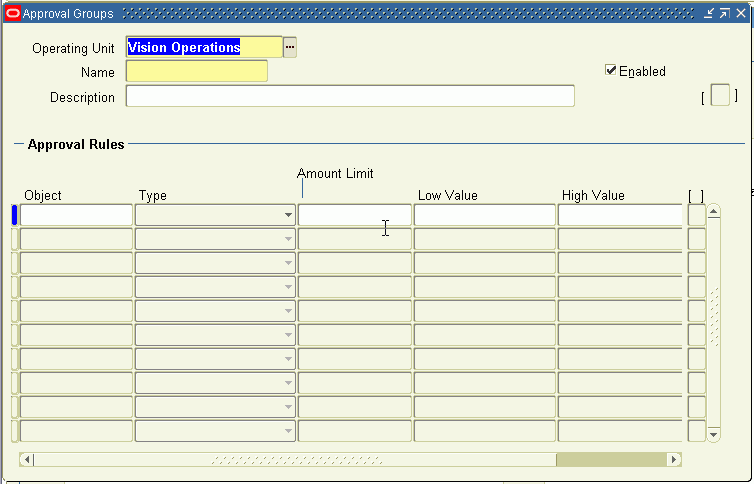
この承認グループの営業単位を選択します。
承認グループ名を入力します。既存の承認グループ名を変更できますが、一意の名称にする必要があります。
「使用可」を選択して、「承認割当」ウィンドウで承認グループを職階または役職に割当可能にします。
次のいずれかのオブジェクトを選択します。
勘定科目範囲: (必須)このオプションを選択した場合は、「下位値」と「上位値」に会計フレックスフィールドを入力します。「含む」タイプのルールで文書に含める勘定科目を識別し、「除外」タイプのルールで文書から除外する勘定科目を識別します。勘定科目に対するルールを入力しなければ、その勘定科目はデフォルトで除外されます。「除外」タイプのルールのみを入力すると、自動的には何も組み込まれません。
たとえば、次の勘定科目のみを入力すると、勘定科目01.000.0451のみが組み込まれ、他の勘定科目はすべて除外されます。
| 勘定科目範囲 | 含む | 01.000.0451 | 01.000.0451 |
次の勘定科目のみを入力すると、すべての勘定科目が除外されます。
| 勘定科目範囲 | 除外 | 01.000.0451 | 01.000.0451 |
次の2つの勘定科目のみを入力すると、01.000.0451を除く全勘定科目が組み込まれます。
| 勘定科目範囲 | 含む | 00.000.0000 | ZZ.ZZZ.ZZZZ | |
| 除外 | 01.000.0451 | 01.000.0451 |
「無効日」はオプションですが、「含む」タイプのルールの場合は「限度額」に値を入力する必要があります。
文書合計: (必須)文書合計は、個別文書の限度額を指します。このオプションを選択すると、「タイプ」は「含む」にデフォルト設定され、入力できるのは「限度額」(必須)と「無効日」(オプション)のみとなります。
品目カテゴリ範囲: このオプションを選択した場合は、「下位値」と「上位値」に購買カテゴリ・フレックスフィールドを入力します。「含む」タイプのルールで文書に含める製造カテゴリを識別し、「除外」タイプのルールで文書から除外するカテゴリを識別します。カテゴリに対するルールを定義しなければ、「含む」にデフォルト設定されます。「無効日」はオプションですが、「含む」タイプのルールの場合は「限度額」に値を入力する必要があります。
品目範囲: このオプションを選択した場合は、「下位値」と「上位値」に品目フレックスフィールドを入力します。「含む」タイプのルールで文書に含める品目を識別し、「除外」タイプのルールで文書から除外する品目を識別します。品目に対するルールを定義しなければ、「含む」にデフォルト設定されます。「無効日」はオプションですが、「含む」タイプのルールの場合は「限度額」に値を入力する必要があります。
事業所: 事業所は、購買依頼上の搬送先事業所と、発注およびリリース上の出荷先事業所を指します。「含む」タイプのルールで文書に含める事業所を識別し、「除外」タイプのルールで文書から除外する事業所を識別します。このオプションを選択した場合は、「下位値」フィールドに事業所を入力します。事業所に対するルールを定義しなければ、「含む」にデフォルト設定されます。「無効日」はオプションですが、「含む」タイプのルールの場合は「限度額」に値を入力する必要があります。
ルール・タイプを選択します。「含む」または「除外」は、選択した範囲内のオブジェクトを許可するかどうかを示します。
限度額を入力します。これは、管理グループが特定のオブジェクト範囲に対して承認できる最大金額です。このフィールドは、「含む」タイプのルールについてのみ必須です。
下位値を入力します。これは、このルールに関連する範囲内の最下位フレックスフィールド(会計、購買カテゴリまたは品目)です。オブジェクトが「事業所」の場合は事業所を入力します。オブジェクトが「文書合計」の場合、このフィールドには入力できません。
上位値を入力します。これは、このルールに関連する範囲内の最上位フレックスフィールド(会計、購買カテゴリまたは品目)です。オブジェクトが「事業所」または「文書合計」の場合、このフィールドには入力できません。
このルールがOracle Purchasingでグループの作成に使用されなくなる無効日を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目
「承認グループの割当」ウィンドウを使用して、職階または役職に承認グループと承認機能を割り当てます。承認階層を使用している(「会計オプション」ウィンドウで「承認階層の使用」オプションが有効化されている)場合は、最初に「承認グループ」ウィンドウを使用して承認グループに関するルールを設定する必要があります。これにより、このウィンドウで職階に承認グループを割当可能になります。承認階層を使用しない場合は、このウィンドウを使用して組織内の役職に承認グループと承認機能を割り当てることができます。
前提条件
承認グループを割り当てる手順は、次のとおりです。
「承認グループの割当」ウィンドウにナビゲートします。
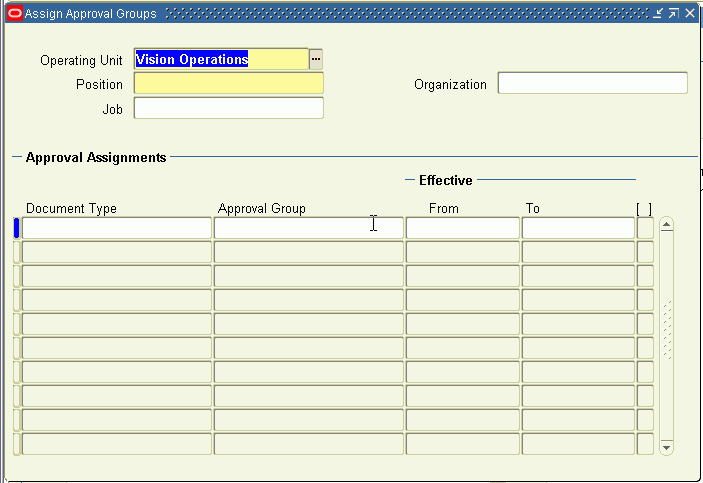
この承認グループ割当の営業単位を選択します。
承認グループと承認機能を割り当てる職階を入力します。「会計オプション」ウィンドウで「承認階層の使用」オプションが有効化されていない場合、このフィールドは適用できません。
承認階層を使用しない場合は、役職を入力します。
この職階または役職に割り当てる承認機能を選択します。
選択した職階または役職に割り当てる承認グループを入力します。値リストには、1つ以上の承認ルールがあって有効化されている承認グループのみが表示されます。関連項目: 承認グループの定義。
割当の開始日および終了日を入力します。
重要: ここで割り当てる開始日と終了日は、割当の有効期間を示す日付です。システム日付が割当の終了日に達すると、ルールが適用されなくなります。ルールが有効でなくなることを示す明示的な警告は表示されません。
作業内容を保存します。
関連項目
『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項
『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の役職と職階の表示に関する項
Oracle Purchasingには、購買文書の添付情報を作成する強力な機能があります。添付情報の文字数に制限はありません。必要なだけテキストを提供し、この添付情報をだれがレビューできるかも指定し、テキスト添付情報を発注に印刷できます。既存の添付情報を変更し、様々な仕入先宛のメッセージのパーソナライズもできます。購買文書の作成時に、必要なすべての情報を簡単に記載できます。次のことができるようになります。
購買文書に必要な文字数のテキスト情報を添付します。
添付情報をレビューする適任者を指定します。
仕入先によるレビュー用に、発注および見積依頼にテキスト添付情報を印刷します。
他の文書に添付情報を再利用します。
既存の添付情報をコピーまたは変更して、データ入力を効率化します。
購買依頼の添付情報を見積依頼および発注にコピーします。
品目に対して標準添付情報を作成し、同じ品目に対して購買文書を作成するときに参照できるようにします。
既存の長い添付情報をコピーできるため、添付情報全体を再入力しなくてもカスタマイズできます。この機能は、仕入先ごとに変更する長い文書がある場合に特に役立ちます。
長い添付情報にアクセスできるユーザーを指定できます。添付情報が承認者、受入担当、購買担当、仕入先のうち、誰に宛てたものであるかを指定します。また、添付情報を社内秘にする場合も指定できます。Oracle Accounts Payable内で請求書照合時に表示される添付情報も入力できます。使用方法に応じた添付情報の入力およびレビュー方法については、「添付情報の管理」を参照してください。
ほとんどの文書に簡易連絡事項を記載できます。添付情報とは異なり、ノートをある文書から次の文書にコピーすることはできません。添付情報が240文字以内のとき、ノートを他の文書に再利用しないとき、またはノートの書式を設定しないときは、ノートを使用する必要があります。それ以外の場合は、添付情報を使用して文書に補足テキストを記載します。
文書に使用するテキストを必要なだけ記載できます。次の文書には、添付情報をヘッダー・レベルと明細レベルで記載できます。
購買依頼
標準発注および計画発注(納入レベルを含む)
包括購買契約
リリース(ヘッダーおよび納入レベル)
購買契約(ヘッダー・レベルのみ)
見積依頼
見積
受入(明細レベルのみ)
受入取引(明細レベルのみ)
品目の添付情報を記載することもできます。添付情報の作成時には、それを仕入先、受入担当、承認者、購買担当のうち誰に使用させるかを指定します。また、特定の文書にオンラインでアクセスできる人は、誰でも添付情報をみることができるように指定できます。様々な使用方法に即した添付情報の作成方法については、「添付情報の管理」を参照してください。
関連項目
品目に関する添付情報を提供できます。購買文書で品目を参照すると、対応する品目添付が検討可能になります。また、品目添付の作成時に使用法として「仕入先」を選択すると、発注と見積依頼にテキスト添付が印刷されます。
購買依頼ヘッダーおよび明細に使用する添付を作成できます。発注への購買依頼明細を自動作成すると、購買依頼ヘッダーおよび明細から対応する発注明細に添付がコピーされます。購買依頼から発注を自動作成した後も、購買担当は発注に添付を追加提供できます。
発注明細で複数の購買依頼明細が参照される場合は、発注明細の基礎となる購買依頼明細からヘッダー添付と明細添付のみがコピーされます。たとえば、1つの発注明細に複数の購買依頼明細を挿入すると、「コピー」オプションを使用した明細からは購買依頼ヘッダーおよび明細の添付のみがコピーされます。
コピーされる購買依頼明細ごとに、対応するヘッダー・レベル添付がコピーされます。たとえば、3つの明細を含む購買依頼に、明細レベル添付が3つとヘッダー・レベル添付が1つあるとします。この購買依頼を3つの明細を含む発注に自動作成すると、発注に含まれる3つの明細にはそれぞれ特定の明細添付と共通のヘッダー添付がコピーされることになります。
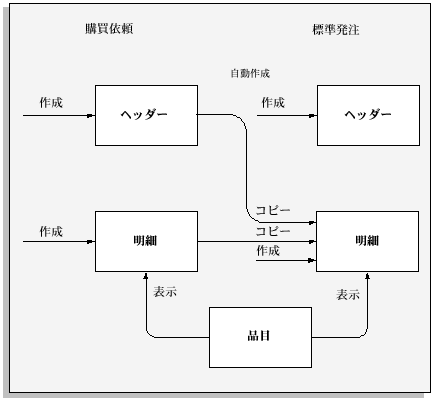
包括購買契約に関する長い添付をヘッダー・レベルと明細レベルで作成できます。包括購買契約ヘッダー添付を対応するリリース・ヘッダー上で検討し、リリース・ヘッダーに新しい添付を入力できます。また、包括購買契約明細の添付を対応するリリース納入上で検討し、納入に関する新しい添付を入力できます。リリースの自動作成時には、購買依頼添付は包括購買契約またはリリースにコピーされません。
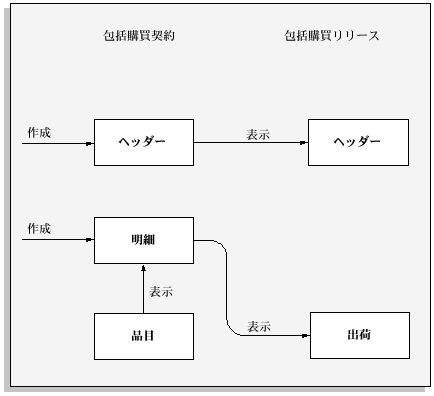
標準発注と同様に、Oracle Purchasingでは購買依頼ヘッダーおよび明細の添付が対応する見積依頼明細にコピーされます。「文書のコピー」ウィンドウで「見積依頼全データ・コピー」または「見積依頼ヘッダおよび明細」オプションを使用して見積をコピーする際に、すべての見積依頼ヘッダーおよび明細添付が対応する見積ヘッダーおよび明細にコピーされます。「見積依頼ヘッダのみ」を使用して見積をコピーする際には、見積依頼ヘッダーの添付のみが見積ヘッダーにコピーされます。見積をコピーする際に「選択」オプションを選択すると、見積依頼ヘッダー添付が見積ヘッダーにコピーされ、どの明細添付を見積明細にコピーするかを指定できます。
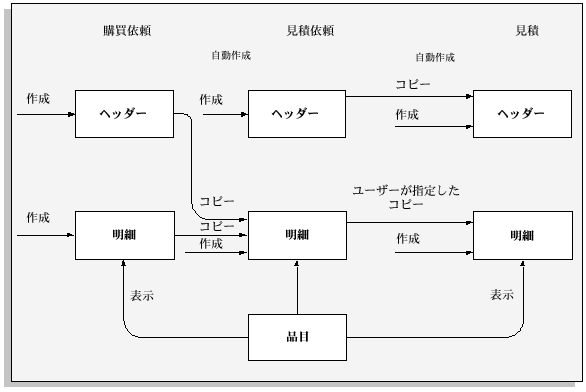
発注と見積依頼にテキスト添付を印刷できます。発注または見積依頼に添付を印刷するには、単に添付の使用法として「仕入先」を指定します。これらの添付は、対応する発注または見積依頼に印刷されます。各ページに最大限の添付が印刷され、該当する場合は引き続き次ページに印刷されます。
Oracle Purchasingでは、品目添付と、「使用法」が「受入担当」に設定されている添付を、受入伝票に印刷することもできます。
どの購買依頼、発注、見積または見積依頼(RFQ)の場合も、入力できる添付に制限はありません。文書とレポートに印刷する標準添付を決定します。特定の文書用に入力した一時添付を、事前定義済の標準添付と容易に結合できます。既存の添付から新しい添付を直接作成したり、添付を使用して購入する品目に関する長い摘要を入力することも可能です。
Oracle Purchasingには、作成する文書のタイプに応じて使用できるように、事前定義済の使用法のリストが用意されています。次のリストに、作成できる各文書に使用可能な使用法を示します。
仕入先
この使用法は発注、見積依頼、見積、購買依頼および品目に使用できます。すべての「仕入先」テキスト添付は文書に印刷されます。
受入担当
この使用法は発注、見積、見積依頼、受入、購買依頼および品目に使用できます。これらの添付は受入ウィンドウで受入担当に対して表示され、受入伝票にテキスト添付が印刷されます。
承認者
この使用法は購買依頼に使用できます。これらの添付は、承認者が購買依頼を承認する際に表示されます。
購買担当
この使用法は購買依頼に使用できます。これらの添付は、購買担当が購買依頼から発注を作成する際に表示されます。
社内調達[文書]
これらの添付は、特定の[文書]にのみ入力可能です。発注、見積、見積依頼、受入、購買依頼または品目に固有の情報を入力する場合は、この使用法を参照します。これらの添付は、文書の入力に使用するウィンドウの外部では印刷または表示されません。ただし、「社内調達受入」添付は受入伝票に印刷されます。
Oracle Payables
この使用法は発注に使用できます。これらの添付は、Accounts Payableで請求書照合中に表示されます。
標準添付を定義するには、単にこの添付の使用法、わかりやすい一意名および添付自体を入力します。開始日と終了日を入力して、この添付の可用性を管理することもできます。Oracle Purchasingでは、標準添付の開始日として今日の日付がデフォルト設定されます。終了日を入力すると、添付を容易に無効化できます。終了日の後は、標準添付を文書に使用できません。標準添付は「文書」ウィンドウで定義します。関連項目: 「Oracle Common Application Components」のノートの使用に関する項。
標準添付を定義した後、その添付を文書で参照できます。文書への標準添付を必要な数だけ参照できます。
関連項目
ノート、注釈、スプレッドシートおよびグラフィックなどのファイルをアプリケーション・データに添付できます。
たとえば、Oracle Purchasingでは、購買文書にファイルを添付できます。
添付ファイルに注釈を含めることができます。たとえば、品目が検査に不合格になった場合は購買担当に連絡するように指示する注釈を含めます。
購買文書にノートを添付する手順は、次のとおりです。
関連項目
『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の添付に関する項
『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の添付の作業に関する項
「購買オプション」ウィンドウを使用して、Oracle Purchasing全体で機能に使用するデフォルト値と管理を定義します。購買オプションは文書の作成時に頻繁に上書きできます。
次の特定カテゴリのオプションを定義できます。
文書管理
受入消込基準などの管理オプションを定義します。関連項目: 文書管理オプション。
文書デフォルト
最小リリース金額などのデフォルト・オプションを定義します。関連項目: 文書デフォルト・オプション。
受入会計
Oracle Purchasingで受入会計に使用する経過勘定方法と勘定を定義します。関連項目: 受入会計オプション。
文書採番
各文書の採番方法、採番タイプおよび次番号を定義します。関連項目: 文書採番オプション。
購買オプションを定義する手順は、次のとおりです。
「購買オプション」ウィンドウにナビゲートします。
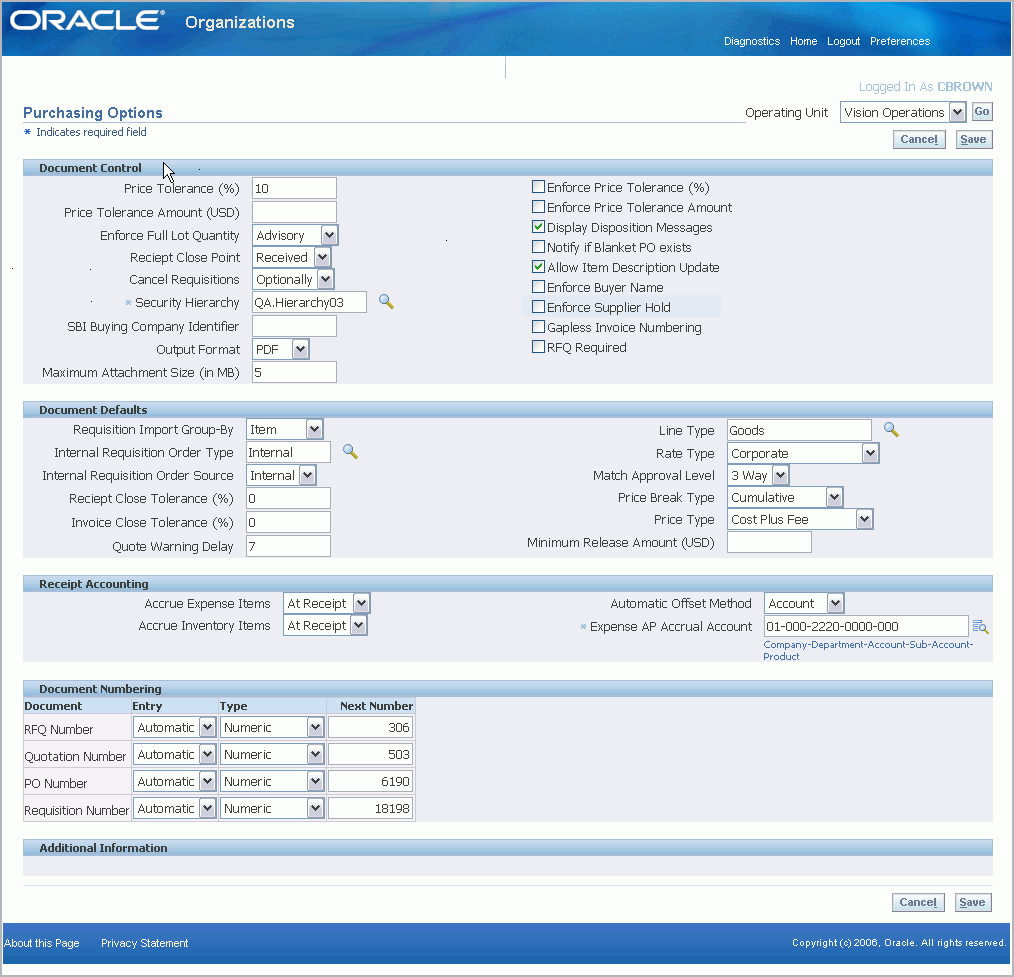
購買オプションの営業単位を選択します。
文書管理オプション
価格許容範囲(%)を入力します。これは、自動作成された発注明細の価格が購買依頼明細の価格を超えることのできる率の上限です。「価格許容範囲の強制(%)」を選択すると、この許容範囲を超える発注を作成できますが、承認はできません。価格の許容低減率に制限はありませんが、明細(数量や単位など)の変更により価格許容範囲を超えることがあります。
注意: 購買依頼明細の価格が0(ゼロ)の場合、価格許容範囲チェックは適用されません。
価格許容範囲金額を入力します。これは、自動作成される発注明細の価格が購買依頼明細の価格を超えることのできる金額の上限です。
注意: 「価格許容範囲(%)」と「価格許容範囲金額」の両方に値を設定すると、2つのうち限定的な値が適用されます。
「全ロット数量強制」オプションで次のいずれかの値を選択します。
なし: 購買依頼数量はロット数量に端数処理されません。
自動: 購買依頼数量は強制的にロット数量に端数処理されます。
勧告: 端数処理と提示端数処理数量を示す勧告メッセージが表示されますが、上書きできます。
「全ロット数量強制」は、次のように社内購買依頼上の数量の端数処理に使用します。
システム・オプション「全ロット数量強制割当」 = Yes
品目の端数処理ファクタ = 75%
品目の出庫単位 = DZ
社内購買依頼の単位 = 各
ユーザーが各社内購買依頼に6と入力すると、数量は0(ゼロ)に端数処理されます。各社内購買依頼に11と入力すると、各数量は12に端数処理されます。
関連項目: 購買依頼の概要
納入が受入に対して消し込まれる時期を示す受入消込基準として「検収済」(検査合格)、「搬送済」または「受入済」を選択します。「デフォルト・オプション」ウィンドウで受入消込許容範囲(%)を設定する必要があることに注意してください。関連項目: デフォルト・オプションの定義。
「購買依頼の取消」オプションは、発注の自動作成に使用された購買依頼にのみ適用されます。次のいずれかを選択します。
常時: 発注を取り消すと、購買依頼も取り消されます。
取消しない: 発注を取り消しても購買依頼は取り消されないため、発注に再び挿入可能になります。
オプション: 発注の取消時に、購買依頼を取り消すためのオプションが表示されます。関連項目: 文書の管理。
セキュリティ階層(「職階階層」ウィンドウからの職階階層)を選択します。「文書管理」ウィンドウで文書のセキュリティ・レベルが「階層」に設定されている場合は、この職階階層により文書のアクセス・セキュリティが管理されます。
重要: このフィールドは、このフォームに「購買」メニューからアクセスした場合にのみ入力可能です。
ビジネス単位全体または特定の仕入先サイトについて「欠番なしの請求書採番」を選択した場合は、SBI購買会社識別子を入力します。これは、「受入時支払」プロセスにより作成される請求書番号に含まれる識別子であり、返品受入により生成されるデビット・メモや購買価格遡及修正により生成される請求書にも使用されます。請求書番号のこの部分は購買ビジネス単位を識別するもので、次のように挿入されます。
<プリフィクス>-<SBI購買会社識別子>-<販売会社識別子>-<請求書タイプ・コード>-<連番>
ここで
プリフィクスはプロファイル・オプション「PO: ERS請求書番号プリフィクス」(オプション)で指定され、「受入時支払」プロセスにより生成される請求書にのみ適用されます。関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ。関連項目: 受入時支払。
SBI購買会社識別子は、営業単位として一意のコードです。これは購買オプションとして定義されますが、一意である必要はありません。
販売会社識別子は、仕入先サイトを表すコードです。このコードは「仕入先サイト」ウィンドウで定義します。販売会社識別子が同じ仕入先内で一意である必要はありませんが、複数の仕入先間では一意である必要があります。
請求書タイプ・コードは、次のとおりです。
ERS(評価済受入精算): 受入時支払用
RTS(仕入先に返品): デビット・メモ用
PPA(購買価格修正): 価格遡及修正により生成される請求書用
連番は、「欠番なしの請求書採番」が有効化されている場合に購買会社/販売会社/請求書タイプの組合せごとに定義される欠番なしの連番です。
欠番なしの請求書番号の全セグメントはハイフンで区切ります。
「発注出力フォーマット」では、印刷、EメールまたはFAXを使用して仕入先に送信される発注の出力フォーマットを定義します。また、その出力フォーマットに関連する機能も有効化されます。
PDF: 発注はAdobe Portable Document Format(PDF)フォーマットで出力されます。完全にフォーマットされた発注を「発注の入力」ウィンドウ、「発注要約」ウィンドウ、「変更履歴」ページ、Oracle iProcurementおよびOracle iSupplier Portalで表示できます。また、発注を「発注要約」ウィンドウから仕入先に通信することも可能です。
テキスト: 発注はテキスト・フォーマットで出力されます。
注意: 発注を「承認」ウィンドウから仕入先に通信する機能は、どちらの設定でも同じです。出力のフォーマットのみが変わります。
関連項目: 仕入先への発注通信の設定
発注出力フォーマットが「PDF」の場合は、最大添付サイズを入力します。これは、Eメールされる発注に対する「ファイル」タイプの添付の最大許容ファイル・サイズ(MB単位)です。
関連項目: 『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』の添付に関する項
Oracle Purchasingで価格許容範囲率(%)を強制する場合は、「価格許容範囲の強制(%)」を選択します。
Oracle Purchasingで価格許容範囲金額を強制する場合は、「価格許容範囲金額の強制」を選択します。
在庫品目が購買依頼に挿入されている場合に、その品目に対して定義済の処理時メッセージを表示するには、「処理時メッセージ表示」を選択します。
品目の購買依頼明細、発注明細または包括購買契約明細の作成時に既存の包括購買契約に関する通知を受け取る場合は、「包括契約時通知」を選択します。品目を調達した場合は、「この品目の包括購買契約[番号]が存在しています。」というメッセージが表示されます。依頼者によるリリースの入力を許可していれば、依頼者は購買依頼または発注を作成するかわりに、包括購買契約に対するリリースを直接作成できます。関連項目: 通知の表示と通知への返答。
購買依頼、見積依頼、見積または発注の明細作成中に品目摘要の更新を許可するかどうかを、品目ごとに定義できます。この更新は、作成中の明細にのみ影響します。新規品目を定義する際に「摘要更新の許可」属性の初期デフォルトを「Yes」にする場合は、「品目摘要更新の許可」を選択します。
発注に購買担当として自分の氏名のみを強制的に入力する場合は、「実施購買担当名」を選択します。それ以外の場合は、任意の有効な購買担当名を入力できます。関連項目: 購買担当の定義。
保留中の仕入先を指定して作成された発注を承認できないようにする場合は、「仕入先保留の強制」を選択します。仕入先を保留にするには、「仕入先」ウィンドウを使用します。関連項目: 『Oracle iSupplier Portal Implementation Guide』の仕入先に関する項。
注意: 「仕入先」ウィンドウで仕入先を保留にした場合も、ここで「仕入先保留の強制」を選択していなければ、その仕入先に対する発注を承認できます。
「受入時支払」処理中に購買組織について欠番なし(連番)の請求書番号を生成可能にするには、「欠番なしの請求書採番」を選択します。関連項目: 受入時支払。
この設定を使用すると営業単位全体に対して欠番なしのSBI採番を有効化するか、または「仕入先サイト」ウィンドウで仕入先サイトに限定できることに注意してください。
発注に対応する購買依頼明細を自動作成する前に品目の見積依頼を必須にするには、「見積依頼要」を選択します。この値は、品目または購買依頼明細ごとに上書きできます。
文書デフォルト・オプション
購買依頼オープン・インタフェースを介してインポートされる購買依頼について、「購買依頼インポート・グループ別」オプションで「全て」(グループ化しない)、「購買担当」、「カテゴリ」、「品目」、「事業所」または「仕入先」のいずれかを選択します。関連項目: 購買依頼インポート処理。
社内購買依頼のデフォルトの発注タイプを選択します。
重要: 「発注タイプ」フィールドは、Oracle Order Managementアプリケーションがインストールされている場合にのみ参照可能です。
発注タイプはOracle Order Managementで定義します。ここでは、Oracle Purchasingで社内購買依頼から受注を作成する際に使用する発注タイプを選択します。
社内購買依頼のデフォルトの購買依頼元を選択します。
Oracle Purchasingでは「社内」のみがデフォルト設定されて使用されます。これは、受注インポートでOracle PurchasingからOracle Order Managementに社内購買依頼を転送する際に使用されるソースです。
納入の受入消込許容範囲(%)を入力します。受入納入データは、受入消込基準による受入消込許容範囲内であれば、自動的に消し込まれます。受入消込基準は「管理オプション」ウィンドウで設定します。このオプションは、特定の品目および発注に関して上書きできます。関連項目: 管理オプションの定義。
納入の請求書消込許容範囲(%)を入力します。Oracle Payablesで請求書が発注または受入と照合されるときに、請求分の納入データが請求消込許容率の範囲内であれば、自動的に消し込まれます。このオプションは、特定の品目および発注に関して上書きできます。関連項目: 管理オプションの定義。
警告後見積失効日を入力します。これは、見積が失効する何日前に失効警告を受け取る必要があるかを示す日数です。ここで入力した日数の範囲内で見積が失効間近になると、「通知要約」ウィンドウに「有効な見積または失効日間近: [日数]」というメッセージが表示されます。関連項目: 通知の表示と通知への返答。
購買依頼、見積依頼、見積および発注の明細のデフォルト明細タイプを選択します。これらの文書のいずれかを作成する場合、明細タイプが品目情報の一部となります。各文書明細の明細タイプは上書きできます。関連項目: 明細タイプの定義。
重要: このフィールドは、このフォームに「購買」メニューからアクセスした場合にのみ入力可能です。
購買依頼、発注、見積依頼および見積にデフォルト設定する通貨レート・タイプを選択します。レート・タイプが「ユーザー」の場合は、このデフォルトを文書明細ごとに上書きできます。機能通貨(元帳に定義)または取引通貨(「購買文書」ウィンドウに入力した通貨)の一方が「ユーロ」(欧州通貨単位の通貨)で、他方が別の欧州通貨の場合、Oracle Purchasingでは該当する換算の「レート・タイプ」、「レート」および「レート基準日」がデフォルト設定されます。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の換算レート・タイプの定義に関する項。
次の「承認照合レベル」オプションを1つ選択します。
2方向: 対応する請求書に対して支払う前に、発注と請求書の数量が許容範囲内で一致する必要があります。
3方向: 対応する請求書に対して支払う前に、発注、受入および請求書の数量が許容範囲内で一致する必要があります。
4方向: 対応する請求書に対して支払う前に、発注、受入、検査および請求書の数量が許容範囲内で一致する必要があります。
関連項目: 受入管理、オプション、およびプロファイル
注意: 発注の「納入」ウィンドウの「請求書照合オプション」とこの手順の「承認照合レベル」は、相互に依存しないオプションです。「請求書照合オプション」では、Oracle Payablesで請求書を発注と照合するか受入と照合するかを指定します。ここで選択した「承認照合レベル」に関係なく納入に必要な「請求書照合オプション」を実行できます。
包括購買契約にデフォルト設定する単価値引タイプとして次のいずれかを選択します。
合計数量値引: 単価値引は品目の全リリース納入の合計数量に適用されます。
個別数量値引: 単価値引は品目の個別リリース納入の数量に適用されます。
発注にデフォルト設定する価格タイプを選択します。価格タイプを定義するには、「参照コード」ウィンドウを使用します。関連項目: 参照コードの定義。
包括購買契約、契約発注および計画発注にデフォルト設定する最小リリース金額を入力します。この金額は機能通貨建です。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の複数通貨会計の概要に関する項。
受入会計オプション
次のいずれかの「計上費用品目」オプションを選択します。
受入時: 費用品目を受入時に計上します。このフラグは、発注およびリリースの入力時に「出荷詳細」ウィンドウで上書きできます。
期末: 費用品目を期末に計上します。
重要: 現金主義会計を使用している場合は、このオプションを「期末」に設定する必要がありますが、通常は「受入差異 - 期末」プロセスは実行しません。
「計上在庫品目」の場合、現在選択できるのは「受入時」のみです。
相殺は、他の会計入力を相殺(貸借一致)させるために作成される会計入力です。「自動相殺方法」は、相殺取引の勘定の自動作成に使用する方法です。ここでは、相殺勘定は受入検査勘定で、受入時の経過勘定取引と搬送時の借方勘定が相殺されます。「自動相殺方法」により、基本勘定科目として使用する2つの勘定科目、上書勘定科目、および基本勘定科目セグメントの上書きに使用するセグメントを管理します。
次のいずれかの「自動相殺方法」オプションを選択します。
なし: 置換は行われず、搬送先組織の受入検査勘定が使用されます。
貸借一致: 基本勘定科目は搬送先組織の受入検査勘定で、貸借一致セグメントは借方勘定の貸借一致セグメントで上書きされます。
勘定科目: 基本勘定科目は借方勘定で、勘定科目セグメントは受入検査勘定の勘定科目セグメントで上書きされます。
注意: 「自動相殺方法」は、遡及的価格設定、共有サービスおよび直接納入フローではサポートされていません。
デフォルトの費用と対応する経過勘定を入力します。
文書採番オプション
見積依頼番号、見積番号、発注番号および購買依頼番号に使用する[文書]採番方法を選択します。
自動: 文書の作成時に、各文書に一意の連番が自動的に割り当てられます。
手動: 文書の入力時に文書番号を手動で入力します。
重要: 文書番号の入力方法はいつでも変更できます。当初は手動入力可能にし、その後で自動入力に切り替える場合は、「次番号」に手動で割り当てた最大番号よりも大きい番号を入力してください。
Oracle Purchasingで見積依頼番号、見積番号、発注番号および購買依頼番号に使用する[文書」番号タイプとして「数値」または「英数字」を選択します。
重要: 「自動」文書番号入力を選択した場合、生成できるのは数値文書番号のみですが、他の購買システムから数値または英数字値をインポートすることもできます。
重要: 英数字番号を参照する外部システムから購買文書をインポートする場合は、採番方法に関係なく番号タイプとして「英数字」を選択する必要があります。
「手動」文書番号入力を選択した場合は、数値または英数字番号を選択できます。文書番号タイプは、必要に応じて「数値」から「英数字」に変更できます。「英数字」から「数値」に変更できるのは、現行のすべての文書番号が数値の場合のみです。
重要: 「英数字」数値タイプを使用すると、値リストに数値がランダムに表示されることがあります。「英数字」採番を使用する場合は、すべての数値を同じ桁数で入力することを考慮してください。たとえば、すべての数値が6桁であると想定できる場合は、最初の値を000001として入力する必要があります。
重要: グローバル基本契約を作成して有効化する予定の全営業単位で、採番タイプが同一になるように設定する必要があります。
「次番号」に値を入力します。これは、「自動」文書番号入力を選択した場合にOracle Purchasingで一意の文書連番の生成に使用する開始値です。新規文書の作成時には、その文書に使用される次文書番号が表示されます。「手動」文書番号入力を選択した場合、このフィールドには入力できません。
Oracle Master Scheduling/MRP、Oracle Inventory、Oracle Work in ProcessまたはOracle以外のシステムを使用して購買依頼を自動作成する場合は、Oracle Purchasingでも対応する購買依頼を自動的に採番するように設定する必要があります。
「保存」をクリックします。
「受入オプション」ウィンドウを使用して、システムでの受入を管理するオプションを定義します。ここで設定するオプションのほとんどは、特定の仕入先、品目および発注について上書きできます。関連項目: 受入管理、オプションおよびプロファイル。
受入オプションを定義する手順は、次のとおりです。
受入オプション
「納入先相違時の対応」オプションを入力し、受入事業所と納入先事業所を同じにする必要があるかどうかを決定します。次のオプションを1つ選択してください。
なし - 受入事業所が納入先事業所と異なっていても構いません。
拒否 - 受入事業所が納入先事業所と異なる受入は許可されません。
警告 - 警告メッセージが表示されますが、受入事業所が納入先事業所と異なる受入も許可されます。
「ASN管理処理」で処理を選択します。このフィールドでは、Oracle Purchasingで事前出荷通知(ASN)のある発注納入に対する受入を処理する方法を指定します。次のいずれかのオプションを選択します。
なし: Oracle Purchasingでは、ASNのある発注納入に対して受け入れようとした場合に、その受入は禁止されず、警告も表示されません。
拒否: ASNのある発注納入に対する受入については、メッセージが表示されて禁止されます。
警告: 発注納入にASNがあることを示すメッセージが表示され、発注納入またはASNに対して受け入れるかどうかを決定できます。
「納期前」および「納期後」の最大の受入許容日数を入力します。
「納期後受入処理」の処理を入力します。このフィールドでは、前のステップで選択した許容日数より前または後の受入の処理方法を指定します。次のオプションを1つ選択してください。
なし - 許容された日数よりも早いか遅い受入が許可されます。
拒否 - 選択された許容日数よりも早いか遅い受入は許可されません。
警告 - 警告メッセージが表示されますが、選択された許容日数よりも早いか遅い受入は許可されます。
「超過受入許容範囲 (%)」に最大許容率を入力します。
「超過受入処理」に処理を入力します。このフィールドでは、受入数量許容範囲を超える受入の処理方法を指定します。次のオプションを1つ選択してください。
なし - 受入は選択した許容範囲を超えることができます。
拒否 - Oracle Purchasingでは、選択した許容範囲を超える受入は許可されません。
警告 - 警告メッセージが表示されますが、選択した許容範囲を超える受入は許可されます。
「RMA受入経路」に、商品に割り当てるデフォルトとして「直送」、「標準受入」または「検査要」を入力します。
「受入経路」に、商品に割り当てるデフォルトとして「直送」、「標準受入」または「検査要」を入力します。「RCV: 受入経路変更可」ユーザー・プロファイルが「Yes」に設定されている場合は、受入時に特定の仕入先、品目および発注の搬送先タイプを変更して、このオプションを上書きできます。関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ。
発注品目のかわりに代替品目を受け入れる場合は、「代替品受入の許可」を選択します。代替品目は、受入前に「品目関連」ウィンドウで定義しておく必要があります。このオプションは、特定の仕入先、品目および発注に関して上書きできます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目関連の定義に関する項。
未発注品目を受け入れる場合は、「未発注品受入の許可」を選択します。後で未発注品の受入を発注と照合できます。このオプションを有効化した場合は、特定の仕入先および品目に関して上書きできます。
簡易搬送および受入を有効化するには、「簡易取引の許可」を選択します。関連項目: 簡易受入および受入取引。
受入と受入取引のカスケードを有効化するには、「カスケード取引の許可」を選択します。関連項目: 受入および受入取引のカスケード。
サイトで無チェック受入を行う場合は、「無チェック受入の許可」を選択します。無チェック受入を使用すると、受入担当は受け入れた正確な数量を確実に記録できます。この場合、品目の受入時には納入の残数量や発注数量を確認できません。Oracle Purchasingでは、仕入先から納入された正確な数量を確実に受入できるように、すべての受入数量許容範囲が無視されます。
シリアル番号を検証する場合は、「RMA受入時のシリアル番号の検証」を選択します。RMA明細のシリアル番号リストに表示されるシリアル番号を制限します。
「受入番号生成」で、受入番号の生成方法を選択します。
自動: 受入の作成時に、各受入に一意の連番が自動的に割り当てられます。
手動: 受入の入力時に受入番号を手動で入力します。
Oracle Purchasingでは、受入が在庫組織間ではなく単一の在庫組織内で採番されます。そのため、同じ受入番号が複数の異なる在庫組織で使用される場合があります。
重要: 受入番号の入力方法はいつでも変更できます。当初は手動入力可能にし、その後で自動入力に切り替える場合は、「次番号」に手動で割り当てた最大番号よりも大きい番号を入力してください。
Oracle Purchasingで受入番号に使用する受入番号タイプとして「数値」または「英数字」を選択します。
重要: 「自動」受入番号入力を選択した場合、生成できるのは数値受入番号のみですが、他の購買システムから数値または英数字値をインポートすることもできます。
重要: システムに英数字番号を持つ文書がある場合は、採番方法に関係なく番号タイプとして「英数字」を選択する必要があります。
「手動」受入番号入力を選択した場合は、数値または英数字による番号を選択できます。受入番号タイプは、必要に応じて「数値」から「英数字」に変更できます。「英数字」から「数値」に変更できるのは、現行のすべての受入番号が数値の場合のみです。
重要: 「英数字」数値タイプを使用すると、値リストに数値がランダムに表示されることがあります。「英数字」採番を使用する場合は、すべての数値を同じ桁数で入力することを考慮してください。たとえば、すべての数値が6桁であると想定できる場合は、最初の値を000001として入力する必要があります。
「次受入番号」に値を入力します。これは、「自動」受入番号入力を選択した場合にOracle Purchasingで一意の受入連番の生成に使用する開始値です。新規受入の作成時には、その受入に使用される次受入番号が表示されます。「手動」受入番号入力を選択した場合、このフィールドには入力できません。
会計
「受入在庫勘定」に、デフォルトとして使用する会計フレックスフィールドを入力します。
「遡及的価格調整勘定」に勘定科目番号を入力します。これは、納入を受け入れて計上した後で価格設定変更用の修正入力を転記するために使用する勘定科目です。関連項目: 購買文書の遡及的価格更新。
「精算勘定」に勘定科目番号を入力します。これは、受入組織が調達組織とは異なる場合に、調達組織で会社間売掛金に使用される勘定です。
原価ファクタ
原価ファクタを計算するためにOracle Advanced Pricingを導入済の場合は、「拡張価格設定へのインタフェース」を選択します。
輸送原価を計算するためにOracle Transportation Executionを導入済の場合は、「輸送実行へのインタフェース」を選択します。
「保存」をクリックします。
関連項目
「購買依頼テンプレート」ウィンドウを使用して、購買依頼テンプレートを定義します。これらのテンプレートにより、事務用品のように共通する発注品目の購買依頼が自動化されます。組織の依頼者は、単にテンプレートを使用して発注する各品目の数量を入力することで、事務用品の購買依頼を作成できます。
テンプレートを作成するには、品目を個別に指定する方法と、既存の購買依頼または発注を参照する方法があります。既存の文書を参照すると、その文書の全明細がテンプレートに追加されます。複数の文書を参照し、その全明細を同じテンプレートに追加できます。
テンプレートを定義した後、そのテンプレートを「仕入先品目カタログ」で参照できます。その場合、搬送先組織に有効なテンプレート明細がすべて表示され、どの明細でも購買依頼に使用できます。購買依頼作成日がテンプレート無効日よりも前の日付であれば、このテンプレートを使用して購買依頼を作成できます。
「購買依頼テンプレート」ウィンドウにナビゲートします。
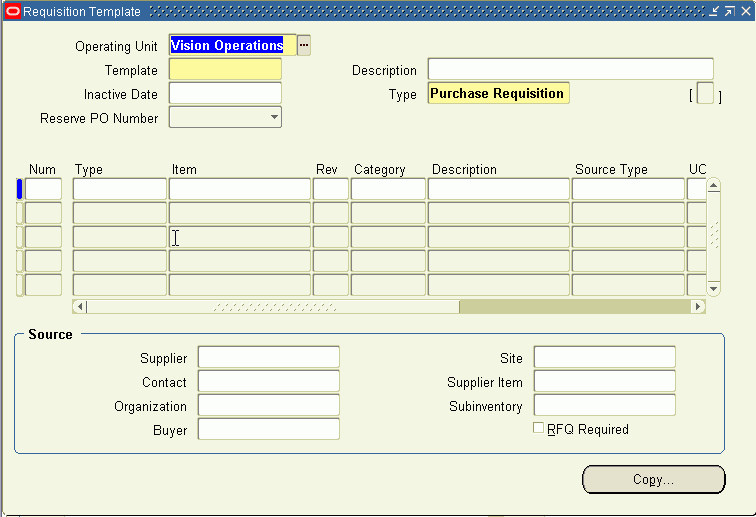
このテンプレートの営業単位を選択します。
購買依頼テンプレート名を入力します。
テンプレートの摘要を入力します。
無効日を入力します。この日付の後は、依頼者はこのテンプレートから購買依頼を作成できなくなります。
購買依頼タイプとして「社内」または「購買」を入力します。いずれの場合も、いずれかのタイプの個別購買依頼明細を入力できます。
このテンプレートをOracle iProcurementで使用する場合は、「予約発注番号」オプションを選択します。
No: 依頼者は購買依頼の承認時に発注番号を予約できません。
オプション: 依頼者は購買依頼の承認時に発注番号を予約できます。
Yes: 購買依頼の承認時に発注番号が自動的に予約されます。
テンプレートに明細をコピーする手順は、次のとおりです。
「コピー」ボタンを選択して「ベース文書」ウィンドウをオープンします。
ベース文書タイプとして「発注」または「購買依頼」を入力します。
テンプレートにコピーする明細を含んでいるベース文書番号を入力します。
「OK」ボタンを選択して、ベース文書の全明細をテンプレートにコピーします。「取消」ボタンを選択すると、コピーせずに「購買依頼テンプレート」ウィンドウに戻ることができます。
複数の文書から同じ購買依頼テンプレートに明細をコピーできます。
テンプレートに明細を手動で追加する手順は、次のとおりです。
「明細」リージョンを使用して、テンプレートに新しい明細を手動で追加します。ベース文書からコピーした明細を削除したり、これらの明細の特定の情報を変更することもできます。
「番号」フィールドに、購買依頼上の明細の順序を識別する番号を入力します。Oracle Purchasingでは、デフォルトの順序番号が増分1で設定されます。
明細タイプを入力します。このフィールドで入力または変更できるのは、新しい明細に関する情報のみです。デフォルトは「購買オプション」ウィンドウから設定されます。関連項目: デフォルト・オプションの定義。
品目番号を入力します。このフィールドで入力または変更できるのは、新しい明細に関する情報のみです。
新しい明細の場合にのみ、品目改訂番号を入力できます。
品目の入力を完了すると購買カテゴリが表示され、このカテゴリは変更できません。それ以外の場合は、購買カテゴリを入力する必要があります。
「ベース文書番号」フィールドで選択した文書からの品目摘要が表示されます。新しい明細を入力している場合、この摘要は品目マスターから取得されます。摘要を変更できるのは、この属性が品目に対して有効な場合のみです。
「ソース・タイプ」では、購買依頼品目のソースを指定します。このフィールドで選択するタイプは、ユーザー・プロファイル・オプションとシステム・プロファイル・オプションに応じて異なります。どちらのレベルでも、オプションが「在庫」または「仕入先」に制限されている場合があります。
両方のオプションが表示される場合は、購買依頼タイプに関係なく購買依頼明細のソースを指定できます。在庫管理から調達する購買依頼明細と仕入先から調達する購買依頼明細を、同じ購買依頼に混在させることもできます。この購買依頼上では、在庫管理ソース・タイプの購買依頼明細ごとに、社内受注が1件ずつ作成されます。仕入先ソース・タイプの購買依頼明細は、「文書の自動作成」ウィンドウでは自動的に、または「発注」ウィンドウでは手動で、発注に入力します。
デフォルト単位を入力します。
必要に応じて、Oracle iProcurementで購買依頼者用に使用する指定数量を入力します。
仕入先ソース明細の場合は単価を入力でき、この価格が「購買依頼」ウィンドウで使用されます。在庫ソース明細の場合、このフィールドにはカーソルが移動せず、在庫からの実際原価が「購買依頼」ウィンドウでの価格となります。
Oracle Services Procurementを導入済の場合は、固定価格サービス明細タイプの金額を入力します。「金額」は必須で、ソース・タイプには「仕入先」を選択する必要があります。
「交渉済」チェック・ボックスを選択して、この明細が交渉済ソースからのものかどうかを示します。この設定を変更できるのは、対応する機能が職責で有効化されている場合のみです。
作業内容を保存します。
ソーシング情報を入力する手順は、次のとおりです。
このウィンドウの下部に、現行明細のソーシング情報を入力できます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、購買依頼明細を割り当てる購買担当の氏名を入力できます。購買担当は、割り当てられた購買依頼明細を発注の自動作成時に問合せできます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、「見積依頼要」を選択し、購買担当が購買依頼に関する発注を作成する前に見積依頼を要求するように指定できます。必須の見積依頼なしで発注を作成しようとすると、警告メッセージが表示されます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、購買依頼品目の指定仕入先を入力できます。使用可能な仕入先のリストから選択できます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、仕入先サイトを入力できます。このフィールドに入力できるのは、指定仕入先名を入力した場合のみです。仕入先サイトは値リストから選択できます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、仕入先サイトにいる担当の氏名を入力できます。
「仕入先」ソース・タイプの明細には、仕入先品目番号を入力できます。
「在庫」ソース・タイプの明細には、ソース組織を入力できます。
「在庫」ソース・タイプの明細には、オプションとして「保管場所」ソースを指定できます。これを指定すると、Oracle Order Managementでは商品が予約され、指定した保管場所のみが配賦に使用されます。指定した保管場所に商品が存在しなければ、別の保管場所に存在する場合でも、Oracle Order Managementではバックオーダーとなります。
関連項目
Oracle Purchasingには、すべての危険物の購入および受入要件を処理するための柔軟な機能が用意されています。危険物を明確に識別して分類し、仕入先が確実に規制に従って危険物を梱包、ラベル貼付して出荷するように、見積依頼と発注に情報を印刷できます。また、品目の受入時に危険物情報を確認し、必要な安全策を講じることもできます。
「危険度区分」ウィンドウ(関連項目: 危険度区分の定義)を使用して、必要な危険度区分を定義します。「国連番号」ウィンドウ(関連項目: : 国連番号の定義)を使用して、使用する識別番号を定義し、危険度区分に割り当てます。「品目」ウィンドウを使用して、危険度区分と国連番号を品目に関連付けます。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の品目の定義に関する項。
ISRS(International Safety Rating System)のSection 19では、危険物に関する全発注を明確に識別して記録することを求めています。米国運輸省も同様の規制を設けています。これらの規制は、危険物に関する広範囲な分類システムを提供しています。この分類の目的は、危険物の出荷と輸送に適用可能な出荷用書類、パッケージのマーク付け、ラベル貼付および輸送車への掲示に関する詳細な要件を提供することです。この分類により、危険物ごとに次の項目が提供されます。
出荷名
発注品目または出荷品目を記述します。出荷名に規制が適用される場合もあります。
例:
亜硫酸水素カルシウム溶液
エピクロルヒドリン
燃料油
オレイン酸水銀、固体
石油蒸留物
小火器弾薬
危険度区分
危険性物質を分類します。ほとんどの危険性物質は、1つの危険度区分にしか属しません。複数の危険度区分に属す資材もあれば、どの危険度区分にも属さない資材もあります。資材が複数の危険度区分に属する場合は、これらの区分を特定の順序でリストアップする必要があります。
例:
腐食剤
引火性液体
禁制品
可燃性液体
毒物A
ORM-A
区分A爆発物
識別番号
危険物を識別します。各識別番号には摘要が付いています。識別番号には2つのタイプがあります。UN(国連)で始まる識別番号には、米国における海外出荷と国内出荷に該当する摘要が付いています。NA(北米)で始まる識別番号は、米国の国内出荷および米国とカナダ間の出荷にのみ適用されます。識別番号は一意ではありません。たとえば、同じ国連番号が密接な関連はあってもタイプの異なる2つの危険物に対応する場合があります。
例:
UN0001 アラーム装置、爆発物
UN0027 黒色火薬
UN0180 ロケット弾
NA1133 セメント
NA2016 手榴弾
UN2016 弾薬
UN2769 ベンゼン誘導体殺虫液
UN2769 ベンゼン誘導体殺虫剤
対応する識別番号のない危険物もあります。
例:
着火剤、ライター
推進剤、爆発物、液体
同じ識別番号で識別する危険物が2つの異なる危険度区分に属している場合もあります。
例:
燃料、航空機、タービン・エンジンのID番号はUN1863ですが、引火性液体または可燃性液体のいずれかの危険度区分に分類できます。
必須ラベル
危険物の各パッケージに必須のラベルを指定します。規制により、ラベルの書式、サイズ、色および印刷に関する詳細な指示が提供されています。
例:
引火性液体
爆発物C
毒物B
梱包要件
危険物の梱包要件、掲示要件および例外を指定します。梱包要件は主として危険物の危険度区分に応じて異なりますが、このルールには多数の例外があります。
出荷要件
使用する輸送モードに応じて梱包ごとに輸送できる危険物の最大量を指定します。また、危険物に関する出荷、取扱、格納またはその他の情報も提供します。
例:
冷蔵
酸から離して貯蔵
このウィンドウを使用して危険物の区分ごとにコードを定義します。区分名、摘要および区分が使用できなくなる日付を入力します。危険度区分を複数の国連番号に割り当てて危険品目を識別できます。
Oracle Purchasingでは、自動的に危険物情報が文書にコピーされ、この情報が発注、見積依頼および受入伝票に印刷されます。また、受入担当には危険物情報が自動的に表示されます。
複数言語サポート(MLS)を使用している場合は、インストール済の各言語で危険度区分の翻訳を入力できます。危険度区分の翻訳を入力するには、「表示」メニューから「翻訳」を選択します。MLSの詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。
「危険度区分」ウィンドウにナビゲートします。

新しい危険度区分を定義する場合は、「危険度区分の追加」をクリックします。既存の危険度区分を変更するには、「検索」リージョンを使用して「危険度区分」フィールドに危険度区分名を入力するか、「摘要」フィールドに摘要を入力します。この2つのフィールドの一方または両方に入力した後、「進む」をクリックします。
定義する危険度区分ごとに一意の名称を入力します。たとえば、爆発、有毒、中毒などの区分名を入力できます。
危険度区分の摘要を入力します。この摘要を使用して危険度区分をさらに詳しく説明できます。
危険度区分の無効日を入力します。この日付以降は危険度区分を使用できません。
「保存」をクリックします。
関連項目
『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の「品目の定義」
このウィンドウを使用して、危険物の国連識別番号を定義します。1つの危険度区分を複数の識別番号に関連付けることができます。また、定義する品目ごとに識別番号と危険度区分を1つずつ割り当てることもできます。
Oracle Purchasingでは、自動的に危険物情報が文書にコピーされます。危険物情報は発注、見積依頼および受入伝票に印刷され、この情報が受入担当と検査担当に表示されます。
複数言語サポート(MLS)を使用している場合は、インストール済の各言語で国連番号の翻訳を入力できます。国連番号の翻訳を入力するには、「表示」メニューから「翻訳」を選択します。MLSの詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。
このステップを実行する前に危険度区分を定義します。関連項目: 危険度区分の定義。
国連番号を定義する手順は、次のとおりです。
「国連番号」ウィンドウにナビゲートします。

新しい番号を定義する場合は、「国連番号の追加」をクリックします。既存の番号を変更するには、「検索」リージョンを使用して、「国連番号」フィールドに番号を入力するか、「摘要」または「危険度区分」に値を入力します。1つまたはすべてのフィールドに入力した後、「進む」をクリックします。
国連識別番号を入力します。摘要が異なっていれば、同じ国連番号の複数インスタンスを定義できます。
識別番号の摘要を入力します。
識別番号に関連付ける危険度区分を入力します。これはオプションです。
必要に応じて、識別番号の無効日を入力します。
「保存」をクリックします。
関連項目
『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の「品目の定義」
「Oracle Purchasing参照」ウィンドウを使用して、Oracle Purchasingの参照コードを定義します。
Oracle Purchasingでは、参照コードを使用してシステム全体で値リストを定義します。参照カテゴリを参照タイプと呼び、参照タイプの許容値を参照コードと呼びます。アクセス・レベルによっては、一部の参照タイプに最初から用意されているコードに独自コードを追加できます。
たとえば、Oracle Purchasingには仕入先タイプ・コードとして「従業員」および「仕入先」が用意されています。コンサルティング・サービスの購入に使用するために、「コンサルタント」というコードを追加定義できます。
重要: 追加して保存したコードは変更または削除できませんが、コードの摘要は変更できます。
参照の定義と更新の詳細は、『Oracle Applications開発者ガイド』の参照に関する項またはオンライン・ヘルプを参照してください。
複数言語サポート(MLS)を使用している場合は、インストール済の各言語で参照の翻訳を入力できます。参照の翻訳を入力するには、「表示」メニューから「翻訳」を選択します。MLSの詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。
参照コードを定義する手順は、次のとおりです。
メニューから「Oracle Purchasing参照」ウィンドウにナビゲートします。
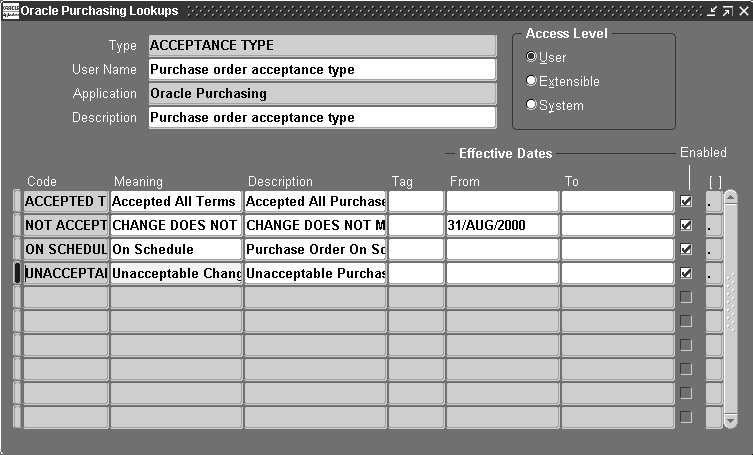
事前定義済の参照タイプから「1099仕入先例外」、「受理タイプ」、「FOB」(本船渡し)、「運送条件」、「少数民族グループ」、「支払グループ」、「発注/購買依頼事由」、「価格タイプ」、「見積承認事由」、「回答/受入方法」または「仕入先タイプ」のいずれかを入力します。
すでに用意されている参照コードに追加する一意のコードを25文字以内で入力します。Oracle Purchasingには、前述の参照タイプ用に次のコードが用意されています。
1099仕入先例外: Oracle Purchasingには1099仕入先例外コードは用意されていませんが、独自に定義できます。この種のコードはOracle Payablesの「1099請求書例外レポート」および「1099仕入先例外レポート」にのみ使用されます。
受理タイプ: Oracle Purchasingには「条件受理済」、「スケジュールどおり」および「受理不可の変更」が用意されています。
FOB: Oracle PurchasingにはFOBコードは用意されていませんが、独自に定義できます。このコードは発注に印刷されます。
運送条件: Oracle Purchasingには運送条件コードは用意されていませんが、独自に定義できます。このコードは発注に印刷されます。
少数民族グループ: Oracle Purchasingには少数民族コードは用意されていませんが、独自に定義できます。少数民族グループ・コードは、レポート作成用に仕入先を分類するために使用されます。
支払グループ: Payables請求書に支払グループを割り当てることができます。これにより、Payables支払バッチを指定の支払グループに割り当てられた請求書に限定できます。システムには支払グループ参照は用意されていませんが、このウィンドウで独自に定義できます。
価格タイプ: Oracle Purchasingには「原価に手数料加算」、「原価に比率マージン加算」、「固定」、「目録」および「可変」が用意されています。
見積承認事由: Oracle Purchasingには「最適搬送」、「最適デザイン」、「最低単価」、「一社のみ」、「品質」および「サービス」が用意されています。
回答/受入方法: Oracle Purchasingには回答/受入方法コードは用意されていませんが、独自に定義できます。
発注/購買依頼事由: Oracle Purchasingには発注、購買依頼、見積依頼および見積用の取引事由/取引性質コードは用意されていませんが、独自に定義できます。
仕入先タイプ: Oracle Purchasingには「従業員」、「仕入先」および「公共部門会社」が用意されています。これらのコードは、レポート作成のための仕入先の分類に使用されます。この値は、「仕入先」ウィンドウの「分類」リージョンの「タイプ」フィールドに入力します。関連項目: 『Oracle iSupplier Portal Implementation Guide』の業種に関する項。また、税金還付ルールの定義にも使用します。「税務当局」仕入先タイプは、源泉徴収税の送金先仕入先を示します。関連項目: 『Oracle E-Business Taxユーザー・ガイド』のOracle E-Business Taxの税金ルールに関する項。
コードが無効になる無効日を入力します。
作業内容を保存します。
「品質検査コード」ウィンドウを使用して、検査コードの定義と更新を行います。必要な数の検査コードを定義できます。各コードには、検査スケールを示す数値ランクを対応付ける必要があります。これらの検査コードは、発注した品目を受け入れて検査する際に使用します。
品質検査コードを定義する手順は、次のとおりです。
「品質検査コード」ウィンドウにナビゲートします。
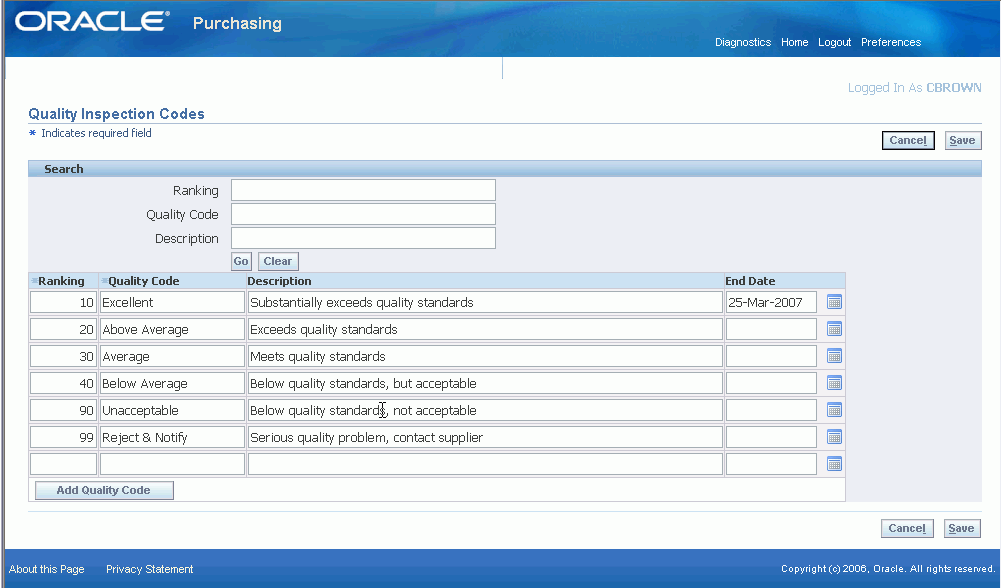
新しいコードを定義する場合は、「品質コードの追加」をクリックします。既存のコードを変更するには、「検索」リージョンを使用して、「ランク」フィールドにランクを入力するか、「品質コード」または「摘要」に値を入力します。1つまたはすべてのフィールドに入力した後、「進む」をクリックします。
特定の品質コードに対応するランク番号を入力します。この値は0から100までの範囲内で入力する必要があり、0は最低品質を表します。たとえば、10で品質ランク「不良」を表し、90で品質ランク「優秀」を表すことができます。これらのランクは、受入の検査時にリスト表示されます。
特定の品質水準を示す品質コードを入力します。たとえば、優秀条件や破損を品質コードとして定義できます。
品質コードの摘要を入力します。この摘要を使用して品質コードをさらに詳しく説明できます。
品質コードが無効になる無効日を入力します。
作業内容を保存します。
Oracle Purchasingには明細タイプ機能があり、商品の発注をサービスまたは外注加工の発注と明確に区別できます。さらに、サービス関連明細タイプでは、一般的なビジネス・サービス、コンサルティング・サービスおよび派遣労働などの幅広いサービス・カテゴリがサポートされています。
通常、依頼元と購買担当は、商品やサービスを数量単位で発注します。必要な品目の数量を特定の単位と所定の価格で発注します。たとえば、購買担当は、単価1,500ドルで10台のコンピュータ端末を発注します。後から、受入担当は端末5台入りの1箱の受入を記録します。買掛管理部門は、端末5台分の請求を受け入れ、請求書を元の発注と照合します。ときには、サービスも同様に発注する必要があります。たとえば、1時間当り40ドルの料率で40時間の製品研修を外部調達します。この場合は、単に発注した研修時間数と1時間当りの単価を記録します。研修受講後、受講時間数を記録します。
ただし、サービスを数量ではなく金額で発注することもあります。たとえば、プロジェクト管理者は、ローカル・エリア・ネットワークを導入するために10,000ドルのコンサルティング・サービスを発注します。この場合、購買担当はサービスの合計金額を記録するのみですみます。
このサービスが半分終了した時点で、プロジェクト管理者は5000ドルの受入を記録します。コンサルティング会社から、サービスの全額またはサービスの一部の請求書が送られてきます。どちらの場合も、買掛管理部門は請求書の金額を元の発注または受入の金額と照合します。
Oracle Purchasingには、商品とサービスの発注に必要な機能が用意されています。次のことができます。
独自の購買文書明細タイプを作成できます。明細タイプごとに、値基準(金額または数量)を指定できます。Oracle Services Procurementを導入済の場合、追加値基準として固定価格またはレートがあります。金額および数量基準のどちらの明細タイプでも、カテゴリ、単位および受入を必要とするかどうかについてデフォルト値を指定できます。数量基準の明細の場合、外注加工に明細タイプを使用するかどうかを指定できます。
必要な明細タイプを組み合せた購買文書を作成できます。
購買依頼明細から発注明細を自動作成できます。購買依頼明細を同じ発注明細上で同じ明細タイプと品目にグループ化します。
固定価格またはレート基準の明細タイプ、カテゴリ、摘要および明細の金額を選択して、サービス発注明細を作成できます。
金額基準の明細タイプ、カテゴリ、品目摘要および明細の合計金額を選択して、金額基準の発注明細を作成できます。
明細タイプによって、作成する購買依頼、発注、見積依頼および見積明細のタイプが決まります。数量基準の明細タイプを使用すると、提供される商品やサービスの数量に基づいて発注と受入または請求(あるいはその両方)を処理できます。金額基準の明細タイプを使用すると、提供されるサービスの金額に基づいて発注と受入または請求(あるいはその両方)を処理できます。
数量基準の明細タイプは、発注する品目の数量、単位および単価を指定する場合に使用します。Oracle Purchasingには、数量基準の初期明細タイプとして「商品」が設定されています。この明細タイプを変更するか、ニーズに合った数量基準の明細タイプを新しく作成できます。
Oracle Services Procurementを導入済の場合、(Oracle Services Procurementで)一般的なビジネス・サービスまたは一時労働サービスを固定金額で発注する際に、固定価格基準の明細タイプを使用できます。固定価格基準の明細タイプ、カテゴリ、品目摘要およびサービスの合計金額を選択して、固定価格サービスの発注を作成します。固定価格サービスは金額別に受け入れて照合できます。
Oracle Services Procurementを導入済の場合、単位当りレートによって一時労働サービスを発注する際に、レート基準の明細タイプを使用できます。この明細タイプではレート差異を使用できます。レート基準の明細タイプ、カテゴリ、単位、価格、品目摘要およびサービスの合計金額を選択して、レート基準サービスの発注を作成します。レート基準サービスは金額別に受け入れて照合できます。
金額基準の明細タイプを使用するのは、金額を指定してサービスや他の品目を発注する場合です。金額基準の明細タイプ、カテゴリ、品名およびサービスの合計金額を選択して、サービスのオーダーを作成します。サービスも金額別に受け入れて照合できます。
外注加工明細タイプを使用すると、外注加工の購買文書を入力することにより、仕入先に対する支払いができます。Oracle Purchasingには、初期の外注加工明細が「外注加工」に設定されていますが、他の外注加工明細タイプを作成できます。Oracle Purchasing、Oracle Work in Process、およびOracle Bills of Materialが導入されていなければ、外注加工明細タイプは使用できません。関連項目: 『Oracle Work in Processユーザーズ・ガイド』の外注加工の概要に関する項。
Oracle Services Procurementを導入済の場合、一時労働購買基準の明細タイプを使用して、購買文書に入力することにより、派遣労働(契約労働)プロバイダへの支払いができます。関連項目: 一時労働のサービス調達の設定
Oracle Purchasingでは、初期明細タイプとして「商品」および「サービス」が用意されています。Oracle Work in Processが導入されている場合、Oracle Purchasingで「外注加工」明細タイプも使用できます。Oracle Services Procurementを導入済の場合、「レート基準一時労働」および「固定価格一時労働」明細タイプも使用できます。「明細タイプ」ウィンドウ内で、これらの明細タイプを変更するか、新しい明細タイプを作成できます。新しい明細タイプを定義するには、値基準として数量、固定価格、レートまたは金額を指定し、明細タイプの名称および摘要を入力するだけですみます。これで、必要に応じてデフォルト・カテゴリ(Oracle Services Procurementの一時労働明細タイプを除く)、受入が必須かどうか、および単位を指定できます。金額基準の明細タイプの場合、単価はデフォルトで1に設定されますが、それ以外はオプションです。値基準が数量でない場合は、明細を外注加工として指定できません。レート基準および金額基準の明細タイプのデフォルト単位を指定する必要があります。金額基準の明細の単位は、参照情報としてしか使用できません。Oracle Purchasingでは、金額基準の明細の単位換算は実行されません。金額基準の明細タイプ用にAMOUNTなどの単位を作成すると、金額を指定して発注したかどうかを判別しやすくなります。関連項目: 明細タイプの定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位の定義に関する項。
Oracle Purchasingでは、実装に応じて、数量、固定価格、レート、金額または外注加工のいずれの文書明細を作成しているかを指定できます。文書明細を作成する際に明細タイプを選択するだけです。明細タイプに応じて、品目、品目摘要、数量、単位、単価または金額を入力します。関連項目: 明細タイプの定義。
通常、ある明細タイプは他の明細タイプより使用頻度が高いため、Oracle Purchasingでは「購買オプション」ウィンドウ内でシステムのデフォルト明細タイプを定義できます。新しい購買文書明細のデフォルトは、すべてこの明細タイプに設定されます。別のタイプの文書明細を作成する場合は、この値を上書きできます。多数の異なる明細タイプを使用する場合は、システム・デフォルトを設定する必要はありません。関連項目: デフォルト・オプションの定義。
「文書の自動作成」ウィンドウを使用すると、品目やサービスの承認済購買依頼明細を発注とリリースに変換できます。同じ明細タイプの購買依頼明細をまとめて、1件の発注に切り替えることができます。また、異なる明細タイプの購買依頼を同じ発注に切り替えることもできます。同じ品目、明細タイプ、単位および品目改訂を持つ購買依頼の数量および金額基準の明細が組み合されて、1つの発注明細にまとめられます。関連項目: 文書の自動作成の概要
Purchasingでは、明細タイプに従って文書明細が印刷されます。数量基準の明細タイプの場合、Purchasingでは、発注および見積依頼の数量、単価および合計金額が印刷されます。Oracle Purchasingでは、固定価格、レートおよび金額基準の文書明細の金額のみが印刷されます。Oracle Services Procurementが導入されている場合、一時労働情報は印刷されないので注意してください。
明細タイプ機能には、数量基準の発注と金額基準の発注を区別する拡張レポート作成が含まれています。明細タイプが印刷されるため、情報の基準を一目で判別できます。固定価格、レートおよび金額基準の発注の場合は、その合計金額のみが印刷されます。
「明細タイプ」ウィンドウを使用して、明細タイプを定義および更新します。
購買文書に明細を入力して明細タイプを選択すると、ここで明細タイプに対して定義したデフォルト情報が自動的に表示されます。
明細タイプを使用すると、数量基準の明細品目と金額基準の明細品目の間で値基準を区別できます。数量基準の明細品目は、発注する明細の数量と価格が判明している場合に使用します。たとえば、1ダースのペンを$10で購入できます。金額基準の明細品目は、サービスの発注時に使用します。
Oracle Services Procurementを導入済の場合は、固定価格およびレート値基準の明細タイプも使用できます。固定価格基準の明細品目は、料金設定済のサービスを発注する際に使用します。レート基準の明細タイプは、単位当りの料金が適用されるサービスの発注時に使用します。たとえば、1時間当り$250のコンサルティング・サービスを発注できます。
購入する品目の様々な特性を反映した明細タイプを作成できます。たとえば、数量と単価で発注する品目用の明細タイプを1つ、時間で発注するサービス用の明細タイプを1つ、さらにOracle Work in Process(WIP)で使用する外注加工工程を示す明細タイプを1つ定義できます。購買文書明細を作成し、定義した商品、サービス、外注加工または他の明細タイプのうち、どのタイプであるかを指定できます。
さらに明細タイプの購買基準を指定して定義を詳細化できます。商品またはサービスの購買基準を選択できます。Oracle Services Procurementが導入済の場合は、一時労働を選択することもできます。前述の値基準には、数量、金額またはレートなど、購入の評価方法が反映されます。購買基準は購買の性質を示し、必須の属性および関連ビジネス・フローのダウンストリームを決定します。
Oracle Work in Processを使用していて、Oracle Work in Processで外注加工工程の購買文書を入力する場合は、外注加工の明細タイプが必要です。購買文書明細で外注加工の明細タイプを選択した場合、入力できるのは外注加工品目のみとなり、選択できる搬送先タイプは「製造現場」のみとなります。
Oracle Purchasingでは、数量基準の「商品」明細タイプが自動的に提供されます。Oracle Work in Processをインストール済の場合、Oracle Purchasingでは「外注加工」明細タイプも提供されます。各購買依頼、発注、見積依頼または見積文書に追加する明細について、デフォルト明細タイプをコピーするように購買オプションを設定できます。作成する文書明細ごとにデフォルト明細タイプを上書きできます。
複数言語サポート(MLS)を使用している場合は、インストール済の各言語で明細タイプの翻訳を入力できます。明細タイプの翻訳を入力するには、「表示」メニューから「翻訳」を選択します。MLSの詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。
前提条件
カテゴリの定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』のカテゴリの定義に関する項。
単位の定義。関連項目: 『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の単位の定義に関する項。
「明細タイプ」ウィンドウにナビゲートします。
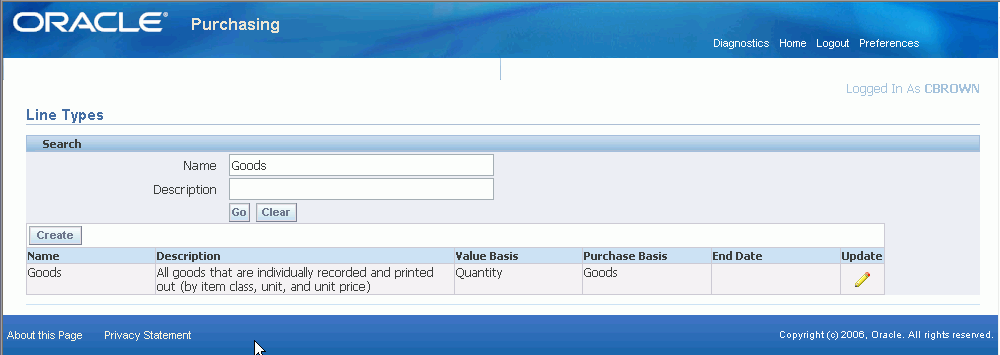
新しい明細タイプを定義する場合は、「作成」をクリックします。既存の明細タイプを変更するには、「検索」リージョンを使用して名称または摘要を入力します。1つまたはすべてのフィールドに入力した後、「進む」をクリックします。明細タイプの「更新」アイコンをクリックし、変更内容を入力します。
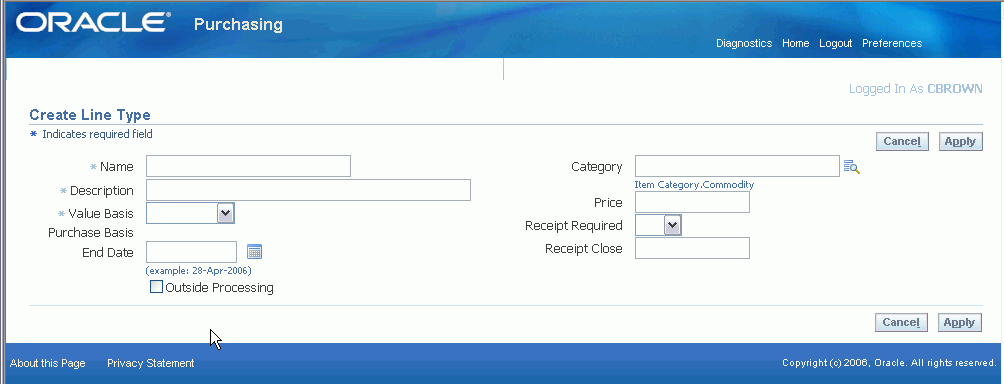
明細タイプの名称と摘要を入力します。
明細タイプの値基準を入力します。
金額: 品目を金額で受け入れます。購買文書明細の単位と単価は変更できません。
固定価格: Oracle Services Procurementを導入済の場合、サービスは金額でのみ入力します。品目は金額で受け入れます。購買文書明細の単位と単価は変更できません。
数量: 品目を数量で受け入れます。外注加工明細タイプには、この値基準が必須です。
レート: Oracle Services Procurementを導入済の場合は、サービスをレート(価格)と金額で入力します。品目は金額で受け入れます。
重要: 明細タイプに関する取引の作成後は、その明細タイプの属性を変更できません。
明細タイプの購買基準を入力します。
商品: 数量値基準の明細タイプに使用します。
サービス: 金額および固定価格基準の明細タイプに使用します。
一時労働: Oracle Services Procurementを導入済の場合、固定価格およびレート基準の明細タイプに使用します。
明細タイプを使用できなくなる終了日を入力します。
この明細タイプを外注加工の購入に限定するには、「外注加工」を選択します。また、購買文書に外注加工明細タイプを使用する場合、品目に選択できるのは外注加工品目のみとなります。このチェック・ボックスを選択できるのは、値基準が「数量」の場合とOracle Work in Processを使用している場合のみです。
この明細タイプの品目のデフォルト購買カテゴリを入力します。この購買カテゴリは購買文書明細上で上書きできます。
これをこの明細タイプの購買文書納入のデフォルトにする場合は、「受入必須」を選択します。デフォルトは納入の入力時に却下できます。
この明細タイプの品目に使用するデフォルト単位を入力します。明細タイプに「金額」値基準を使用する場合は、デフォルト単位を入力する必要があります。この単位は、「数量」値基準の非外注加工明細タイプを使用する場合にのみ購買文書明細上で上書きできます。
「金額」値基準を使用する場合は、単位として機能通貨を選択できます。たとえば、機能通貨がUSドルであれば、「金額」値基準の明細タイプに使用できるようにUSDという単位を定義できます。
Oracle Services Procurementを導入済の場合は、「レート」値基準の明細タイプの単位区分をプロファイル「PO: 一時労働サービスの単位区分」の設定により制限できます。
この明細タイプの品目に使用するデフォルト単価を入力します。Oracle Purchasingでは、「金額」値基準を使用すると自動的に単価1が入力され、この価格は明細タイプの作成時に更新できません。この単価を購買文書明細上で上書きできるのは、「数量」値基準の明細タイプを使用する場合のみです。
「保存」をクリックします。
関連項目
『Oracle Work in Processユーザーズ・ガイド』の外注加工の概要に関する項
Oracle Purchasingでは、商品およびサービスの両方の発注に必要となる機能が用意されています。サービスを調達する購買担当の特殊なニーズに応えるため、Oracle Purchasingでは、ここで説明する機能が提供されています。さらに、Oracle Services Procurementの導入を検討できます。
Oracle Purchasingでは、サービスおよびその他の金額基準の発注について購買依頼明細を作成できます。固定価格基準およびレート基準の明細タイプは、サービスの調達用に特別に設計されています。
金額基準: 金額基準の明細タイプを選択すると、明細の単価は1に自動的に設定され、明細タイプのデフォルト単位が入力されます。金額基準の購買依頼明細の場合は、単価や単位を変更できません。サービスの金額を「数量」フィールドに入力します。明細の合計金額は、「数量」フィールドに表示される値と同じになります。配分時には「数量」フィールドを使用して発注金額を複数の会計フレックスフィールドに配分できます。
固定価格基準: Oracle Services Procurementが導入済の場合、一般的なビジネス・サービスに固定価格サービスの明細タイプを使用できます。この場合、購買および請求書はドル建てのサービスに基づきます。定義した後は、固定価格購買依頼明細を完成させるために金額を入力するだけで済みます。
レート基準: Oracle Services ProcurementおよびOracle iProcurementが導入済の場合、派遣労働にレート基準購買依頼明細を作成できます。この場合、時間単位などの単位当りレートが請求されます。また、この明細タイプでは、超過勤務レートまたは休日レートなどの価格差異について合意レートを取得できます。
「発注の自動作成」を使用すると、承認済の購買依頼から発注明細とリリースを作成できます。特定の購買依頼明細を発注に記載する前に、すべてのサービス購買依頼明細を収集してレビューできます。また、金額基準の明細の場合、あるサービスの購買依頼明細を商品とサービスに関する複数の購買依頼明細に分割できます。選択したすべての購買依頼明細に対して1件の発注が作成されます。
また、サービス明細タイプおよびその明細タイプの適切な情報を入力して、サービスの発注を手動で入力できます。
Oracle Services Procurementが導入済の場合、サービス明細では、「一時労働」タブ・リージョンで、役職、価格差異および詳細の入力が必要となることがあります。
特定のサービスについて仕入先に見積を要求する場合は、要求するサービスの詳細な仕様を記載できます。それをソーシングのために使用する場合は、「カタログ」の見積タイプを選択する必要があります。
金額基準の購買依頼明細と発注明細を選択すると、選択した見積納入データから購買文書の「数量」フィールドに合計金額がコピーされます。金額基準の明細を作成中であり、単価は1に設定されるため、「数量」フィールドにはその明細の合計金額が表示されます。
注意: 見積または見積依頼(RFQ)については、Oracle Services Procurementの固定価格およびレート基準の明細タイプはサポートされていません。
商品を受け入れる場合と同様にサービスを受け入れます。サービスを受け入れると、数量フィールドには発注金額が反映されます。受入、訂正または返品する金額を「数量」フィールドで指定するだけですみます。明細タイプが表示されるため、金額で受け入れるか数量で受け入れるかを判別できます。サービスや他の金額基準の購買は、発注で指定された単位で受け入れる必要があります。
注意: Oracle Services Procurementの固定価格明細タイプは、Oracle Purchasingのウィンドウを使用して受入、訂正、差戻できません。これらの取引は、Oracle Purchasingの受入オープン・インタフェースまたはOracle iProcurementでのみ実行できます。
Oracle Services Procurementのレート基準明細タイプは、「Oracle Time and Laborからの時間の取出し」処理を使用することでのみ受け入れることができます。
買掛/未払金請求書をサービス発注または受入明細と照合する場合、金額に基づいて照合します。金額基準の明細の場合、照合の際にOracle Accounts Payableによって単価がデフォルトで1に設定されます。単価は変更しないでください。
「文書タイプ」ウィンドウを使用して、すべての購買文書のアクセス、セキュリティおよび管理仕様を定義します。新しい文書タイプは入力できません。見積依頼と見積についてのみ新しい文書サブタイプを入力できます。
複数言語サポート(MLS)を使用している場合は、インストール済の各言語で文書タイプの翻訳を入力できます。文書タイプの翻訳を入力するには、「表示」メニューから「翻訳」を選択します。MLSの詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。
前提条件
文書タイプを定義する手順は、次のとおりです。
「文書タイプ」ウィンドウにナビゲートします。
営業単位を選択して「進む」をクリックします。
リストから文書タイプを選択し、「更新」列のアイコンをクリックします。文書タイプが「購買契約」、「発注」、「見積」、「リリース」、「見積依頼」または「購買依頼」の場合は、後述する属性を更新できます。

「見積」および「見積依頼」文書タイプについてのみ、ユーザー定義の文書サブタイプを入力できます。作成した「見積」および「見積依頼」文書タイプは、そのタイプの実際の文書が存在しない場合にのみ削除できます。Oracle Purchasingには、次の文書サブタイプが用意されています。
購買契約: 「包括購買契約」および「契約」(これらの文書タイプの詳細は、「発注タイプ」を参照してください)。
発注: 「計画購買」、「標準」、「依頼者変更オーダー」(これらの文書タイプの詳細は、「発注タイプ」を参照してください)。
発注: 「計画購買」、「標準」、「依頼者変更オーダー」(これらの文書タイプの詳細は、「発注タイプ」を参照してください)。
リリース: 「包括購買契約」および「計画済」(これらの文書タイプの詳細は、「発注タイプ」を参照してください)。
見積依頼: 「見積(個別)」、「カタログ」および「標準」(これらの文書タイプの詳細は、「見積および見積依頼のタイプ」を参照してください)。
購買依頼: 「社内」および「購買」(これらの文書タイプの詳細は、「購買依頼タイプ」を参照してください)。
文書の文書名を入力します。摘要は、指定した文書タイプに対して一意である必要があります。ここに入力した名称は、該当する文書入力ウィンドウの「タイプ」フィールドの値リストに選択肢として表示されます。たとえば、「見積」ウィンドウの「見積タイプ」フィールドの値リストには、選択肢として「見積区分見積(個別)」とともに「名称見積 (個別)」が表示されます。
見積区分は、「見積」および「見積依頼」文書タイプにのみ適用可能です。次のいずれかのオプションを選択します。
見積(個別): 見積または見積依頼は、特定の固定数量、事業所および日付を対象としています。
カタログ: 見積または見積依頼には、様々な数量レベルの価格値引が含まれます。
「見積(個別)」および「カタログ」の詳細は、「見積および見積依頼のタイプ」を参照してください(見積には「見積(個別)」、「標準」および「カタログ」の3タイプがありますが、見積区分は「見積(個別)」および「カタログ」の2つのみで、「標準」は「カタログ」区分に属します)。
購買依頼以外の購買文書の場合は、「文書タイプ・レイアウト」フィールドでこの文書タイプ用のスタイルシートを選択します。
発注の出力フォーマットとして「PDF」を選択した場合は、「文書タイプ・レイアウト」でレイアウト・テンプレートを選択する必要があります。関連項目: 管理オプションの定義。関連項目: 仕入先への発注通信の設定。
Oracle Procurement Contractsを導入済の場合は、「契約条件レイアウト」で契約条件レイアウト・テンプレートを選択する必要があります。「文書タイプ・レイアウト」を指定すると、Oracle Purchasingではそのテンプレートが出力のフォーマットに使用されることに注意してください。詳細は、『Oracle Procurement Contracts Implementation and Administration Guide』を参照してください。
文書作成者が自分の文書を承認できることを示すには、「所有者は承認可能」を選択します。文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、このフィールドは適用できません。
重要: 予算管理を使用していて、このオプションを有効化した場合は、「会計オプション」ウィンドウで「購買依頼完了時予約」オプションも有効化する必要があります。同様に、このオプションを無効化した場合は、「購買依頼完了時予約」オプションも無効化する必要があります。
文書承認者が文書を変更できることを示すには、「承認者は変更可能」を選択します。文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、このフィールドは適用できません。
ユーザーが文書の転送先ユーザーを変更できることを示すには、「転送先変更可能」を選択します。文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、このフィールドは適用できません。
このフィールドと次の2つのフィールドが承認経路にどのように影響するかの詳細は、「承認経路」を参照してください。
作成者と承認者が「文書の承認」ウィンドウでデフォルト承認階層を変更できることを示すには、「承認階層変更可能」を選択します。文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、このフィールドは適用できません。
作成者が文書作成者名を変更できることを示すには、「転送元変更可能」を選択します。このフィールドを適用できるのは、文書タイプが「購買依頼」の場合のみです。
購買依頼の場合にのみ、購買依頼作成の自動ソーシング・ロジックに承認済購買契約を含めるように要求するには、「自動ソースの基本契約の使用」を選択します。このボックスの選択が解除されている場合は、プロファイル「PO: 自動文書ソーシング」が「Yes」に設定されていても、購買依頼作成の自動ソーシング・ロジックでは購買契約が考慮されません。
カタログ外依頼を含む: Oracle iProcurementの場合にのみ、このチェック・ボックスが「自動ソースの基本契約の使用」と併用されます。カタログ外購買依頼の自動ソーシング時には、このチェック・ボックスを選択して購買契約を使用可能にします。
ユーザー定義の見積と見積依頼の場合、Oracle Purchasingではセキュリティ・レベルのデフォルトとして「標準見積」または「標準見積依頼」が表示され、このフィールドには入力できません。それ以外の場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
階層: これらの文書にアクセスできるのは、定義済の購買セキュリティ階層で所有者よりも上位にいる文書所有者およびユーザーのみです。
個人: これらの文書にアクセスできるのは、文書所有者のみです。
制限なし: これらの文書にはすべてのユーザーがアクセスできます。
購買: これらの文書にアクセスできるのは、文書所有者と「購買担当の定義」ウィンドウに購買担当として表示されるユーザーのみです。
セキュリティ・レベルとアクセス・レベルの概要は、「文書セキュリティとアクセス」を参照してください。
ユーザー定義の見積と見積依頼の場合、「アクセス・レベル」の対象は標準見積または標準見積依頼で、このフィールドには入力できません。それ以外の場合は、次のいずれかの「アクセス・レベル」オプションを選択します。
全て: ユーザーは文書を表示、変更、取消および最終消込できます。
変更: ユーザーは文書の表示および変更のみ可能です。
表示のみ: ユーザーは文書の表示のみ可能です。
文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、「転送方法」フィールドは適用できません。次のオプションは、承認経路の決定に職階階層を使用するか従業員/管理者関連を使用するかに関係なく適用されます。次のいずれかのオプションを選択します。
直接: デフォルト承認者は、作成者の承認経路内で十分な承認権限を持つ最初の承認者です。
階層: デフォルト承認者は、承認権限の有無に関係なく作成者の承認経路内の次の承認者です(承認経路内の各承認者は、十分な承認権限を持つ承認者に達するまで承認処理を実行する必要があります)。
「アーカイブ時点」フィールドは、文書タイプが「購買契約」、「発注」または「リリース」の場合にのみ適用可能です。次のいずれかのオプションを選択します。
承認: 文書は承認時にアーカイブされます。このオプションはデフォルトです。「変更オーダー」ワークフローは、このオプションが選択されている場合にのみ開始されます。関連項目: 変更オーダー承認のワークフロー・プロセス。
通信: 文書は通信時にアーカイブされます。文書通信処理は、印刷、FAXまたはEメールです。
文書タイプが「見積」または「見積依頼」の場合、「デフォルト階層」フィールドは適用できません。それ以外の場合は、「会計オプション」ウィンドウで「承認階層の使用」が有効化されていれば、「職階階層」ウィンドウから職階階層を入力できます。この階層は、「文書の承認」ウィンドウのデフォルトとなります。
特定の文書タイプの承認ワークフロー
Oracle Purchasingでは、すべての承認がOracle Workflowテクノロジによりバックグラウンドで処理されます。Oracle Purchasingのデフォルトの承認ワークフロー・プロセスでは、「文書承認とセキュリティの設定」の設定ステップに従って定義した承認管理および階層が使用されます。独自のワークフロー・プロセスを作成しており、それを特定の文書タイプに関連付ける場合は、ここでそのワークフロー・プロセスを選択します。
この文書タイプに使用する承認ワークフローを選択するか、または用意されているデフォルトを使用します。
発注の承認には「発注承認」ワークフローが使用されます。購買依頼の承認には「購買依頼の承認」ワークフローが使用されます。独自のワークフローを作成した場合は、それをこの文書用に選択できます。関連項目: 承認ワークフロー。
この文書タイプに使用するワークフロー起動処理を選択するか、または用意されているデフォルトを使用します。
通常、「ワークフロー起動処理」はワークフローの最上位プロセスです。「発注承認」ワークフローのデフォルト起動処理は「発注承認最上位プロセス」で、「購買依頼の承認」ワークフローのデフォルト起動処理は「主要購買依頼承認」プロセスです。独自の起動処理を作成した場合は、それをこの文書用に選択できます。
購買依頼についてのみ承認取引タイプを選択します。Oracle Approvals Managementを導入済の場合は、この選択により購買依頼文書タイプに取引タイプが関連付けられます。Oracle Purchasingの標準承認ロジックを使用するには、このフィールドを空白にします。関連項目: 『Oracle iProcurementインプリメンテーションおよび管理ガイド』および『Oracle Approvals Managementインプリメンテーション・ガイド』。関連項目: 文書承認とセキュリティの設定。
購買依頼についてのみ、承認済購買依頼明細からの発注またはリリースの自動作成に使用する自動作成ワークフローを選択するか、または用意されているデフォルトを使用します。
Oracle Purchasingに用意されているデフォルト・ワークフローは、「発注文書の作成」ワークフローです。独自のワークフローを作成した場合は、それをこの文書用に選択できます。関連項目: 「発注またはリリースの作成」ワークフロー。
購買依頼についてのみ、使用する自動作成ワークフロー起動処理を選択するか、または用意されているデフォルトを使用します。
「発注文書の作成」ワークフローの最上位プロセスは「文書作成全体/承認の起動」プロセスです。独自の起動処理を作成した場合は、それをこの文書用に選択できます。
関連項目
『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の会計オプションの定義に関する項
『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の役職と職階の表示に関する項
『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の個人情報入力に関する項
『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の予算管理とオンライン残余予算チェックに関する項
「文書形式」ウィンドウを使用して、発注形式を作成および更新します。
発注文書形式を使用すると、組織は購買文書の使用方法にあわせてアプリケーションの外観を管理できます。組織は再利用可能な文書形式を介して各種のOracle Purchasing機能のオンとオフを切り替えることで、ユーザー・インタフェースを簡素化できます。また、文書形式により、組織のビジネスのネーミング規則に即した購買文書名を定義できます。文書形式を使用して購買文書を作成する際には、使用不可になっている機能は表示されません。
たとえば、一時労働のような特定の商品に使用する文書形式を作成できます。この文書形式により、その商品のフィールド・ラベルと表示が最適化され、発注入力が簡略化されます。
前提条件
文書形式を定義する手順は、次のとおりです。
「文書形式」ウィンドウにナビゲートします。
新しい文書形式を定義する場合は、「作成」をクリックします。既存の形式を変更するには、「検索」リージョンを使用して名称、摘要またはステータスを入力します。1つまたはすべてのフィールドに入力した後、「進む」をクリックします。文書形式の「更新」アイコンをクリックし、変更内容を入力します。
注意: 保存した形式を更新する場合、より限定的な形式には更新できません。
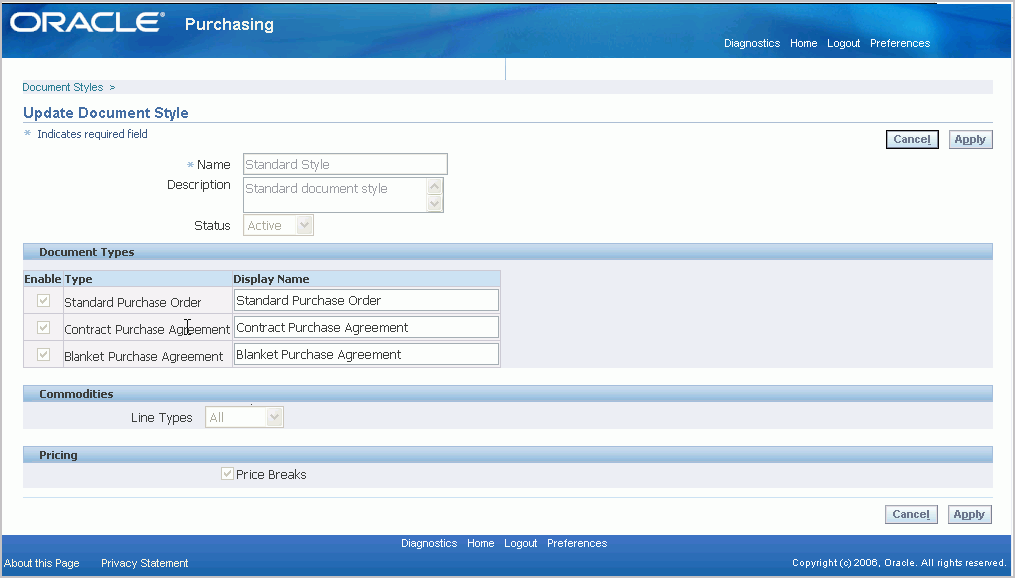
文書形式の名称と摘要を入力します。一意の形式名を入力する必要があります。
「ステータス」で、新しい形式の場合は「有効」を選択し、使用しなくなった形式の場合は「無効」を選択します。
「標準発注」の場合は一意の表示名を入力する必要があります。これは、「購買担当ワーク・センター」に表示される名称です。
購買契約または包括購買契約に適用する形式を定義する場合は、対応するボックスを選択して一意の表示名を入力します。
Oracle Services Procurementを導入済の場合は、この文書形式に適用する購買基準を選択します。関連項目: 購買基準の定義。
この文書形式に対して特定の明細タイプを有効化するか、全明細タイプを有効化するかを選択します。関連項目: 購買文書の明細タイプ。
包括購買契約を含む形式を定義する場合は、「価格分岐」チェック・ボックスを使用して価格分岐を有効化します。
Oracle Services Procurementを導入済で、一時労働基準を有効化している場合は、「価格差異」チェック・ボックスを使用して価格差異を有効化します。
Oracle Services Procurementを導入済の場合は、適用する「複合支払」属性を有効化します。
仮払を許可する場合は、「仮払金」を選択します。
契約に基づく全作業が検収されるまで支払の一部の源泉徴収を許可するには、「留保金」を選択します。
契約実施中の一部支払を有効化するには、「分割払い」を選択します。「分割払い」が有効化されている場合は、支払項目を1つ以上選択する必要があります。
マイルストン: 進捗イベントに基づく支払の場合に有効化します。「商品」明細タイプの場合はデフォルトで有効化されます。
率: 支払額が作業完了率に基づいて按分される場合に有効化します。
一括金額: 支払額が作業完了率に基づく固定金額の場合に有効化します。
この形式の分割払いに適用する場合は、「分割払いを契約融資として処理」を有効化します。
「適用」をクリックします。
関連項目
購買文書の明細タイプ
Oracle Services Procurement
この項では、仕入先の優先通信方法を定義する設定ステップについて説明します。Oracle Purchasingでは、次の発注通信方法がサポートされています。
印刷
FAX
電子メール(Eメール)
eXtensible Markup Language(XML)
電子データ交換(EDI)
関連項目: 仕入先への発注の通信
重要: PDF出力(後述)を有効化すると、「発注要約」ウィンドウの「ツール」メニューで「通信」コマンドが有効化されることに注意してください。
発注の印刷
発注を仕入先に通信する標準的な方法は、印刷してコピーを仕入先にメールで送信することです。発注の印刷には、テキスト形式またはPDF(Adobe Portable Document Format)形式を使用できます。この方法を使用するには、使用するコンピュータ・システムに接続されているプリンタを構成するようにシステム管理者に依頼する必要があります。関連項目: 設定ステップ。
印刷済発注の設定ステップは、次のとおりです。
「仕入先サイト」ウィンドウにナビゲートします。
「一般」タブで、「仕入先通知方法」として「印刷文書」を選択します。
FAX発注
発注のFAXを送信するには、テキスト形式を使用する方法とPDF形式を使用する方法があります。テキスト形式を選択した場合は、サード・パーティのFCL互換FAXソフトウェア(RightFaxなど)を実装する必要があります。PDF形式を選択した場合は、サード・パーティのFAXソフトウェアを使用することもできます。関連項目: PDFによる発注。
この通信方法の場合も、FAX送信をサポートするためにOracle Applicationsを構成するように、システム管理者に依頼する必要があります。関連項目: 『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』。
FAX発注の設定ステップは、次のとおりです。
「仕入先サイト」ウィンドウにナビゲートします。
「一般」タブで「仕入先通知方法」として「FAX」を選択します。仕入先サイトのデフォルトFAX番号を入力します。デフォルトのFAX番号または通知方法は、文書の通信時に変更できます。
Eメール発注
発注のEメール・コピーをHTML形式またはPDF形式で送信できます。
注意: PDF形式の発注は添付ファイルとして送信されます。関連項目: PDFによる発注。
Oracle Purchasingでは、長い添付テキストや短い添付テキストに加えて、購買文書に添付できる各種の添付ファイル(Microsoft Word、Excel、PDFなど)がサポートされています。発注を仕入先にEメールで送信すると、対応する添付ファイルがEメールに添付されたZIPファイルとして表示されます。このZIPファイルの最大許容サイズを指定して、「購買オプション」ウィンドウを介したネットワーク通信量を最小限に抑えることができます。
注意: Eメールを使用してPDF発注を通信すると、すべてのファイル・タイプの添付は、「Attachments.zip」という名称の単一のZipファイルに圧縮されます。
この通信方法を使用するには、Eメール送信をサポートするために、Oracle Application通知メーラー・ワークフローを構成するようにシステム管理者に依頼する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflow管理者ガイド』の通知メーラーの導入に関する項。
Eメール発注の設定ステップは、次のとおりです。
「仕入先サイト」ウィンドウにナビゲートします。
「一般」タブで「仕入先通知方法」として「Eメール」を選択します。仕入先サイトのデフォルトEメール・アドレスを入力します。デフォルトのEメール・アドレスまたは通信方法は、文書の通信時に変更できます。
Eメール発注のコピーを自社に送信するには、「PO: 代替Eメール・アドレス」プロファイル・オプションで代替Eメール・アドレスを定義します。Eメールを再送信する場合、ユーザーはこの代替Eメール・アカウントにログインし、そこから再送信する必要があります。
一般条件をテキスト・ファイルにすると、Eメール発注の本文に追加できます。このテキスト・ファイルは、INIT.ORAファイルのUTL_FILEパラメータに指定されたディレクトリのいずれかに置く必要があります。データベース・サーバーが稼働中の既存のディレクトリにファイルがあることを確認してください。Eメール発注で条件ファイルを読み取ってEメール本文に表示するには、このディレクトリにファイルを置いた後、次のプロファイル・オプションを設定する必要があります。
「PO: ファイル・パス」プロファイルに、条件ファイルのあるディレクトリの絶対パスを設定します。
「PO: 条件ファイル名」プロファイルにファイル名を設定します。
前述のプロファイルを設定した後、ワークフロー通知メーラーを再起動します。メーラーを再起動するには、「要求」->「要求の発行」にナビゲートし、「通知メーラー」コンカレント・プログラムを実行します(詳細は、『Oracle Workflowユーザーズ・ガイド』のOracle Workflowの設定に関する項を参照してください。また、MetaLinkで通知メーラー設定ドキュメントも確認してください)。
Eメール・アドレスの誤りなどが原因で失敗したEメールは、メーラーにより破棄ファイルに配信されます。このファイルをモニターし、未公開受信者などのように一般的な表現を調べて、その表現をワークフロー・メーラー構成ファイルのTAGFILEパラメータで定義されているタグ・ファイルに挿入する必要があります。その後、これらのタグを調べて適切な処理(管理者または購買担当への通知送信)を実行するように、標準エラー・ハンドラ・ワークフローを変更してください。
XML発注
Oracle XML Gatewayを導入済の場合は、XMLを使用して発注と変更オーダーを仕入先に通信できます。Oracle Purchasing用にXML Gatewayを設定する方法の詳細は、『Oracle Purchasing XML Transaction Delivery Guide』を参照してください。
EDI発注
Oracle e-Commerce Gatewayを導入済の場合は、EDIを使用して発注と変更オーダーを仕入先に通信できます。Oracle Purchasing用にe-Commerce Gatewayを設定する方法の詳細は、『Oracle e-Commerce Gatewayユーザーズ・ガイド』を参照してください。
PDFによる発注
発注をAdobe Portable Document Format(PDF)形式でオンライン表示したり、EメールやFAXで仕入先に送信できます。スタイルシート・テンプレートを指定して、フォーマット済PDFファイルの外観とレイアウトを管理できます。Oracle Procurement Contractsを導入済の場合は、スタイルシート・テンプレートを指定して、契約条件の外観とレイアウトを発注PDFファイルの一部として管理できます。これらのテンプレートの管理には、Oracle XML Publisherを使用します。関連項目: 『Oracle XML Publisherユーザーズ・ガイド』。
PDFによる発注の設定ステップは、次のとおりです。
Oracle Procurement Contractsを導入済の場合は、調達文書テンプレート用の条件を定義します。詳細は、『Oracle Procurement Contracts Implementation Guide』を参照してください。
次の手順で仕入先を設定します。
仕入先サイトに優先通信方法を割り当てます。前述の指示を参照してください。
仕入先サイトに言語を割り当てます。
「購買オプション」ウィンドウの「管理」タブで、「発注出力フォーマット」を「PDF」に設定します。関連項目: 管理オプションの定義。
「PO: 発注文書のFAX出力ディレクトリ」プロファイルにUnixディレクトリを割り当てます。FAX通信の場合は、システムにより生成されたPDF文書がこのディレクトリに格納されます。
「文書タイプ」ウィンドウで文書タイプ・レイアウトを定義します。文書タイプにはレイアウト・テンプレートが1つ必要です。Oracle Procurement Contractsを導入済の場合は、契約条件用のレイアウト・テンプレートを定義します。関連項目: 文書タイプの定義。これらのスタイルシートの作成には、Oracle XML Publisherのテンプレート・マネージャを使用します。関連項目: 『Oracle XML Publisherユーザーズ・ガイド』。
Oracle Procurement Contractsを導入済の場合は、購買担当に対するセキュリティを定義します。管理者は、条件へのアクセス権を持つ購買担当を定義できます。条件へのアクセス権を持たない購買担当の場合、PDF文書には発注詳細のみが表示されます。条件へのアクセス権を持つ購買担当の場合は、PDF文書に発注詳細と条件テキストが表示されます。詳細は、『Oracle Procurement Contracts Implementation Guide』を参照してください。
Oracle Purchasingには、すべてのグローバル・ビジネス単位間で類似する機能を連結する機能が用意されています。通常、この連結を集中調達またはソーシング・サービス・センターと呼びます。その目的は、企業内に自律調達ビジネス単位を作成することです。
主な機能
グローバル契約
グローバル契約とは、ビジネス単位間で共有可能な仕入先との契約(包括購買契約または購買契約)です。グローバル契約により、集中サービス単位が他の一部またはすべてのビジネス単位にかわって交渉を行い、交渉結果を単一文書に格納できます。この単一文書は、有効化されている全ビジネス単位からの購買依頼需要の自動ソーシングに使用できるようになります。
センター主導調達の自動ソーシング
ソーシング・ルール、ソーシング・ルール割当および承認済仕入先リスト(ASL)は、所有ビジネス単位で作成します。これにより、自動ソーシングで参照されるグローバル契約を、購買担当が使用可能な全ビジネス単位で実行可能になります。プロセスを完全に自動化するには、実行側ビジネス単位内でグローバル契約のソーシング・ルール割当を定義します。
センター主導調達の会計処理
集中調達環境では、ある営業単位で発注を作成しても、異なる営業単位への出荷が必要な場合があります。調達ビジネス単位と受入ビジネス単位の間で会社間請求を使用して適切な会計消込を実行できるように、勘定科目が用意されています。この会計処理では、2つの組織間で取引フローを定義する必要があります。
センター主導調達のステップ
取引フローの定義
取引フローでは、異なる営業単位間の調達関連を定義します。この関連の詳細では、あるビジネス単位から他のビジネス単位(または他の元帳)に費用を転送する方法を定義します。
取引フローを定義するステップは、次のとおりです。
取引フローの定義
中間ノードの定義
会社間関連の定義
取引フローの設定の詳細は、『Oracle Inventoryユーザーズ・ガイド』の取引設定に関する項を参照してください。
グローバル契約の設定ステップ
グローバル契約は、集中調達環境で使用するために作成された包括購買契約および購買契約です。
グローバル契約を定義する手順は、次のとおりです。
すべての集中調達機能を使用するには、「HR: 複数ビジネス・グループ間」プロファイルをサイト・レベルで「Yes」に設定します。
グローバル契約の購買組織として定義する各営業単位で、仕入先の仕入先サイトを定義します。仕入先サイト名は、グローバル契約での仕入先サイト名と同じでなくてもかまいません。
「グローバル」チェック・ボックスを有効化して、新しい包括購買契約または購買契約を作成します。関連項目: 発注ヘッダーの入力。
グローバル契約を参照している発注に対する権限を持った営業単位に対して、グローバル契約を有効化(購買組織と購買サイトを選択)します。関連項目: 購買契約情報の入力。
実行側営業単位でグローバル契約に対するソース・ルール割当を定義します。関連項目: ソース・ルールの定義。
グローバル購買担当の設定ステップ
集中購買を使用する企業は、購買文書を作成、更新およびデフォルト設定できるグローバル購買担当を設定できます。これにより、重複する設定手順を実行しなくても、複数のビジネス単位の購買担当がこれらの処理に完全に参加できるようになります。
Oracle Human Resourcesの「個人情報入力」ウィンドウを使用して、グローバル購買担当を所属ビジネス・グループ内で従業員として定義します。
Oracle Purchasingの「購買担当の入力」ウィンドウを使用して、グローバル購買担当を購買担当として定義します。この操作は、任意のビジネス・グループで実行できます。
「HR: 複数ビジネス・グループ間」プロファイル・オプションをサイト・レベルで「Yes」に設定します。
このグローバル購買担当に必要な数のOracle Purchasing職責を割り当てます。これらの職責を特定のビジネス・グループにリンクする必要はありません。
グローバル依頼者の設定ステップ
集中購買を使用する企業は、グローバル依頼者を設定できます。これにより、複数のビジネス単位(営業単位)から購買依頼を作成できるようになります。
「HR: 複数ビジネス・グループ間」プロファイル・オプションをサイト・レベルで「Yes」に設定します。
営業単位に関連付けられているOracle Purchasing職責を依頼者に割り当てます。必要な職責をすべて割り当てることができます。
依頼者が該当する職責を選択して購買依頼を作成します。
グローバル管理者の設定ステップ
集中購買を使用する企業は、購買依頼を承認するグローバル管理者を設定できます。これにより、複数のビジネス単位から承認できるようになります。
注意: グローバル管理者機能を使用できるのは、従業員/管理者承認経路を使用している企業のみです。
管理者を定義し、通常設定するとおりに承認グループに割り当てます。
「HR: 複数ビジネス・グループ間」プロファイル・オプションをサイト・レベルで「Yes」に設定します。
このプロファイルが「Yes」に設定されている場合、購買依頼を異なるビジネス・グループにいる個人にルーティングして転送できます。処理履歴には、異なるビジネス・グループにいるユーザーを含めて、処理を実行するユーザーの氏名が反映されます。
関連項目
「購買期間の管理」ウィンドウを使用して、「会計カレンダ」ウィンドウ内で設定した購買期間を管理します。購買期間を使用して、GLシステム内で仕訳を作成します。Oracle Purchasingで作成できるのは、オープン購買期間中に入力する取引の仕訳のみです。GL仕訳は、購買依頼や発注の引当時、または受入の計上時に作成します。
予算引当または予算管理を使用している場合は、発注配分と購買依頼配分で指定するGL記帳日がオープン購買期間に含まれるかどうかが検証されます。関連項目: 『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の予算管理とオンライン残余予算チェックに関する項。
Oracle Purchasingのセンター主導調達機能を使用する場合、発注および受入を処理する可能性が高いすべてのビジネス単位で購買期間がオープンのままであることを確認する必要があります。関連項目: センター主導調達の設定。
前提条件
購買期間を管理する手順は、次のとおりです。
メニューから「購買期間の管理」ウィンドウにナビゲートします。
既存の各期間の「期間ステータス」、「会計期間番号」、「会計年度」、「期間名」、「開始日」および「終了日」が表示されます。
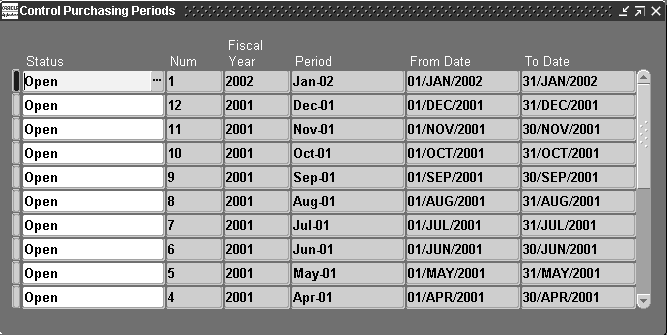
「期間ステータス」フィールドには、次のオプションがあります。
クローズ: このオプションを使用して当購買期間をクローズします。購買期間をクローズすると、この期間中にはそれ以上経過勘定を実行できなくなります。必要な場合は、次の期間に経過勘定を実行できるように、経過勘定済発注明細のステータスが戻されます。
将来: このオプションは、将来、当購買期間をオープンするときに使用します。このオプションを使用できるのは、現在のステータスが「未オープン」になっているときのみです。
未オープン: Oracle Purchasingは、過去に当期間をオープンしていない場合に、デフォルトのステータスを表示します。
オープン: このオプションを使用して当購買期間をオープンします。
永久クローズ: このオプションは、将来、当購買期間をオープンしない場合に使用します。このオプションは、一度選択すると取り消せません。
関連項目
『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』のAP会計期間のステータス管理に関する項
勘定科目ジェネレータでは、「費用」搬送先タイプの明細に使用するデフォルト借方勘定を判別する際に、従業員レコードに定義されている借方勘定が参照される場合があります。勘定科目ジェネレータにより従業員レコードが参照される場合は、費用借方勘定ルールを使用すると、そのデフォルト勘定の1つ以上のセグメントを品目カテゴリに基づいて上書きできます。この上書き機能は勘定科目ジェネレータの処理を妨げず、単に勘定科目ジェネレータによる借方勘定の作成後に構成したセグメントが置換されます。
注意: この機能は、「費用」搬送先タイプの単発品目または在庫品目を含む明細に使用できます。
このウィンドウで定義した勘定科目セグメントを使用できるのは、次の条件に該当する場合のみです。
搬送先タイプが「費用」であること。
購買依頼から発注が作成されていないこと。
作業環境で勘定科目が設定されていないこと。
勘定科目がプロジェクト・ベースのルールから正常に導出されていないこと。
勘定科目が品目設定から正常に導出されていないこと。
設定ステップ
「費用借方勘定ルールの定義」ウィンドウにナビゲートします。
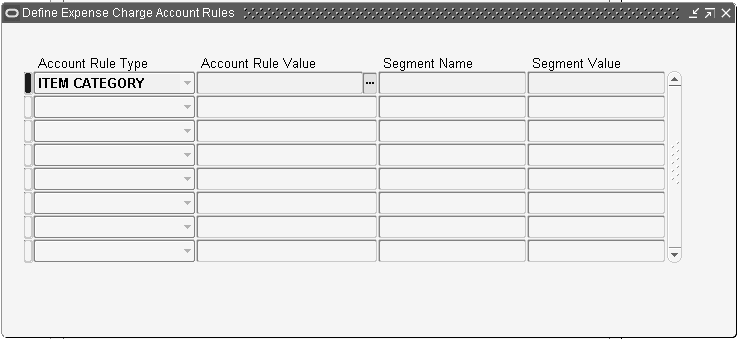
「勘定ルール値」で品目カテゴリを選択します。同じカテゴリで重複するルールは定義できません。
勘定科目セグメント名を選択します。同じ勘定科目セグメントに対して重複するルールは定義できません。
「セグメント値」で、この品目カテゴリの従業員借方勘定科目セグメントを上書きする勘定科目を選択します。
作業内容を保存します。
Oracle Purchasingでは、Oracle Workflowにより自動化されたプロセスにデフォルト機能が提供されます。この項では、このデフォルト機能について説明します。このデフォルト機能が不要な場合は、Oracle Workflow Builderで変更できます。
まだOracle Workflowを設定していない場合は、Oracle Purchasingでいずれかのワークフローを使用または変更する前に設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
Oracle WorkflowはOracle Purchasingとともに自動的にインストールされますが、インストールまたはアップグレードの一環として実行していない場合は、『Oracle Workflowガイド』に記載されている追加の設定ステップを完了する必要があります。Oracle Purchasingで提供されるデフォルト・ワークフローを変更する場合、またはOracle Workflow Builderにグラフィック表示されるワークフロー・プロセスを確認して理解するのみでよい場合にのみ、Oracle Workflow Builderをインストールします。
前提条件
まだOracle Workflowを設定していない場合は、Oracle Purchasingでいずれかのワークフローを使用または変更する前に設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
Oracle PurchasingはOracle Workflowテクノロジと統合されており、承認済購買依頼明細から自動的に標準発注または包括購買リリースが作成されます。購買文書を自動的に作成するためのワークフローは、「発注文書の作成」と呼ばれます。「発注文書の作成」には、Oracle Workflow Builderで評価して変更を検討することが必要な重要な属性が含まれています。関連項目: 自動文書作成ワークフローのカスタマイズ。
項目属性「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」は、「購買依頼の承認」ワークフローの「主要購買依頼承認」プロセスで使用されます。「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」により、承認ワークフローで自動文書作成をバックグラウンド・モードで起動するかどうかが決定されます。デフォルトでは、この項目属性は「Y」(Yes)に設定されます。ただし、自動文書作成をオンライン・モードで処理する場合は、「N」(No)に変更できます。
バックグラウンド・モードとオンライン・モードは、システム・パフォーマンスに異なる影響を及ぼします。バックグラウンドとオンラインの意味の詳細は、「Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ」の「PO: ワークフロー処理モード」を参照してください。
注意: 「PO: ワークフロー処理モード」プロファイル・オプションによりOracle Purchasingの承認ワークフロー全体の処理モードが設定されますが、「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」項目属性を使用すると、購買依頼承認後の自動文書作成の処理モードを、「PO: ワークフロー処理モード」プロファイル・オプションの設定に関係なく特別に変更できます。
デフォルトの「バックグラウンド」モードを保持する場合の手順は、次のとおりです。
「システム管理者」職責で「要求の発行」ウィンドウを使用して「ワークフロー・バックグラウンド・プロセス」を開始します。このプロセスはバックグラウンド・モードで実行する必要があります。
重要: 「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」項目属性にはデフォルト値の「Y」が含まれており、この値は自動文書作成がバックグラウンド・モードで発生することを意味するため、デフォルトを保持する場合は「ワークフロー・バックグラウンド・プロセス」を開始する必要があります。
このプロセスは全ワークフローに対して発行するか、特定のワークフロー(この場合は「購買依頼の承認」ワークフロー)に対してのみ発行できます。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のワークフロー・バックグラウンド・エンジンの計画に関する項。
デフォルト・モードを「オンライン」に変更する場合の手順は、次のとおりです。
Oracle Workflow Builderを起動し、「購買依頼の承認」ワークフローをオープンします。
関連項目: 『Oracle Workflowガイド』の項目タイプのオープンと保存に関する項
「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」項目属性を選択して「プロパティ」ウィンドウをオープンします。
デフォルト値を「Y」から「N」に変更します。
自動文書作成を「購買依頼承認ワークフロー」プロセスから起動すると、オンライン・モードで実行されるようになります。
タイムアウト機能を使用するかどうかの決定
前提条件
まだOracle Workflowを設定していない場合は、Oracle Purchasingでいずれかのワークフローを使用または変更する前に設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
承認ワークフローのタイムアウト機能を使用すると、承認者から応答がない場合に催促を送信するまでの期間を指定できます。タイムアウト機能を使用して、承認者に催促を2件まで送信できます。また、特定の期間後に文書を階層内の次の承認者に自動的に転送するように指定することもできます。必要に応じて、この機能をOracle Workflow Builderで設定できます。
タイムアウト機能を設定しなければ、承認ワークフローはタイムアウトせず、単に各承認者からの応答の受信を待機します。
タイムアウト機能を使用して承認催促を設定する手順は、次のとおりです。
Oracle Workflow Builderを起動し、発注の「発注承認」ワークフローまたは購買依頼の「購買依頼の承認」ワークフローをオープンします。
関連項目: 『Oracle Workflowガイド』の項目タイプのオープンと保存に関する項
次のいずれかのアクティビティの「プロパティ」ウィンドウをオープンし、タイムアウト期間を入力します(手順は、『Oracle Workflowガイド』を参照してください)。
「発注承認」ワークフローでタイムアウト機能を有効化するには、「プロパティ」ウィンドウでタイムアウト期間を入力して、「承認者に通知」サブプロセスの「発注通知を承認」、「発注承認催促1」および「発注承認催促2」アクティビティを変更します。
「購買依頼の承認」ワークフローでタイムアウト機能を有効化するには、「プロパティ」ウィンドウでタイムアウト期間を入力して、「承認者に通知」サブプロセスの「購買依頼通知を承認」、「購買依頼承認催促1」および「購買依頼承認催促2」アクティビティを変更します。
たとえば、次のように、3つの発注承認通知すべてに次のタイムアウト日数を入力するとします。
発注通知を承認: 3日
発注承認催促1: 2日
発注承認催促2: 1日
この例では、最初の通知である「発注通知を承認」は、承認者が通知に基づく処理を実行しなければ3日後にタイムアウトし、「発注承認催促1」により催促通知が送信されます。「発注承認催促1」は2日後にタイムアウトし、「発注承認催促2」は1日後にタイムアウトします。その後、ワークフローで次の承認者が検索されます。
変更内容を保存します。
タイムアウト機能を有効にするには、「ワークフロー・バックグラウンド・プロセス」を実行する必要があります。
関連項目: ワークフロー・バックグラウンド・エンジンの使用
変更オーダー・ワークフロー・オプションの変更
前提条件
まだOracle Workflowを設定していない場合は、Oracle Purchasingでいずれかのワークフローを使用または変更する前に設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
Oracle PurchasingはOracle Workflowテクノロジと統合されており、完全な再承認を必要とする発注変更またはリリース変更の内容(金額、仕入先または日付など)を定義できます。変更オーダーに関連するワークフロー・プロセスと機能はすべて、「発注承認」ワークフローに含まれています。変更オーダー・ワークフロー・プロセスでは、Oracle Purchasingで定義されているのと同じ再承認ルールが使用され、文書の再承認が必要かどうかが文書タイプに応じて判別されます。変更オーダー・ワークフローで使用する再承認ルールを変更する場合は、単価、数量または文書合計について再承認が必要な変更率を決定する再承認ルールを変更できます。これらのルールを変更するには、Oracle Workflow Builderで属性を変更する方法もあります。関連項目: 「変更オーダー承認のワークフロー・プロセス」の「変更オーダー・ワークフローのカスタマイズ」。
変更オーダー・ワークフローの場合、「文書タイプ」ウィンドウで「アーカイブ時点」に「承認」を選択する必要があります。「アーカイブ時点」に「承認」オプションを選択すると、発注を承認または再承認するたびに、Oracle Purchasingで発注情報がアーカイブ表にコピーされます。変更オーダー・ワークフローでは、このアーカイブ情報を使用して変更前と変更後に文書を比較する必要があります。
「購買文書通知の発送」プロセスの開始
「購買文書通知の発送」ワークフロー・プロセスでは、未完了、否認済または要再承認の文書が検索され、その文書のステータスに該当するユーザーに通知が送信されます。この通知を送信するには、標準設定の一環として開始していない場合は、「購買文書通知の発送」コンカレント・プログラム・プロセスを開始する必要があります。関連項目: 購買文書通知の発送。
前提条件
まだOracle Workflowを設定していない場合は、Oracle Purchasingでいずれかのワークフローを使用または変更する前に設定する必要があります。関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のOracle Workflowの設定に関する項。
次のオプションを使用する場合は、ワークフロー・バックグラウンド・エンジンが実行中である必要があります。
Oracle Purchasing承認用の「バックグラウンド」モード。デフォルトでは、「PO: ワークフロー処理モード」プロファイル・オプションは「バックグラウンド」に設定されます。バックグラウンド・モードを機能させるには、ワークフロー・バックグラウンド・エンジンを起動する必要があります。関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ。
いずれかのワークフローのタイムアウト機能。タイムアウト機能により催促通知が送信されます。
「購買依頼の承認」ワークフローの「発注自動作成をバックグラウンドへ送付」項目属性の「バックグラウンド」モード。関連項目: 自動文書作成の処理モードの選択
「受入確認ワークフロー発注の選択」プロセス。これは「要求の発行」ウィンドウから発行するプロセスです。このプロセスを発行する場合は、ワークフロー・バックグラウンド・エンジンも実行中である必要があります。関連項目: 「受入確認ワークフロー発注の選択」プロセス。
タイムアウト機能にワークフロー・バックグラウンド・エンジンを使用する場合は、このプロセスを1日に1回または2回実行するように計画することをお薦めします。バックグラウンド・モードに使用する場合は、より頻繁に実行するように計画する必要があります。バックグラウンド・モードに設定されているワークフロー・アクティビティは、ワークフロー・バックグラウンド・エンジンにより処理のために取得されるまで開始されません。
購買依頼と発注の両方にワークフロー・バックグラウンド・エンジンを使用する場合は、「発注承認」に対して1回と「購買依頼の承認」に対して1回、合計2回発行する必要があります。または、項目タイプを指定しなければ、全項目タイプに対して発行できます。
レポート/要求の発行
「システム管理者」職責を使用して、「要求の発行」ウィンドウの「名称」フィールドで「ワークフロー・バックグラウンド・プロセス」を選択します。
関連項目: 『Oracle Workflowガイド』のワークフロー・バックグラウンド・エンジンの計画作成に関する項
次のウィンドウはOracle iProcurement設定の一部です。これらのウィンドウはOracle Purchasingの「設定」メニューに表示され、Oracle iProcurementでのみ使用されます。Oracle iProcurementは、Webで購買依頼の作成に使用されるセルフ・サービス製品です。この種の購買依頼は、Oracle Purchasingで発注となります。これらのウィンドウは、Oracle iProcurementを設定する場合にのみ使用します。
「情報テンプレートの定義」: 追加情報のテンプレートを作成できます。
注意: 情報テンプレートは、Oracle Purchasingの購買依頼テンプレートとは異なります。Oracle Purchasingの購買依頼テンプレートは、頻繁に発注する品目が事前に入力されたリストです。情報テンプレートは、Oracle iProcurementで依頼者が特定の品目に関して入力する追加情報のテンプレートです。
「品目ソース」: 品目の社内または外部カタログ・ソースの定義に使用します。
「カタログ・サーバー・ローダー値の定義」: システムにロードするカタログ・データを定義できます。
「カタログ・サーバー・ローダー値の定義」: システムにロードするカタログ・データを定義できます。
「範囲」: 社内または外部カタログに対するユーザー・アクセス権限の作成に使用します。
これらのウィンドウに関する指示は、『Oracle iProcurement Implementation Manual』を参照してください。
注意: Oracle Services Procurementには、Oracle Purchasingとは別のライセンスが必要です。
この項では、Oracle Services Procurementの設定について説明します。Oracle Services Procurementを使用すると、派遣労働、設備管理、マーケティング、情報テクノロジおよびコンサルティング・サービスなどのサービスをソーシング、調達および管理するプロセスを合理化できます。通常、これらの商品分野では組織による多額の出費が見込まれます。Oracle Services ProcurementとOracle Purchasingを使用すると、サービス調達フローで次の重要なビジネス機能が有効化されます。
指定仕入先の識別と管理
固定価格およびレート・ベースのサービスに関する長期契約
発注管理
タイムカード管理と支払要求承認
請求書の生成と支払
Oracle Services Procurementの設定ステップ
Oracle PurchasingにOracle Services Procurementを導入するには、次の設定ステップを実行する必要があります。
Oracle Services Procurementと最新のOracle Applications Financialsファミリ・パックをインストールします。(必須)
「PO: サービス調達の使用可能」プロファイルを「Yes」に設定します。(必須)関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ。
Oracle Human Resourcesで役職関連のサービス調達を定義します。(必須)関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の役職と職階の表示に関する項。
役職とカテゴリ関連を定義します。(必須)関連項目: 役職とカテゴリ関連の定義。
次の手順でタイムカード用にOracle Time & Laborを有効化します。
Oracle Time & Laborをインストールして構成します。(オプション)
Oracle Human Resourcesでサービス調達の契約者を作成します。(オプション)関連項目: 『Oracle HRMS Enterprise and Workforce Management Guide』の新しい個人レコードの作成に関する項。
「PO: 一時労働サービスの単位区分」プロファイルを設定します。(必須)関連項目: Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ。
価格差異参照コードを定義します。(必須)
このステップには、次のタスクが含まれます。
一時労働購買基準の明細タイプを定義します。(必須)関連項目: 明細タイプの定義。
通知のシステム・オプション・プロファイルを設定します。(オプション)
PO: 請求金額のしきい率
PO: 契約者割当完了警告後失効
「OTLから時間を取り出す」プロセスの計画を考慮します。(オプション)関連項目: Oracle Time and Labor(OTL)からの時間の取出し。
Oracle Services Procurementの設定の一部は、購買カテゴリ・セットをHR役職に関連付けることです。この設定は、一時労働明細タイプを入力するには必須です。
前提条件
関連を定義する手順は、次のとおりです。
メニューから「役職カテゴリ関連」ウィンドウにナビゲートします。
「作成」をクリックして新しい関連を定義します。
役職、カテゴリまたはビジネス・グループを選択して既存の関連を検索できます。次に、「更新」アイコンをクリックして関連を変更します。
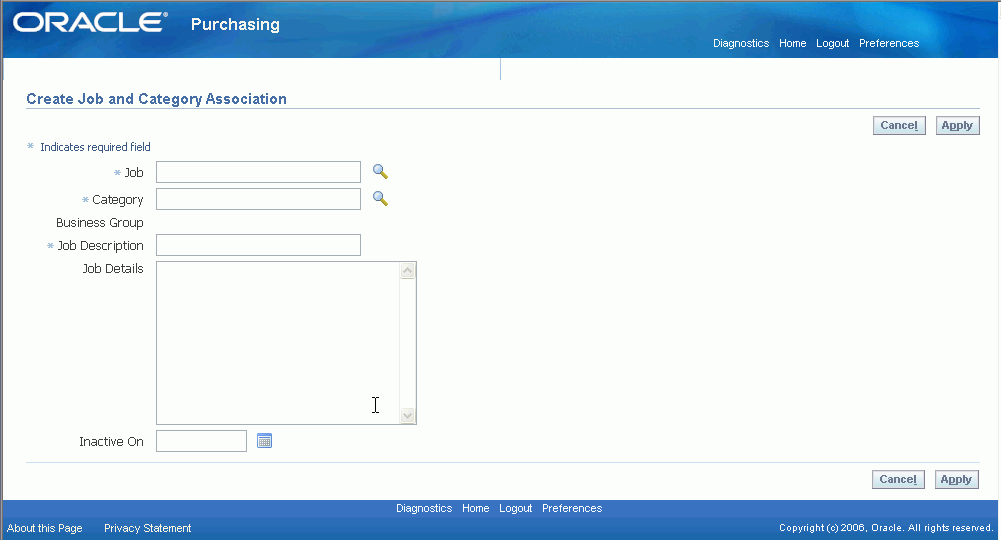
役職を入力または選択します。
「HR: 複数ビジネス・グループ間」プロファイルが「Yes」に設定されていないかぎり、入力できるのは自分のビジネス・グループに属している役職のみです。
カテゴリを入力または選択します。
「役職摘要」にわかりやすいタイトルを入力します。
「役職詳細」に、この役職の詳細を入力します。
無効日を入力します。
作業内容を保存します。
関連項目