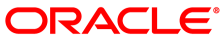このドキュメントで説明するソフトウェアは、Extended SupportまたはSustaining Supportのいずれかにあります。 詳細は、https://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-support-policies-069172.pdfを参照してください。
Oracleでは、このドキュメントに記載されているソフトウェアをできるだけ早くアップグレードすることをお薦めします。
この部の内容は次のとおりです。
第1章「Yum」では、yumユーティリティを使用してソフトウェア・パッケージをインストールおよびアップグレードする方法について説明します。
第2章、「Ksplice」では、実行中のシステムでカーネルを更新するようにksplice Uptrackを構成する方法を説明します。
第3章「ブート構成」では、Oracle Linuxブート・プロセス、GRUBブート・ローダーの使用方法、システムの実行レベルの変更方法、および各実行レベルで使用可能なサービスの構成方法について説明します。
第4章「システム構成の設定」では、システムの構成設定を変更する際に使用できるファイルおよび仮想ファイル・システムについて説明します。
第5章「カーネル・モジュール」では、カーネル・モジュールのロード、アンロード、および動作の変更を行う方法について説明します。
第6章「デバイス管理」では、システムでデバイス・ファイルを使用する方法、およびudevデバイス・マネージャでデバイス・ノード・ファイルを動的に作成または削除する方法について説明します。
第7章「タスク管理」では、特定の期間内、特定の日時、またはシステムの負荷が軽いときにタスクを自動的に実行するようにシステムを構成する方法について説明します。
第8章「システムの監視とチューニング」では、Oracleサポート用にシステムに関する診断情報を収集する方法、およびシステムのパフォーマンスを監視およびチューニングする方法について説明します。
第9章「システムのダンプの分析」では、システム・クラッシュが発生するとメモリー・イメージを作成するようにシステムを構成する方法、およびcrashデバッガを使用してクラッシュ・ダンプ内または稼働中システムのメモリー・イメージを分析する方法について説明します。
目次
- 1 Yum
- 2 Ksplice
- 3 ブート構成
- 4 システム構成の設定
- 5 カーネル・モジュール
- 6 デバイス管理
- 7 タスクの管理
- 8 システムの監視とチューニング
- 9 システムのダンプの分析
- 10 コントロール・グループ